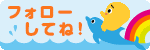4章 ジュレット
祈りの宿から少し西。髪を振り乱して草原を走り抜けるウェディの青年がいた。首筋までのネイビーブルーの髪が風に舞い、シアンブルーの耳ビレがぱたぱたと揺れている。はあはあと息を上げ、チラチラと後ろを気にしながら青年は走っていた。その振り向く先には、同じ速度で青年を追う一匹のウサギ。アルミラージだった。紫の体に、やや赤みを帯びている。
「くそー。こんな強い敵がいるなんて聞いてなかったぞ。これじゃこっちが脱兎みたいじゃないか。」
青年は必死に逃げるが、赤みを帯びた紫のウサギも執拗に追い続ける。なかなか振り切ることができない。やがて青年は、桟橋へと走り着いた。
桟橋にはオールを持ったウェディがのんびりと座っていた。走り込んだ青年を見て、ん~?なんだぁ~?と、のんびりとした調子で立ち上がる。
「おい、あんた!逃げてくれ!アルミラージだ!」
青年が叫んだ。とは言え、青年もオールのウェディも、すでに桟橋に上がり込んでいて、逃げ場はない。追い詰められていた。
「アルミラージねぇ。ほぉ、赤くなってる。チカラをためたときのアルミラージってのは危険だぜぇ。まぁいっけど。ヒャド。」
オールを持ったのとは逆の手でアルミラージを指差したかと思うと、指先から氷の矢が飛び出した。青年が驚いている間に、氷の矢がアルミラージを射抜く。
「イケメンの兄さん、気をつけなよ。」オールを振りながら、のんびりとした調子だ。
「イケメン?僕のことか?ああ、そうか、こっちのアディールはイケメンなのか。・・・あ、いや、助かったよ。ありがとう。」
青年の名はアディール。不幸な事故で命を落としたウェディに転生して、今、ジュレットに向かっているところだった。
「あんたヒャドが使えるんだな。」アディールは感心したように言った。
「兄さんは使えないのかい?」オールのウェディは、少し意外そうな表情だった。
「ああ。うん。その。まだ。」
「唱えるときにイメージしてるかい?呪文ってのはイメージが大事でね。強くイメージするほど明確な形として早く使えるようになるんだ。こんなところで渡し守してると、護身のためにいろいろと覚えるのさ。」
「渡し守・・・ここから舟に乗れるのかな?」
「ジュレー島行きの舟だぜぇ。乗るかい?」渡し守は右手の親指で自分の後ろのほうを指差した。陰に隠れて見えなかったが、一隻の小舟が浮かんでいた。
「ちょうどよかった。お願いするよ。ジュレットに行きたいんだ。」と、アディールは舟に乗り込む。
「しかし不思議な兄さんだ。」渡し守は杭の紐をほどき、舟を桟橋から離す。「アルミラージに追われたら、みんな海に飛び込んで逃げるものなんだけどなぁ。陸ばかり走って船着き場まで来るとは。よっぽど走るのに自信があるんだなぁ。」オールで海をかきながら話す。
「あ、そっか。ウェディだったんだ。泳げばよかったんだな。」
「ははっ。おもしろい兄さんだ。」
「綺麗な海だなぁ。」アディールは今、海原を進んでいる。
「まるでウェディじゃないみたいな話ぶりだなぁ、兄さん。ウェナ諸島は小さな島がいくつもあるが、陸が隔たってて歩いて遠方には行けねぇ。もちろん泳ぐっていう手はあるんだけどなぁ。おっと兄さん、泳げないんだったか?わはは、そんなウェディいるわけないなぁ。島から島へは、こうして舟やイカダで渡るんだぜぇ。ヴェリナードの女王様のご厚意で、この舟は公営だから金もいらねぇ。気兼ねなく乗ってくれなぁ。おっと、そろそろ着くぜぇ。」
ジュレー島の桟橋が見えてきた。桟橋の向こうは洞窟になっている。
小舟が桟橋にくくり付けられた。「ジュレー島下層は洞窟になってるんだ。ここを抜けて、ミューズ海岸を越えればジュレットの町さ。じゃな兄さん、気をつけて。」
渡し守と別れて少し歩くと、後ろのほうからカサカサと音がするのが聞こえた。岩の上を何かが歩いているような音にも聞こえる。アディールは音のほうを振り向いた。軍隊ガニだった。それも3匹。
アディールが短剣を構えると、カニはハサミを高々と掲げ、上下左右に振った。アディールのほうに向かってきているわけではない。攻撃しないのか?と、はじめアディールは思った。しかし、その行動の意味がすぐにわかった。他のカニが続々と湧いて出てきたからだ。しまった、仲間を呼んだのか!
この多勢に無勢、まともに戦ってはいられない。アディールはカニの群れに背を向けて、一目散に逃げ出した。ウサギと違って、カニから逃げるのは簡単だろう、と思っていたが、そう容易なことではなかった。カニの動きは、思ったよりずっと速かった。アディールは必死に走ったが、最後の1匹がどうしても振り切れない。
くそう。こうなったら呪文だ!イメージするんだ。氷の矢、氷の矢。
「ヒャド!」走りながら背後を指差して呪文を唱えた。
すると、カニの上に氷の石が落ちてきた。ゴツッという音がして軍隊ガニがひっくり返り、ぶくぶくと泡を吹いた。
「イメージとはだいぶ違ったけど、まいっか。結果オーライということで。」
アディールは洞窟の出口へと向かった。
ミューズ海岸を北上すると、やがてジュレットへと辿り着いた。
ジュレットは都会だった。レーンともエテーネとも違った雰囲気。しかし、それは単に人口の違いのみならず、街の特徴のひとつである文化の混合性が挙げられる。エテーネは人間の村だった。レーンもウェディばかりの村。ところが、ここジュレットでは、ウェディだけではなく、様々な種族が行き交っている。のしのしと歩く赤い巨人族、あれがオーガだろう。パタパタと羽を振るわせるのは人間の子供ほどの色白な妖精、こちらはエルフだろうか。エルフよりも小さい緑色人種がとことこと小走りに動き回る、ドワーフのようだ。とんがり耳の黄色の小人の足取りはピコピコと回転が早くて見えないほどだ、プクリポなのだろう。それから人間も。ウェディだけではない、異種族混合の街。それがここ、ジュレットだった。
ジュレットは都会だった。レーンともエテーネとも違った雰囲気。しかし、それは単に人口の違いのみならず、街の特徴のひとつである文化の混合性が挙げられる。エテーネは人間の村だった。レーンもウェディばかりの村。ところが、ここジュレットでは、ウェディだけではなく、様々な種族が行き交っている。のしのしと歩く赤い巨人族、あれがオーガだろう。パタパタと羽を振るわせるのは人間の子供ほどの色白な妖精、こちらはエルフだろうか。エルフよりも小さい緑色人種がとことこと小走りに動き回る、ドワーフのようだ。とんがり耳の黄色の小人の足取りはピコピコと回転が早くて見えないほどだ、プクリポなのだろう。それから人間も。ウェディだけではない、異種族混合の街。それがここ、ジュレットだった。
物珍しげに街の中を歩いていると、裁縫ギルド、という職人ギルドを見つけた。裁縫、と言われると、シンイのことを思い出す。そういえばシンイの針さばきは鮮やかだった。練習すれば僕にでもできると、シンイはそんなことを言っていた。アディールはちょっと入ってみることにした。
軽い気持ちでギルドに入会したアディールだったが、裁縫をはじめてみると、日が暮れるのも気付かないほどに熱中してしまっていた。はじめは何度も針で手を刺したものだが、力加減にも徐々になれて、簡単な衣類なら作れるようにまでなっていた。
「なるほどなるほど、このレシピどおりに縫えばいいんだな。こうして、ここを通して、ここで結んで・・・できた!若手芸人の服!」
アディールは服を広げて見てみた。裏返して背面もよく見る。
「うーん。いびつと言えばいびつだけど、でも僕の裁縫の第一作だ。明日からこれを着て冒険しよう。」
翌朝。
アディールはジュレットの町長の家の前に立っていた。腕のいい旅人を探している、という情報を聞いたからだった。
腕に自信があるかと言われると、そう堂々と名乗ることはできない。ウサギからもカニからも逃げてばかりだったことをアディールは気にしていた。しかし、町長の信頼を得られれば、今後はもっと旅をしやすくなるだろうことを考えると、このチャンスを逃したくはない。大丈夫だ、この若手芸人の服と、今バザーで買ったばかりのシーブスナイフとライトバックラーがある。ホイミだってヒャドだって使える。
トントン。と、扉を叩いた。
「はい。どちらかな?」ガチャリと扉が開き、中から壮年のウェディが顔を出した。
「あの、腕のいい旅人を探してると聞いて来ました。」
「ほう。君は腕がいいのかね?」ジロジロと見られると視線が痛かった。「なにか腕前を示す証を持っているかね?」
「あ、あります!バルチャ爺にもらった一人前の証!」
「ほう、すると君はレーンから来たのか。うむ、証は確かに本物だ。」壮年のウェディは扉を全開にし、アディールを部屋の中へと招いた。「立ち話もなんだ。中に入ってくれ、アディール君。」
「え?僕を知ってるんですか?」
「おや、娘は何も言わなかったのかな?私はキールの父のボーレンだよ。この町の町長をやっている。君はシェルナーとしてキールを助けてくれたそうじゃないか。私からも礼を言わせてもらうよ。ありがとう。」
そうだった。キールはジュレットの町長の娘だと、確かに聞いたことを思い出した。
「ところでアディール君。君にお願いしたいのはこちらのキンナー調査員の護衛だよ。」ボーレンが掌で示したのは若い青年ウェディ。紫のローブと紫の学者帽という身なりだった。
「はじめまして。ボクはヴェリナード王立調査員のキンナーと申します。」キンナー調査員はくるりと回って正面を向き、右手の肘を水平に曲げてアディールに一礼した。「あなたには、ボクを遺跡まで保護してもらいたいと思っています。」またくるりと回って、両手の人差し指でアディールを指差した。どうやら決めポーズであるようだ。「王立調査団は今、ラーディス王島にある知恵の眠る遺跡の調査を行おうとしています。ところがボクは完全な頭脳派。調査はできるが遺跡まで辿り着けません。」調査員の話が、何故だか自慢げに聞こえた。
「あー、アディール君。彼も悪気はないのだよ。」ボーレンが小声で教えてくれた。
「遺跡にはボクたちウェディにとってとても大切なものがあるのですが、それに異常の兆候が見られました。アディールさん、もう準備が整っているのなら」キンナーはくるりと回って目的地の方向を指さした。「行きましょう。」ひとことひとことにポーズをとっているが、あまり様になっているわけではない。
アディールとキンナーは、ミューズ海岸を南下し、ラーディス王島への船着き場を目指す。海岸では、スライムナイトやキメラやトンブレロが行く手を阻んだが、新しい武器と防具のおかげで、アディールは大きな苦労をすることもなく砂浜を進むことができた。
もう少しで船着き場というところで、奥まった岩場の陰で何かをしているウェディの少女が見えた。
「なんでしょうね。子供が遊ぶような場所ではなさそうですが。」
キンナーが心配そうに言うので、アディールも奥の岩場を覗き込んだ。少女が、誰かに話しかけるような声が聞こえてきた。
「ミルク持ってきたよ。お腹すいたでしょう?」
アディールは首をかしげてキンナーのほうを見た。キンナーも同じように首をかしげている。
「誰!?誰かいるの!?」
少女が、アディールたちの気配に気付いて、驚きながら叫ぶような声を上げた。その声にアディールたちも驚いた。
「やあ、女の子が遊ぶようなところじゃないなと思ってね。」警戒されないようにと思うと、何故だか両手を上げてしまう。「どうしたのかな?」なるべく優しい声で言った。
「なんでもないよ。なにもいないよ。ひとりで遊んでいるだけだもん。」少女は両手を開いて、とおせんぼをしている。「本当だもん。」と、何度も繰り返す。
しかし後ろから、みゃあ、と声が聞こえると、少女は慌てて声のほうへ駆け寄り、抱きかかえた。「お願い!みんなには内緒にして!みんながこの子をいじめちゃう!」少女の手の中で、子猫がみゃあみゃあと鳴いていた。「砂浜に流れ着いたこの子を私が見つけたの。きっとこの子も両親に捨てられたんだって思って。私とおんなじだって思って。だから私がこの子の母親になるの!私がこの子を守るの!ねえ!お願い!」少女は涙を浮かべてアディールを見つめた。
「本当だ。」アディールは膝をついて少女の頭をなでた。「本当になにもいないや。君は正直者だね。」自然と優しい表情になった。
「え?」少女がアディールを見上げる。
アディールが目配せをすると、キンナーは「ボクは何も見ていませんよ。」と背中を向けた。
「こんなところでひとりで遊ぶのは危ない。次は僕が一緒に遊んであげるから、今日は街へお帰り。」ポケットをごそごそと探ると、さっき倒したキメラの羽が出てきた。「これを持ってお行き。キメラの翼には、無事に街まで帰れるおまじないがかかってるんだ。」
「・・・ソーミャ。」少女がぼそりとつぶやいた。
「え?」
「私ソーミャって言うの。お兄ちゃんは?」
「僕はアディール。こっちの学者さんはキンナー調査員だ。」
「ありがとう、アディールお兄ちゃん。」
「うん。気をつけて帰るんだ、ソーミャ。」
アディールは、ソーミャが見えなくなるまで見つめてから船着き場へと向かった。
「ソーミャはなんであんなところで子猫をかくまっているんだろう。」ラーディス王島行きのイカダの上でアディールが言った。
「確かに不思議ですね。街に連れて帰ればいいのに。」キンナーも首をかしげている。
「お客さんたち、知らないのかい?」イカダの船頭がオールを漕ぎながら言った。「ジュレットでは今、巨猫の被害が相次いでいるんだよ。街の人はみんな猫にビビっちまってる。子猫と言えども、神経質になるのが、子供にもわかることだろうな。」
イカダを降り、王島を東へと進むと、やがて遺跡へと辿り着いた。
「この奥に波紋の音叉があるはずです。」と、キンナーが歩を進めた。
「波紋の音叉?」アディールが周囲を警戒しつつ問う。いつ魔物が出ても、キンナーを守らなければならない。
「はい。ヴェリナード女王ディオーレ様の美しい歌声をウェナ諸島全体に響かせるための装置です。海が荒れることなく、ボクたちが海の幸に恵まれているのは、ディオーレ様の恵みの歌のおかげなのです。しかし今、女王様の歌声が諸島中に響かなくなってしまい、人々は海の恩恵を受けられなくなりつつあります。だからボクが、この遺跡の音叉を調査しに来たんです。」
「なるほど、この遺跡はその波紋の音叉のために作られたんだな。」
「いえ。ボク個人の見解ですが、それだけではないと思います。この遺跡は、当時は神殿だったのですが、17代前のヴェリナード国王ラーディス様によって作られました。」
「ラーディス?この島の名前じゃないか。」
「はい。ヴェリナード国最後の男王です。王は時の王妃に王位を譲り、この島で、この神殿と波紋の音叉を作りました。恵みの歌をウェナ諸島全体に響かせるためです。王はその後ヴェリナードへ戻ることはなく、ラーディス王を最後に、ヴェリナードでは男王ではなく女王を立てるようになりました。以来、ヴェリナードはずっと女系王族。この遺跡はヴェリナード王家にとって、なにか重要な意味があるような気がしてなりません。」
地下に降りてしばらく進むと大きな扉があったので、扉を開けて中に進んだ。大聖堂のような大きな部屋の奥に巨大なU字型の金属棒が立てられているのが見えた。
「これです。これが波紋の音叉。恵みの歌の増幅装置です。しかし、どうやら故障しているようですね。音叉が振動していません。でも、これならすぐに修理できますよ。少し待ってくださいね。」
修理の終えた音叉は、微音を響かせている。聞こえるか聞こえないかわからないほどの、耳鳴りとは違う心地よい耳への響き。
「アディールさん。どうやらディオーレ様の恵みの歌が始まりそうですよ。」
歌声が聞こえてきた。恵みの歌。つい最近ウェディになったばかりのアディールでも、もう何度も聞いた歌だった。歌詞こそ違えど、その旋律は同じ。魔瘴に憑かれたレグを救ったダーリアの美しい歌声。愛するアーシクに向けた花嫁キールの優しい歌声。そして、今聞いている女王の澄みきった歌声。澄んだ歌声は音叉に響き部屋で反響し、アディールの全身を包む。アディールは目を閉じた。自分の呼吸の音よりも静かで、さざ波に揺られるように安らかで、空を飛ぶ小鳥のさえずりのように心地よい歌声だった。
「どうしたんですかアディールさん?」
アディールはふと目を開けた。頬を冷たい筋が伝った。気がつかないうちに涙がこぼれていた。
「あれ。なんでだろう。不思議な気持ちになったんだ。」アディールは涙を指で拭った。
「そうでしたか。」キンナーはくるりと回って両手の親指を立てた。「これでウェナ諸島も安泰です。」
アディールとキンナーはジュレット町長の家に戻ってきた。
「お疲れさまだったね。」ボーレン町長がアディールをねぎらった。
「助かりましたよ、アディールさん。これでボクも役割を果たすことができました。」キンナーは腰袋をひとつアディールに渡した。「これはお礼のお金です。ヴェリナードへ来ることがあったら、ぜひボクに声をかけてくださいね。」
そうしてキンナーはヴェリナードへ帰って行った。
町長の信頼の証を手にできるのではないかと思って依頼を引き受けたアディールだったが、これはキンナー調査員の依頼である。町長の礼を受けれようはずもない。では、と、アディールも町長の家を後にしようとした。扉の前まで行ったときに、なんだか表が騒がしいことに気付いた。
「なんだ?どうしたんだ?」と、ボーレンが扉を開けて歩き出た。
「町長!ネコが・・・巨猫が街の中をうろついてやがったんだ!」
「きっとソーミャが呼びよせたに違げえねぇ!」
「ちょっと待ちなさい。ソーミャと猫に何の関係があるのだね?」ボーレンは、街人たちの言葉の意味がよくわからないでいた。
「とにかくソーミャの家に来てくれ!」
「ふうむ。」ボーレンが顎をさすりながら少し考え「アディール君、君も来てくれるかね?」と言うので、アディールはそれについて行くことにした。
「ソーミャ。いるのかソーミャ。」ボーレンが、ひとつの民家の家の扉を叩く。返事はない。
「くそ!隠れているんだ!」
「扉をぶち破るぞ!」
「待ちなさい君たち。」ボーレンが手で制しながら、扉に向かったゆっくりした口調で話した。「ソーミャ。いたら返事をしてほしい。どうしたんだ?なにかあったのか?」それでも返事はなかった。
アディールが「あの。」と一歩進み出た。「僕に任せてもらえませんか?」ソーミャが子猫をかくまっていることは秘密にしておきたい。しかし、子猫や、子猫を取り返しに来た親猫にソーミャが襲われていたりするのかもしれないと思うと、気が気ではなかった。「ソーミャ、僕だ。アディールだよ。」アディールは街人の目も考えて言葉を選んだ。「この前約束したからさ。一緒に遊びに来たんだよ。いるのかい?」
しばらく待つと、扉の鍵を開ける音がして、ソーミャが俯きながら顔を出した。中からはみゃあみゃあと子猫の声が聞こえた。
「ほら!いやがった!」
「やっぱり猫を呼び寄せてたんだ!」
「違うの!これは違うの!」ソーミャは必死に子猫を庇っている。
「ソーミャ、私はね、君を問い詰めようとか咎めようとか、そういうことを考えているわけじゃないんだ。だがね、私もこの街の町長だ。街のみんなが不安に思うことを取り払わねばならん。子猫をこっちに渡してもらえんだろうか。」
ボーレンはそう言いながら、ソーミャのほうに両手を差し出した。はじめは頑なに拒んでいたソーミャだったが、辛抱強く待つボーレンの手に、しぶしぶと子猫を渡そうとした。そのとき、子猫がひょいと宙に持ち上げられた。ボーレンではない。ボーレンの後ろから、何者かが棒のようなもので子猫を包む布を吊り上げたのだ。
「ヒューザ!」アディールが驚きの声を上げた。
「よう。アディール。」ヒューザが大剣の先に子猫をぶら下げている。「要するに、この猫を街から出せばいいんだろうが。」
「待て!君は誰だね!?」ボーレンにとっても突然のことである。赤いバンダナの青年とは面識がない。
「知らねーのも無理はないが、一応オレもキールのシェルナー候補だったんだぜ?」子猫をぶらぶらと揺らしながら「オレはヒューザだ。」と名乗った。
「ああ、そうだったのかヒューザ君。しかし、その子猫を捨てるのは考え直してくれ。巨猫たちがその報復に来ないとも限らん。それに、ソーミャもそれは望んでおらんだろう。」
「慌てるなよ町長。捨てるとは言ってない。親元に返そうってことだ。」
「そ、そうか。それなら私としてもありがたい話だ。街の者も安心できるだろうし、ソーミャ、君もそれでいいだろう?」
「・・・うん。」うつむき加減に頷いた。
「決まりだな。アディール、おまえが持てよ。」ヒューザ軽く手首を返して、大剣の先の子猫を放り投げた。
おっと、とアディールが受け止め、丁寧に抱きかかえる。「なんだ、ひとりで行くんじゃないのか。」と、軽く皮肉を言ってみた。
「よく考えたら、ひとりでそいつを守りながら行くのは楽じゃねえと思っただけだ。」少し言い訳染みていたのが、アディールにはおかしく感じる。
「待って!」ソーミャがアディールに駆け寄った。「私も行く!」
「おい、チビ。何言ってんだ?おまえみたいな足手まといを連れていくわけないだろ。」ヒューザがぶっきらぼうに言った。
「嫌!絶対に一緒に行く!私はその子の母親なの!」
「ふん。じゃあ勝手について来な。何があってもオレは知らねえからな。」
「ありがとう、ヒューザ兄ちゃん。」
「おい。オレのことを気安く呼ぶんじゃねえ。」
街の出口に向かうアディールたちに、ボーレンが声をかけた。「ミューズ海岸に、ラーディス行きとは別の舟がある。猫島に渡って、巨猫の巣へ行くんだ。」
【続きを読む】
【前に戻る】
【目次】
序章:誕生【1】【2】
1章:エテーネの民【1】【2】
2章:旅立ち【1】【2】
3章:ランガーオの戦士【1】【2】【3】
4章:ジュレット【1】【2】
5章:グロリスの雫【1】【2】
6章:赤のエンブレム【1】【2】【3】
7章:港町【1】
8章:嘆きの妖剣士【1】【2】
9章:風の町アズラン【1】【2】
10章:世界樹の約束【1】
11章:ガラクタの城【1】【2】
12章:五人目の男【1】
13章:団長の策謀【1】【2】【3】【4】
14章:娯楽の島【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】
15章:三つの願い【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】
16章:太陽の石【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】【11】【12】【13】
17章:白き者【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】【11】
18章:恵みの歌【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】【11】【12】【13】
19章:錬金術師【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】【11】【12】
20章:時渡りの術者【1】【2】【3】【4】
21章:ふたつ目の太陽【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】【11】【12】
22章:冥府【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】【11】【12】【13】
終章:レンダーシアヘ【1】【2】