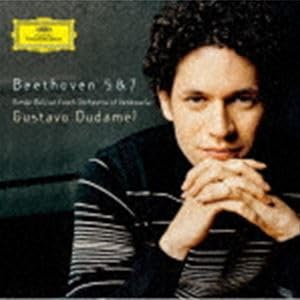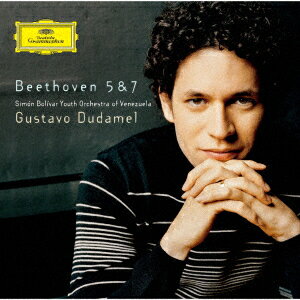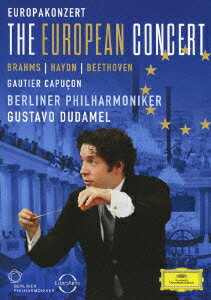第32回西春吹奏楽団定期演奏会
スマホで入力して記事をアップしようとすると投稿完了の表示が出るものの、実際にはアップされていないと言う事態がここしばらく続いています。この記事も実際には9時40分ぐらいにアップしようとしていたのですが、肝心の記事が消えてしまっていましたので、そこから再度作り直しています。
この西春吹奏楽団の演奏は、毎年楽しみにしているものの1つで、車椅子で生活している母親を連れて行ける数少ない演奏会の1つです。今年もこれを楽しみにしていました。
プログラム
どこの吹奏楽団でもそうですが、演奏会は2部形式で、その第1部は、自分たちの1年間の練習の成果を発表する吹奏楽のオリジナル作品の演奏になっています。今回もその例にもれず、前半はそういう作品が演奏されました。今回のトップで演奏されたのは「天国の島」と言う作品でした。この作品2011年度の全国日本吹奏楽コンクールの課題曲として使われたものになります。実際の北海道北西部に周囲12キロの小さな島「天売島」(てうりとう)という島があります。作曲者の佐藤博昭さんは、ここで中学校の音楽教師として1年間勤務した経験もあるそうです。生徒数が7名と少なく、毎日一緒に生活していると言う感覚の中で、この島の魅力をこの作品に込めて書き上げています。たまたまこの作品テレビ番組の「ザ・鉄腕!dash!」で使われたこともあり、あっという間の人気曲になっていきました。多分皆さんも耳にしたことがあると思います。和楽器のテストを盛り込んだ、この作品はこれからも末永く演奏されるのではないでしょうか。
1998年にジェームズ・ホルジンガーが作曲したこの作品は、アイルランドのケルトミュージックを要素に取り入れた作品です。ただあまり演奏される機会がないので、知らない人の方が多いかもしれません。
選曲が凝っていて、3曲目にはレハールの「メリー・ウィドウ」から(ヴァリアの歌」が演奏されました。吹奏楽の父と称されるアルフレッド・リードが吹奏楽編曲した作品で、オペレッタの中に流れるメロディーとは多少違っているのが特徴です 。
この作品は、昨年度も別の吹奏楽団が演奏していましたが、作曲者の酒井渉氏が、高校時代に作曲したと言う早熟な作品です。しかし、ソロ楽器によるアンサンブルや息継ぎを考慮した自然なフレーズなど、吹奏楽のエキスをいっぱい詰め込んだ作品になっています。名曲です。
第二部
第二部は打って変わってポップスステージとなっていました。ただ最初はジャズのウェザーリポートの代表曲「バードランド」が演奏されました。一般にはメイナード・ファーガソンのトランペット版が有名なようですが、こういう吹奏楽版の演奏も楽しいものです。
小生はほとんど知らないのですが、次に演奏されたのはMrs. GREEN APPLEのメドレー曲でした。この作品では、やはり小さい子供たちが一緒に口ずさみながら手拍子を打っているのが印象的でした。
次のスーパーマリオブラザーズでは、お馴染みのファミコンから流れるゲーム音が次々と登場するので、子供たちは目をキラキラさせていました。冒頭の和音は実ファらのサウンだけで構成されている。そのシンプルさから、当時は強い印象を受けたものです。
ムーン・リバーは楽曲の紹介曲として取り上げられたようで、各楽器のソロが色々とフューチャーされていましたが、今回の選挙の中ではちょっと違和感がある作品であったことも事実です。
「アナと雪の女王」「のメロディーはいろいろな編曲がありますが、ここではハイライトとして「ベリーー雪だるま作ろうー生まれて、初めてーLet It Go」と言う4曲が演奏されました。
小生たちの世代には懐かしいのですが、1969年から71年にテレビで放送された「巨泉×前武ゲバゲバ、90分」と言う番組のテーマソングとして、作曲された曲が演奏されました。今回聞いてこんな賑やかな曲だったんだと言う思い出とともに、この番組で有名になったはじめの「と驚く玉五郎」「と言うフレーズも懐かしく思い出されました。
「明日と言う日が」は、東日本大震災の被災地で歌われた、復興支援のシンボル曲 として広まったと言う事ですが、個人的には「花が咲く」「の方がどうしても印象が強いものです。こちらのほうは合唱曲として広く広まったようです。
今回の演奏会で圧倒的だったのは、最後に演奏された千と千尋の神隠しの音楽として、久石 譲が作曲した「スピリットドアウェイ」と言う作品でした。もともとミニマル音楽の手法に精通している久石氏ですが、ここでは映画に登場する(龍の少年#カオナシ、#あの夏へ#底なし穴#湯婆狂乱#いつもいつでも#再び)という曲が、メロディーで演奏され、まるで映画の交響詩のような作品に仕上がっていました。メリハリのある演奏で、素晴らしく、充実したコンサートを盛り上げていました。
一緒に同行した妹も今年の演奏会はすごく楽しめたと言うことを言っていました。