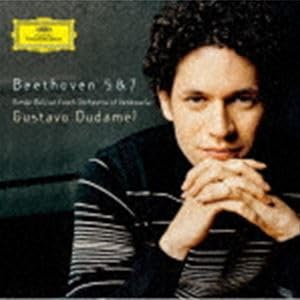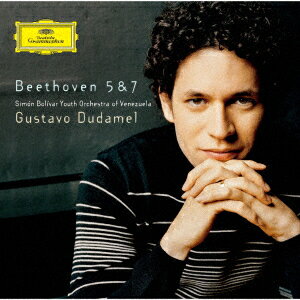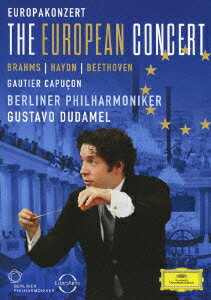グスターボ・ドゥダメル
ベートーヴェン 運命 第7
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 ≪運命≫
1.第1楽章:Allegro con brio 07:24
2.交第2楽章:Andante con moto 11:31
3.第3楽章:Allegro 05:22
4.第4楽章:Allegro 08:39
交響曲 第7番 イ長調 作品92
5.第1楽章:Poco sostenuto - Vivace 11:29
6.第2楽章:Allegretto 08:42
7.第3楽章:Presto 09:41
8.第4楽章:Allegro con brio 06:15
録音/2006/09 ベネズエラ中央大学、アウラ・マグナ講堂、カラカス
独GRAMMOPHON 477 6228(00289 479 2988)
昨日、ドゥダメルを取り上げるにあたりそういえばCDを持っていたことを思い出し、引っ張り出しました。手元にあるのは「100GREA SYMPHONY」と題するボックスセットに含まれるもので、そっけないタイトルだけ書かれたジャケットだったので見逃していました。上はオリジナルで発売された時のジャケットです。どういうものかDGGはデビューの時このベートーヴェンの5番と7万をカップリングして発売するのが常套のようでクライバーも、ティーレマンもこの組み合わせで発売していました。まあ、聴かせるなら一番派手な曲の組み合わせということでしょうか。
最初の「運命」の第1楽章では,冒頭の運命の主題から力みはないものの,アンサンブルは引き締まっていて弾力性があって,リズミカルで溢れるばかりの表現意欲の伝わる演奏になっています。普段写真で見るバカでかい編成ではなく通常の規模の編成で録音されているところも表書きます。そのため、弦のアンサンブルがピシッと纏まっていて管とのバランスもしっくりといっています。それでいてコントラバスは力強く明瞭ですし、とにかくバランス感覚は聴いていてハッとさせられるものがあります。最近ではショルティとウィーンフィルの旧録音が
オーソドックスな中にショルティの意志が強く感じられてなかなかよかったのですが、このドゥダメルの演奏もそういう指揮者の意志が反映されていて面白い演奏です。
第2楽章は、じっくりとしたテンポで演奏しています。意外にもショルティ/シカゴ響のテンポです。そして、細かく聴くとヴァイオリンの響きが指示がないのにクレッシェンドしていく様や、音のフレーズをつないでスラー気味に演奏するところなどいろいろ細かいテクニックをつかっています。それでいて一本筋の通った演奏でまとめているところはなかなかです。
第3楽章でも重苦しい印象はなく、流れの良さと厚みのあるハーモニーには 強い訴求力があって胸に迫ります。トリオでのチェロとコントラバスは切れ 味良く、表現の幅の広い大変に聴き応えのある演奏をつくりあげてい ます。ただ、時々管の響きが一本調子になるところがあり若さが露呈します。なにしろこの録音時ドゥダメルは若干25歳です。
第4楽章に突入しても力強い足どりで前へ前へすすんでいく推進力が あります。弦の合奏は流石によく練れていて一糸乱れぬアンサンブルと、コントラストの強いフレーズの刻みが演奏の勢いをさらに増していき、ただテンポの早い演奏だけに終始はしていません。惜しむ楽は録音スタッフが聴きなれないメンバーで、明らかに編集した後というのが聴いていてわかります。このため、音楽の流れがそこで一瞬止まってしまうということが起きています。そのためコーダの部分で一度溜めを作る部分ではテンポを落とすのですがその部分が音楽に乗り切れていない甘さが露呈しています。
確かに衝撃的なデビュー録音ですが、DGとしては続けてベートーヴェンを録音しなかったのはまで時期早尚と判断したのでしょう。下の演奏はこのデビュー盤ではなく、2015年の全紙ュゥによる配信音源です。
続いて演奏されている交響曲第7番になると,第1楽章の冒頭から,オケの 響きに透明感があって,スカッと晴れ渡っているのが印象的です。まあ、Poco sostenutoですからそれほど重くならないテンポが最適なのでしょう。意外にもこのテンポ、カラヤンの2回目の1976年の店舗と頬同一です。ただ一つ不満なのはテインパニの音の扱いです。流石に最近の傾向の頭の小さいマレットの乾いた音ではなくしっかりとした音を拾っているのですが、どうもボンボンと響いて浮いています。カラヤン/ベルリンフィルのようなどっしりとしたティンパニの響きがないのが一つ弱点です。ここでの木管のソロは生き生きとして見事ですし,力感がありながらリズムのキレとフットワー クはなかなかのものです。
第2楽章は,初演当時からアンコールされるほど旋律美に優れた音楽で、ここでも「不滅のアレグレット」と言われるように比較的落ち着いたテンポと、強弱の幅の大きいダイナミクスの中で奏でられる,明朗で愉悦感のあるフレージングが大変に新鮮です。ここてはいたずらにテンポを揺らすことなく美しい弦の弱音で紡いでいます。
第3楽章においても、持って回ったところのないストレートな表現で,すっきり鮮やかにリズムを刻んでおり,軽く跳ねるようなフレージングも心地良い ですし、トリオの全奏のところでの壮麗な響きも印象的で心沸き立つ精力的な演奏が堪能できました。
第4楽章に入った途端テンポの速さに一瞬驚きましたが、大変明瞭でキレも良く強弱の表現も巧みですし,たたみかけるような和音の刻みやアタック のスピード感は大変スリリングで、一気呵成に楽章を駆け抜けていきます。まさに 息を呑む思いで聴き入ってしまいました。 実演でもこの第3楽章と第4楽章は間髪を入れずまるでアタッカのように演奏されるのがよくありますが、このCDでもそういう編集がされています。5番の第3楽章と第4楽章を退避させる意味でもこれは効果的な演出なのでしょう。
このCD、シモンボリバル交響楽団の実力を知らしめるには格好のデモンストレーションになったのではないでしょうか。ただ、今後のこのオーケストラとの関わりはベネズエラの内政の混乱との絡みで余談の許さないものがあり、ドゥダメル自身も2026年シーズンからはニューヨーク・フィルハーモニックに拠点を移すことによる環境の変化をどのようにオペレーションしていくのか今後に注目したいところです。