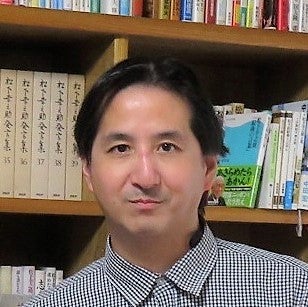【松下幸之助、創業者、名経営者、政治家に学ぶ】
松下幸之助はじめ、明治、大正、昭和の創業者、名経営者、政治家の生き方に学ぶ
プロフィール
最新の記事
テーマ
カレンダー
月別
ブログ内検索
2025-03-16 11:50:02
第404回【稲盛和夫哲学の源流を探索】
テーマ:ブログ稲盛和夫さんは自身の経営について
「私の経営についての考えは、松下幸之助さんの考え+禅宗(ぜんしゅう)の教え÷2」
と述べています
稲盛さんは、全ては心の反映であると言いますが
心について松下幸之助さんはこのように述べています
「自分の周囲にある物、いる人、これすべてわが心の反映である。わが心の鏡である。すべての物がわが心を映し、すべての人が、わが心につながっているのである」
臨済宗の住職、平井正修氏の著書『禅がすすめる力の抜き方』にはこのように書かれています
「一切唯心造(いっさいゆいしんぞう)」という禅語があります。読んで字のごとく、すべては心がつくり出したもので、あらゆる存在や現象は心の働きの反映であるという考え方です」
稲盛和夫さんは晩年の著書『心。人生を意のままに』でこのように述べています
「人生で起こってくるあらゆる出来事は、自らの心が引き寄せたものです。それらはまるで映写機がスクリーンに映像を映し出すように、心が描いたものを忠実に再現しています」
稲盛和夫さんの経営哲学がどこからきたのか
その多くが松下幸之助さんの経営哲学と禅宗の教えで説明ができるのではないかと思い
最近、研究を進めております(^^)/
2025-03-11 13:13:34
第403回【初めて亭主(ていしゅ)を経験】
テーマ:ブログ松下幸之助さんが茶人で毎日お茶を点てていたことから
私も昨年の10月から毎日お茶を点て145日続けております
そして初めて亭主(お茶を点てる人)としてお茶を出しました
お客(お茶を飲む人)をしていただいたのは
松下政経塾22期生で島根県の益田市長をされ
現在はデジタルサイネージ関連のベンチャー企業で執行役員をされている福原慎太郎さんです
福原さんは松下政経塾時代に茶道を習われており
茶道をしていて良かったお話をしてくださいました
ある支援者のところに行くと
上に松。下に鯉が描かれている掛け軸があった
思わず「この掛け軸は何ですか?」
と聞いたら
「松と鯉で松鯉(しょうり)。今日はあなたの勝利を祈願してこの掛け軸をかけました」
と言われたそうです
「茶道をしていたので何となく掛け軸が気になり聞いたけど」
「もし茶道をしていなければ掛け軸には全く目もくれず素通りしていたと思う」
とのことでした
いい話を聞いたと思い
私が所属している茶道の先生や茶道を習っている人達のコミュニティで
この掛け軸の話をシェアしたところ
「胸が熱くなる良い話しですね」とみんな感動しておりました
福原さんが松下政経塾に入塾された頃は
松下幸之助塾主が亡くなり10年以上がたち
今思えば松下塾主の研究がとても少なかったように思うと、当資料館に来てくださいました
おもに松下塾主の哲学の根幹「新しい人間観」や「無税国家」について話し合いました
やはり松下幸之助さんが提唱された無税国家を今こそ目指さなければならないと強く思いました
財政、税制、予算についても勉強していこうと思います
福原さん有難うございました
2025-03-06 09:54:25
第402回【政経塾の黎明の鐘にまつわる謎】
テーマ:ブログ茅ヶ崎市にある松下政経塾でいちばん高くそびえたつのが黎明(れいめい)の塔で
この塔のてっぺんにあるのが黎明の鐘である
この黎明の鐘は松下幸之助さんが最もこだわったものかもしれない
長崎大浦天主堂はじめノートルダ寺院、チューリッヒなど世界中の素晴らしい鐘を
14種類も聴いてつくったのが黎明の鐘である
鐘の音色について松下さんの要望は高いものであった
「悪心が良心にかわる。心が洗い清められる澄んだ音色にしてほしい。日本を立て直すために襟を正すような清らかな音色にすること」
ところがこの黎明の鐘を鳴らしたのは2ヵ月ほどで
その後は今にいたるまで録画した音色を放送で流しているという
なぜか
鐘の音がうるさいと近所に住む人や団地に住む人達から苦情がきたのだという
「赤ちゃんが目を覚ます」
「夜勤明けに眠れない」
と理由はさまざまであった
そして苦情を言ってきた人には
私の最も好きな作家の一人である経済小説のパイオニア、城山三郎さんがいたという
城山さんは政経塾の近所に住んでいたのだ
最近、図書館でいらなくなってタダでもらえる本があるので
35年前に発刊された『文化の星』という本をもらった
一見、なんの関係もなさそうな本に思わぬことが書かれているものである
この本に城山三郎さんが郷里の名古屋から茅ヶ崎に引っ越してきた理由が書かれており、城山さんが鐘の音に怒った理由がわかった
城山さんは「輸出」で文学界新人賞を受賞した
この賞でにわかに身辺がにぎやかになった
無名に戻りたい。そのために名古屋を離れたい。できれば海の見える家に住みたい
そして茅ヶ崎に引っ越してきたのである
10階の部屋からは相模湾が見える
季節により海の色も変わる
沖合を通る船も見える
晴れた日には伊豆大島が見える
ところが、政経塾ができてから朝、夕に毎日、鐘の音が鳴るので
「うるさい」となったのであろう
そしてこの『文化の星』には驚くべき衝撃的なことが書かれていました
なんと、城山三郎さんの茅ヶ崎の住所が書かれています
今度、政経塾にいった時はこの住所のところに必ず行こうと思う
城山さんが亡くなり18年が経ちますが、跡地がどうなっているかがとても気になります(^^)/