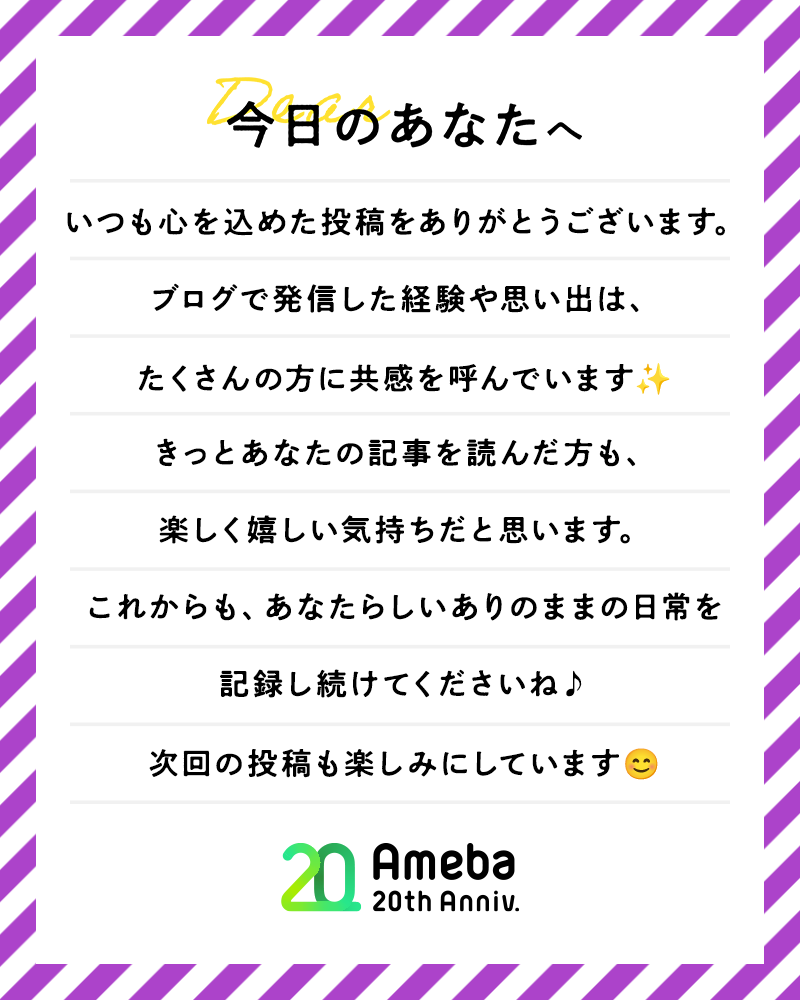久々の写真投稿。
毎年恒例の小松川千本桜まつりに行って来ました。
今年は開花が遅れて、イベントの当日はほとんど蕾だったり、開花したばかりの桜が多かったんですけど、品種によってはピンク色の花が咲いていたり、膨らみ始めた蕾と開いたばかりの花が並んでいたり、良い写真が撮れました。
淡いピンクの桜。花弁が細くて可憐な感じ。
少し濃いピンクの桜。花弁が🌸っぽいから、上の桜より色が濃く見えるのかな?
白い桜は大島桜かな?
自分の地元ではないのに、毎年このイベント来るのは、江戸川区平井のご当地キャラ「こーた」くんに会うためでもあります。
毎年、この坂道の両側には満開の桜が咲くんですけど、今年は蕾のまま。
去年はこんな感じでした。
桜の花の蜜を吸いに来たのかな?
桜以外にも、花壇の花が綺麗に咲いていました。
来年は、満開の桜の下でこーたくんの写真を撮りたいなぁ。