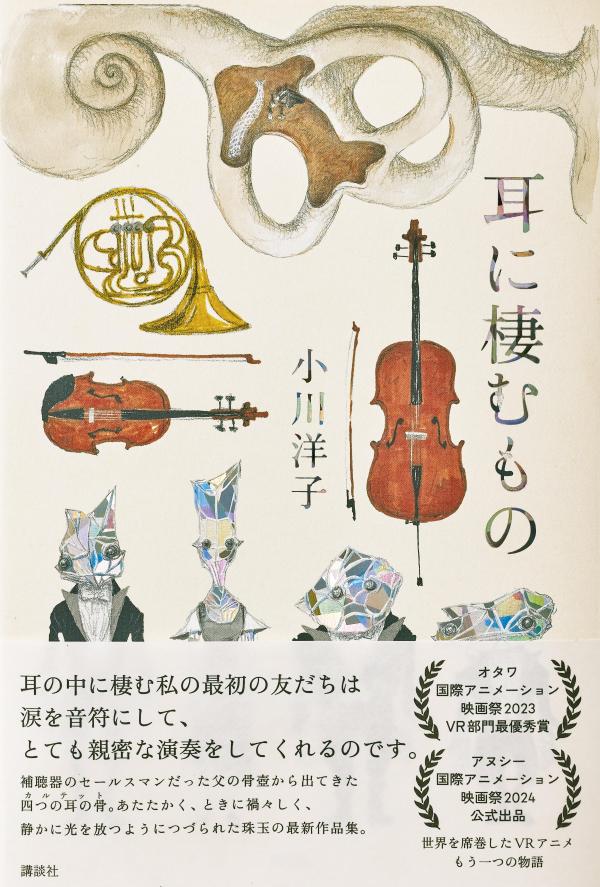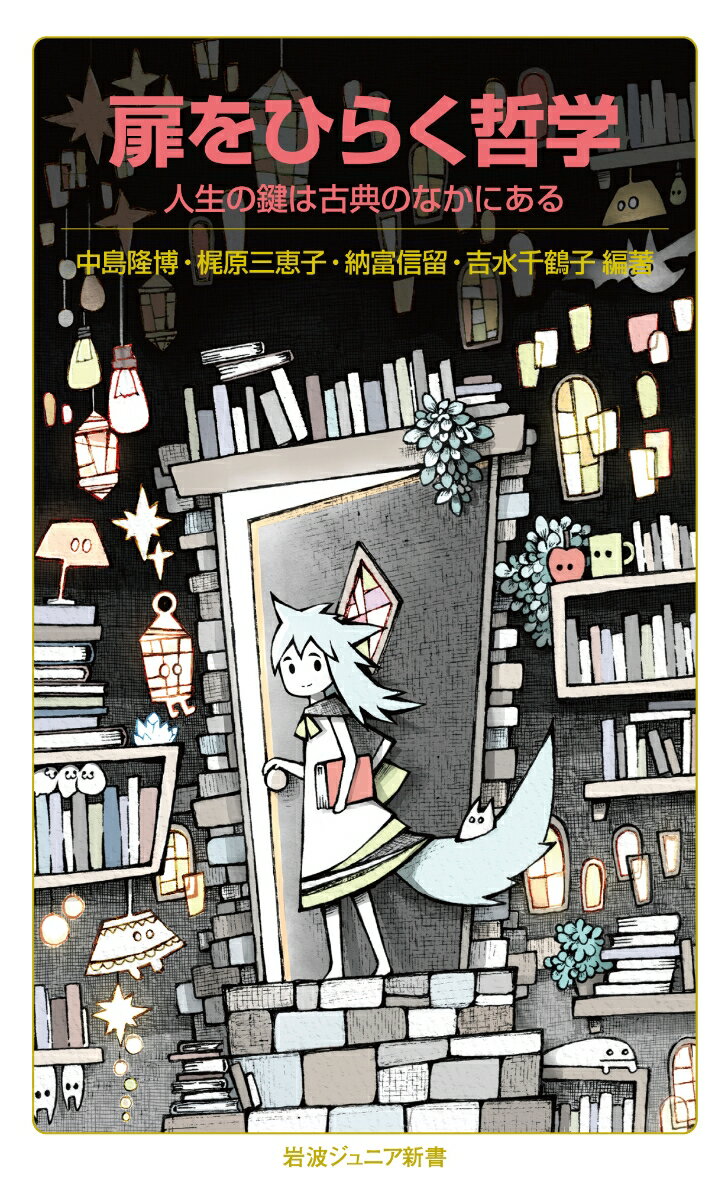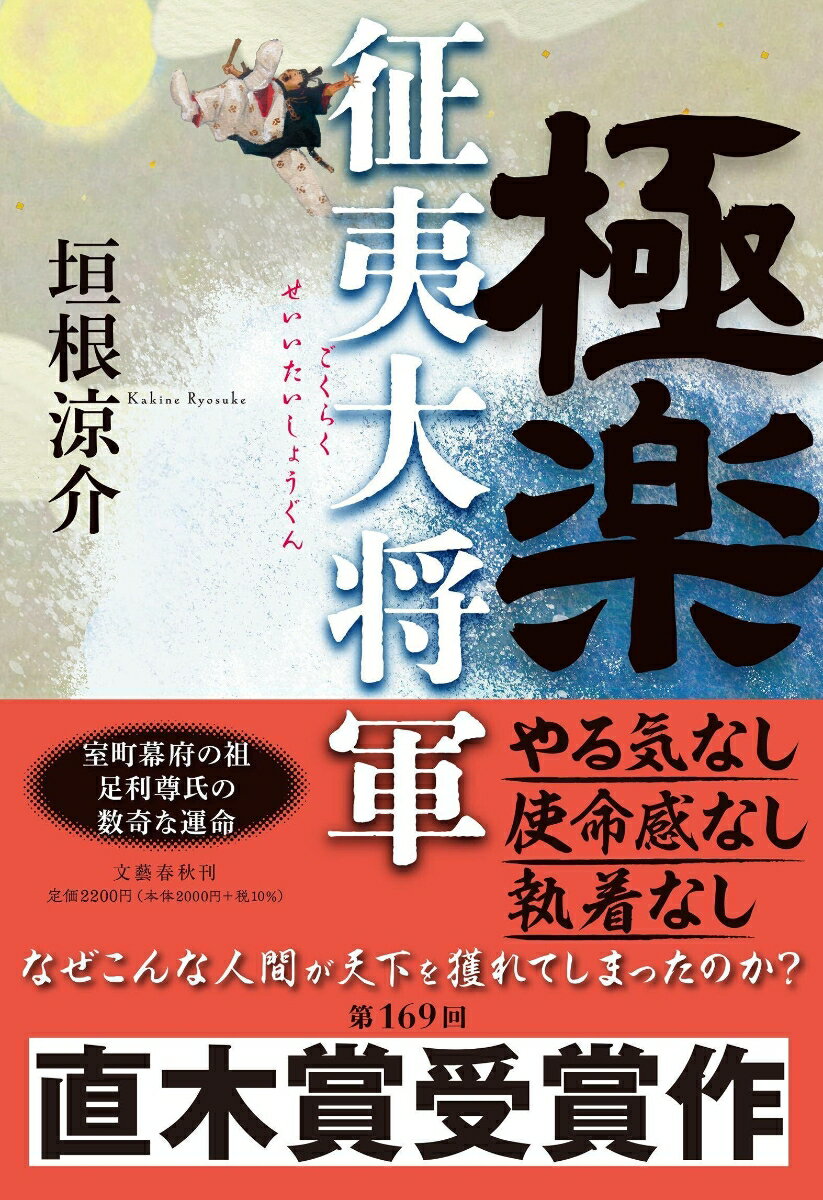本日2回目の更新です。
小川洋子さんの『耳に棲むもの』を読了しました。
私がパーソナリティを務めている みのおエフエムでは毎月、講談社さんのご提供で新刊本を1冊ご紹介し、その本をリスナーさんにプレゼントしています。
「ブックプレゼンター」というコーナーです。
小川洋子さんの『耳に棲むもの』は10月のブックプレゼンターで紹介しました。
しかも小川洋子さんへのスペシャルインタビュー付きで!
小川洋子さんとお話ができる?!と 大喜びしたのですが、スケジュールの問題で、みのおエフエムの別のスタッフがインタビューさせていただきました。
とても興味深いお話でした。
後日、みのおエフエムのYouTubeチャンネルにアップされましたら、ご案内しますね。
小川洋子さん『耳に棲むもの』
まずはタイトルについて。
『耳に棲むもの』とは何とも不思議なことばです。
耳に棲む?何が?もしかしたら比喩かな?
色々なことを考えてしまいます。
小川洋子さんの小説には時々、こういうことがあります。
常識では考えられないようなことが、当然のように静かに語られることが。
『耳に棲むもの』はまさにそれでした。
この小説には5つの短編が収められていまして、冒頭にその不思議が語られます。
補聴器のセールスマンだった父が亡くなった。いつも出張ばかりしていた父だった。
納骨を翌日に控えた日、昔から家族全員がお世話になっていた耳鼻咽喉科の院長先生が最後のお別れに来てくれた。
父はこの院長先生のことを本当に信頼しており、風邪や胃が痛いといった専門外の疾患の時でさえ、まずはこの耳鼻咽喉科で院長先生に診察していただいていたものだ。院長先生はその度に、誠実に対応してくれたいた。そして父のことを、特別な補聴器セールスマンだったと評価してくれていた。
院長先生は父の骨壷から、4つの骨片を取り出してくれた。
それはただの骨片ではなく”耳に棲むもの”だという。
”耳に棲むもの”は本来誰の耳にもいて、その人の心の声を発するものだという。ただ、その存在に気がつき、声(音)を聞き分けられる人は滅多にいない。父はそのものたちの声をちゃんと聞いていたらしい。それこそが優秀な補聴器セールスマンの証だったのかもしれない。
(小川洋子さん『耳に棲むもの』内「骨壷のカルテット」を私なりにご紹介しました。)
もう少し詳しく説明すると、耳に棲むものはカルテットで、その人が流した涙が音符になってできた楽譜を奏でるのだとか。
もちろん、最初から骨片だったわけではありません。
その人が生きている間は、耳の中に住んでいる”生き物”だったのですが、荼毘にふされてそれらも骨片になったのです。
なんと不思議なことでしょうか。
涙を音楽に変えて演奏するカルテットが誰の耳にもいるだなんて。
でもどんな不思議な設定も、小川さんの文章にかかると「そんなことがあってもおかしくないなぁ」と
思わせられるのが不思議です。
先ほども書きましたが、この本には5つの短編が収められています。
タイトルをご紹介しましょう。
骨壷のカルテット
耳たぶに触れる
今日は小鳥の日
踊りましょうよ
選鉱場とラッパ
(小川洋子さん『耳に棲むもの』 目次より引用)
いずれの短編にも登場するのが、補聴器のセールスマンだった男性です。
「骨壷のカルテット」では亡くなってしまっていますが、『耳たぶに触れる』以降は、補聴器セールスの出張先で起こった出来事が描かれていきます。
時系列でいうと、短編ごとに時を遡っているようで、「踊りましょうよ」では、どうやら将来妻になる人との出会いが描かれていました。
そして最終章「選鉱場とラッパ」ではぐんと遡り、”補聴器のセールスマンだった父”の子ども時代が描かれていて、彼が最初にカルテットの奏でる音楽を聴く場面が出てきます。
補聴器のセールスマンだった男性が出会う人々、遭遇する場面はどれも不思議なものばかり。
「今日は小鳥の日」などは可愛らしいタイトルとは逆に、グロテスクですらありましたし、彼の子ども時代が描かれる「選鉱場とラッパ」などは、心がザラザラするような物語でした。
読み終えた時に、爽快感はありません。ただ、シーンと心が静かになる感覚が残りました。
いつもながら小川洋子さんの小説には不思議な気持ちにさせられます。
私が担当できなかった、みのおエフエムでの小川洋子さんインタビューでは、私からの質問を一つ、預かってもらっておりました。
「小川洋子さんの小説には、現実にはありえないような不思議な設定があり、しかも小川さんの文章にかかると、こんなことがあってもおかしくないかもと思わせられます。そういう不思議な世界が小川さんの中にあるのでしょうか」
これに対する小川洋子さんのお答えは
「自分の中にあるものを書くのではありません。それらはいつも私の外側にあります」でした。
(短くまとめています。正確には違う言い回しでした)
このお答えには目から鱗が落ちる気持ちでした。
確かに、自分の中にあるものを書いていては、いずれネタ切れになるはず。
外側の世界を見て、そこから何かを生み出すからこそ、新しい作品を生み出していけるのですね。
不可思議な世界ではありますが、難解な言葉はありません。
短編ごとに区切ることができるので、時間に余裕がない方にも読みやすい小説ではないかと思いました。
ちなみにこの作品は、小川洋子さんが脚本を手がけたVRをもとに作られた小説なんですって。
動画が先にあって、そこから小説が生み出されたということです。
この動画はオタワ国際アニメーション映画祭2023のVR部門最優秀賞を受賞しました。
とても短いので、よろしければご覧になってください。
みのおエフエム ブックプレゼンター 小川洋子さんインタビュー
ーーーー準備中ーーーー
声の書評 stand.fm
アプリstand.fmでは声の書評をお送りしています。
いつもはこのブログとは少し違う切り口で同じ書籍についてお話ししていますが
今回は声の書評はお休み。
よろしければ、これまでの声の書評をお聞きください。
↓
stand.fm「パーソナリティ千波留の読書ダイアリー」
ブログランキングに挑戦中
もし記事を気に入っていただけたなら、
ポチッとクリックよろしくお願いします。
↓
 扉をひらく哲学 人生の鍵は古典のなかにある (岩波ジュニア新書 968) [ 中島 隆博 ]楽天市場小難しい本かと思ったらそうではなかった。青少年の悩みに対して、解決のヒントを古典に見つけたらどう?という話。
扉をひらく哲学 人生の鍵は古典のなかにある (岩波ジュニア新書 968) [ 中島 隆博 ]楽天市場小難しい本かと思ったらそうではなかった。青少年の悩みに対して、解決のヒントを古典に見つけたらどう?という話。 極楽征夷大将軍 [ 垣根 涼介 ]楽天市場これまで足利尊氏について全く知らなくて、とても面白く読めた。 人の上に立つ人はコセコセしていちゃダメなのね。
極楽征夷大将軍 [ 垣根 涼介 ]楽天市場これまで足利尊氏について全く知らなくて、とても面白く読めた。 人の上に立つ人はコセコセしていちゃダメなのね。 さまよえる神剣 [ 玉岡 かおる ]楽天市場幼い安徳天皇とともに壇ノ浦に沈んだはずの草薙剣が四国にある?!歴史小説であり、冒険小説であり、ファンタジー小説でもある。
さまよえる神剣 [ 玉岡 かおる ]楽天市場幼い安徳天皇とともに壇ノ浦に沈んだはずの草薙剣が四国にある?!歴史小説であり、冒険小説であり、ファンタジー小説でもある。 777 トリプルセブン [ 伊坂 幸太郎 ]楽天市場伊坂幸太郎さんの殺し屋シリーズ。人と比べずに生きていこうというメッセージあり。殺し屋シリーズに人生を教わるとは。
777 トリプルセブン [ 伊坂 幸太郎 ]楽天市場伊坂幸太郎さんの殺し屋シリーズ。人と比べずに生きていこうというメッセージあり。殺し屋シリーズに人生を教わるとは。