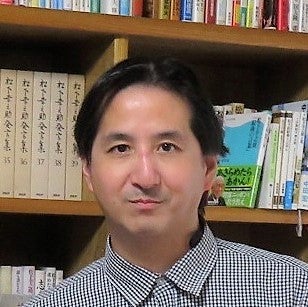【松下幸之助、創業者、名経営者、政治家に学ぶ】
松下幸之助はじめ、明治、大正、昭和の創業者、名経営者、政治家の生き方に学ぶ
プロフィール
最新の記事
テーマ
カレンダー
月別
ブログ内検索
2009-10-09 23:59:05
第60回_製薬産業は情報産業である
テーマ:製薬松下幸之助や本田宗一郎は生前、メーカーはどんなにいいものを作ったとしてもそれを世に知らしめなければ何の意味もないと言っていたといいます。つまりどんなに性能のいい家電製品や自動車を作ったとしてもその良さや特徴が消費者に伝わらなければ売れないということなのでしょう。それを考えると情報伝達のツールである広告・宣伝やPRがいかに大切であるかが分かります。
特に家電業界や自動車業界以上に情報伝達が必要になるのが製薬産業ではなかろうか。たとえば目の前に白い錠剤が一粒あったとしても、その錠剤が何に効くのか、適応症・禁忌症は何か、用法・用量は、相互作用はといったことが分からなければ何の役にも立たない。たった一粒の薬にも、たくさんの情報が必要です。白い錠剤は、情報と一緒でなければ何の価値もない。そう考えると製薬産業は情報産業ともいえるかもしれません。
アボット・ラボラトリーズ社の創業者、ウォレス・カルビン・アボットは自社製品を当時広く医師に読まれていた、メディカルワールド誌に製品広告を載せ大ヒットさせた。それから自身が発行した100ページほどのアルカロイド療法に関する無料の小冊子や、製品カタログをアメリカ、カナダの医師向けに配布した。その後、1891年アルカロイド治療誌を買収し同年クリニックパブリッシングという出版社まで設立し、これらのことが功を奏しアボット社は売上をどんどん伸ばしていった。
1880年代後半ジョンソン&ジョンソンは『殺菌による外傷治療の新方法』という本を出版した。この本は400万部も売れ、ジョンソン&ジョンソンの強力な販促ツールになっただけでなく、アメリカ中で消毒操作の標準テキストにもなった。
漢方の津村順天堂(現株式会社ツムラ)の創業者、津村重舎は1895年(明治28年)に、日本初のガスイルミネーション看板を店舗に取り付けるなど斬新なアイディアで広告、販売戦略を進め後にPRの神様と呼ばれるようになった。
このように製薬産業の発展史をみていくと情報伝達力のある企業が皆発展していることが分かってくる。製薬産業は研究開発力の勝負であり情報伝達力の勝負ともいえるだろう。
日本では医療用医薬品はテレビCM等の宣伝ができない。いわゆるMRといわれる医薬品のセールスマンが医師や医療機関に医薬品の情報を伝達しています。一昔前は接待が多かったことからMRは胃袋の勝負とも言われたが、MRほど伝達情報能力を求められるセールスもないのではなかろうか。実際にMRは知的でコミュニケーション能力の高い人達が非常に多いです。しかし世間的にあまり認知されていないのが気の毒である。
文責 田宮 卓
AD
2009-10-01 23:55:42
第59回_ハンク・マッキンネル_世界のトップ企業の経営者に必要な条件は理想的な外交官の素養
テーマ:製薬「世界各地を訪れる機会に恵まれ、各国の大統領や首相、そしてネルソン・マンデラやU2のボノなど偉大な人々と知り合う幸運にも恵まれた。世界のトップクラスの創造的頭脳を持つ人達と一緒に働くことができたのも、この仕事に就いたおかげである。健康で長生きすることに役立つ薬の開発や普及に貢献できることを、私は誇りに思っている。私にとって、これ以上に充実した人生は考えられない。」こう語ったのは2001年に世界最大の製薬メーカー、ファイザーの会長兼CEOに就任したハンク・マッキンネルである。
戦後のわが国での外務省の新人研修で「外交官というのは、外交、政治、経済、哲学、歴史、文学、芸術が分かって人間を完成させ、その人間的魅力で相手とわたりあう仕事である」と教えていたという。これはあくまでも理想でしょうが、実際に世界的な大企業のトップともなると理想の外交官としての素養が求められるようだ。すなわちマッキンネルのように世界各地の政治家や経済人や文化人と話が出来るだけの知識や教養を持っていないととても務まるものではない。
戦後の日本人でそういった意味での最高の国際人といえばまず名前があがるのが石坂泰三(東芝社長、経団連会長、万国博会長等、歴任)であろう。世界各地に一流の人物を友人、知人に持っていた石坂は財界きっての教養人でもあった。
英語ならシェイクスピア、テニソン、エマーソン、カーライル、バイロン、スコット、ドイツ語ならゲーテ、シラー、アンデルセン等、全て原書を読破していたという。当時はあまり翻訳本がなかったこともあり古今東西の書物を原書で読破し教養を身につけていたといいます。
石坂の教養の深さに欧米人が驚嘆したエピソードがある。スコットランドを訪れた時のこと。石坂を招待してくれた英国の実業家と一緒に夜の散歩をしていた。月夜の晩だった。ゆっくりと歩きながら、石坂はスコットの「湖上の美人」の一節を朗々と吟じたのである。石坂と同道した英国人は驚嘆した。英国人でも滅多に諳んじている人がいないのに、東洋の実業家が英国の古典を朗々と吟じたのだから無理はない。逆に考えれば、こちらが外国人を地方に案内をしたら、その外国人がその地のゆかりの謡曲、民謡を唸りだすようなものだ。
スコットランドのような例はいくらでもあり、石坂はスイスではシラーの「ウィルヘルム・テル」の一節を披露し国際会議でやんやの喝采を受けたこともあった。かくして年ごとに、石坂の英語、ドイツ語の教養の深さは世界の実業家の間で有名であった。
会社は経営者の器以上にはならないと言われます。製薬業界で日本のトップ企業は武田薬品工業であるが世界ではトップテンにも入らず、17位(2007年度売上ランキング)である。グローバル化した市場の中で日本の製薬企業が生き残り、さらに世界を相手に戦うのであるならば、まずは経営者がマッキンネルや石坂泰三のように理想的な外交官としての素養を身につけることだろう。世界各地の要人から魅力的と思われる言語(知性、教養)をもたなければならない。
文責 田宮 卓
2009-09-24 23:52:44
第58回_加藤辨三郎_産業人が失いつつある精神
テーマ:製薬戦後は政治家も経営者も国民を飢えさせないことを第一に考えそれぞれの立場で日本の経済復興に全力で取り組んできました。そこには名誉欲、金銭欲といった私利私欲はあまりなかったでしょう。このことを医薬の分野で経済復興に貢献した加藤辨三郎(かとうべんざぶろう)という人物のエピソード通じて一例を述べてみます。
1950年(昭和25年)の夏、協和発酵工業(現協和発酵キリン)の創業者、加藤辨三郎は発酵バイオビジネスで世の中に貢献するという壮大のビジョンを携えアメリカに行った。目的は米国メルク社と結核治療薬ストレプトマイシン製造の技術導入に関する契約を結ぶためだ。契約の交渉は交渉というよりも先方の提案を丸呑みさせられる結果となった。
しかしこのことが、日本人の死亡率の最高が結核によるものであったのが、それを一挙に6位にまで下げることができた。協和発酵工業は利益を上げることが出来、日本の結核撲滅に大きく貢献した。
それから数年後の1956年(昭和31年)協和発酵工業はグルタミン酸製造法で画期的な発明をした。グルタミン酸はアミノ酸の一種で「味の素」の主成分である。味の素社は創業以来、これを小麦または大豆のタンパク質を塩分で分解して造っていた。
そこへ、協和発酵工業はそれと全く異なる方法を発明したのである。澱粉(でんぷん)または糖蜜とアンモニアを原料とした発酵法で造るのだが、分解ではなく合成によるものである。原料も安く工程も簡単なためグルタミン酸の原価が大幅に下げられることが予想された。
この発明が海外にもいち早く報ぜられ、数社から技術を買いたいと申込みが来た。その一社がメルク社であった。メルク社にはかつてストレプトマイシン製造の技術導入をした時の契約書を題目とアメリカとあるところを日本にすりかえた程度でそのまま提示した。メルク社は条件が厳しすぎるといったが、「これはかつてあなたがたが私を説得したそのままの条件ですよ。ご不満はよく分かるが、かつての私の不満も察してもらいたい」といったところ契約は原案がそのまま通った。こうしてわずか数年の間に協和発酵工業は外国から特許料を受け取る会社に成長したのである。
加藤辨三郎は食料とも、医薬品ともなるアミノ酸類が大量に安価に生産されることは将来、人間の生活の上で大きな貢献をするのにちがいないと確信したという。
医薬品産業の特色は研究開発指向という点であり、売上に対する研究開発費の比率が10%を超えるといわれ、全産業でトップクラスである。新薬(自社品)として市場に出る確率は、10000分の1~20000分の1ともいわれる。それだけ、ハイリスク・ハイリターンな産業といえます。リスクが高い分、成功すると新薬は何万人もの医師に匹敵をするともいわれるように人類に大きな貢献をもたらすことが出来ます。
しかし私利私欲に囚われた利益だけを考えての新薬の開発は必ず失敗します。過去の成功したケースを調べてみると、加藤辨三郎のように世のため人のためという純粋な精神が必ずあります。新薬にかかわらず、どの産業にもいえることだと思いますが、現代の産業人はこの純粋な精神を失いつつあるような気がします。
文責 田宮 卓