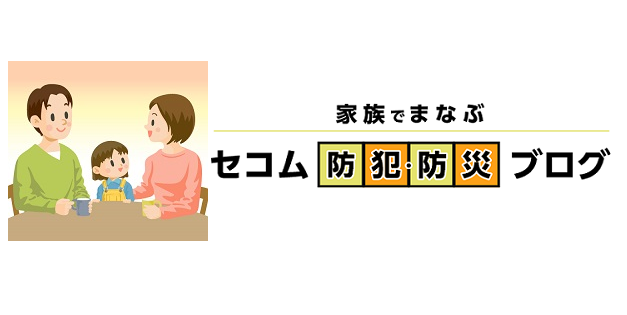私の防災・その459 「コンビニは我が家の冷蔵庫」にしてはダメ
自己紹介&ブログ紹介
先天性の遺伝子疾患と重度知的障害ありの娘(22歳)
特撮オタクの旦那(5歳年上)
アニメ&防災オタクの私(アラフィフ)
元々は娘の子育て中の記録として始めたブログですが、現在は主に障害児(者)家族の防災ブログとなってます
一昨日で阪神・淡路大震災から30年が過ぎました。
1/21迄は防災とボランティア週間で災害用伝言ダイヤルのお試しが出来ますので、まだ試したことがない方も、最近ご無沙汰だった方も是非大切な方とLet's Try!
離れて暮らすご家族とのコミュニケーション兼ねて如何ですか?![]()
30年前の阪神・淡路大震災以降、日本は地震の活動期に入ったとも言われていますね。
阪神・淡路大震災は活断層地震で、予測が難しいタイプの地震です。
そして、活断層は全国何処にでもあります。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250117/k10014695221000.html
南海トラフ地震臨時情報が出されたこともあってプレート境界型地震の方にばかり目が行きがちですが、
日本全国何処に居ても大きな地震に襲われる可能性は常にある
訳で。
つまり全ての家庭で地震対策&防災備蓄は必須
だと言うのに、何処かで大きな地震が起きる度に他の地域でも慌ててあれこれ買いに走る人が多数。
いきなりお店の棚から商品が消えますよね。
ネットでも防災関連商品が軒並み売り切れとなります。
それでも被害がなかった&軽かった地域は、お店が営業を継続したり再開するのも早いし商品が届くのも早いですが、被害が大きい地域だとどうでしょう。
お店も被害を受けて営業も出来なかったり、何とか在庫だけはと販売したとしても売り切れてしまったら新しい商品が入ってくる目処も立たない。
ネットで注文しても物流網がダメージを受けていると届けて貰えません。
「物が入ってこなくなるのは地方(田舎)だから」
「物が豊富な都市部なら何とでもなる」
と思っている人も居るかもしれませんが、実際には都市部の方が生産者より消費者の方が圧倒的に多いわけですから、
物流が途絶えた時には地産地消が出来ない分都市部の方が地方より影響が大きくなる
と考えた方が良いと思います。
時々都市部に住む人の中に「コンビニは我が家の冷蔵庫」だと自宅には殆ど買い置きせず必要な時に必要な分だけ買いに行けば良いと考えて生活している人がいます。
ですがそれは、商品が毎日滞りなく補充されている平常時だから出来ることです。
コンビニエンスストアは日常も災害時にも頼もしい味方になってくれる存在ではあります。
災害時にはコンビニエンスストアが帰宅支援ステーションに指定されていたり、「指定公共機関」として物資の調達や被災地への供給を担うことになっています。
災害時にも営業が継続できるような備えも行われています。
https://www.bosai.yomiuri.co.jp/article/1965
ですが、
3日前の1月16日阪神・淡路大震災から30年を迎える前日にコンビニエンスストア各社から
「巨大地震が発生したら被害が大きい地域では1週間程度は再開できない」
との見解が出されました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250116/k10014694961000.html
被害が長期化する可能性もあるので「各家庭で」食料などの備蓄をしておいて欲しいと言うのです。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/withbloomberg/1671769?display=1
「コンビニが“冷蔵庫”としてあるから、(備蓄は)いらないという方も実は多いが、(災害時は)どうしても物が届かないところが出てしまう」
営業を継続するための努力をしていてもやはり道路が被害を受けて使えなくなっていたり商品の生産が滞っていたりすればお店が開いていても商品が棚に並びません。
自分達が必要なものは自分達で充分に自宅に備えておいてくださいね。
私の防災・その458 非常用トイレの備蓄は最優先 何回分必要?
自己紹介&ブログ紹介
先天性の遺伝子疾患と重度知的障害ありの娘(22歳)
特撮オタクの旦那(5歳年上)
アニメ&防災オタクの私(アラフィフ)
元々は娘の子育て中の記録として始めたブログですが、現在は主に障害児(者)家族の防災ブログとなってます
昨日は阪神・淡路大震災から30年と言うことで父が被災した体験をもとに私に残してくれた教訓について書きました。
その中で父が人が生きていく上で何よりも大切だと力説していたのが「水」と「トイレ」でした。
避難所のトイレに汚物が山になってしまっている現実を目の当たりにした父は
特に女性や子どもは絶対に安心して用を足せるトイレが必要
だと繰り返し話していました。
トイレに行きたくなくて水分補給を控えて体調を崩してしまった人も見たそうです。
災害時にライフラインが途絶えると必ずトイレ問題が起きます。
「トイレパニック」と紹介する記事がありました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/cc57a77b8e888596efbac5ebe36c2f89538e086a?page=2
自宅のトイレが使えなければ避難所に行けば何とかなると考えている人もかなりの割合で居るようですが、
自宅のトイレが使えないのに避難所のトイレが使える訳がありません
また、トイレに行きたくなる度にわざわざ避難所のトイレまで足を運ぶのは無理があります。
避難所のトイレに集まる人が多ければ長蛇の列が出来ますが、切迫した状態で並べますか?
特に我慢が難しいお子さんや高齢者、頻尿、過敏性腸症候群の方などはなおさらです。
私自身薬で改善されていますが過活動膀胱で1日10回以上トイレに通っていたことがあります。
水洗トイレが使えなければ、避難所のトイレの衛生状態が適切に保たれているかもわかりません。
出来るだけ避難所のトイレに集まる人を減らしておく努力が必要なのです。
では、何回分を備蓄しておくべきなのか。
内閣府は1人1日5回を1週間分で35回は備蓄しておく様に呼び掛けています。
https://www.secom.co.jp/homesecurity/bouhan/bosai_bouka/bouhan067.html
ですが、私の様に過活動膀胱だったり過敏性腸症候群などでお腹を下しやすい人等はそれでは足りません。
自分がトイレに行く回数を把握して更に体調を崩す可能性も考慮して備蓄する数を決めた方が良いと思います。
1日7回行く人なら余裕を見て10回とかですね。
また、個人的には1週間分と言うのは最低量だと思います。
ライフラインが復旧してトイレで用を足せる様になるまでどの位時間がかかるかわからないからです。
収納スペースの問題も有るので難しいところですが、可能な限り多数備蓄しておく方が良いと思います。
非常用トイレだけ備蓄してもこれで安心して用を足せると言うものでもありません。
例えば停電していたら灯りも必要ですしね。
https://www3.nhk.or.jp/news/special/saigai/basic-knowledge/basic-knowledge_20220419_01.html
災害時の非常用トイレは基本的には便器に被せて使うものですが、股間に当てて用を足す簡易な物を非常用リュックに入れている方も多いのでないでしょうか。
便器が無くても使える便利アイテムですが、1つ気を付けていただきたいのが容量です。
少ない容量の物だとなかなかトイレに行けずギリギリの状態でやむを得ず使う場合、溜め込んだ大量の尿を受け止めきれない可能性があります。
実際に私自身が試した時に溢れました。
それ以降、私が備えているのは全て大容量(1000ml)の物です。
写真右側
また、我が家のもえもえは基本的には日中はトイレで用を足せますが、夜間は朝に間に合わない事があるので紙パンツ使用してます。
非常時にはトイレで用を足すことが出来ない可能性もあるので紙パンツの備蓄は日中も使用する前提で揃えています。
そして、もえもえは回数少なく量を溜め込むタイプです。
紙パンツは大容量タイプ(1000ml以上)を愛用。
災害時に長時間外出しなければならない場合はもえもえ用の紙パンツを私も拝借するつもりでいます。
予定通りの受診が出来なくて過活動膀胱の薬が切れる可能性も否定できませんしね。
短時間なら念のための尿漏れパッド(200~300ml)で充分かな。
嫌な話になりますが、避難所のトイレは性被害の現場になりやすいそうです。
こちらの記事でも触れてます
出来るだけ
避難所のトイレに行かずに済む備え
をしておくことと、
行かなければならない状況の時は
女性や子ども1人で行くことは避ける
ことをお勧めします。
衛生的で安心して用を足せる環境は人としての尊厳を守る意味でも絶対に必要です。
参考過去記事
どうぞ充分な備えをしてくださいね❗
私の防災・その457 阪神・淡路大震災から30年 父の残した教訓
自己紹介&ブログ紹介
先天性の遺伝子疾患と重度知的障害ありの娘(22歳)
特撮オタクの旦那(5歳年上)
アニメ&防災オタクの私(アラフィフ)
元々は娘の子育て中の記録として始めたブログですが、現在は主に障害児(者)家族の防災ブログとなってます
今日は私の父が被災した阪神・淡路大震災から30年。
昨日も書きましたが、私の父は自分の体験を隠すこと無く折に触れて話してくれました。
これから先大きな災害が起きて私が被災しても無事に生き延びられるようにと言う強い思い、愛情だったと思います。
自宅が倒壊したり家具が転倒して家族や当人が下敷きになり命を落としたり閉じ込められてしまった知り合いも何人もいますし、その現場にも足を運んでいます。
家族が下敷きになっても自力では救助も出来ず、救助活動中の消防隊に助けを求めても中から生存を知らせる声や音がしないからと立ち去られてしまった方もいます。
救助する側も全ての人を助けられる訳じゃないので苦渋の選択です。
生きていると確実に判断できる人から助けるしかないのです。
救助される側ではなく救助する側に回れる人が多ければ、少なくとも救助の必要がない人が多ければ、救助隊員にしか助けられない状況の人を一人でも多く助けられるかもしれません。
一級建築士でもあった父は被災する前から自宅の安全性には強くこだわっていましたから、耐震性の高い家に住んでいれば助かった可能性があるのにと非常に残念と言うか悔しい思いもしたようです。
家と言うのは命を守る器でなければならないとの信念があったと思います。
私たち夫婦が自宅を新築する時にも色々とアドバイスをくれました。
- 地盤調査はしっかりと、必要に応じて地盤改良もすること
- 基礎はベタ基礎
- 耐震性の高いメーカーで建てること
- 河川の近くの土地なので氾濫した時の避難場所に堤防よりも高い屋上を活用すること
- 家具の転倒防止をすること、特に寝室は安全な場所にすること
また、知り合いを探して訪れた避難所では
不特定多数の人達が狭くて寒い避難所でプライバシーなど無い状態で雑魚寝していたり、
混乱状態で物資も行き届かず、
断水したトイレは汚物が山になってしまっている
のを目の当たりにしています。
これは私も報道で見ましたが、断水したので飲み水が手に入らず壊れた水道管から道路に溢れた水を必死に汲んで飲み水にしようとしていた人もいます。
ですから、耐震性の高い住宅で避難所に行かずに過ごせる備えをする様に口酸っぱく言われました。
具体的には
- 水とトイレは絶対に食料も出来るだけ備えておくこと
- 支援物資は個人のニーズに合わせてはくれないから、もえもえが生まれてからはもえもえが必要なもの(食料等)を充分にストックしておくこと
- 電気、ガス、水道が止まっても生活できる知恵を身に付けておくこと
- 無駄と予備(余裕)は別物だから必需品は必ず多めに準備すること
等ですね。
その年の春に就職することが決まっていた私に仕事中に被災したら歩いて帰宅しなければならない可能性も頭に入れておくようにと話してくれました。
正直職場から歩いて帰るには距離があることはわかっていましたので、基本的には職場の安全が確認できたらその場に残って他の人と協力して過ごす方が良いと前置きした上でのことです。
被災した人同士の助け合い「共助」が一番早く一番大きな力になったことも身に染みていたからだと思います。
父自身の立場が当時職場のトップだったこともあり、動けるようになるとすぐ職場の人達の安否確認を行い、動ける人を集めて連絡がつかない人の情報収集や被害が大きかった人達の支援活動の指示をしたそうです。
阪神・淡路大震災の時には早朝で仕事中の人が少ない時間帯だったから自宅での犠牲者が多くあまり注目されていませんが、多くのビルも大きな被害を受けています。
ピロティ部分が潰れたり、鉄骨の継ぎ目部分が破損して途中の階が潰れて斜めに折れ曲がったり、道路を塞ぐ形で倒壊したビルもあります。
父が当時住んでいたマンションは新築物件だったので無事でしたが、震災直前まで住んでいたマンションは大きな被害を受けました。
建てられた時期、つまり新耐震基準を満たしているかどうかは大きな分かれ目になったようです。
その点、私の就職先がまだ新しいビルだと言うことも父にとっては大きな安心材料だったようです。
ですから、職場に留まる選択肢を最初にあげたのでしょう。
その上で言われたのが
- 歩きやすい靴で通勤するか職場に常備しておくこと
- 飲み物と軽食を通勤鞄に入れておくこと
- 職場から自宅までの徒歩経路がわかる地図を持ち歩くこと
今なら防災の基本、当たり前に聞こえるようなアドバイスばかりかもしれません。
でも、防災意識がまだまだ低かった30年前にこれだけのことを
自身の体験をもとに具体的な言葉で伝えてくれた
父は大切なことを見逃さない鋭い感覚を持っていたと思います。
1月17日と言う日は私にとって父の残してくれた教訓を大切にしていきたいと改めて感じる日なのです。