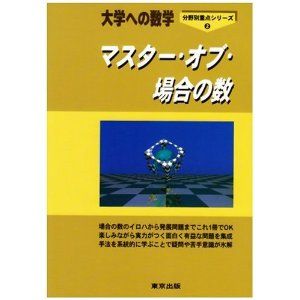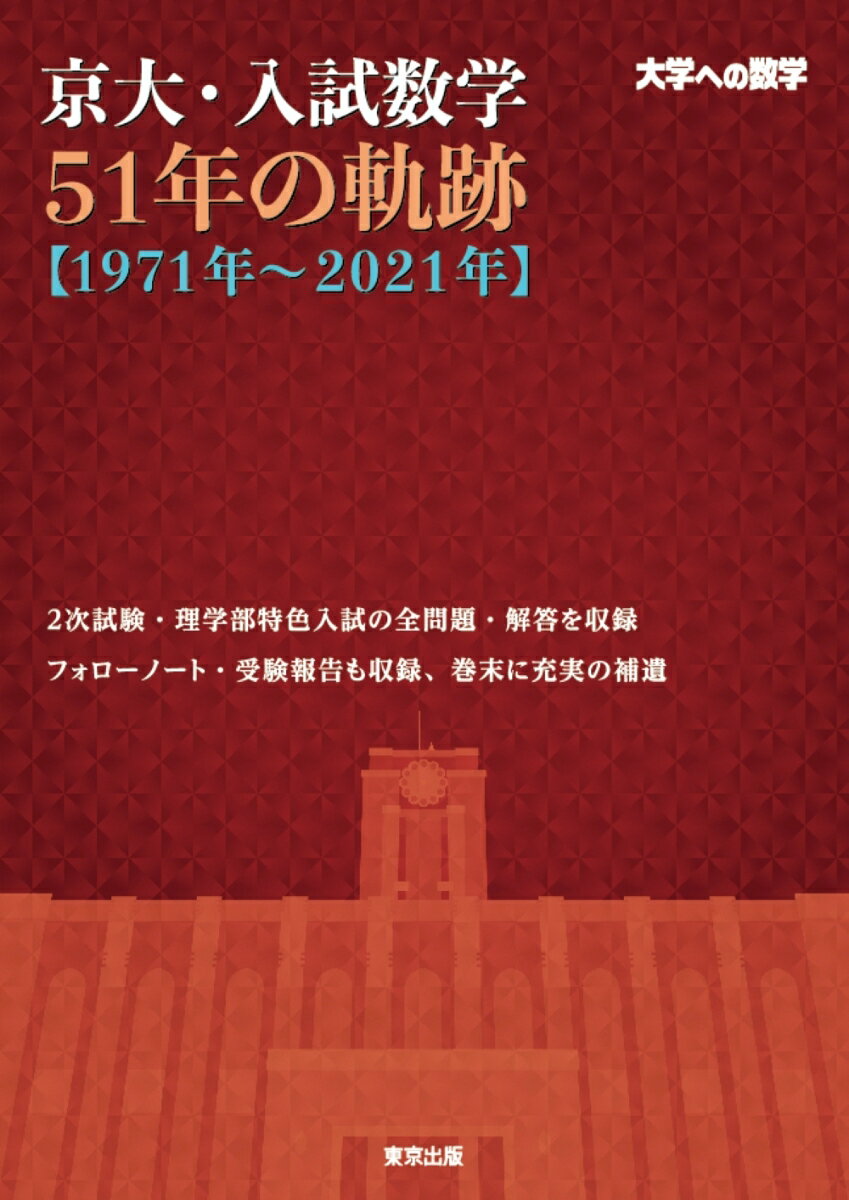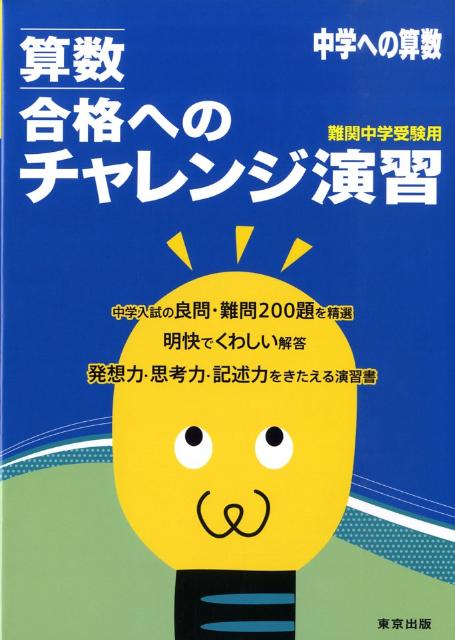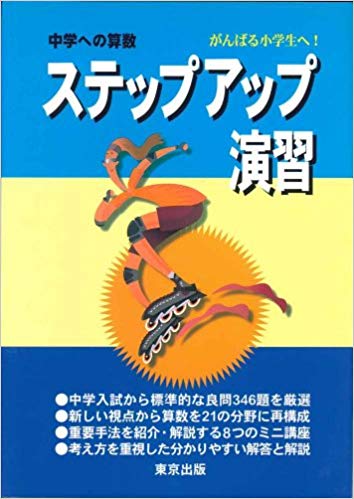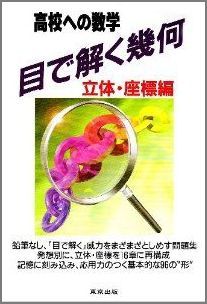nを3以上の整数とする。
(1)kを整数とする。k<a<b<c≦k+nを満たす整数a、b、cの選び方の総数をnの式で表せ。
(2)1≦a<b<c≦2nを満たす整数a、b、cのうち、a+b>cとなるa、b、cの選び方の総数をLとする。このとき、L>nC3であることを示せ。
(注)
2n→2×n
nC3→異なるn個のものから重複を許さず3個のものをとる総数(この記号を知っている小学生もいるでしょうね)
文字になっていて難しそうな感じがしますが、(2)はともかく、(1)は小学生でも簡単に解けるでしょうね。
(1)を小学生向けの表現にすると、1以上n以下の整数から、異なる3つの整数を選ぶとき、選び方は何通りありますかという問題にすぎませんからね。
(2)は(1)の誘導をどう利用するか考えれば解決策が見つけられるでしょう。
(1)の答えを問題文に出してまで誘導してくれているので、Lを直接求めようとしてはいけません。
詳しくは、下記ページで。