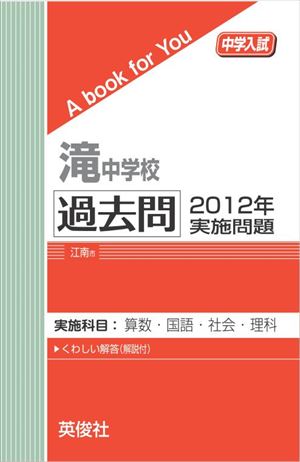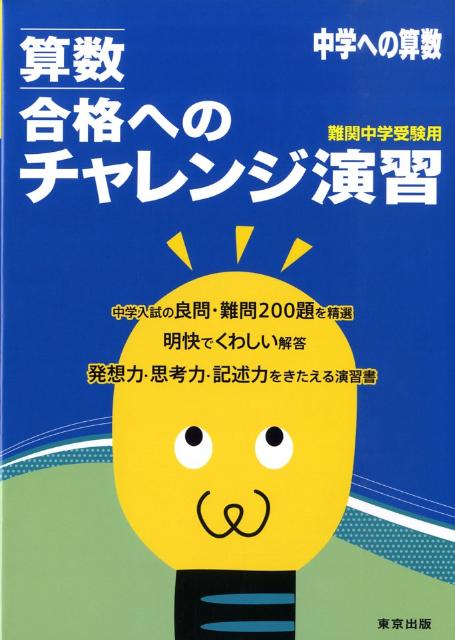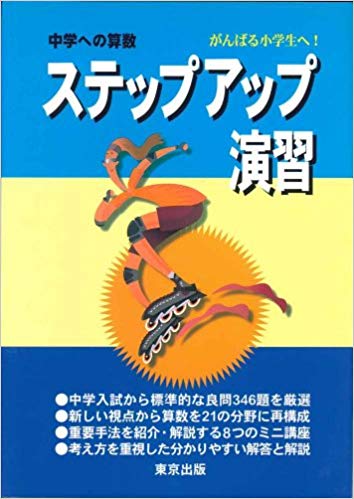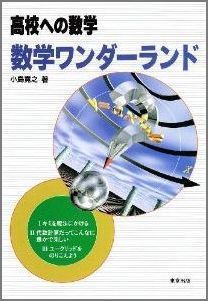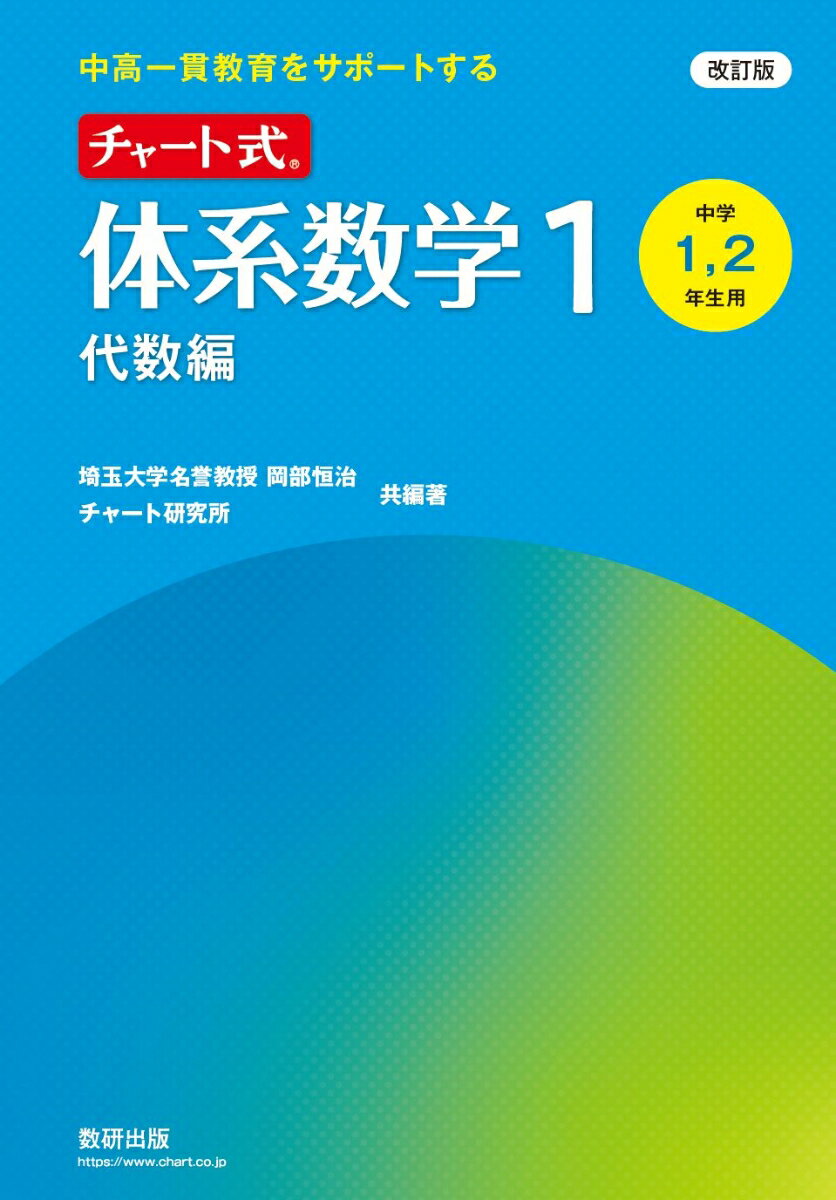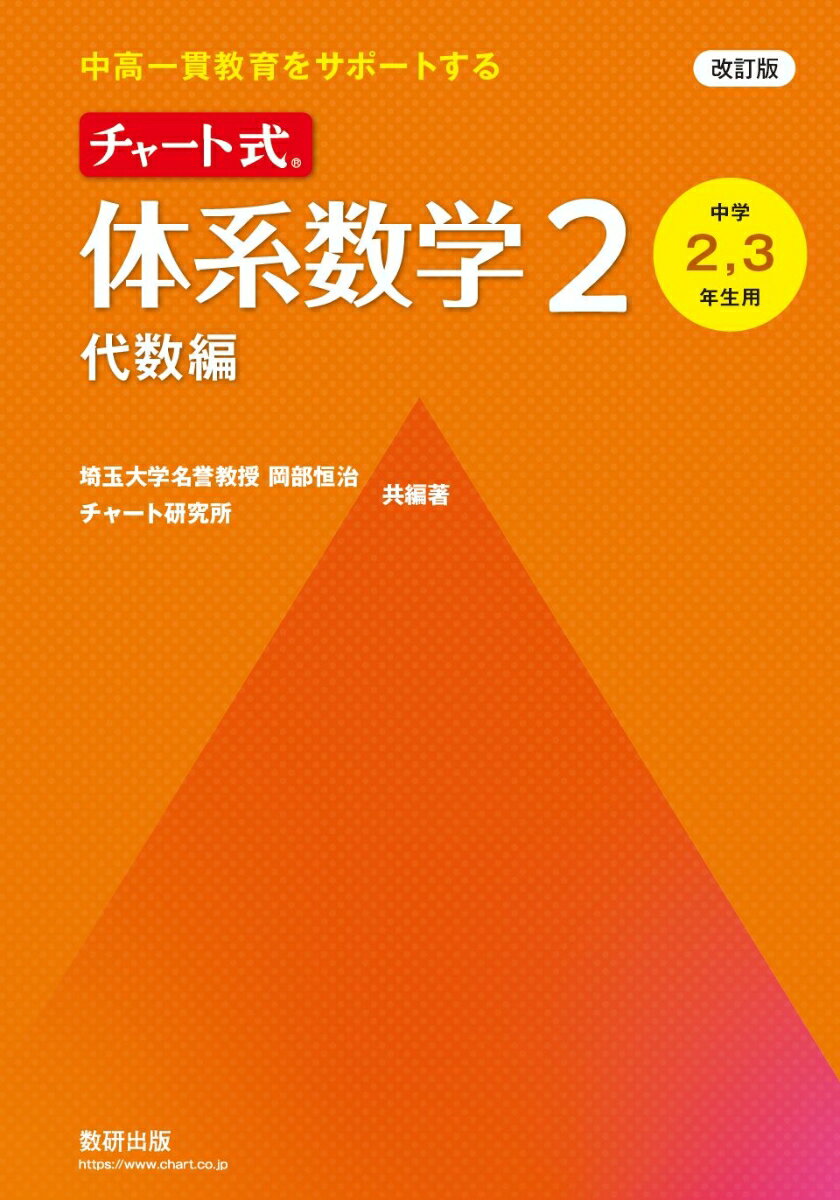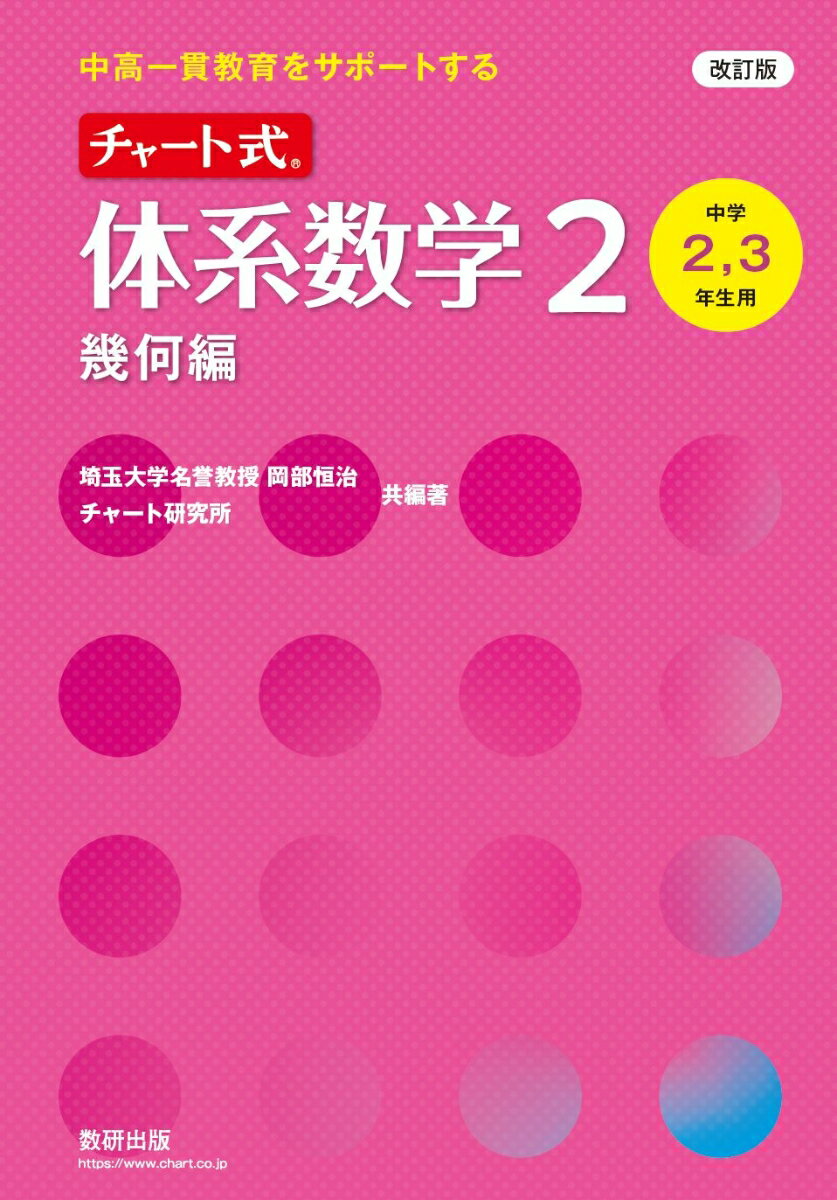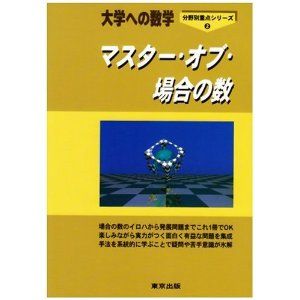数学の中学準備講座の授業の内容を少し紹介します。
(-14)×5÷(-7/2)-(-3)×(-14)÷(-6/11)
まずどこから計算? (-14)×5÷(-7/2)
符号は? マイナスとマイナスでプラス
じゃあ、あとは14×5×2/7を計算するだけで 20
次に、-(-3)×(-14)÷(-6/11)の部分の符号は? マイナスが4個でプラス
じゃあ、あとは3×14×11/6を計算するだけ 77
じゃあ、答えは? 20+77=97
ちまちまの計算式を書くのではなく、かたまりを見つけてその部分を一気に処理します。
まず、符号を判定して慣れ親しんだ小学生の計算にいち早く持ち込みます。
最初は符号のミスが起こりやすいので、それをしっかり確認することが大切です。
細かいことですが、(-3)×(-14)÷(-6/11)の部分で符号判定するのではなく、引き算の記号も含めて符号判定するのもポイントです。
(-6)5÷24×(-52)÷(-3)3÷(-10)2
まず、それぞれの符号は? マイナス、プラス、マイナス、マイナス、プラス
全体の符号は? マイナス3個でマイナス
じゃあ、あとは65÷24×52÷33÷102を計算して、マイナスをつけるだけ。
6=2×3、10=2×5だよね。2,3,5はそれぞれ何個残る? 2は分母に1個、3は分子に2個、5は0個
じゃあ、答えは? -9/2
指数については、例えば、(-52)と(-5)2の違いを確認するため、パーツごとに符号をいったん確認しています。
洛南高等学校2024年数学第1問(1)
{1-(2)3÷(-4)}×56÷(-7/8)+9を計算しなさい。
まず、どこから計算? -(2)3÷(-4)
符号は? マイナスが1個、3個、1個の合計5個でマイナス
数字は? 2
結局、{ }の中は? -1
次に、どこを計算? -1×56÷(-7/8)
符号は? マイナス2個でプラス
じゃあ、あとは56×8/7を計算するだけで 64
じゃあ、答えは? 64+9=73
(-5x3)×(-6y2)÷(-3x2y/2)+(-6x4y)÷(-xy)2×(-3x)
まず、どこから計算? (-5x3)×(-6y2)÷(-3x2y/2)
符号は? マイナス3個でマイナス
数字は? 5×6×2/3で20
文字は? xが1個、yが1個
それで? -20xy
次に、+(-6x4y)÷(-xy)2×(-3x)の符号は? マイナスが1個、2個、1個の合計4個でプラス
数字は? 6×3=18
文字は? xが3個、yが分母に1個
それで? 18x3/y
じゃあ、答えは書き並べるだけだね。
文字式になったところで、正と負の数の計算と指数の計算などの組合せにすぎません。
中学受験算数プロ家庭教師の生徒募集について
中学受験算数プロ家庭教師のお申込み・ご相談