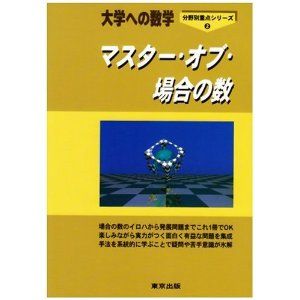〇と書いてあるカードと、△と書いてあるカードが、それぞれたくさんある。これらのカードを、△と書いてあるカードが隣り合わないように横一列に並べていく。例えば3枚のカードの並べ方は〇〇〇、〇〇△、〇△〇、△〇〇、△〇△の5通りである。次の問に答えよ。
(1)4枚のカードの並べ方が何通りあるか求めよ。
(2)5枚のカードの並べ方が何通りあるか求めよ。
(3)n枚のカードの並べ方がはじめて200通りを超えるときのnの値を求めよ。
高校入試だけでなく、中学入試や大学入試でも昔からよく出される問題です。
(出題例)
大阪星光学院中学校2007年算数第4問(ラ・サール中学校1996年算数1日目第5問の表記が変わっただけの問題)
上の出題例からわかるように、カードを並べるという表面的なことに本質があるわけではありません。
最難関中学校の受験生であればルーティーンワークと言える問題で、表(のようなもの)をかいておしまいです。
(3)はともかく、(1)と(2)は低学年の子でも解ける問題です。
因みに、この問題を小学生向けの表現にしたものを教え子に出して、まず1枚の場合から考えてみようかとヒントを出したら、次のようにして解けていました。
1枚・・・〇、△の2通り
2枚・・・〇〇、〇△、△〇の3通り
3枚・・・5通り
4枚・・・〇〇〇〇、〇〇〇△、〇〇△〇、〇△〇〇、△〇〇〇、△〇△〇、△〇〇△、〇△〇△の8通り
ここで、何か思うことはある?って尋ねると、2+3=5、3+5=8という規則性に気付いて、(3)も解けていました。
低学年の場合、こういう風に手を動かして解くということが非常に大切です。
受験生なら、この程度の問題はもっと理論的にさっと解けないといけませんが。
詳しくは、下記ページで。