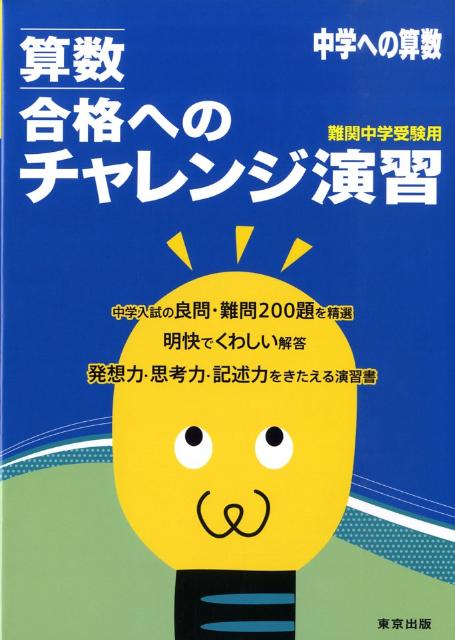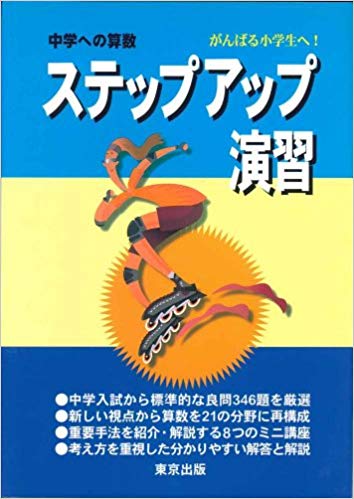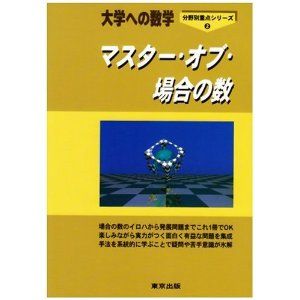0以外の数字を使ってできる整数を小さい方から順に1から999まで並べると、
1,2,3,4,5、6,7,8,9,11,12,……,999
となります。
これらの整数について、次の問いに答えなさい。
(1)整数は全部でいくつ並んでいますか。
(2)並んでいる整数をすべてたすといくらになりますか。
(3)並んでいる整数をすべてかけ合わせた整数を考えます。
(ア)0は一の位から続けていくつ並びますか。
(イ)一の位、十の位、百の位、…と順に見ていくとき、0以外で初めて現れる数字は何ですか。
(3)の(ア)までは標準的な問題で、洛南の受験生(特に合格最低点が高い女の子)なら、絶対に落としてはいけない問題です。
(3)の(イ)は算数オリンピックレベルの難問で、受験生にはきつい問題だったかもしれません。
実際、ジュニア広中杯(算数オリンピックの中1、中2版)のファイナルで同じような問題が出されたことがあります(ジュニア広中杯2012年ファイナル第2問(3)で、2012以上4024以下の整数の積の末尾に並ぶ0をすべて取り除いた数の一の位を求める問題)。
昔、ジュニア広中杯で入賞した教え子が、一応解けたけど、もっと簡単に解ける解法はないですかと質問してきた問題で、この問題を見た瞬間に面倒だなぁと思いましたから。
ジュニア広中杯の問題も洛南の問題も安易に一の位だけを考えると間違えてしまいます。
例えば、15×2=30の0を取り除くと3になりますが、一の位の数だけを考えた場合、5×2=10の0を取り除くと1となり、一致しませんからね。
5の倍数と偶数の積によって新たに生み出される「一の位」を考える必要があるわけです。
ただ、答えとして考えられるものは2、4、6、8であることがすぐにわかるので、適当に答えを書いて偶然正解した受験生が結構いたかもしれませんね。
検証していませんが、安易に一の位だけ考えたときに偶然正しい答えと一致していたらよくない問題でしょうね。
詳しくは、下記ページで。