SIMIAN MOBILE DISCO その1 ―3rd『Unpatterns』まで―
【お知らせ:2019.6.30】令和の大改訂の一環で、本記事に対する全体的な改訂を行いました。この影響で、後年にアップした記事へのリンクや、以降にリリースされた作品への言及が含まれる内容となっています。
趣旨説明
本記事では、SIMIAN MOBILE DISCO(シミアン・モバイル・ディスコ)の音楽を特集します。レビューの対象は、ナンバリングアルバム準拠で言えば1stから4thまでとなりますが、コンピレーション盤を含む「Delicaciesシリーズ」や、アルバム未収録の楽曲についても、網羅的にふれる内容に仕上げました。ゆえに文章量が多く、一つの記事では全てを書き切ることが出来なかったため、或いはYouTubeの埋め込みが多く、表示が過剰に重くなることを防ぐ目的で、記事を二つに分割しています。
副題にある通り、「その1」では3rdまでの3枚を、「その2」では4thおよびその他の作品群を、それぞれ取り扱う次第です。加えて、後者には2019年の改訂の際に、5thと6thをレビューした記事へのリンクを貼り付けてあるので、キャリアの殆ど全てに言及する内容だと捉えていただいて差し支えありません。
イントロダクション
それでは早速と1stのレビューに入りたいのは山々ですが、その前にSMDのアーティスト像を語るところから始めることをご了承ください。偏見に満ちた私感であると断っておきますが、日本に於けるSMDの評価は、1stと2ndを聴いただけの人に「あぁ、こういう感じね。」と思われて、今尚このイメージが幅を利かせているとの認識です。こう思う理由には、彼らがシーンの中でどのように頭角を現してきたかということが関係してくるので、そのあたりの事情も込みで詳しく解説していきます。
その内容を端的にまとめると、「商業的ムーブメントの功罪とEDM批判」となり、SMDに関係するとは言っても脱線の向きが強いため、早く本題に入ってくれとお望みの方は、ここをクリックすれば1stのレビュー位置までジャンプが可能です。なお、ここで僕が使う「EDM」というワードは、Wikipediaの「エレクトロニック・ダンス・ミュージック」のページで言うところの「狭義的な解釈」に基いたものであるため(=従来のダンスミュージックとは区別する立場)、この点に留意して読み進めてください。
フェーズⅠ:エレクトロ・ブームの中で
SMDの1st/2ndが出た頃の、つまり2000年代後半のダンスミュージックシーンに於いては、「エレクトロ」がフィーチャーされていたと記憶しています。Wikipediaの同名のページにも記述があるように、これは日本でのみ通用するジャンル名でしょうが、まだ「EDM」といった便利な言葉が国内で市民権を得ていない段階では、「厚みのある電子的なサウンドが特徴のポップなダンスミュージック全般」を指すものとして、確かに「エレクトロ」はキーワードでした。ロックとの親和性が高かったのも、その通りだと思います。
SMDもこのブームの中に表れた一組であるとの印象に関しては僕もご多分に洩れずで、海外アーティストに限っては、他にもJustice・Digitalism・Boys Noize・AutoKratz・Spirit Catcherあたりの有名どころは、好んでよく聴いていました。ここに名前を挙げた面々は、いずれも一定の成功を収めたと言っていいであろう存在ですが、同時に「消費された」感も非常に強くあるとの認識です。ブームには得てしてこういう面があるものですが、ブームの言わば「負の側面」の煽りをもろに食ったと感じられる点が、ゼロ年代後半に名を轟かせたエレクトロ勢に共通する哀しき特徴ではないでしょうか。
セールスや知名度の向上に関しては、ブームの恩恵を存分に受けていることは確かでありながら、ブームの中で消費されたという事実が、音楽的な質の評価にまで及んでしまっているのが、とりわけ不幸に思える所以です。両者は本来別個に論じられて然るべきものですが、現実的には一緒くたにされ、不当に低い評価を得る結果につながっている気がします。
「別にブームでも一定の評価を受けたのだから良いじゃないか」との考えにも一理ありますし、このブームがダンスミュージックにフォーカスした一過性のものであったならば、僕も態々「負の側面の煽りをもろに食った」とまでは言いません。問題はこの後に程無くして「EDM」が登場してきた;正確にはより包括的な概念「EDM」がジャンル名として台頭してきたことで、これが余計にゼロ年代後半エレクトロ勢を不遇だと位置付ける理由になります。
フェーズⅡ:EDMの出現
僕は元々、それこそ「EDM」なる形容が出てくるよりずっと前から、エレクトロニックなダンスミュージックが大好きです。当ブログのテーマ一覧から、界隈で有名なアーティスト名を選んで、そこにある記事を幾つかご覧いただければ、それが証左となるでしょう。
しかし、そんな僕にとっての「EDM」は未だに「謎の新興勢力」のイメージで、従来のダンスミュージックとは地続きではないところから生まれた、全く新しいものだと見做しています。勿論、使われがちな音やコード感などを含むトラックメイキングのハウツーは把握していますし、音楽のジャンル名とするよりは、オーディエンスの嗜好やライフスタイルなども含めた、カルチャー全体の呼称とするのが適切なのではと、結論じみたものも持ってはいますけどね。
Ⅰの内容と併せて言わんとしているのは、ダンスミュージックを受け入れる土壌は2010年代に入って更に拡大していったにもかかわらず、地続きではない新興勢力「EDM」の出現、延いてはこれを好む人々(主に作り手側の傾向)によって、それ以前のダンスミュージックの影が薄くなってしまったと感じるということです。前述の「狭義的な解釈」も、この手の反発意識があるからこそ出てくるものだと考えますが、このカウンター思考の根底には、何処か「ルーツの欠如」を覚えてしまうからといったもどかしさがあると、僕は分析しています。
この点はもう少し掘り下げて説明したいのですが…というか、下書きの段階では実際に作り手側の姿勢にフォーカスしたEDM批評の文章(=「本質」vs「現象」のダンスミュージック論)を長々と認めはしたのですが、内容が辛辣な上に脱線が過ぎるのでオールカットにしました。従って、批判には当たらない別のアプローチとして、EDMを好んで聴く層の;即ち受け手側の捉え方を推測することで、当該の不遇問題に迫ってみたいと思います。
流れの中で「こういう音楽がEDMだ」と言えるようなサウンドが確立してきて、それで初めてダンスミュージックを好きになった人達にとっては、従来のものは「踊れない音楽」と判断されているのではないでしょうか。従来のダンスミュージックには、電子音楽的な技巧性やリスニング志向の作り込みが窺え、その上でフロアを盛り上げる機能もあるといった、言わば二面性があると捉えていますが、対するEDMは完全フロア志向の音楽である面が強く、繰り返し聴いて細部のトラックメイキングに酔い痴れるといった、リスニングメインの味わい方には乏しい気がします。先に「オーディエンス」という形容をしたのも実は意図的で、EDMフリークに対して「リスナー」を持ち出すと、彼らは寧ろ嫌がるのではないかと忖度したからです。
80/90年代の古さならともかく、ゼロ年代のそれも後半の比較的新しいサウンドであれば、EDM好きの人でも取っつき易いのではと個人的には思うのですが、どうも実際にはそうでないと感じます。やはり「踊るための音楽」であることが殊更重要視されているのか、そもそも「聴く」という発想が希薄なのか、或いは単に知らないだけなのか(若年層は致し方ないとしても)。ともかく、ダンスミュージックであることには変わりないはずなのに、これまでに述べてきた「地続きではない」もしくは「ルーツの欠如」に起因するEDMの特殊性のせいか、シーンの狭間に取り残されてしまった感が、ゼロ年代後半エレクトロ勢の悲哀であるとまとめます。
フェーズⅢ:迎合か、解釈か、反発か
ここまでの内容を受けると、僕がEDMを毛嫌いしているように映るかもしれませんが、他のジャンルにEDM的なマナーを取り入れるといった、クロスオーバーなサウンドメイキングは寧ろ好みの範疇です。フロア向けのEDMをリスニングにも適うように昇華したものであれば、繰り返しの鑑賞にも耐えられる中毒性の高い音楽となるため、EDMを構成する要素自体は嫌いではないのだと熟々思います。
その証拠に当ブログ内を「EDM」で検索すれば、本記事のような批評的なものも勿論ヒットしますが、褒める文脈で登場させているものも幾つか発見出来るはずです。以降に例示する記事群も、特に「解釈」に分類しているものに関しては、EDMの昇華を好意的に見た結果の産物となります。
さて、新興勢力に対して既存勢力が取り得るパターンは、単純化して「迎合」と「解釈」と「反発」の三つが考えられるでしょう。本記事に於いては、「迎合」はEDMに寄せた、「解釈」は前述した通りの、「反発」はEDMに背いたサウンドメイキングを、それぞれ指しているとご理解ください。各パターンの根拠を具体的に説明し出すと長くなるので、2019年の改訂時までにアップした記事の中から、ワードとして「EDM」を出しているものに限って、それぞれに当て嵌まる記述を含んだエントリーへのリンクを貼り、それを解説代わりとします。
当然ですが、対象は10年代以降のエレクトロニックなダンスミュージックで、基本的には既存勢の動向に関するものです。ただし、以下の例示はあくまでも「僕がそう捉えている」だけの区分であるため、アーティスト側の姿勢を規定するものではない点にも留意していただけると助かります。また、僕は好きな音楽でない限りレビューの対象とはしないので、ここまでのEDM批評と矛盾するようにも思えるでしょうが、「迎合」についても批判の意味合いはありません。
例示
迎合の例(皮肉的な場合もあり)
■ 第3期のm-flo(2012~)
■ セブンスシスターズ「SEVENTH HAVEN」(2016)
補足:同曲はフェスアンセム的な迎合で、後発のエネミーユニット・AXiSによるアンサーソング「HEAVEN'S RAVE」(2019)はクラブバンガー的な迎合で、巧く対比させているとの分析です。
■ きゃりーぱみゅぱみゅ「原宿いやほい」(2017)
■ 忍迅雷音「Ninja Fanka」(2018)
補足:同記事内にはSkrillexに対する言及もあります。
解釈の例(結果としてEDMらしくなくても可)
■ KARAKURI「B.A.A.B.」(2015)
■ DÉ DÉ MOUSE『dream you up』(2017)
■ 中田ヤスタカ『Digital Native』(2018)
補足:ヤスタカワークスに関しては、CAPSULE『WAVE RUNNER』(2015)が解釈の好例だとの認識です。
■ パスピエ「始まりはいつも」(2019)
反発の例(明示的な否定でないものも込み)
■ The Chemical Brothers『Born in the Echoes』(2015)
補足:次作『No Geography』(2019)でも、カウンターの姿勢は維持されています。
■ 80KIDZ『80:XX - 05060708』(2017)
■ KOTOKO『tears cyclone -廻-』(2018)
反発の例に更に補足しますと、確かに存在する「EDMに懐疑的な流れ」に於ける最たるものは、グラミー賞も獲得したDaft Punkの『Random Access Memories』(2013)でしょう。同盤は最早「エレクトロニック」に対するアンチテーゼかもしれませんが、「お手軽に躍らせるだけがダンスミュージックの神髄ではない」ということを、EDMに傾くことなく証明した名盤であると絶賛します。寧ろもっと古いサウンドたる、ディスコ回帰的なアウトプットが印象深いものでした。
SMDの場合
超絶に長い前置きは以上で、ここからが本題となります。Ⅰの項で述べた通り、SMDもゼロ年代後半のエレクトロ・ブームの中に表れた一組であるとの認識に相違はありません。しかし、EDMが猛威を振るい始める10年代に突入してからのSMDは、上掲の三パターンに区分するなら、明確に「反発」のスタンスを突き付けていく存在になったと言えます。
その根拠となるのが、2012年リリースの3rdです。同作は当時の商業的な動きや流行りのサウンドに逆行した内容が特徴的で、それまでのSMDのイメージを打ち破る衝撃の一枚でした。より厳密には、2009年の2ndの限定盤(ディスク2)の内容が伏線的ではありましたし、2010年のコンピ盤で既に方向転換を図っていたとも分析可能ですが、ナンバリングタイトルのメインディスクの内容で比較するという基本に則れば、転換を迎えたのは3rdであると位置付けさせてください。
ともかく、転換後のことを語るには転換前から振り返るのがベターなので、以降は1stアルバムから通時的にレビューをしていきます。単純にリリース順とするなら、2ndと3rdの間に『Delicacies』の紹介を挟むべきですが、同盤を含む「Delicaciesシリーズ」は、その後数年に亘って関連楽曲のリリースが続くプロジェクトであるため、本記事「その1」での言及は避け、全て「その2」に回しました。
1stアルバム『Attack Decay Sustain Release』(2007)
シンセサイザーをいじる方であれば馴染み深いであろうADSRを冠した、SMDのデビューアルバムです。エレクトロ・ブームの中にリリースされた作品としては、良くも悪くも期待通りの一枚だと言えるでしょう。SMDはロックバンド・Simianを前身としていることもあってか、ロック的なアプローチが窺えるトラックも収められており、それがゼロ年代後半のダンスミュージック界の流行と合致していたことが、ヒットの一因だと思います。まさにそこを狙った結果の産物かも知れませんけどね。
前置きで述べてきた通り、僕が好きなSMDのサウンドは主に3rd以降のものではありますが、本作は本作で程好く纏まった良盤であると評価しています。全体的にキャッチーでボーカル曲も多く、ボーナストラックを除けば各曲3~4分台のコンパクトな仕上がり。ただ盛り上げるためだけの冗長なパートが見受けられない点でも、まだ本格的にEDMの波が来る前の作品だなと感じます。
同盤の中で最も好きなのは、シングル曲でもある04.「Hustler」です。ゲストボーカルにはChar Johnsonが迎えられ、彼女のハスキー且つセクシーなボーカルと反社会的な歌詞内容が相俟って、ダーティなサウンドが殊更に強調されたサグいアウトプットが堪りません。非英語ネイティブならではの小ネタ的な感想を付しますと、歌詞の"if i had the money to go to a record store i would, i would"は、仮定法過去を学ぶのが苦手な人にはもってこいの教材だと思います。"i would"が繰り返されるので尚更。笑
初っ端にダークなトラックを紹介してしまいましたが、ポップなセンスが光るナンバーも多く存在します。その代表例は03.「It's The Beat」で、子供向け番組やエクササイズビデオで流れていそうな、ハッピーでグルーヴィーなサウンドがアディクティブです。また、06.「I Believe」や09.「Love」も、ダンスミュージックの分野を離れた普通のヒットチャートにインしていても何ら可笑しくないくらいには、キャッチーで聴き易いと言えます。
一転、攻撃的なサウンドのニーズにも、05.「Tits & Acid」や07.「Hotdog」できちんと応えており、両曲ともケミブラを好むような方が気に入りやすいのではと思いました。同じくテクノ四天王の音を彷彿させるという点では、ボートラたる11.「Clock」は、Orbitalがたまに作る可愛いタイプの楽曲っぽくてお気に入りです。後の方向性の片鱗が窺えるトラックとしては、02.「I Got This Down」、ボートラの12.「System」、ボーナスディスク2の06.「Wooden (Uncut)」が挙げられ、いずれももう少しアレンジを上品にしたならば、3rd以降に収められていても違和感がない気がします。
2ndアルバム『Temporary Pleasure』(2009)
1stの粒揃いなところは今でも評価されるべきだと考えていますし、先に「良くも悪くも期待通りの一枚」とは述べたものの、他のエレクトロ勢の同時期の作品と比べても、当時のSMDのサウンドは頭一つ抜けている印象です。…が、この好感触を活かしきれずに終わったなというのが、続いてレビューする2ndへの僕の正直な感想となります。
こう思う最たる理由は、ボーカルトラックを際立たせる方向へとシフトしたからでしょう。1stではきちんと取れていたバックトラックとの均衡が、2ndでは敢えて崩されていると感じ、その結果ボーカル曲が並のポップスに聴こえてしまうのが残念なポイントです。
特筆するほど好きな曲は一つもないのが本音ですが、それでも敢えてフェイバリットを挙げるなら、02.「Audacity of Huge」と05.「Off the Map」は格好良いと擁護します。また、今後の進化を予感させるナンバーとしては、03.「10000 Horses Can't Be Wrong」では3rdへの、09.「Ambulance」ではコンピ盤への布石らしい音作りが披露されており、試行錯誤の跡が見て取れる点では意義のある一枚です。
この2ndに対する酷評は僕の個人的なものに過ぎませんが、イントロダクションの項に記した「1stと2ndを聴いただけの人に~」との偏見は、おそらく2ndを機にSMDから離れてしまった人が多いのだろうと感じたから、もっと言えばそれも已むなしの出来だとがっかりしたからで、後に方向転換するとは予想していなかったこの段階では、確かに僕もSMD熱が一旦引いていたなと顧みます。
しかし、結果として僕がSMDから完全に離れることがなかったのは、2ndの限定盤『Extra Temporary』(もしくは『Extra Pleasure』)の存在があったからです。同盤に収録されているのは全て長尺のインストナンバーで、そこにこそ僕の求めていたSMDサウンドがありました。前置き部の「SMDの場合」の項でも述べたように、転換後の方向性を先取りした伏線的な内容です。おそらくSMDとしても、今後の在り方を悩んでいたからこそ、このエクストラを提示してきたのだと分析します。
01.「Flea In Your Ear」は、「小言」を意味する英語の慣用句が曲名の元で、直訳通り蚤が耳の中を跳ね回っているかのように、キュートな電子音が右へ左へ行き来するキラキラした楽曲です。溜めて溜めて徐々に喧しくなってから、4:05~で解放される展開が気持ち好い。02.「Are You in the Picture?」は非常に幻惑的なトラックで、二次元と三次元の狭間で溺れてしまうようなトリップ感が素晴らしくあります。03.「Babaghanoush」はレバント地方の料理の名前を冠していますが、なぜこの曲名なのかはよくわからないアグレッシブなナンバーです。笑
04.「Do Not Exceed Stated Dose」は、日本語で言うところの「用法・用量を守って正しくお使いください」で、Peter Loveseyの短篇集にも同名(正確には'the'を間に挟む)のものがあります。曲の内容はタイトルとは裏腹に不安に満ち満ちており、OD患者の苦悩に晒されている気分です。05.「Belvedere」の曲題は「望楼」に相当する語で、インダストリアルなサウンドスケープと合わさると、監視されているようなビジョンが浮かびます。
3rdアルバム『Unpatterns』(2012)
これまでにも幾度かふれている通り、SMDは本作で大きな方向転換を図り、EDMの隆盛に歯向かうスタンスを明確にしました。3rdから顕著になるのは、テクノやミニマルの要素を取り入れたアプローチで、メリハリのある展開で高揚感を煽るよりも、徐々に音を変化させていくことで生じる陶酔感に重きが置かれたトラックメイキングが冴え渡っています。ボーカルの使用方法もこれまでとは異なり、とてもサンプリング的です。
ジャンル名を使いこそすれ、細かくジャンル分けをすることに実質的な意味を感じない考え方で居るので、不正確な表現をしていたら申し訳ないと断っておきますが、本作は所謂テックハウスやディープハウスに分類されるのではないでしょうか。
MVの内容も含めていちばん好きなのは、08.「Your Love Ain't Fair」です。うねりのあるシンセを軸に、スウィートなボーカルが表題のフレーズを繰り返しなぞる、実にセクシーなナンバー。構成は至ってシンプルながら、徐々に音の厚みが増していき、情熱的なサウンドへと変貌を遂げます。
MVは「点灯の瞬間」というシンプルなアイデア一本で撮影されており、次第の変化に妙味を覚える映像である点で、本曲に相応しいビジュアライズです。なお、以降にも幾つか埋め込んである通り、SMDのMVは3rd以降特にアーティスティックなものが顕著となるため、僕のお気に入りのMVを紹介する特集記事の中にも、本MVを含めた言及があります。
純粋にサウンドだけを評価した中でのいちばんの好みは、ラストを飾るインストゥルメンタルの09.「Pareidolia」です。表題の語は、天井のシミが人の顔に見えるとか、雲の形が動物のように見えるとか、そういった類の錯覚を指す言葉。同曲はまさにパレイドリアを;とりわけ雲によるものを表現している風に僕には聴こえます。以下、この妄想音解釈を文章化。
高所から滴り落ちて反響する水音を思わせるサウンドと、行軍然として洗脳混じりの単調さで迫り来るドラムス、そして単純なフレーズを繰り返す細切れのシンセが特徴的な序盤は、雲が錯覚を引き起こすような像を形作ろうとしている段階。この情景を破るのが2:08からの展開で、ここで唐突に挿入されるパッドによるぶつ切りは、宛ら雲を散らす風の如く、何事も無かったかのようないつもの空に戻る焦らしの演出。この鬩ぎ合いが幾度か繰り返された後、4分に差し掛かろうとするあたりから、俄にビート感を増したダンサブルなトラックメイキングとなります。ここからが愈々パレイドリアのターンで、雲が作りし錯覚像が現実感を伴って暴れ出し、視界と脳内を侵食していく様が浮かぶ。ラストにかけて増大するパッドは、文字通りの雲散霧消、全てかき消されて無に帰す完璧な楽想で、アルバムタイトルの「Unpatterns」を体現せし楽曲であると絶賛します。
テクノ的なストイックさが光るという点では、02.「Cerulean」および07.「The Dream of the Fisherman's Wife」も非常に好みです。両曲とも聴けば聴くほどに良さが滲み出てくるタイプで、表向きのシンプルさの陰に潜む複雑な作り込みに気付く過程ごと楽しめます。ちなみにですが、後者の曲名は葛飾北斎の超有名春画『蛸と海女』の英題です。このことを考慮すると、縦横無尽に暴れ回る電子音も何処か淫靡に響いてきます。
従来のSMDと比べると難解な印象を受けるナンバーが多いのは事実ながら、キャッチーな要素を巧く融合させて聴き易いものもあり、03.「Seraphim」や06.「Put Your Hands Together」などは、これまでのサウンドが好みだった方が気に入りやすいのでないでしょうか。
ボートラにも名曲が隠れており、iTunes盤収録の11.「Everyday」は08.に近しい路線の曲なので、気に入らない道理がありませんでした。また、日本盤ボートラ(同盤の11.は「Supermoon」なので注意)からの一曲たる12.「Witches of Agnesi」は、楽想のミニマルさからは想像が出来ないほどに、発展性のある壮大なサウンドが披露されており、電子音楽の醍醐味があると高く評価しています。直訳で「アグネシの魔女(達)」とは一体何なんだと思って調べてみると、これは数学用語で「アーネシの曲線」と呼ばれているもののことらしいです。…余計になぜこの題を冠しているのか、わからなくなってしまいました。笑
インターミッション
以上、SMDの3rdアルバムまでのレビューでした。冒頭の趣旨説明でも述べた通り、都合上ここで一度記事を終える必要があるため、続きは「SIMIAN MOBILE DISCO その2 ―4th『Whorl』から―」へ持ち越します。
リンク先で扱うのは、4thおよびコンピ盤を含むその他の作品群(「Delicaciesシリーズ」やアルバム未収録曲など)が中心ですが、2019年の改訂時にその後のディスコグラフィーに関しても追記したので、実質的には6thまで網羅した内容です。
趣旨説明
本記事では、SIMIAN MOBILE DISCO(シミアン・モバイル・ディスコ)の音楽を特集します。レビューの対象は、ナンバリングアルバム準拠で言えば1stから4thまでとなりますが、コンピレーション盤を含む「Delicaciesシリーズ」や、アルバム未収録の楽曲についても、網羅的にふれる内容に仕上げました。ゆえに文章量が多く、一つの記事では全てを書き切ることが出来なかったため、或いはYouTubeの埋め込みが多く、表示が過剰に重くなることを防ぐ目的で、記事を二つに分割しています。
副題にある通り、「その1」では3rdまでの3枚を、「その2」では4thおよびその他の作品群を、それぞれ取り扱う次第です。加えて、後者には2019年の改訂の際に、5thと6thをレビューした記事へのリンクを貼り付けてあるので、キャリアの殆ど全てに言及する内容だと捉えていただいて差し支えありません。
イントロダクション
それでは早速と1stのレビューに入りたいのは山々ですが、その前にSMDのアーティスト像を語るところから始めることをご了承ください。偏見に満ちた私感であると断っておきますが、日本に於けるSMDの評価は、1stと2ndを聴いただけの人に「あぁ、こういう感じね。」と思われて、今尚このイメージが幅を利かせているとの認識です。こう思う理由には、彼らがシーンの中でどのように頭角を現してきたかということが関係してくるので、そのあたりの事情も込みで詳しく解説していきます。
その内容を端的にまとめると、「商業的ムーブメントの功罪とEDM批判」となり、SMDに関係するとは言っても脱線の向きが強いため、早く本題に入ってくれとお望みの方は、ここをクリックすれば1stのレビュー位置までジャンプが可能です。なお、ここで僕が使う「EDM」というワードは、Wikipediaの「エレクトロニック・ダンス・ミュージック」のページで言うところの「狭義的な解釈」に基いたものであるため(=従来のダンスミュージックとは区別する立場)、この点に留意して読み進めてください。
フェーズⅠ:エレクトロ・ブームの中で
SMDの1st/2ndが出た頃の、つまり2000年代後半のダンスミュージックシーンに於いては、「エレクトロ」がフィーチャーされていたと記憶しています。Wikipediaの同名のページにも記述があるように、これは日本でのみ通用するジャンル名でしょうが、まだ「EDM」といった便利な言葉が国内で市民権を得ていない段階では、「厚みのある電子的なサウンドが特徴のポップなダンスミュージック全般」を指すものとして、確かに「エレクトロ」はキーワードでした。ロックとの親和性が高かったのも、その通りだと思います。
SMDもこのブームの中に表れた一組であるとの印象に関しては僕もご多分に洩れずで、海外アーティストに限っては、他にもJustice・Digitalism・Boys Noize・AutoKratz・Spirit Catcherあたりの有名どころは、好んでよく聴いていました。ここに名前を挙げた面々は、いずれも一定の成功を収めたと言っていいであろう存在ですが、同時に「消費された」感も非常に強くあるとの認識です。ブームには得てしてこういう面があるものですが、ブームの言わば「負の側面」の煽りをもろに食ったと感じられる点が、ゼロ年代後半に名を轟かせたエレクトロ勢に共通する哀しき特徴ではないでしょうか。
セールスや知名度の向上に関しては、ブームの恩恵を存分に受けていることは確かでありながら、ブームの中で消費されたという事実が、音楽的な質の評価にまで及んでしまっているのが、とりわけ不幸に思える所以です。両者は本来別個に論じられて然るべきものですが、現実的には一緒くたにされ、不当に低い評価を得る結果につながっている気がします。
「別にブームでも一定の評価を受けたのだから良いじゃないか」との考えにも一理ありますし、このブームがダンスミュージックにフォーカスした一過性のものであったならば、僕も態々「負の側面の煽りをもろに食った」とまでは言いません。問題はこの後に程無くして「EDM」が登場してきた;正確にはより包括的な概念「EDM」がジャンル名として台頭してきたことで、これが余計にゼロ年代後半エレクトロ勢を不遇だと位置付ける理由になります。
フェーズⅡ:EDMの出現
僕は元々、それこそ「EDM」なる形容が出てくるよりずっと前から、エレクトロニックなダンスミュージックが大好きです。当ブログのテーマ一覧から、界隈で有名なアーティスト名を選んで、そこにある記事を幾つかご覧いただければ、それが証左となるでしょう。
しかし、そんな僕にとっての「EDM」は未だに「謎の新興勢力」のイメージで、従来のダンスミュージックとは地続きではないところから生まれた、全く新しいものだと見做しています。勿論、使われがちな音やコード感などを含むトラックメイキングのハウツーは把握していますし、音楽のジャンル名とするよりは、オーディエンスの嗜好やライフスタイルなども含めた、カルチャー全体の呼称とするのが適切なのではと、結論じみたものも持ってはいますけどね。
Ⅰの内容と併せて言わんとしているのは、ダンスミュージックを受け入れる土壌は2010年代に入って更に拡大していったにもかかわらず、地続きではない新興勢力「EDM」の出現、延いてはこれを好む人々(主に作り手側の傾向)によって、それ以前のダンスミュージックの影が薄くなってしまったと感じるということです。前述の「狭義的な解釈」も、この手の反発意識があるからこそ出てくるものだと考えますが、このカウンター思考の根底には、何処か「ルーツの欠如」を覚えてしまうからといったもどかしさがあると、僕は分析しています。
この点はもう少し掘り下げて説明したいのですが…というか、下書きの段階では実際に作り手側の姿勢にフォーカスしたEDM批評の文章(=「本質」vs「現象」のダンスミュージック論)を長々と認めはしたのですが、内容が辛辣な上に脱線が過ぎるのでオールカットにしました。従って、批判には当たらない別のアプローチとして、EDMを好んで聴く層の;即ち受け手側の捉え方を推測することで、当該の不遇問題に迫ってみたいと思います。
流れの中で「こういう音楽がEDMだ」と言えるようなサウンドが確立してきて、それで初めてダンスミュージックを好きになった人達にとっては、従来のものは「踊れない音楽」と判断されているのではないでしょうか。従来のダンスミュージックには、電子音楽的な技巧性やリスニング志向の作り込みが窺え、その上でフロアを盛り上げる機能もあるといった、言わば二面性があると捉えていますが、対するEDMは完全フロア志向の音楽である面が強く、繰り返し聴いて細部のトラックメイキングに酔い痴れるといった、リスニングメインの味わい方には乏しい気がします。先に「オーディエンス」という形容をしたのも実は意図的で、EDMフリークに対して「リスナー」を持ち出すと、彼らは寧ろ嫌がるのではないかと忖度したからです。
80/90年代の古さならともかく、ゼロ年代のそれも後半の比較的新しいサウンドであれば、EDM好きの人でも取っつき易いのではと個人的には思うのですが、どうも実際にはそうでないと感じます。やはり「踊るための音楽」であることが殊更重要視されているのか、そもそも「聴く」という発想が希薄なのか、或いは単に知らないだけなのか(若年層は致し方ないとしても)。ともかく、ダンスミュージックであることには変わりないはずなのに、これまでに述べてきた「地続きではない」もしくは「ルーツの欠如」に起因するEDMの特殊性のせいか、シーンの狭間に取り残されてしまった感が、ゼロ年代後半エレクトロ勢の悲哀であるとまとめます。
フェーズⅢ:迎合か、解釈か、反発か
ここまでの内容を受けると、僕がEDMを毛嫌いしているように映るかもしれませんが、他のジャンルにEDM的なマナーを取り入れるといった、クロスオーバーなサウンドメイキングは寧ろ好みの範疇です。フロア向けのEDMをリスニングにも適うように昇華したものであれば、繰り返しの鑑賞にも耐えられる中毒性の高い音楽となるため、EDMを構成する要素自体は嫌いではないのだと熟々思います。
その証拠に当ブログ内を「EDM」で検索すれば、本記事のような批評的なものも勿論ヒットしますが、褒める文脈で登場させているものも幾つか発見出来るはずです。以降に例示する記事群も、特に「解釈」に分類しているものに関しては、EDMの昇華を好意的に見た結果の産物となります。
さて、新興勢力に対して既存勢力が取り得るパターンは、単純化して「迎合」と「解釈」と「反発」の三つが考えられるでしょう。本記事に於いては、「迎合」はEDMに寄せた、「解釈」は前述した通りの、「反発」はEDMに背いたサウンドメイキングを、それぞれ指しているとご理解ください。各パターンの根拠を具体的に説明し出すと長くなるので、2019年の改訂時までにアップした記事の中から、ワードとして「EDM」を出しているものに限って、それぞれに当て嵌まる記述を含んだエントリーへのリンクを貼り、それを解説代わりとします。
当然ですが、対象は10年代以降のエレクトロニックなダンスミュージックで、基本的には既存勢の動向に関するものです。ただし、以下の例示はあくまでも「僕がそう捉えている」だけの区分であるため、アーティスト側の姿勢を規定するものではない点にも留意していただけると助かります。また、僕は好きな音楽でない限りレビューの対象とはしないので、ここまでのEDM批評と矛盾するようにも思えるでしょうが、「迎合」についても批判の意味合いはありません。
例示
迎合の例(皮肉的な場合もあり)
■ 第3期のm-flo(2012~)
■ セブンスシスターズ「SEVENTH HAVEN」(2016)
補足:同曲はフェスアンセム的な迎合で、後発のエネミーユニット・AXiSによるアンサーソング「HEAVEN'S RAVE」(2019)はクラブバンガー的な迎合で、巧く対比させているとの分析です。
■ きゃりーぱみゅぱみゅ「原宿いやほい」(2017)
■ 忍迅雷音「Ninja Fanka」(2018)
補足:同記事内にはSkrillexに対する言及もあります。
解釈の例(結果としてEDMらしくなくても可)
■ KARAKURI「B.A.A.B.」(2015)
■ DÉ DÉ MOUSE『dream you up』(2017)
■ 中田ヤスタカ『Digital Native』(2018)
補足:ヤスタカワークスに関しては、CAPSULE『WAVE RUNNER』(2015)が解釈の好例だとの認識です。
■ パスピエ「始まりはいつも」(2019)
反発の例(明示的な否定でないものも込み)
■ The Chemical Brothers『Born in the Echoes』(2015)
補足:次作『No Geography』(2019)でも、カウンターの姿勢は維持されています。
■ 80KIDZ『80:XX - 05060708』(2017)
■ KOTOKO『tears cyclone -廻-』(2018)
反発の例に更に補足しますと、確かに存在する「EDMに懐疑的な流れ」に於ける最たるものは、グラミー賞も獲得したDaft Punkの『Random Access Memories』(2013)でしょう。同盤は最早「エレクトロニック」に対するアンチテーゼかもしれませんが、「お手軽に躍らせるだけがダンスミュージックの神髄ではない」ということを、EDMに傾くことなく証明した名盤であると絶賛します。寧ろもっと古いサウンドたる、ディスコ回帰的なアウトプットが印象深いものでした。
SMDの場合
超絶に長い前置きは以上で、ここからが本題となります。Ⅰの項で述べた通り、SMDもゼロ年代後半のエレクトロ・ブームの中に表れた一組であるとの認識に相違はありません。しかし、EDMが猛威を振るい始める10年代に突入してからのSMDは、上掲の三パターンに区分するなら、明確に「反発」のスタンスを突き付けていく存在になったと言えます。
その根拠となるのが、2012年リリースの3rdです。同作は当時の商業的な動きや流行りのサウンドに逆行した内容が特徴的で、それまでのSMDのイメージを打ち破る衝撃の一枚でした。より厳密には、2009年の2ndの限定盤(ディスク2)の内容が伏線的ではありましたし、2010年のコンピ盤で既に方向転換を図っていたとも分析可能ですが、ナンバリングタイトルのメインディスクの内容で比較するという基本に則れば、転換を迎えたのは3rdであると位置付けさせてください。
ともかく、転換後のことを語るには転換前から振り返るのがベターなので、以降は1stアルバムから通時的にレビューをしていきます。単純にリリース順とするなら、2ndと3rdの間に『Delicacies』の紹介を挟むべきですが、同盤を含む「Delicaciesシリーズ」は、その後数年に亘って関連楽曲のリリースが続くプロジェクトであるため、本記事「その1」での言及は避け、全て「その2」に回しました。
1stアルバム『Attack Decay Sustain Release』(2007)
 | Attack Decay Sustain Release 815円 Amazon |
シンセサイザーをいじる方であれば馴染み深いであろうADSRを冠した、SMDのデビューアルバムです。エレクトロ・ブームの中にリリースされた作品としては、良くも悪くも期待通りの一枚だと言えるでしょう。SMDはロックバンド・Simianを前身としていることもあってか、ロック的なアプローチが窺えるトラックも収められており、それがゼロ年代後半のダンスミュージック界の流行と合致していたことが、ヒットの一因だと思います。まさにそこを狙った結果の産物かも知れませんけどね。
前置きで述べてきた通り、僕が好きなSMDのサウンドは主に3rd以降のものではありますが、本作は本作で程好く纏まった良盤であると評価しています。全体的にキャッチーでボーカル曲も多く、ボーナストラックを除けば各曲3~4分台のコンパクトな仕上がり。ただ盛り上げるためだけの冗長なパートが見受けられない点でも、まだ本格的にEDMの波が来る前の作品だなと感じます。
同盤の中で最も好きなのは、シングル曲でもある04.「Hustler」です。ゲストボーカルにはChar Johnsonが迎えられ、彼女のハスキー且つセクシーなボーカルと反社会的な歌詞内容が相俟って、ダーティなサウンドが殊更に強調されたサグいアウトプットが堪りません。非英語ネイティブならではの小ネタ的な感想を付しますと、歌詞の"if i had the money to go to a record store i would, i would"は、仮定法過去を学ぶのが苦手な人にはもってこいの教材だと思います。"i would"が繰り返されるので尚更。笑
初っ端にダークなトラックを紹介してしまいましたが、ポップなセンスが光るナンバーも多く存在します。その代表例は03.「It's The Beat」で、子供向け番組やエクササイズビデオで流れていそうな、ハッピーでグルーヴィーなサウンドがアディクティブです。また、06.「I Believe」や09.「Love」も、ダンスミュージックの分野を離れた普通のヒットチャートにインしていても何ら可笑しくないくらいには、キャッチーで聴き易いと言えます。
一転、攻撃的なサウンドのニーズにも、05.「Tits & Acid」や07.「Hotdog」できちんと応えており、両曲ともケミブラを好むような方が気に入りやすいのではと思いました。同じくテクノ四天王の音を彷彿させるという点では、ボートラたる11.「Clock」は、Orbitalがたまに作る可愛いタイプの楽曲っぽくてお気に入りです。後の方向性の片鱗が窺えるトラックとしては、02.「I Got This Down」、ボートラの12.「System」、ボーナスディスク2の06.「Wooden (Uncut)」が挙げられ、いずれももう少しアレンジを上品にしたならば、3rd以降に収められていても違和感がない気がします。
2ndアルバム『Temporary Pleasure』(2009)
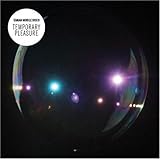 | Temporary Pleasure 855円 Amazon |
1stの粒揃いなところは今でも評価されるべきだと考えていますし、先に「良くも悪くも期待通りの一枚」とは述べたものの、他のエレクトロ勢の同時期の作品と比べても、当時のSMDのサウンドは頭一つ抜けている印象です。…が、この好感触を活かしきれずに終わったなというのが、続いてレビューする2ndへの僕の正直な感想となります。
こう思う最たる理由は、ボーカルトラックを際立たせる方向へとシフトしたからでしょう。1stではきちんと取れていたバックトラックとの均衡が、2ndでは敢えて崩されていると感じ、その結果ボーカル曲が並のポップスに聴こえてしまうのが残念なポイントです。
特筆するほど好きな曲は一つもないのが本音ですが、それでも敢えてフェイバリットを挙げるなら、02.「Audacity of Huge」と05.「Off the Map」は格好良いと擁護します。また、今後の進化を予感させるナンバーとしては、03.「10000 Horses Can't Be Wrong」では3rdへの、09.「Ambulance」ではコンピ盤への布石らしい音作りが披露されており、試行錯誤の跡が見て取れる点では意義のある一枚です。
この2ndに対する酷評は僕の個人的なものに過ぎませんが、イントロダクションの項に記した「1stと2ndを聴いただけの人に~」との偏見は、おそらく2ndを機にSMDから離れてしまった人が多いのだろうと感じたから、もっと言えばそれも已むなしの出来だとがっかりしたからで、後に方向転換するとは予想していなかったこの段階では、確かに僕もSMD熱が一旦引いていたなと顧みます。
 | Extra Temporary 900円 Amazon |
しかし、結果として僕がSMDから完全に離れることがなかったのは、2ndの限定盤『Extra Temporary』(もしくは『Extra Pleasure』)の存在があったからです。同盤に収録されているのは全て長尺のインストナンバーで、そこにこそ僕の求めていたSMDサウンドがありました。前置き部の「SMDの場合」の項でも述べたように、転換後の方向性を先取りした伏線的な内容です。おそらくSMDとしても、今後の在り方を悩んでいたからこそ、このエクストラを提示してきたのだと分析します。
01.「Flea In Your Ear」は、「小言」を意味する英語の慣用句が曲名の元で、直訳通り蚤が耳の中を跳ね回っているかのように、キュートな電子音が右へ左へ行き来するキラキラした楽曲です。溜めて溜めて徐々に喧しくなってから、4:05~で解放される展開が気持ち好い。02.「Are You in the Picture?」は非常に幻惑的なトラックで、二次元と三次元の狭間で溺れてしまうようなトリップ感が素晴らしくあります。03.「Babaghanoush」はレバント地方の料理の名前を冠していますが、なぜこの曲名なのかはよくわからないアグレッシブなナンバーです。笑
04.「Do Not Exceed Stated Dose」は、日本語で言うところの「用法・用量を守って正しくお使いください」で、Peter Loveseyの短篇集にも同名(正確には'the'を間に挟む)のものがあります。曲の内容はタイトルとは裏腹に不安に満ち満ちており、OD患者の苦悩に晒されている気分です。05.「Belvedere」の曲題は「望楼」に相当する語で、インダストリアルなサウンドスケープと合わさると、監視されているようなビジョンが浮かびます。
3rdアルバム『Unpatterns』(2012)
 | Unpatterns 931円 Amazon |
これまでにも幾度かふれている通り、SMDは本作で大きな方向転換を図り、EDMの隆盛に歯向かうスタンスを明確にしました。3rdから顕著になるのは、テクノやミニマルの要素を取り入れたアプローチで、メリハリのある展開で高揚感を煽るよりも、徐々に音を変化させていくことで生じる陶酔感に重きが置かれたトラックメイキングが冴え渡っています。ボーカルの使用方法もこれまでとは異なり、とてもサンプリング的です。
ジャンル名を使いこそすれ、細かくジャンル分けをすることに実質的な意味を感じない考え方で居るので、不正確な表現をしていたら申し訳ないと断っておきますが、本作は所謂テックハウスやディープハウスに分類されるのではないでしょうか。
MVの内容も含めていちばん好きなのは、08.「Your Love Ain't Fair」です。うねりのあるシンセを軸に、スウィートなボーカルが表題のフレーズを繰り返しなぞる、実にセクシーなナンバー。構成は至ってシンプルながら、徐々に音の厚みが増していき、情熱的なサウンドへと変貌を遂げます。
MVは「点灯の瞬間」というシンプルなアイデア一本で撮影されており、次第の変化に妙味を覚える映像である点で、本曲に相応しいビジュアライズです。なお、以降にも幾つか埋め込んである通り、SMDのMVは3rd以降特にアーティスティックなものが顕著となるため、僕のお気に入りのMVを紹介する特集記事の中にも、本MVを含めた言及があります。
純粋にサウンドだけを評価した中でのいちばんの好みは、ラストを飾るインストゥルメンタルの09.「Pareidolia」です。表題の語は、天井のシミが人の顔に見えるとか、雲の形が動物のように見えるとか、そういった類の錯覚を指す言葉。同曲はまさにパレイドリアを;とりわけ雲によるものを表現している風に僕には聴こえます。以下、この妄想音解釈を文章化。
高所から滴り落ちて反響する水音を思わせるサウンドと、行軍然として洗脳混じりの単調さで迫り来るドラムス、そして単純なフレーズを繰り返す細切れのシンセが特徴的な序盤は、雲が錯覚を引き起こすような像を形作ろうとしている段階。この情景を破るのが2:08からの展開で、ここで唐突に挿入されるパッドによるぶつ切りは、宛ら雲を散らす風の如く、何事も無かったかのようないつもの空に戻る焦らしの演出。この鬩ぎ合いが幾度か繰り返された後、4分に差し掛かろうとするあたりから、俄にビート感を増したダンサブルなトラックメイキングとなります。ここからが愈々パレイドリアのターンで、雲が作りし錯覚像が現実感を伴って暴れ出し、視界と脳内を侵食していく様が浮かぶ。ラストにかけて増大するパッドは、文字通りの雲散霧消、全てかき消されて無に帰す完璧な楽想で、アルバムタイトルの「Unpatterns」を体現せし楽曲であると絶賛します。
テクノ的なストイックさが光るという点では、02.「Cerulean」および07.「The Dream of the Fisherman's Wife」も非常に好みです。両曲とも聴けば聴くほどに良さが滲み出てくるタイプで、表向きのシンプルさの陰に潜む複雑な作り込みに気付く過程ごと楽しめます。ちなみにですが、後者の曲名は葛飾北斎の超有名春画『蛸と海女』の英題です。このことを考慮すると、縦横無尽に暴れ回る電子音も何処か淫靡に響いてきます。
従来のSMDと比べると難解な印象を受けるナンバーが多いのは事実ながら、キャッチーな要素を巧く融合させて聴き易いものもあり、03.「Seraphim」や06.「Put Your Hands Together」などは、これまでのサウンドが好みだった方が気に入りやすいのでないでしょうか。
ボートラにも名曲が隠れており、iTunes盤収録の11.「Everyday」は08.に近しい路線の曲なので、気に入らない道理がありませんでした。また、日本盤ボートラ(同盤の11.は「Supermoon」なので注意)からの一曲たる12.「Witches of Agnesi」は、楽想のミニマルさからは想像が出来ないほどに、発展性のある壮大なサウンドが披露されており、電子音楽の醍醐味があると高く評価しています。直訳で「アグネシの魔女(達)」とは一体何なんだと思って調べてみると、これは数学用語で「アーネシの曲線」と呼ばれているもののことらしいです。…余計になぜこの題を冠しているのか、わからなくなってしまいました。笑
インターミッション
以上、SMDの3rdアルバムまでのレビューでした。冒頭の趣旨説明でも述べた通り、都合上ここで一度記事を終える必要があるため、続きは「SIMIAN MOBILE DISCO その2 ―4th『Whorl』から―」へ持ち越します。
リンク先で扱うのは、4thおよびコンピ盤を含むその他の作品群(「Delicaciesシリーズ」やアルバム未収録曲など)が中心ですが、2019年の改訂時にその後のディスコグラフィーに関しても追記したので、実質的には6thまで網羅した内容です。