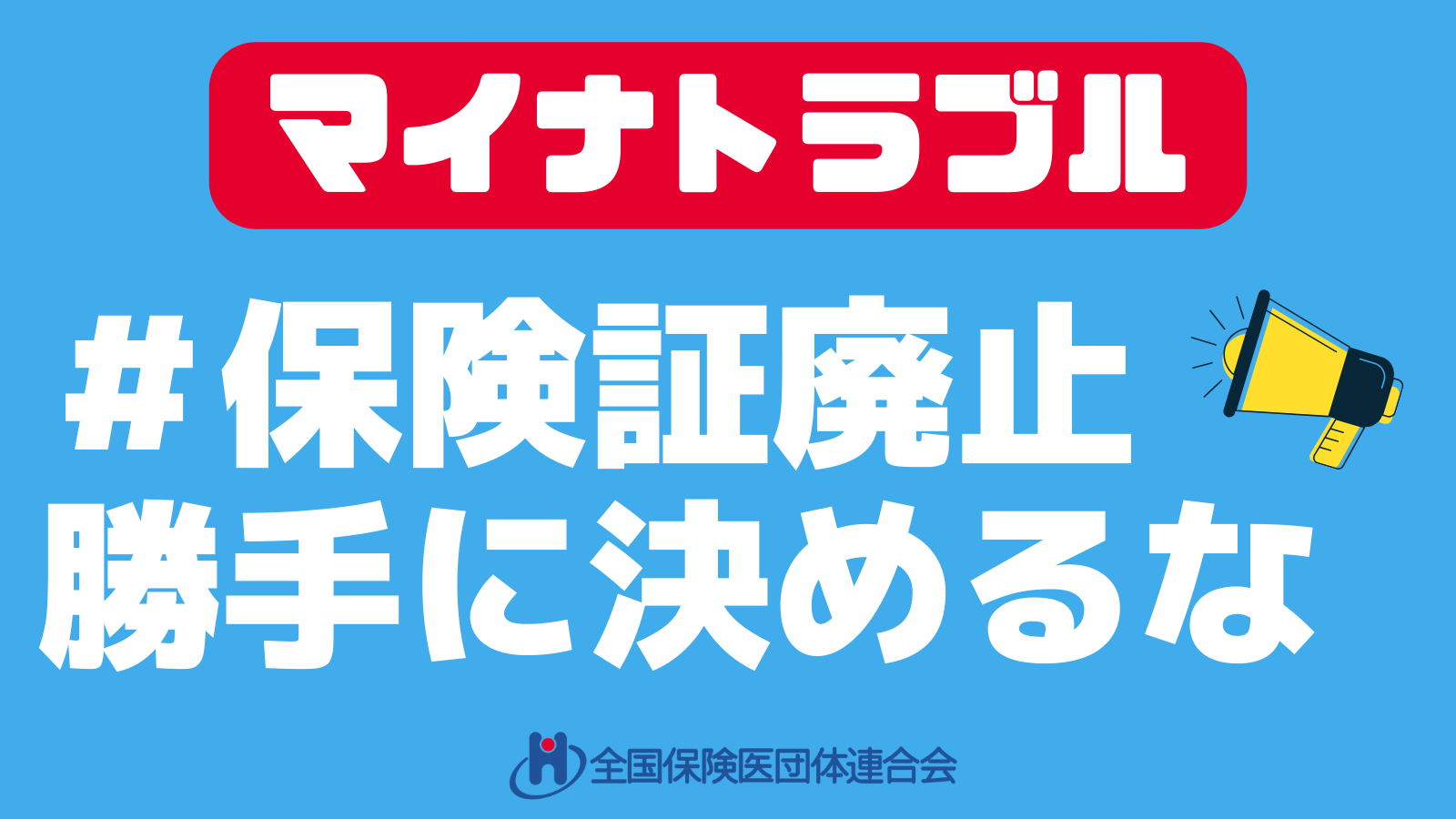一般の人たちは、精神疾患や向精神薬について興味を抱かず、何らかのきっかけがないと、どのようなものか調べることがないと思う。
主治医から見て、精神疾患や向精神薬に妙に詳しいと思える時は、必ずと言って良いほどそうなった理由がある。
例えば子供が統合失調症やASDと診断されて、それについて書物やインターネット上で調べるなどである。患者さんをサポートする家族が興味を持ち、詳しく調べるのである。それにより、自分の家族がどのような疾患であるとか、その経過中のどのあたりに位置しているか理解が深まる。
一方、子供が例えば統合失調症や双極性障害と診断されても、主治医にまかせっきりか、ある種のネグレクトのために疾患についてほとんど理解が深まらない家族も意外に多い。僕は統合失調症や双極性障害こそ、服薬の必要性も含め理解を深めることを望んでいる。という理由は、患者さんの訴えを聴くと、家族が精神疾患について理解がなさ過ぎて困るという話もよく聴くからである。
精神疾患や向精神薬に詳しくなるのは良いが、疾患や薬の理解がズレていて主治医が困るケースもある。これは例えば本人は統合失調症など内因性疾患だが、ASDかグレーゾーンと思われる家族に時々みられる印象である。これは背景に反精神医学的な思考があり、容易に通常の薬物治療を受け入れない。
精神科は基本的に対症療法なので、何らかの症状に応じて向精神薬を処方することが多い。このブログでも、抗精神病薬は統合失調症や双極性障害だけに限らず色々な疾患で処方されうると記載している。それは今の非定型精神病薬は、精神疾患のさまざまな症状に治療的に働くからである。
ところが、そのような妙に詳しい家族は、○○の疾患は△△の薬を使うとか、頭にデジタルにインプットされており、患者さんの治療の際に拒否的な言動をとる。しかも和訳版の精神科薬理学の分厚い本などを持参してきており、
そういう治療は聴いたことがない。
くらいは普通に言う。ちょっと考えられない治療の拒絶があったため、紹介した医師に事情を伝えた。その家族にもどういう意図で、そのような処方をすべきか説明したが、デジタルに考えている人に、柔軟な治療は理解できないようであった。そもそも、彼らには添付文書に登録されていない疾患の適切な処方はわからないのである。
添付文書に登録されていない、つまり出てこない精神疾患はかなり多い。例えば、非定型精神病、身体表現性障害などはおそらく添付文書には登録されていないと思う。
このケースでは、元の身体科の主治医に説得されて、治療自体が進んだので、患者さんの症状は短期間に劇的に改善した。それは適切な薬物治療をしたからに他ならない。
しかし、最初拒絶したのに良い経過になったことも、その家族には気に入らなかったようであった。
その後、家族の病院に対する迷惑行為が続き、ある時、本人はともかく家族との信頼関係が保てなくなり、遂にクビにした。こういう話はかなり前の記事にも記載したことがある。
だって、思うように治療などできないのに。
精神科医が、なぜ処方すべきか説明しているのに、「そんな治療は聴いたことがない」と言うことは侮辱行為である。
精神科で患者本人や家族との信頼関係が保てないために治療を断わられることはそう多くはないが、時々あることである。
以下のPDFは、医師の応召義務について令和元年に厚生労働省からアナウンスされたものである。従来に比べて現場の状況を汲む内容になっており、少しだけ医師の立場に寄り添う内容になっている。
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000581246.pdf