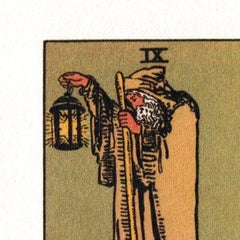「自分たちのことを自分たちで決められるまちに」⎯⎯なるほど、美しいスローガンです。しかし、そういう「まち」を目指すことが人を幸せにするとは限らない、のもまた事実でありまして。
「自分たち」⎯⎯そんなものが、今だけでなく、金だけでなく、自分だけでなく、長期間にわたって積み上げてきたものや、広範囲におよぶ関連施策にまで思いを致し、冷静に賛否を判断する(できる)ものでしょうか。
「自分たち」⎯⎯その大多数は、今の自分が使うか使わないか、あるいは近しい人にとって今必要か必要でないか、そして、そのためにどれほどのお金がかかるのか、そういった部分だけで決めてしまうものではないですか。
●埼玉県北本市 平成25(2013)年
成功体験として語るか、批判素材として取り上げるか、は別として。
こちら、その筋では有名(らしい)な、埼玉県北本市で実施された住民投票に関するニュースです(2013年12月16日 23:30配信)。
埼玉県北本市がJR高崎線北本―桶川間の新駅設置の賛否を問うために15日実施した住民投票の結果が反対多数だったのを受けて、同市の石津賢治市長は16日の記者会見で、新駅の建設計画について「白紙にする」と語った。今年度中に市費で建設するための請願駅設置を求める要望書をJRに提出することも「行わない」と明言した。設置計画が振り出しに戻ったことで、新駅をテコに商業系の開発が予定されていた南部地域のまちづくりにも影響を及ぼしそうだ。
住民投票は即日開票の結果、賛成8353票に対し反対2万6804票と反対票が投票者総数の7割以上を占めた。このことについて、石津市長は「ここまで差が開くとは考えていなかった。賛否が拮抗(きっこう)すると思っていた」と述べた。
ただ、住民投票条例で「市長はその結果を尊重する」と明記していることや、市議会などで「一票でも多い方の意見に従う」との考えを示してきたことを理由に、建設計画を白紙にする考えを表明した。
今後の対応に関しては「白紙以下でも以上でもない」と明言を避けたが、「今でも将来の人口減少を食い止めるために新駅は必要だと思っている」と強調した。
新駅の建設をテコに商業地域としての開発が予定されていた南部地域(約9ヘクタール)周辺の開発については「区画整理事業などの計画変更はない」としたが、デベロッパーなど民間事業者の開発意欲は下がりそうだ。
三期目の市長はもともと推進派、議会も全会一致で議決した「新駅設置」だったというのに、結局中止になったそうです。
その後「南部地域のまちづくり」がどうなったか、結果、今日の市民がどう感じているかは分かりません。
●「感情」に訴える反対派
北本市民の方が、当時書かれたブログを見つけました。
数週間前から反対派のインフォメーションが新聞広告や、移動
広告車のスピーカーから流される。
「反対です!税金72億円の新駅」
「新駅設置には桶川市の参加が絶対条件」
「今回の計画は無謀だ!棄権は危険だ!」
新駅建設における借金のみがクローズアップされ、どうしたら
実現に至るのか、どのような街並みが形成されるのか、人口
推移がどう期待できるのか、そのような前向きな言葉を見出す
ことは出来ない。
〜〜〜 〜〜〜 〜〜〜
立ち行かなくなった政策を民意に問うのは簡単なこと。
民意の意向により、行政の方策を決めるのであれば政治家は不要
ではないか。
うん、まあ、そうなるだろうし、そのとおりだなと思います。
地図を見れば、なるほど南隣桶川市からの利用者が多くなりそうですし、そしたら「新駅設置には桶川市の参加が絶対条件」というのは、実際、かなりの説得力があったことでしょう。
(Googleマップより)
●本来、必要のない住民投票だった
推進派の市長と、同じ方向で全会一致の議会。
では、なぜ、わざわざ住民投票を実施したのか。
自治基本条例があったから、必ず賛成多数になると踏んでいた市長が、自らの4期目当選へ向けはずみにしようとした、などと論評されてはいますが、真実のほどは分かりません。
その市長は、結局、新駅設置の白紙撤回を余儀なくされ、その後の市長選挙でも落選してしまったとのことです。
こうしてみると、北本市長選挙は毎回接戦だったのですね。
●住民投票を求める理由は?
ぶっちゃけ、大抵の人にとって、大抵の公共施設は「知らない間にできた」「気がついたらできてた」ものだと思います。
それを個別に「新たに造るのに賛成ですか、反対ですか」と聞かれたら、実際に自分が使う、あるいは自分や自分と近しい人にとって必要だという人以外は「どっちでもいい」となるのではないでしょうか。
新たな施設の意義について「ちゃんと」知らねばならないという動機も、そのために割く時間もないのが「ふつうの人」ですし。
ところがそこに「造るのに、いくらいくらかかります」とお金が絡むと、にわかに反対寄りになってしまうのが人の弱さというもので。
世の中には、そこにつけこむ、良い人のフリした悪い人が少なからずいるのです。
理論的に反対している(ように見える)人でも、要は(体制が)気に入らないからそうするのであって、施設そのものについては有っても無くても、本音は「どっちでもいい」、いや、むしろ「どうでもいい」だったりもして。
そんな人達が蠢く中、いやいや、使う人がいるならと、必要とする人がいるならと、そういう見方ができて、公共事業・施設としての費用対効果を冷静に判断できる人は、決して多くはないでしょう。残念ながら。
ましてや、建設・整備の方向性が定まるまでの、ヒアリング、アンケート、ワークショップ、関係諸団体からの要望等、過去の記録まで紐解く人など、それこそ極少数なのではないですか。
「自分」と「自分たち」とが常に同じなら良いのだけれど、そうでないことも多いのが人の世の習いです。
●「職業としての政治家」
個々の公共施設・事業に関して、いちいち「賛否を問う」などしていたら、新しいもの、大きいもの、は、ことごとく「反対」意見が優り、いわゆる長期ビジョン、総合計画の類に沿った行政は立ち行かなくなる気がします。
だからこそ、そのためにこそ、物事を大所高所から判断し、また、それらについて言葉を以て他者を説得する政治家という職業があるわけで。
我が豊橋市の状況を見るにつけ、まあ、何と言いましょうか、
頼みますよ!
といった感じです。
「有志議員」の皆さんは頑張ってくれているのですが、
もう一声 !!
●北本市住民投票関連資料集
住民投票とは、実際どういったモノになるのか。公にされた文書がネット上に残っていたので、以下、参考までに。
◆条例
北本市における新駅建設の賛否を問う住民投票条例の制定について
有効投票率の設定は特になし。投票資格は「有権者」。投票結果は「尊重しなければならない」としています。
◆広報
3ページまで、基本、新駅設置を推進する側として、これまでの経緯、設置の意義、効果など、を掲載しています。
◆投票結果
これは確かに「ここまで差が開く」ものなのか、と思いますね。ちなみに、投票率は62.34%だったとのことです。
🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥
住民投票について、「個人の(雑な)感想」です。
もう一人の私「素顔の愚者」が書いた連作。お時間あればで。
私個人は、積極的とまではいかないけれど、どうしても、というなら、絶対不可でもない、くらいではあるのですが・・・
参考までにの資料編。眺めていると、実際、特定の人達が「満足する」以外の意味があるのか、ちょっと分からなくなります・・・
大抵の公共施設・事業は、他の施策とも密接に絡んでいるもの。それを、日々の暮らしに忙しい市民に対して、1つだけヨッコイショと切り離して単純に賛否を問う・・・良いのかなあ、と思いますけどね。