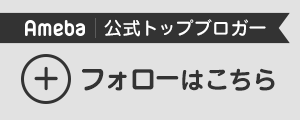皆さま、おはようございます!
北海道に行けば
古い木造駅舎が山ほど見れるとお思いのアナタ!
木造駅舎が残る率は路線によって偏りがあり、
中でも石北本線は低くて
32駅ある中で2駅しか存在してないのです。
ひとつは石北本線の中核駅である遠軽駅。
もうひとつは北見市内にあるこちらの駅でした。
石北本線・東相内(ひがしあいのない)駅です!
戦前築の木造駅舎を持つ駅がありましたが、
利用者が減少したことから廃止
もしくは信号場に変わってしまい、
今は2駅だけになってしまいましたの。
東相内駅、遠軽駅の駅舎はどちらも昭和9年に建てられたモノ。
駅舎に竣工年を記す建物財産標が貼られてましたっけ。
東相内駅は湧別軽便線の駅として大正元年に開業、
当時は軌間が762ミリで「相ノ内駅」という駅名でした。
その後、大正5年に現在の1,067ミリゲージに改軌されると
唱和9年に「東相ノ内駅」に改称。
平成9年には地域名の表記に合わせ、
「東相内駅」に3度目の改称をされてます。
駅名と地域名、読みは一緒でも違う表記…
地元の東北で言ったら常磐線・原ノ町駅(南相馬市原町)や
仙石線・陸前原ノ町駅(宮城野区原町の最寄り)と
同じパターンですね。
今でもどこかに旧駅名「東相ノ内駅」の表記が
残っているんじゃないかと探しましたが、
さすが仕事が丁寧なJR北海道、
「東相ノ内駅」の形跡はどこにも残してませんでしたわ。
唯一見つけることが出来たのがホームに貼られた銘板。
さすがにココは誰も気にしませんわね。
そんなことで、
石北本線内では貴重な戦前築の木造駅舎である
東相内駅の駅舎を堪能してきました。
まずは待合室の中の様子からです。
東相内駅は簡易委託駅の時代を経て
平成4年に無人化されたとのこと。
有人駅時代に使われていた出札窓口や荷物の受け渡し窓口が
形跡がわかる感じで残されてました。
自衛隊や警察の掲示物がやたら多く貼られてました。
このポスター、イラストは心強いですけど
文章の改行に弱点を見たのは自分だけかな?
国鉄時代は、旧・相内村(昭和31年に北見市に編入)の
玄関口である相内駅よりも利用者数が多かった東相内駅。
待合室は広いので、
昔は売店があったのではないでしょうかね?
続いてはホームにイン。
東相内駅は列車の行き違いが可能な
駅舎側に背を向けた単式ホームを2面持つ駅です。
2面のホームは構内踏切で結ばれてましたよ。
ここでは構内の北側に広がる空き地に注目です。
旧・相内村は古くから林業が盛んな地域で
東相内駅から木材の貨物輸送が行われてましたが、
昭和40年代半ばにこれらの荷役施設の用地を転用して
石油基地や農産物の出荷基地が設けられたのです。
下は国土地理院のサイトから転載した昭和52年撮影の航空写真ですが、
構内の西側(左側)に有蓋車や冷蔵車、
東側(右側)にタキ級のタンク車がズラリと並んでる姿が
見えますよね。
昭和45年版の専用線一覧によれば
当時は出光興産、大協石油の貨物専用線が伸びてたようですよ。
もう1本、東相内駅から石北本線に並走するカタチで
北見地方卸売市場に繋がる、
総延長1.8キロの北見市が管轄する専用線もありました。
おそらくは、東相内駅を北見地区の一大貨物拠点に変えようと
構内の改良を試みたのだと思いますが、
昭和60年に東相内駅を発着する貨物列車は廃止され
専用線もまもなく撤去されたのです。
卸売市場まで伸びる専用線が開通したのは昭和46年ですから、
わずか14年で廃止されたわけでして…
広大な空き地はそんな時代があった証です。
駅ファンが空き地を見ながら寂し気な顔をしてるのは
脳内でそんな時代を振り返ってるだけですので、
そっとしてあげてくだされ。
最後はホームから見た木造駅舎の姿で〆ます。
かつて軽便線(軌間762ミリ)の時代があった東相内駅。
2本のホームの間隔が狭いのはその時代の面影なのかな?
などと考えてましたが、
今あるホームは軽便線時代から存在するモノなのか、
ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
訪問駅リスト(JR線)
石北本線(遠軽駅-網走駅)
↑(遠軽駅方面)
東相内駅(平成29年5月23日)
駅探訪記、旅情報を不定期に更新中。
新着情報がすぐ受け取れるフォロワー登録をお願いします!