From:ななころ
プライベートオフィスより
◆『人を動かす』を7回を読むプロジェクト
日本を代表する商売人が、
「この本は良い!」
「私の本を読むぐらいならこの本を読め!」
「7回は読みなさい!」
というほどの名著。
「人を動かす」(デール・カーネギー)
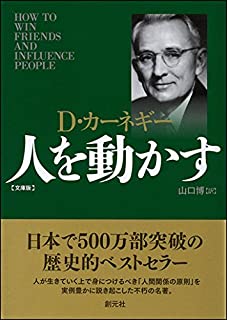
しかし、簡単なようでいて難しい。
なかなか7回も読むことができない。
さらに言うと、1回すらちゃんと読むことができない。。。
ということで、1話づつクイズ形式にしてブログでシェアすれば、ななころが本の内容を理解しながら読み進められるのではないか!?
ついでに、ブログの読者のために役立つのではないか!?
と思い立って始めたプロジェクト。
「『人を動かす』を7回を読むプロジェクト」
「不動産投資のブログなんだから、不動産投資に関して発信してよ」と文句が出そうな企画(笑)。
自己啓発系に興味の無い方や毛嫌いしている人は、どうか読み飛ばしてしまってください。
(毎週1回だけの配信の予定です。)
とはいえ、人生をより良く描くには人間関係を良好に保つことが不可欠。
「人の動かす」の原文タイトルは、
「How to win friensd and infulence people」
(友と影響力のある人を獲得する方法)
ブログ読者様と一緒に「人を動かす」を読み進めながら、良好な人間関係を築いていきたいと考えている次第です。
【第二話】アメリカの最も偉大な大統領リンカーンが、良好な人間関係を保つために大切にしていた言葉は?
【第三話】人を動かすためのたった1つの秘訣とは ?
【第五話】数年間ずっと断られ続けてきた営業マンが、相手の方から「買うよ」と言われるようになった秘訣とは?
【第六話】人生を強力に変える「◯◯」の効果とは?
【第七話】少年時代の成功体験にもととなる、鉄鋼王アンドリュー・カーネギーの成功の秘訣は何か?
【第八話】歴史的なアメリカ女性誌を作り上げた人物が、少年時代にアメリカ中の成功者とつながった秘訣とは?
【第九話】史上最年少42歳でアメリカ大統領になったルーズベルトが考えていた「人の心をとらえる近道」とは?
【第十話】人間関係の重要な法則「相手に重要感を持たせる」その具体的な方法は?
【第十一話】相手と議論になった時、この世にただ1つ最善の解決策とは?
【第十二話】相手が明らかに間違っている時でも、意固地にさせず、誤りを認めさせて、納得してもらうには?
【第十三話】自分の非がある時、相手がすんなり許してくれるためには?
◆カーネギーからのクイズ #013
ある技師の男が、アパートの家賃を下げてもらいたいと大家さんに交渉したいと考えた。
しかし、この大家さん、頑固者で有名。
他の入居者もことごとく交渉に失敗していた。
ところが、この「人を動かす」に書かれていることを実践してみたところ、大家さんの方から「家賃をを少し下げよう」と言ってきた。
さらに、「部屋の装飾を変えてあげよう」とも言ってきた。
さて、この男はどのように大家さんと交渉したのだろうか?

◆答え
ことわざ
「1ガロンの苦汁よりも、一滴のハチミツの方が、多くのハエが取れる」
(A drop of honey catches more flies than a gallon of gall.)
この技師の男は、このことわざ通りのことを実践した。
・このアパートの苦情は決して言わない
・管理が悪いなどとも決して言わない
・そして、家賃が高いなどは決して言い出さない
まずはこう心に誓った。
そして、
・このアパートがとても気に入っていること
・管理が行き届いて感謝していること
・もう一年はここに住みたいと思っていること
こう大家さんに素直に打ち明けたのです。
すると、大家さんは自分の苦労を打ち明け始めたのです。
・苦情ばかり言ってくる入居者
・侮辱的な手紙をよこしてくる入居者
・無茶苦茶な言いがかりをつけてくる入居者
そうした入居者のお陰で苦しめられていることを、正直に話し始めたのです。
そして、入居者の方から、大家の立場を理解してくれたことに感謝を示し、そして家賃を下げようとも提案してくれたのです。
一滴のハチミツの方が、1ガロンの苦汁よりも、ハエをいっぱい捕まえることができるということを、実践してみせたのです。
人を説得する原則④「穏やかに話す。」
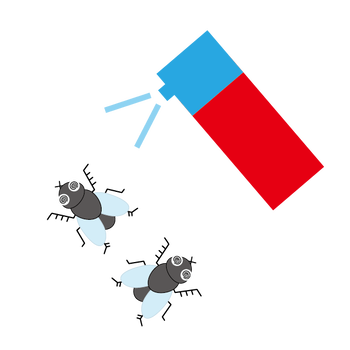
◆ななころの体験談と今後の実践
この章の冒頭にもある通り、
「相手をやり込めようとすればするほど、自分は気持ち良くなるかもしれないが、決してその人を納得させて動かすことは決してできない。」
このことはこの本で、繰り返し繰り返し述べられています。
人を動かす上で最も大事なことなのだと、この本を読みななころは感じています。
不動産投資において、書籍やネットの情報では、
「物件の悪いところを指摘して値下げ交渉をする」
ということが書かれていたりしますが、これはよほど注意しなければなりません。
ななころの失敗談として、購入を検討していた物件で、「建物がひどい状態なので、○○円の修繕が必要なこと」を正直に伝えたところ、破談となってしまいました。
事実だけを伝えるならまだしも、売主との軋轢を生んでしまったのです。
そして数ヶ月後。。。
ななころが購入しようと考えていた金額よりも、さらに安い金額で売買が成立していたことを知ったのです。
もう数年前の話ではありますが、この物件を買えていたら、今ごろはもっと安定した経済基盤を確立できていたことでしょう。
今でも悔やまれる1件です。
ですから、今回この著書から学んだこのことわざをいつまでも教訓として、胸に刻んでおきたいと考えている次第です。
「1ガロンの苦汁よりも、一滴のハチミツの方が、多くのハエが取れる」
(A drop of honey catches more flies than a gallon of gall.)
◆編集後記
このことわざに出てくる「1ガロン」ってどのくらいの量なのだろう?と思って調べてみました。
1ガロンは、イギリスとアメリカが違っていて、それぞれリットルに直すと以下の通りだそうです。
英国=4.545リットル
米国=3.785リットル
もともとガロンはイギリスの単位だそうですから、4.5リットルが正式なのでしょう。
1.5リットルのペットボトル3本分ですね。
人間関係において、こういった「単位の違い」のような小さなミスコミュニケーションによって、いざこざがよく起こるものです。
特に夫婦喧嘩や親子喧嘩でよく起こりますよね。
片方が「これは絶対に1ガロン」と言い張り、もう一方が「これは絶対に4.5リットル」だと言い張って喧嘩になったりするのです。
「どっちが正しいか」の勝ち負けの土俵になってしまうのです。
本当はどちらも正しいことを言っているのにも関わらず。。。。
今回の章もあらため気づきの多くありました。
