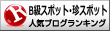前回、日本のマチュピチュといわれる御所ヶ谷神籠石を訪問しました。
もっとも、神籠石のほうがメキシコの遺跡よりずっと古いのですが。
古さでいえば日本だってすごい遺跡があるんだぞーっ、って私は言いたい。
今回は、福岡県飯塚市にある鹿毛馬(かけのうま)神籠石を訪ねました。
こちらの遺跡は、神籠石としては最も標高が低い所にあります。
だから、周辺には住宅街が多いです。神籠石自体は山、というか丘陵の中にあります。
昭和天皇も行幸されたくらい、訪問しやすい神籠石です。
神籠石に妖しい魅力を感じていた私が、最初に訪ねた神籠石でもあります(本当は御所ヶ谷よりも早く訪れていました)。
早速、訪ねてみましょう。
福岡空港からレンタカーで1時間ほど、福岡都市高速や九州自動車道を乗り継いでたどり着きました。
レンタカーを駐車場に止め、最初に訪問した際は牧野神社の参道を歩きました。
入口には史跡指定当時の記念碑が建てられています。
天皇陛下も行幸されたくらいですからね、石碑も建てたくなったことでしょう。
「特別史跡」とありますが、私が調べた範囲では特別史跡に指定されたことはありません。
それでも貴重な遺跡であることは変わりありませんが。
史跡指定記念碑
神籠石の分布は、下の地図のようになっています。
実はここには2度訪ねていて、一度目は地図の中に「大駐車場」の方へ車を止めました。
すると上の写真の石碑があります。
さらに、ここが神籠石の中に祀られている牧野神社の参道入口に当たりました。
鹿毛馬神籠石分布地図
牧野神社は列石の中央に祀られています。
今では鳥居と石祠があるだけです。
2回目に訪ねた際は、丘陵中央を断ち割るように谷筋があることを知って、そちらに近い駐車場(小駐車場)に車を止めました。
この谷、とても気になります。
なぜかというと、列石が囲う丘陵のちょうど真ん中を断ち割るように谷筋があるからです。
鹿毛馬神籠石 中央にある谷筋
しかも、谷の入り口(谷口)には堰堤が設けられているのです。
この堰堤、最初に訪ねた時に私は近代に入ってから造られた貯水用のものだと思っていました。
谷口の土塁
ところがなんと、古代に造られた土塁だと知ったのは、2回目に訪ねる直前でした。
土塁の一部は発掘調査されていて、地中から暗渠が2ヶ所検出されていました。
最初に訪ねた時はこの事を知らなかったので気にも留めていませんでした。
第一の暗渠は排水口が地上に露出していて、現在も見学できます。
第一水門と呼ばれて、排水口の石組が露出していました。
第一水門
第一水門の石組
自然の湿地に排水していたようです。だから水が溜まっているんですね。
切石の風化具合が、いかにも古代から残された遺構っぽいです。
第二暗渠は埋め戻されているため、現在は見ることができません。
そして、谷口を塞ぐように設けられた堰堤。
今回はこの堰堤上の道から神籠石にアプローチします。
藪に覆われた丘陵の中腹を、堰堤から延びる平坦な道を辿っていきました。
列石が頭を出しているので神籠石があるのはわかりますが、あまり人が立ち入る場所ではないようです。とにかく蜘蛛の巣によく引っ掛かりました。
藪をかき分け、蜘蛛の巣を振り払いながらしばらく進むと絶壁が現れました。その裾には四角い石が並んで続いています。
しかしその絶壁、よく見れば土塁の断面です。昭和の初めには列石しか関心が向かなかったのでしょう。
人為的に削られて、版築による土塁の構築の様子が見られます。
鹿毛馬神籠石 列石とその上部の土塁(神籠石北側)
列石はだんだん大きな石になっていきました。
どうですか、豆腐のように真四角な巨石が連なっている様は?
初めて目にしたら「異様」の一言ではないでしょうか?
列石の様子(神籠石北側)
巨大な石が連なる様子
特に牧野神社の参道付近は、人の背丈の半分にも及ぶような高さの石が連なり、列石の異様さに壮大さが加わります。
牧野神社参道付近の列石
この牧野神社、謂われはよくわかりませんが「神籠石=神域」説にひと役買いました。
今は鳥居と石祠が残るのみです。
牧野神社参道脇の列石
この辺りの列石は特に巨大なため、最も異様な感じを醸し出しています。
ああ、でもこれは昭和の初めに造られたものなのか。
最初に訪ねた時はそのことを知らなかったので、遊歩道に沿った列石に、只々異様な印象を見たのでした。
この遊歩道も、昭和の初めに天皇陛下のために削りだされたものなのかと思うと脱力モノです。
北側の列石はこの先で再び石が徐々に小さくなり、やがて確認ができなくなります。
南側の列石も辿ってみました。南側は土塁がまだ見られるだけ遺構の残りは良好です。
ただ北側に比べたら石が小さく、「謎の史跡」としてのインパクトは小さいです。
南側の列石
鹿毛馬神籠石は昭和の初めに列石が強調され過ぎてしまい、その印象ばかりが強い史跡となってしまいました。
何の前情報もなく尋ねた最初の時には、豆腐のように真四角に成形された巨石が並ぶ異様さにインパクトもありました。
でも、その後訪ねた御所ヶ谷や雷山などの神籠石を見ると、今の姿は昭和の初めに造られたものと知ってしまったこともあって、残念さから一歩引いて見てしまうようになりました。
しかし、列石が囲う丘陵の中心部は全く調査の手が入っていませんし、私は丘陵を貫く谷(谷口に堰堤や水門が築かれている谷)の谷頭にきっと何かあると踏んでいます。
だって、マップで見ればそこが中心となって列石があるのですから。
そこに私は神籠石研究を大きく進展させる大きな発見があるのではないかと思います。
また、谷口の水門付近では調査も行われて、面白い発見があったようです。
摩訶不思議な感じを醸す鹿毛馬神籠石、その潜在的な可能性に私は期待しています。
-----------
鹿毛馬神籠石(昭和20年2月・国指定史跡 福岡県飯塚市鹿毛馬)
鹿毛馬神籠石は飯塚市の北東部、鹿毛馬川の東岸にある標高約76mの丘陵中腹に、延々と列石が連なっている遺跡です。神籠石の姿としては典型的なもののようですが、これは昭和10年代に地元の青年団によって露出されたものであり、遺構としては破壊されてしまったものと考えられます。
それは時代の流れとして残念ではありますが、その後も丘陵を横切るように南西方向へ開く谷口にある土塁などが調査され、水門や土塁などが残存していることが明らかになってきました。
神籠石は北九州から中四国、近畿西部に渡って分布しています。
長いこと遺跡の性格がわかっておらず、近年は白村江の戦に関わって築かれた古代山城であるとの説が有力となっていますが、十分な調査は進んでいません。
そのため、はっきりしたことはまだまだ明らかになっていません。
鹿毛馬神籠石はそれらの神籠石の中でも最も低い標高に位置し、その低さは他の神籠石に比しても格段に低い位置にあるためかなり特異な神籠石と考えられます。列石周辺の遺構は失われたかもしれませんが丘陵全体に及んだわけではなく、調査が進めばきっとおもしろい発見が得られる遺跡だろうと私は期待しています。
参考文献:
『よみがえる古代山城』 向井一雄・著、歴史文化ライブラリー、吉川弘文館(2016)
ブログが気に入ったらクリックをお願いします