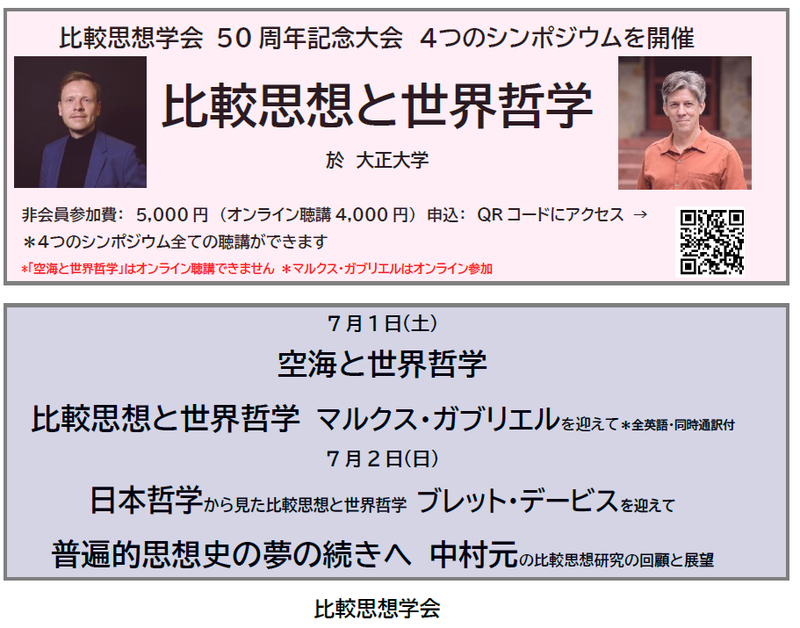: Voix et voies de la décroissance
Les liens qui libèrent
2010
読んだ本
セルジュ・ラトゥーシュ
Serge Latouche(1940- )
〈脱成長〉は、世界を変えられるか? 贈与・幸福・自律の新たな社会へ
中野佳裕訳
作品社
2013年5月
ひとこと感想
本書はイバン・イリイチの「脱~論」の延長線上にあることは間違いない。私はイリイチの所謂「脱学校論」「脱医療化論」「脱自動車社会論」等を学生時代に知り、今なお問い続けているが、こうした論述にふれられること自体、良い刺激ではある。しかし。
***
1960年代後半、フレイレ、イリイチらが、社会における「学校教育」のあり方について、問いを投げかけた後、世界的に「脱学校」論が大きなうねりをつくりあげていったが、その際、イリイチは「脱」ということに用心深くあるべきだととらえていた。
英語では「脱学校」は「deschooling」であるので、少し丹念に言うのであれば、これは「脱学校教育」である。
「schoolong」(学校教育)に対して、イリイチは「deschooling」という語を用いた(正確には出版社がこの言葉を書名にするよう促した)。
de-schooling とは?
私は、この「de- 」とは、端的に、ジョン・レノンが「イマジン」で「天国」や「国」や「所有」がないということを想像してみてほしい、と歌ったあの「Imagine no ~」と同じ意味合いだと思っている。
イリイチは自ら「詩人」であると言っているが、同時に「歴史家」とも言っていた。
すなわち、この「歴史家」とは「物語作家」に近いと思われる。もしくは本質的な意味での「詩人」ということである。
したがって、その後彼が、「開発」や「経済成長」に対する批判を展開していった際にも、端的に「脱」という言葉を用いることに用心深かった。
さらに言えば、この「脱」とは同時に「de- 」のみならず、「ポスト post」の意味合いをも含むゆえ、どうしても、現状批判に対する、これからの指針を打ち出す際に、ごく自然に用いられている(結局のところ「de- 」はデリダの言う「脱構築」を意味することになる)。
それゆえ、このラトゥーシュの言う「脱成長」という言葉に私は、最初は、そのまま素朴に肯定的に受け取ることができなかった。
本書には「補論」として、「"décroissance"という単語の翻訳について」が挿入されている。そこでは成長を前提とした経済の縮小を目指すのであれば、同時に、経済成長という価値観の信仰をやめる、という意味合いが、「croissance」によって(すなわち「信仰 croyance」との近似性から伝わるが、英語やゲルマン語系に置き換えるのは難しいとされている。
近いところで「decreasing growth」や「shrinking」「shrinkage」が提案されているが、ラトゥーシュは「declining」や「decreasing」ではないため、やむなく「degrowth」を受け入れている、ということのようである。
不勉強だったせいで今まで気付かなかったが、この後、ラトゥーシュは、Alain Caillé, Marc Humbert, Serge Latouche, Patrick Viveret, De la convivialité : Dialogues sur la société conviviale à venir, ouvrage collectif Paris, La Découverte, 2011.という共著も出している。
はっきりと、イリイチの遺した思索の延長線上に、「脱成長」の新たな社会を構築しようという強い意志が見いだされる。
本書はこの、イリイチに加え、ジャン=ピエール・デュピュイやコルネリュウス・カストリアディスの思索が大きくとりあげられている。
また、アンドレ・ゴルツや、マーシャル・サーリンズ、ジャン・ボードリヤール、カール・ポランニーはもとより、ギュンター・アンダースやハンス・ヨナス、ローマクラブなど、ところどころに登場する人物や組織名もなじみのあるものばかりである。
それでは、ラトゥーシュの言う「脱成長」とは何か。
「経済成長優先社会、つまり経済成長のために経済成長を行う以外の目的を持たない経済によって構築されている社会との決別の必要性を主張するために発明さえた論争的なスローガンである」(57ページ)
ただし、こう定義した後で、ラトゥーシュは、この言葉が必ずしも「良い」ものとは言えないとしている。
意図されているのは、ともかく、経済成長や経済発展から抜け出すこと、である。
「抜け出す」すなわち「脱」は、「言葉」(表象)の次元と「物」(具体的現実)の次元の両方において求められている。
「持続可能な発展」という語も、当然、「撞着語法」「冗語法」として問題視される。
「発展は持続可能でも維持可能でもない」(61-62ページ)
具体的には、8つの「R」というものを提唱している。
・再評価する
・概念を再構築する
・社会構造を再構築する
・再ローカリゼーションを行う
・再配分を行う
・削減する
・再利用する
・リサイクルを行う
これらによって、「コンビビアルな」脱成長運動が始動可能だとしている。
ただし、これだけではなかなかどっぷりと「成長」のなかに生きている人たちには伝わらないとして、10の政策案を2007年にフランスに対して提案している。
1 持続可能なエコロジカル・フットプリントを回復させる
2 適切な環境税による環境コストの内部化を通して、交通量を削減する
3 経済、政治、社会的諸活動の再ローカリゼーションを行う
4 農民主体の農業を再生する
5 生産性の増加分を労働時間削減と雇用創出に割り当てる
6 対人関係サービスに基づく「生産」を促進する
7 エネルギー消費を1/4まで削減する
8 宣伝広告を行う空間を大幅に制限する
9 科学技術研究の方向性を転換する
10 貨幣を再領有化する
どうであろうか、この10の「指標」は、受け入れられるだろうか。
なお、「コンビビアリティ」について、ラトゥーシュはマルセル・モースの「贈与」論との近似性を指摘している。
「社会的交換の中に贈与の精神を再導入し、アリストテレスの定義するフィリア(友愛)と結びつく」(120ページ)
「楽しみと分かち合いにあふれる生活をつくる道具」(120ページ)が「コンビビアルな道具」であり、具体的には、自転車やミシンが挙げられている。
何よりもイリイチからいろいろなことを学んできた私にとって、こうしたラトゥーシュの言述は、素朴に諸手を挙げて受け入れられるものではないとしても、十分に、共感をもって受け入れられるものではある。
とはいえそう簡単にこうした発言が何かを変えられるかどうか、その点においては、非常に悲観的にとらえざるを得ないのである。