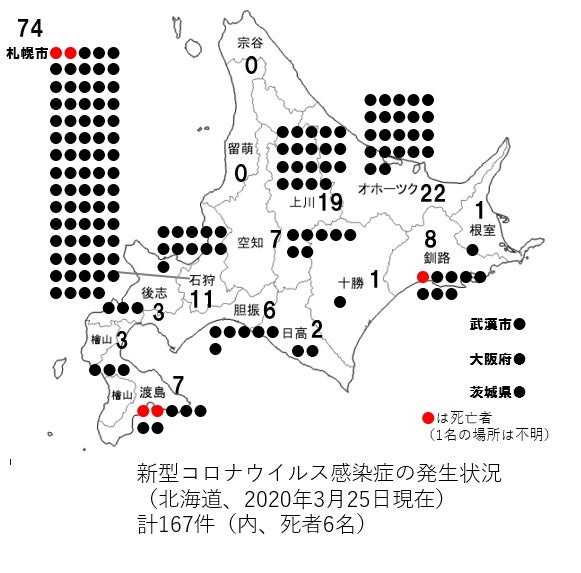観た映画作品
Night of the Living Dead ナイト・オブ・ザ・リビングデッド
George A. Romero ジョージ・A・ロメロ 監督
1968年10月
ひとこと感想
「ゾンビ」映画は、この作品より以前にも現れているが、ゾンビに食われた人間もまたゾンビとなる、という、所謂「ゾンビ映画」のオリジンが本作である。ただし、ここでは「ゾンビ」という言葉は用いられず、「リビング・デッド」と言われている。「リビング・デッド」が放射線の影響により生み出されたのではないか、という設定がなされている。
ロメロは、「ゾンビ」シリーズとして、本作を含め6編をこの世に出している。
1 Night of the Living Dead (1968) ナイト・オブ・ザ・リビングデッド
2 Dawn of the Dead (1978) ゾンビ
3 Day of the Dead (1985) 死霊のえじき
4 Land of the Dead (2005) ランド・オブ・ザ・デッド
5 Diary of the Dead (2007) ダイアリー・オブ・ザ・デッド
6 Survival of the Dead (2009) サバイバル・オブ・ザ・デッド
40年間、ゾンビ映画を作り続けた、骨太である。
しかし、気になるのは、1作目が「リビング・デッド」だったのが、2作目以降は「デッド」となっていることだ。これでは単に「生者」に対する対立項としての「死者」に「ゾンビ」を収めることになってしまう。
「リビング・デッド」すなわち「生ける屍」という矛盾した表現が何とも、たまらない。
それはさておき、この1作目が公開された「1968年」とは、どういう時代だったのか。
「プラハの春」「キング牧師暗殺」「パリ五月革命」「ケネディ暗殺」「三億円事件」などが、出来事として並ぶ。
情報通信関連の環境はどうだったのか。
作品内では、自動車にはラジオが取り付けられており、家には電話とラジオとテレビがある。当然パソコンやインターネット、スマホはない。
ラジオやテレビは有益な情報を提供するが、あくまでも一方向である。世の中で何が起こっているのかを理解するためには役に立つが、自分のまわりで起こっていることを他者や世の中に伝えることはできない。肝心の、双方向でやりとりができる電話は、不幸にもつながらない。
登場人物たちは、一軒家に隠れるが、結局、外部とのやりとりができず、ゾンビに囲まれる。しかも、人間どうしも互いに信頼関係が結べず、対ゾンビの協力もしあえない。
すなわち、7人の人間たちは、「リビング・デッド」によって滅ぼされるのではなく、「リビング・デッド」をきっかけにして、自分たちの共同体の共同性の脆弱性によって敗北するのである。
おそらく、「ゾンビ」映画への関心の高さは、こうした、人間どうしが不信感を抱いて共存しているという現実に対する不安が根底にあるように読める。
この不安感に対して、そうした「他者」を同じ「人間」とみなしたくない、理解したくない、受け入れたくない、殺してしまいたい、という無意識の欲望が垣間見られる、と言うと言い過ぎだろうか。
ともあれ、ゾンビと向き合う人間とその社会が問われているのである。
ところで、本作に登場する「リビング・デッド」の特徴は、以下の通りである。
・挙動はゆっくり
・人間と意思疎通ができない
・人間を食べる
・火が苦手(身体は簡単に燃える)
・頭部への銃撃により活動が止まる
その後多数生み出されるゾンビものは、これらを基本としながらも、さまざまなバリエーションがある。
しかし、ここで注目したいことは、ゾンビの性質や本質よりも、彼らがどうしてこの世にあらわれたのか、その、生み出された原因である。
作品内のラジオやテレビで流された情報によれば、金星に向けて発射された探査衛星が地球に帰還する途中でNASAによって爆破された結果、高水準の放射性物質が地上に降り注ぎ、その結果、死体が「突然変異」を引き起こして、動き出したのではないか、と推定されている。
死者が突然変異を起こすのであれば、生者にも起こっていてもおかしくない、というつっこみは、ここではしないでおこう。
ともかく、死者が放射能によって突然変異を起こし、ゾンビと化したのだ――これは、一体どういうことだろうか。
1960年代後半、世界は、米ソ対立により大量の核兵器が用意され、それらがいつ用いられるか分からない恐怖に怯えていた。1968年に暗殺されたケネディも、一度は核兵器のボタンを押しそうになったことがあった(1962年、キューバ危機)というほど、緊張が続いていた。
それに伴い、映画やアニメ、漫画といった表象の世界においては、核戦争や放射能やその他による人類や地球の滅亡がたびたび語られていたが、それと同時に、放射線の影響で「突然変異」「奇形」「ミュータント」を題材とした作品も現れていた。
放射線による被曝は、遺伝子レベルで影響を与えうるが、短時間における低線量の照射など、条件によっては、結果的にはっきりとしたダメージとならない場合もあることが、現在では知られている。
しかし、広島や長崎における原爆被害や各地で行われた核実験、さらにはTMIやチェルノブイリ原発事故が起こった当時は、さまざまなことが言われた。
核に対する恐怖は、単に、死に至るかもしれないという、けた外れの破壊力というだけでなく、生存者にも、その胎児にも、深刻な影響を及ぼすのではないかという懸念があった。
今のように、放射線の健康被害が明確に数値で示すことができなかった時代があった。その時には、だが、その後の調査からは、はっきりとした影響がある、という結論には至っていない。
それゆえ、科学的には、「放射線」と「突然変異」は今では、結びつきにくくなっている。
しかし、当時jは、この両者は、結びつきうる懸念があった。
さらに言えば、もう一つ、気になる映画作品がある。
邦画で、関川秀雄の「ひろしま」である。これは、「被曝者」と「ゾンビ」との近似性を描いている、と言える。
表象の世界では、このように、ある種の「歪曲」をもって、放射線に対する恐怖心が、「ゾンビ」を生み出したと言える。
人間が人間を食らう、という「禁忌」を破るふるまいが、いわば、放射線がもたらす「影響」ということになるのかもしれない。
すなわち、放射線は、人間社会が形成してきた「禁忌」を踏み越えるのである。
その後、「ゾンビ映画」もバリエーションが増え、寄生虫、ウイルス感染など、さまざまな理由によってゾンビが生み出されるに至り、必ずしも「放射線」でなければならないということはなくなってゆく。
しかし、他方では、ロメロ以外にも、「放射能」を原因とした作品は作られ続けている。
Incubo Sulla Cittá Contaminata ナイトメア・シティ
1980
「ゾンビは放射線の影響により異常に身体能力が向上した人間であり、壊れた赤血球を補充するために血を求めて人を襲い、さらに感染していく」(Wikipediaより)
SOLAR IMPACT ディープインパクト セカンド・クライシス
2019
「隕石の放射線を浴びた人体のDNAが突然変異して凶暴化し、その感染者が爆発的に増殖」といった内容のようである。
なお、ゾンビ映画に関しては、数多くの研究があり、それらを参照したうえで、もう少しきめの細かい考察もしてみたいものだが、残念ながら本稿は今回はここまでにしておく。