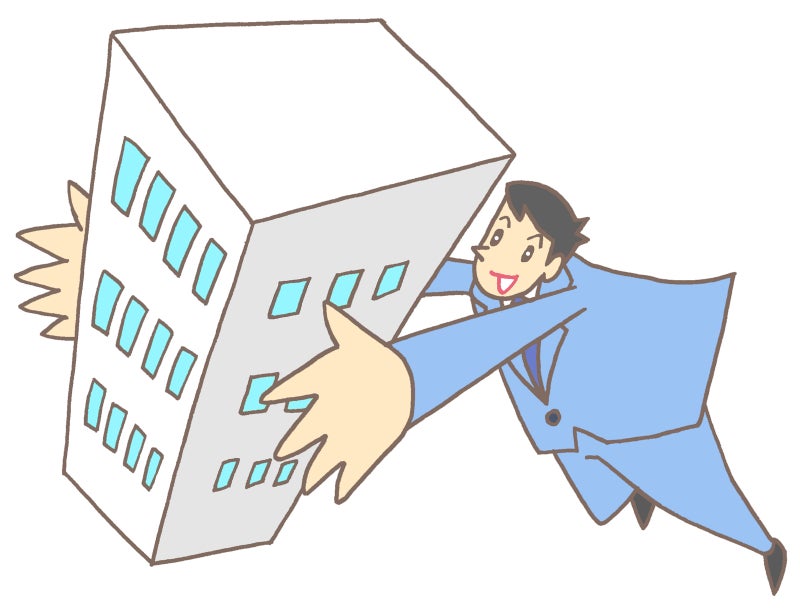●テレビCMが盛んです
テレビで大手の鉄鋼メーカー、素材メーカーやゼネコン、IT企業など一般消費者とは直接取引がない企業が有名女性タレントを起用して、膨大な広告宣伝費を使って求人広告を流している。
これは、ほとんどが新卒学生およびその親向けのブランディング戦略によるリクルートが目的である。
自分の子どもが応募しようとしたところ「そんな会社聞いたことがないからやめときなさい」と反対されないように企業の知名度とイメージアップを図るため、ゴールデンタイムにも流しているのである。今は恒常的に売り手市場が定着した感がある。
大手企業でもこうして人集めには苦労しているくらいなので、ましてや広告宣伝や有料の紹介会社など支払う手数料(求人費)にお金をかけられない中小企業となると、採用の苦労が尽きない。
もっと人を採用したいのだが、どうしたら応募者数が増えるのか、社労士も社長さんから相談を受けることが多い。
●HWでもいろいろサービスがありますが・・
こうした問題の解決策の一つとして、一部のハローワーク(HW)ではリクエスト制度といって、求職者の相談窓口で、求人者から、自社の求人票を希望条件に該当する求職者に(事業所には匿名で)郵送するサービスを受付ていた。(ただし、利用回数と送付数には上限あり)
求人をだしているが全く応募がなく、人手不足で困っている地元の中小企業の採用担当者が時々来窓されて利用されていたが、実際のところ、求人票を郵送してもその求人票を窓口まで持参して応募する人はあまりいなかった。
採用担当者もあまり期待していない感があったが、他に策もなく「ダメ元」の思いで依頼されていた。
(この他にも、場所にもよるがHWの会議室等を利用した個別の就職面接会を実施するサービスもあるので希望するなら一度窓口で相談してみてほしい)
従業員が20~80人くらいの中小企業が多く、その際、採用担当者からいろいろ悩みを聞くことも多かった。
「うちは、給料はそんなに高くないけど、社長は社員思いのいい人で、まあまあええ会社やと思うんやけど、応募が無いんや」
「特に能力の高い人を求めているわけではなく、真面目にコッコツ長く働いてくれる人でええんやけど・・・。窓口でいい人がいたら、うちの求人を勧めてくれへんか」
など、切実な感じでよく相談(依頼)をうけていた。
●求人票の見るところ
一般的に、応募者数を伸ばす方法としては・・・
・HW以外にも他の求人メディア(有料・無料)に掲載し露出度を上げる。
・ホームページで継続した情報発信をしながら企業イメージをあげる。
・競合他社の求人と比べて、雇用条件(賃金、休日等)に遜色はないか確認する。
などが考えられるが、残念ながら即効薬はない。
採用担当者には、求職者は求人票のどこを見ているか? 何を重視するか?という観点で気づいた範囲でアドバイスしていた。
まず、求職者が真っ先に求人票で確認するところは、仕事の内容、賃金、年間休日ということになる。
○仕事の内容
仕事の内容はできるだけ具体的に記載すること。これからはキャリア採用の場合、ジョブ型雇用が主流となっていく。中小企業では職務内容を明確化することは難しいが、例えば「一般事務」だけではなくて「備品管理、受発注業務、伝票処理、役員秘書、電話の応対、来客へのお茶出し、官公庁への届け出 など」とできるだけ具体的に書くことにより、そこで働くイメージがわきやすい。
さらに、この仕事を経験するとこんなスキルが身につきますということが記載されてあればさらに印象はよくなる。
○賃金
賃金は一定額の範囲内なら1円でも多いところという求職者は少なかった。
ただ、昇給のイメージがわきやすいように、例えば 賃金モデルの一例として
30歳 25万円~30万円
35歳 32万円~38万円
:
などと書かれてると、自分のキャリアアップと生活基盤の安定がイメージできるようになり、応募につながることが考えられる。
また、経営リスク(人件費リスク)を考慮するあまり、月額給与は押さえた金額にして、業績連動型の賞与を安定的に高額支給する経営方針の場合、年収ベースでは同額になることが多いのだが求職者にはわかりにくい。給与体系を変えることは大変だが、今の賃上げの流れに合わせて、この機会に賞与の支給月数は減っても、月額給与の思い切った賃上げを検討するいいタイミングかもしれない。
○年間休日
正直、今のご時世、年間休日は、製造業では120日以上、サービス業でも105日以上はないと厳しい。
実際、窓口で求人情報を提供する際に、賃金が多少よくても「この会社は年間休日が少ないのでやめておく」という声が多かったような気がする。併せて平均時間外労働も気にする人も多かった。今の若い人はワークライフバランスを重視する傾向が強いようだ。
この他、転勤のないことも若い人からよく確認をされた。中小企業は該当しないことが多いが、大手企業も「地域限定正社員」という転勤のない職種を設けるようになってきている。
●会社のいいところをできるだけ「見える化」する
そして、なによりいちばん気にするのは「ここは安心して働けるか?」という不安に応えられるようなことが書かれてあるかということになる。
こうした不安を少しでも払拭できるように、求人票の「特記事項」欄に具体的に記載することを勧めていた。
例えば・・・
・この3年で社員○人中、自己都合で退職した人は○人
・正社員の平均勤続年数○年
・年次有給休暇取得率80%以上
・これまでの育児休業利用者○名
・ハラスメント撲滅運動を実施中(通報窓口あり)
・1年に2回、自己申告制度があります
・資格取得に報奨金制度あります
・応募する前に事前の会社見学歓迎。先輩社員との座談会も可能です。仕事のやりがい以外にもつらいことも聞けます。 など
この他『(第75話)ブラックorホワイト迷ったら・・・』で企業の見極め方法を述べたように、国や社労士による優良企業の認証をうけて、求人票に記載するのも有効かと思われる。
ここで「風通しのいいアットホームな雰囲気です」など抽象的なことを書いても、他に書くことがないのかと思われ逆に印象が悪くなる。
これらはいずれも中小企業では難しいことばかりだが、本当にいい人材を採用したいのなら経営者もできる範囲で少しずつでいいので、雇用管理や職場改善をしていかないと、残念ながら応募は増えないことになる。
結局、「応募がない!」と嘆く前に、現在働いている社員の声を大切にし、離職を防ぐ施策を実施して、それをしっかりアピールすることが、応募を増やす一番の方法なのかもしれない。