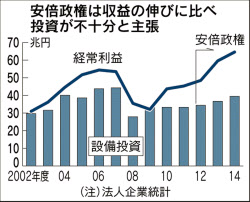絶対に受けたい授業「国家財政破綻」
ブログの説明を入力します。
プロフィール
最新の記事
テーマ
カレンダー
月別
ブログ内検索
このブログのフォロワー
お気に入りブログ
ブックマーク
2016-01-07 05:09:51
鳥巣清典の時事コラム1549「『2016年度も心地の良いぬるま湯状態が続く』元日銀理事」
テーマ:小泉進次郎議員かく語りき 元日銀理事の早川英男・富士通総研エグゼクティブ・フェロー。

NHK『視点・論点』で「2016年の日本経済と世界経済」。
ポイントを記録しておきます。
1、2016年の世界経済の成長率が高まる事は期待しない方がよい。
2、日本経済は昨年の秋頃から輸出も少し増え、一時期の踊り場から抜け出しつつある。世界経済さえ安定していれば、今年も緩やかな回復基調を続ける。
3、ただし政府経済見通しが1・7%、民間見通しで1・5%程度という16年度の経済成長率についてはやや期待が高すぎ。企業収益は高水準を続けるが、昨年が円安と原油安の恩恵をダブルで受けたのと比べれば増益率は下がる。賃金が十分に上がれば良いが、史上最高益、人手不足という絶好の環境にもかかわらず労働組合、連合の賃上げ要求は大変に慎重。政府の要請があってもベア率が昨年を大きく上回る事はないだろう。
4、一方で原油安の影響が薄れていくと物価上昇率は高まっていくため実質賃金はあまり上がらない。16年度の成長率が15年度より目立って高まるとは考えにくい。
5、来年4月の消費税引き上げを前に16年度後半には駆け込み需要が発生する。成長率1%はいくだろう。日本経済の成長天井である潜在成長率が0・5%がない事を考えれば、まずまずともいえる。
6、企業は最高益、労働市場は完全雇用だから強い不満を持つ人は少ないはず。おまけに(2年半が経つが、日銀の物価目標の)2%インフレはまだ遠く、日銀が大量の国債買い入れを続けるので、日本経済の最大の弱点である財政赤字の問題が火を噴く事も当面はない。心地の良いぬるま湯状態が今年も続く事になる。
【鳥巣注】
日銀が大量の国債買い入れを続ける間は、金利の急騰もなく(=国債価格の暴落もなく)、政府のもくろみ通りの「ぬるま湯」状態。もっとも、2020年度までには「プライマリー・バランスの黒字化」という国際公約があります。内閣府の「中長期の経済財政に関する試算」(2015年7月22日)では、「一般会計+一部の特別会計+地方」を合せて2020年には6・2兆円の削減が必要との試算が出ています。
===
【プライマリー・バランス】
<税収から歳出を引いたもので、国債の利払いなどは含んでいない。「黒字化」にするには、過去の債務の利払いは関係なく、毎年入ってくる分と使う分が均衡すればいい。>(髙橋洋一著『アベノミクスの逆襲』) ただしプライマリー・バランスの試算結果は、発生主義という事もあり複雑で国民には数字の意味が分かりにくい。私のそんな感想に内閣府は「先進国でもアメリカは州ごとに政府があり、その上に連邦政府がある。ドイツも、かなり複雑だと聞いています。”見える化”が全て良いという訳ではないという気がします」。(*どうしても実態を知りたい方は、右<ブログテーマ一覧>の「松田まなぶ氏かく語りき」をご覧ください。)
===
いつまで”ぬるま湯”に浸れるのでしょう。
ある会議で小泉進次郎大臣政務官(内閣府)は、こう述べています。

「2020年までの日本経済はそれなりの熱気で運営されるだろう。 しかし2020年を過ぎると、見たくない現実がすべて見えてくる。見たくない現実――人口減少による集落の消滅、財政の危機的な悪化、介護難民の増加、貧困の拡大、 経済の活力の一層の低下、などだ。だからこそ、2020年までのこのチャンスを活かして、思い切った経済活性化を断行しなければならない」。
私も、財務省は最後までハイパーインフレにしない努力を尽くすーーハイパーインフレにすれば政府の借金はチャラになると分かっていてもーーとみています。(もっと深く考えたい人は、右<ブログテーマ一覧」の中の「絶対に受けたい小林慶一郎教授の授業」、あるいは「与謝野馨衆議院議員インタビュー」などを参考にされたらいかがでしょう。)
そのためには、(大幅な歳出カット~消費税アップなどの歳入増の)大ががりな外科手術をする前に経済を活性化させ、国民負担を少しでも少なくする必要がある。
だが現実には日銀が異次元の金融緩和をしていても、企業の設備投資への反応はーー企業論理によりーー鈍い。もともと大企業の海外進出で、円安にすれば輸出でどんどん儲かるという時代でもない。
経済活性化への道には暗雲がたちこめている。
設備投資拡大、官民ですれ違い 企業「規制緩和先決」
NHK『視点・論点』で「2016年の日本経済と世界経済」。
ポイントを記録しておきます。
1、2016年の世界経済の成長率が高まる事は期待しない方がよい。
2、日本経済は昨年の秋頃から輸出も少し増え、一時期の踊り場から抜け出しつつある。世界経済さえ安定していれば、今年も緩やかな回復基調を続ける。
3、ただし政府経済見通しが1・7%、民間見通しで1・5%程度という16年度の経済成長率についてはやや期待が高すぎ。企業収益は高水準を続けるが、昨年が円安と原油安の恩恵をダブルで受けたのと比べれば増益率は下がる。賃金が十分に上がれば良いが、史上最高益、人手不足という絶好の環境にもかかわらず労働組合、連合の賃上げ要求は大変に慎重。政府の要請があってもベア率が昨年を大きく上回る事はないだろう。
4、一方で原油安の影響が薄れていくと物価上昇率は高まっていくため実質賃金はあまり上がらない。16年度の成長率が15年度より目立って高まるとは考えにくい。
5、来年4月の消費税引き上げを前に16年度後半には駆け込み需要が発生する。成長率1%はいくだろう。日本経済の成長天井である潜在成長率が0・5%がない事を考えれば、まずまずともいえる。
6、企業は最高益、労働市場は完全雇用だから強い不満を持つ人は少ないはず。おまけに(2年半が経つが、日銀の物価目標の)2%インフレはまだ遠く、日銀が大量の国債買い入れを続けるので、日本経済の最大の弱点である財政赤字の問題が火を噴く事も当面はない。心地の良いぬるま湯状態が今年も続く事になる。
【鳥巣注】
日銀が大量の国債買い入れを続ける間は、金利の急騰もなく(=国債価格の暴落もなく)、政府のもくろみ通りの「ぬるま湯」状態。もっとも、2020年度までには「プライマリー・バランスの黒字化」という国際公約があります。内閣府の「中長期の経済財政に関する試算」(2015年7月22日)では、「一般会計+一部の特別会計+地方」を合せて2020年には6・2兆円の削減が必要との試算が出ています。
===
【プライマリー・バランス】
<税収から歳出を引いたもので、国債の利払いなどは含んでいない。「黒字化」にするには、過去の債務の利払いは関係なく、毎年入ってくる分と使う分が均衡すればいい。>(髙橋洋一著『アベノミクスの逆襲』) ただしプライマリー・バランスの試算結果は、発生主義という事もあり複雑で国民には数字の意味が分かりにくい。私のそんな感想に内閣府は「先進国でもアメリカは州ごとに政府があり、その上に連邦政府がある。ドイツも、かなり複雑だと聞いています。”見える化”が全て良いという訳ではないという気がします」。(*どうしても実態を知りたい方は、右<ブログテーマ一覧>の「松田まなぶ氏かく語りき」をご覧ください。)
===
いつまで”ぬるま湯”に浸れるのでしょう。
ある会議で小泉進次郎大臣政務官(内閣府)は、こう述べています。
「2020年までの日本経済はそれなりの熱気で運営されるだろう。 しかし2020年を過ぎると、見たくない現実がすべて見えてくる。見たくない現実――人口減少による集落の消滅、財政の危機的な悪化、介護難民の増加、貧困の拡大、 経済の活力の一層の低下、などだ。だからこそ、2020年までのこのチャンスを活かして、思い切った経済活性化を断行しなければならない」。
私も、財務省は最後までハイパーインフレにしない努力を尽くすーーハイパーインフレにすれば政府の借金はチャラになると分かっていてもーーとみています。(もっと深く考えたい人は、右<ブログテーマ一覧」の中の「絶対に受けたい小林慶一郎教授の授業」、あるいは「与謝野馨衆議院議員インタビュー」などを参考にされたらいかがでしょう。)
そのためには、(大幅な歳出カット~消費税アップなどの歳入増の)大ががりな外科手術をする前に経済を活性化させ、国民負担を少しでも少なくする必要がある。
だが現実には日銀が異次元の金融緩和をしていても、企業の設備投資への反応はーー企業論理によりーー鈍い。もともと大企業の海外進出で、円安にすれば輸出でどんどん儲かるという時代でもない。
経済活性化への道には暗雲がたちこめている。
設備投資拡大、官民ですれ違い 企業「規制緩和先決」
- 日本経済新聞 2015/10/16
会議には安倍晋三首相をはじめとする閣僚や経済3団体のトップらが出席した。冒頭、甘利明経済財政・再生相は「過去最高の原資があるのに、投資しないのは重大な経営判断の誤りだ」と口火を切った。首相も「今こそ企業が設備、技術、人材に積極果敢に投資すべきだ」と要請した。
政府による異例の要請の根拠は、2014年度で354兆円にまで積み上がった企業の内部留保だ。このうち現預金は210兆円を占める。ところが7~9月期に日本経済が2期連続のマイナス成長の可能性が指摘されるなど経済の勢いが鈍い。政府内では「過去最高益を上げる企業がお金を貯め込み、投資に回さないからだ」との声が多い。
経済界は露骨な圧力への警戒を強める。経団連の榊原定征会長は「投資拡大のためには法人税率の早期引き下げや前倒し、規制緩和の環境整備が必要だ」と注文を並べ立てた。経済同友会の小林喜光代表幹事も「新産業の創造が不十分で、投資機会が乏しい」と指摘した。
政府は円安が企業の輸出競争力を高めていることを根拠に、製造業による国内回帰が進むとの期待を強めている。ここでも企業側の事情は複雑だ。大手化学メーカー幹部は「海外の工場設備をたたんで国内復帰させるのには1年や2年で済むわけがない」と反発。国内での設備増強に力を入れる素材メーカー首脳は「計画策定から工事まで3~4年は時間がかかる。来年に設備投資をできるほど簡単なものではない」と話す。
製造業の設備年齢は13年時点で16.3年と、過去20年間で5年も老朽化した。設備の更新投資が必要な点については民間側でも異論はない。実際、15年度の設備投資は計画段階で前年度比10%増と総じて強気だ。
だが中国減速などで外需の動向は一段と雲行きが怪しくなっており、企業も投資判断に慎重な姿勢を強めている。金融危機時の教訓から、手元資金を潤沢に確保しておきたいとの考えも企業側には根強い。
脱デフレを掲げたアベノミクスの旧3本の矢のもとで、経済界は政府が求める賃上げに2年連続で応じた。海外の収益環境が悪化するなかで、賃上げ時と同じように政府主導の設備投資増が実現するかは不透明だ。甘利氏は会議終了後の記者会見で、企業が設備投資に積極的な姿勢を示さないなら「さらに強い要請をしたい」と話した。
AD
2016-01-06 08:10:56
鳥巣清典の時事コラム1548「2016年の踊り始めは<スロー>と<サンバ>から」
テーマ:ソーシャル・ダンス2016年頭のレッスン。K先生にも皆さんにも「あけまして、おめでとうございます。本年もよろしくお願いします」。3時間踊るとけっこうな充実感ーー爽快さは格別です。
その後、ダンスの先輩E氏といつものイタリアンワイン&カフェレストラン『サイゼリヤ』へ行き、いつものドリンクバーを注文(280円)。
いつものように私の反省会。E氏は私の踊りで気づいた点や、私からの質問に答えてくれました。いつもながら感謝です。「本年もご指導、ご鞭撻をよろしくお願いします」と頭を下げました。
まずは「スローフォックストロット」ーーK先生の指導の内容確認から。
❶「男性は女性の背中に回した手でしっかりホールド、腰骨を密着させる」。
❷「出だしはТ(「toe」トゥ=つま先)スタートだが、ワルツよりも低く出る。そうすると自然に上がろうとする」。
❸「S(スロー)、Q(クイック)の後のQ(クイック)はすぐに降りないで流す感じ」
❹天秤棒を担いでいるイメージで進み、左右の肩を入れ替える際には大胆に。
❺私の反省点=「スリー・ステップ」の時に右足がアウトステップになりがち。ここだけはタンゴの足ーー後ろ足で送るーーを使う事を忘れないように。
❻ナチュラルターン~インピタスターンのところ、角度も含め上手くいかないーーレッスン中にТ氏から指導してもらいました。
➐テーマは「肩」だと神経はそちらの方にいき、足は「Т(トゥ)」になっていなかったりする。自転車乗りと同じで、全体に自然に神経が行き渡るまでには経験が必要なのでしょうね。
サンバⅢ
次にサンバ。
❶サンバの出だし。
(1)ホイスク×4(4回目回転してP・Pへ)=1a2、1a2、1a2、1a2.
(2)サンバウォークinP・P×3&サイドサンバウォーク=1a2、1a2、1a2、1a2。
(3)クリスクロスボタフォゴ=1a2、1a,2,1a2、1a2。
(4)クリスクロスボルタ=1a2a3a4
私の場合は、とくに(2)のところがうまくない。Т氏に教えてもらったがうまくいかない。Т氏も「僕も最初は相当に苦労した」。いろんな人から教えてもらっています。
❷K先生曰く「流れないで、止めると、もっと楽になる」。体力的にも楽になるし、「溜め=キレ」にもつながるのでしょう。全く初めてのサンバでしたが、やはり楽しくノリやすい踊りのひとつです。
2016-01-05 23:11:14
鳥巣清典の時事コラム1547「15~17世紀『大航海時代の植民地政策』でスペイン帝国は黄金期」
テーマ:西洋史・中東史 歴史書『地中海』を著したブローデル氏の歴史観は、ーー「地理と経済が政治史をつくる」。
スペイン帝国の黄金期の理由は大航海時代の植民地政策
スペイン帝国が黄金期を迎えたのは、大航海時代の「植民地政策」によるものだった。大航海時代は、15世紀中ばから17世紀中ばまで続いた、ヨーロッパ人によるアフリカ・アジア・アメリカ大陸への大規模な航海が行われた時代。主にポルトガルとスペインにより行われた。大航海時代の始まりは、1415年におけるポルトガルのセウタ攻略。終わりの年は、三十年戦争が終結した1648年である。スペインは地中海へも勢力を伸ばし1503年にはナポリ王国を獲得した。
新大陸征服政策はアフリカから黒人奴隷を労働力に
スペイン帝国の黄金期の理由は大航海時代の植民地政策
スペイン帝国が黄金期を迎えたのは、大航海時代の「植民地政策」によるものだった。大航海時代は、15世紀中ばから17世紀中ばまで続いた、ヨーロッパ人によるアフリカ・アジア・アメリカ大陸への大規模な航海が行われた時代。主にポルトガルとスペインにより行われた。大航海時代の始まりは、1415年におけるポルトガルのセウタ攻略。終わりの年は、三十年戦争が終結した1648年である。スペインは地中海へも勢力を伸ばし1503年にはナポリ王国を獲得した。
新大陸征服政策はアフリカから黒人奴隷を労働力に
新大陸への征服は継続され、エンコミエンダ制のもとイスパニョーラ島やキューバなどで砂金の採掘が始まった。また苛酷な労働と疫病で先住民が死亡したため、スペイン人はアフリカから黒人奴隷を新たな労働力として持ち込み、プランテーションでの奴隷労働に従事させた。
スペインは東南アジアではフィリピンを植民地にした
このような新大陸での苛酷な現状はドミニコ会司祭バルトロメ・デ・ラス・カサスによって激しく非難された。ポルトガルがインド航路を発見したことに対抗して、フェルナンド・デ・マガリャーネスに新大陸周りで香料諸島への航路を探検させた。マガリャーネスはマクタン島でラプ=ラプとの戦いによって戦死したが、この大航海をきっかけに、スペインは東南アジアのフィリピンを植民地にした。
アステカ・マヤ・インカ文明などを次々と滅亡させた
1521年にはエルナン・コルテスがアステカ文明を滅ぼし、1520年代中にはペドロ・デ・アルバラードがマヤ文明を滅ぼし、続いて1532年にフランシスコ・ピサロはインカ文明を滅ぼし、スペイン人によって三つの文明が滅ぼされ、アメリカ大陸本土はあらかたスペインの植民地となった。
1545年ボリビアで銀採掘が開始され黄金時代へ
このような新大陸での探検と征服が進む一方で、スペイン人による先住民の支配は社会の荒廃と資源の収奪を極め、メキシコや中央アメリカ、アンデス地方では麻疹や天然痘、百日咳などで人口が激減し、1545年に現ボリビアのポトシ銀山で銀の採掘が開始されると、先住民は徴発され「ミタ」と呼ばれる賦役制度を課された。1550年にはこのような状況の是非を問う「バリャドリード論争」が、ラス・カサスとセプルベダの間で展開された。
だが、このような多大な犠牲の元スペインには大量の銀がもたらされ、スペイン黄金時代を築くことになった。
1571年オスマン帝国とのレバント海戦では雪辱を
16世紀中頃から17世紀前半までの約80年間はスペインが繁栄した時期であり、スペイン史上「黄金の世紀」と呼ばれる。カルロス1世はフランスのフランソワ1世と熾烈な争いの末に神聖ローマ皇帝に即位し、ヨーロッパにも広大な領土をもつことになった。
しかし、オスマン帝国に第一次ウィーン包囲の脅威にさらされ、プレヴェザの海戦ではオスマン帝国に敗北を喫した。
次のフェリペ2世の時代には、新大陸からもたらされた富で最盛期を迎え、1571年のレパントの海戦でオスマン帝国を破り先王の雪辱を果たした。1580年にはポルトガルを併合したことで、ブラジルやアフリカ、インド洋に広がっていたその植民地をも獲得し「太陽の沈まぬ帝国」(スペイン帝国)となった。
スペイン銀の大量流入で価格が下落してインフレに
一方で、それまで南ドイツ、すなわちチロルやボヘミアの銀山が栄えていたが、南米からのスペイン銀の大量流入で、銀の流通量増加による価値の低下でインフレ傾向が起こるいわゆる価格革命、商業革命が起こった。
【商業革命】
コロンブスの新大陸の発見や、ヴァスコ・ダ・ガマの東インド航路の発見などによって、世界貿易の構造が一変し、ヨーロッパにおける交易の中心はローマ帝国以来の地中海域から大西洋岸地域へとシフト。その結果ヨーロッパ内での勢力の交代や、経済・社会・生活に変化が生じた。イタリア、ドイツの東方貿易は衰え、代わってスペイン、ポルトガル、オランダ、イギリスが世界貿易の覇権を握った。そしてヨーロッパ織物工業の勃興を促し、資本主義の発展の前提をつくった。
オランダ・イギリスへ流出した富でスペインは敗戦
さらに、人々の奴隷労働によってアメリカ大陸からスペインに流出した富のほとんどはオランダ、イギリスといった新興国に流出し、スペイン国内では蓄積も産業形成もなされずに、これら西ヨーロッパ先進国の資本の本源的蓄積過程を支えることになった。
最盛期を迎える一方で、足元では”オランダ独立戦争”と呼ばれる八十年戦争やイギリスへ侵攻したアルマダ海戦の敗北など衰退の兆しも現れ始めていた。さらには、スペインの経済を支えていたユダヤ人の追放、改宗への強要など、これらはスペインの停滞・衰退へと向かう要因となった
2016-01-04 08:07:55
鳥巣清典の時事コラム1546「16世紀『地中海』での2項対立を循環する運動と描写したブローデル」
テーマ:西洋史・中東史 16世紀。
日本の歴史では以下のようになる。
中国では、明王朝の時代。
そしてヨーロッパでは、地中海の東西でスペインとトルコの2大帝国が覇を競った時代。
そんな16世紀の地中海を舞台にブローデルは革命的な歴史書『地中海』を書いた。


【フェルナン・ブローデル(Fernand Braudel)】
1902年8月24日 - 1985年11月27日)はフランスの歴史学者。経済状態や地理的条件が世界史において果たす役割に注目し、20世紀の歴史学に大変革を起こした。

『地中海』は「経済・社会史」の視点からの歴史研究
【訳者あとがき】
『地中海』がなぜこれほど多くの人々から賞賛される本であるかを知るた めには、この本が構想から出版までにたどった変遷、つまり『地中海』の歴史その ものをかいつまんで記しておく必要があるだろう。
ブローデルは学位論文のテーマを初めは「フェリーペ2世の地中海政策」(序 文、第I分冊、一九頁)としていた。この研究のモデルとなったのは、リュシアン・ フェーヴルが一九一一年に提出した学位論文『フランシュ・コンテとフェリーペ二 世』(一九一二年刊行)である。

【フェリペ2世(Felipe II, 1527年5月21日 - 1598年9月13日)】
ハプスブルク家のカスティーリャ王国・アラゴン王国(=スペイン)の国王(在位:1556年 - 1598年)。イングランド女王メアリー1世と結婚期間中共同統治者としてイングランド王フィリップ1世(Philip I)の称号を有していた。また1580年からはフィリペ1世(Filipe I)としてポルトガル国王も兼ねた。
1580年にはポルトガル国王も兼任し、イベリア半島を統一するのと同時にポルトガルが有していた植民地も継承した。その繁栄の様は「太陽の沈まない国」と形容された。ポルトガルはイギリスの飛び地ともいえるような同盟国であったから、スペインの繁栄はイギリスにとって面白くなかった。1588年、イギリスはフェリペをアルマダ海戦で破った。
~~~~
現在フランスの一地方であるフランシュ・コンテ は十六世紀には神聖ローマ帝国の一部であった。フェーヴルがやった地域史を拡大 して、地中海地域全体での十六世紀スペインの外交を研究するつもりであった。一 九二三年、ブローデルが二十三歳のとき、つまりアルジェリアのコンスタンティー ヌにリセの教師として赴任する前年のことである。
アルジェリアには一九三二年ま で滞在した。その後、ブラジルのサン・パウロ大学に一九三五年から一九三七年ま で勤めた。ブラジルからフランスに帰る船にリュシアン・フェーヴルが乗り合わせ ていた。これが歴史学的に言って、運命的な転回点となった。 「地理学の成果はどうでもよく、経済や社会問題にはほとんど目を向けることも なかった」(同上)ブローデルが、歴史学の新しい形態、今までの歴史学とは別な かたちで歴史学を構築する。
それは一九二九年にマルク・ブロックとリュシアン・ フェーヴルによって創刊された『アナール』に始まると言ってよい「経済・社会 史」の視点からの歴史研究である。こうして博士論文の主題は地中海とフェリーペ 二世となった。フェリーペ二世と地中海でない点に注意を払っておこう。
「地中海」を巨大な登場人物として描いている
ブローデ ルは地中海を巨大な登場人物として描いているが、この二人の登場人物は、フェー ヴルの言うように、「偉大さは同じではない」(Combats pour l'histoire, 4 Armand Colin, 1992, p. 432)。しかも「地中海」を第一の登場人物とした点が 「すでに大変な新しさ」(同上)である。「フェルナン・ブローデルの博士論文は まったく新しい、ある意味で革命的な」(同上)歴史書であった。
(4) いかなる意味で革命的であったか、フェーヴルやその他の歴史家の所見を 参考にまとめてみよう。 (A) まずブローデルの歴史の理解の仕方ということにふれておく。リュシアン・ フェーヴルが一九五〇年に書いた書評「のびゆく本」(井上幸治編『フェルナン・ ブローデル』新評論、1989)に次のような記述がある。
「見事な腕前を徹底し て持っている歴史家のこの優れた書物、この完璧な著作が、どういう点で、専門家 の傑作とはまったく別のものであり、はるかそれ以上のものになっているかを、概 括的に述べてみよう。それは、歴史の理解の仕方における革命であり、我々が古く から持っている習慣をひっくり返したことである。すなわちきわめて重要な〈歴史 的突然変異〉である。」(三〇七頁)フェーヴルはテーマの選択の見事さもさるこ とながら、「方法、そこに大きな革命がある」(三〇八頁)と述べている。
アフリカ大陸が上で北極海が下の世界地図での地中海
ここで ブローデルの三分法による時間の問題が方法として強調されるが、私としてはブ ローデルが我々の習慣をひっくり返して見せた点を指摘しておこうと思う。本書第 一分冊281頁に「地中海とその他の世界」という図版がある。この地図は通常 我々が思い描く地球の姿と異なって、アフリカ大陸が上に、北極が下になってい る。この上下さかさまの地図で見ると、地中海の空間が真ん中にあって、その上に 人の住めない広大なサハラ砂漠があり、人の住んでいるところは、さらに上のアフ リカ大陸の一部と下の方のヨーロッパ大陸の一部に限定されていることが見えてく る。さらに地中海の半島部分の高地にはあまり人が住んでいないこともわかる。
地理的に見える「16世紀の世界の中心は地中海にある」
こ うして、さかさまの地図から自然の大きさに比べて人間がいかに小さいかといった ことも見えてくるはずである。また地中海を最大規模で考えた場合、陸上ならびに 海上の交通網の中心に地中海があり、十六世紀の世界の中心は、地中海にあるとい うことが地理的に見えてくる。
このことは現在の政治・経済・社会・文化などの諸 問題を考えるときにも大変有効な方法である。つまり普段見ている世界像はつねに 見る者の位置からしか見えないというわけで、たとえば第三世界の人々から現代の 世界を見れば、その世界像は必然的に我々の世界像とは異なるということである。
欧州から見るのではなく世界全体の動きから見る視点
このことはブローデルの地中海を見る視点に大変動があったことを示唆してい る。フランス北東部の出身であるブローデルは「地中海をこよなく愛した」と序文 を書き始めているが、南側のアルジェリアに住み、次いで南半球のブラジルで仕事 をした経験から、地中海をヨーロッパ中心の視点から見るのではなく、世界全体の 動きから見る視点を獲得したのであろう(ただし、現在の時点からブローデルの視 点にイスラム世界に対する配慮が少ないといった批判があることに対してあらかじ め弁護しておけば、ブローデルが本書のもとになる古文書の調査を行っていた時代 には、トルコ側の資料は整理されていないから「内側から迫ることは」できず、西 側世界に残されたトルコ関係の資料に限られていたという時代的制約があったこと を忘れないでいただきたいし、「トルコの古文書を徹底的に調査したとき、はじめ て事態の全体を掴むことができるようになる」と著者自身が述べている)。
政治・外交・経済・社会・文明をひっくるめた「全体史」
全体の動きというのは、ブローデルの言葉で言うなら「全体史」ということにな る。政治史だけでない。外交史だけでない。経済も社会も文明もひっくるめて一つ の世界を考察するということである。そういう視点から歴史を見れば、歴史に登場 する個々の人間の営為は「長期の時間」の展望のなかでは小さなものである。しか しながらいわゆる事件史が決してないがしろにされているわけでないことも本書の 記述からわかるだろうし、人名・地名索引に登場する人物の数を列挙してみれば、 本書に登場する人物がいかに多いかもわかるだろう。
個人の意志を超えた集団の「運命」が最後に勝利を収める
ただブローデルは個人の意志 を越えた集団の「運命」が最終的には勝ちを収めると考えているのだ。 (B) 方法の新しさとして指摘しておくべきことは、スペインの政治の大枠をその歴 史的、地理的な環境のなかで位置づけ直し、人間のさまざまな意志に働きかける 「恒常的な力」を研究したことである。これはブローデルが「構造」と呼ぶもので あり、この力はそれと知らずに人間の意志に作用を及ぼして、しかじかの方向に人 間を導いていくものである。(中略)
「地理」をブローデルは”ほとんど動かない歴史”と呼んだ
7 (C) ブローデル以前の歴史書のほとんどが地理を歴史の後景としてほんの序論程度 にしか扱っていなかったのとは大きく異なり、ヴィダル=ド=ラ=ブラッシュの 『人文地理学原理』の影響で、第I部は長大な地理学的試論となっている。これも大 きな特徴である。フランソワ・ドスは「ブローデルの仕事はすべてヴィダルの遺産 のなかで読むことができる」(Ibid., p. 134)とさえ述べているが、私は「地理学者 ブローデル」という一章を書いている地理学者イヴ・ラコストにならって、これは のちの『フランスのアイデンティティー』に当てはまる言葉だと思う (Yves Lacoste, Paysages politiques, le livre de poche, 1990, p. 108)。
歴史を考察する上で地理が果たす役割は非常に大きい
しかしながら、たとえば経済史が話題になる本書第II部で経済活動にとっての 「第一の敵としての空間」がニュースの伝播速度や地中海を航行する船の速度とい う時間との関係で問題になるように、ブローデルにとって歴史を考察する上で地理 が果たす役割は非常に大きいのである。
地理という概念そのものがヴィダル=ド= ラ=ブラッシュよりもはるかに広く、ダイナミックである。ダイナミックであると いうのは、たとえば地中海の交易が盛んになってガレー船の数が増えれば、まずガ レー船建造のための木材が大量に必要になって、森林乱伐がおこなわれ、その結果 洪水が起こりやすくなり、一方の繁栄が他方の破壊をもたらすというエコ・システ ムの構造を視野に入れているという意味である。
地中海の衰退は1650年か1680年以降ーと遅めの設定
ブローデルは「地理学的決定論」 という言い方さえしているけれども、「ほとんど動かない歴史」と呼んだ地理を考 える際に、この「ほとんど」という言葉は重要である。まったく動かないという意 味ではなく、たとえば三十周年の周期で氷河が移動しているように、あるいは気候 の変化には温暖化と寒冷化の繰り返しがあるように、徐々に変化している歴史をも つ地理、まさに「長期持続」と名付けられる長期の時間における「変化」を「新しい歴史」の対象としているからである。
こうして地中海の衰退がいつかという問題 が論じられるが、ブローデルはまさに長い物差しで測定した上で、十六世紀ではな く、一六五〇年か一六八〇年以降という遅めの日付にしている。
地中海の東西にスペインとトルコの2大帝国が覇権争い
(D) さらに、これはヨーロッパの思考法の根幹をなしているものだが、ブローデル の歴史研究の方法の基本に言語学では馴染み深い二項対立がはっきりと見られる。
十六世紀にスペインとトルコという二大帝国が地中海の東西にあって、覇権を争う 時代を考察する際に、思いつくままに列挙するだけでも、次のような二項対立があ る。山/海、陸路/海路、自然/人間、夏/冬、戦争/平和、地中海の東/西、キリス ト教世界/イスラム教世界、地中海/大西洋、大西洋/インド洋、北欧の小麦/トルコ の小麦、定住/遊牧、北ヨーロッパ/南ヨーロッパ、カトリック/プロテスタント、 人間の住む地中海地域/人の住めない砂漠、金/銀、都市国家/領土国家、繁栄/衰 退、など数えだしたら切りがないほどである。
2項対立を循環する”運動”というダイナミズムで描写
二項対立という古典的な比較の方法 を完全に我がものとしているが、それだけなら別に目新しいものではない。ブロー デルはこれらの対立、相補関係、相互干渉を、要するに景気循環に見られるような 運動を持つものというダイナミズムにおいて描き出しているのである。歴史はすべ てダイナミズムであるということであり、ブローデルの歴史の展望は必然的に世界 的規模となり、地中海世界の概念そのものも北はロシアのカスピ海、南はサハラ砂 漠の南まで、西は大西洋、東は黒海、さらにはシルクロードを経由して中国まで、 と大変広い範囲にわたるものである。
この空間的規模の大きさ自体、地中海を考える際に画期的なことであった。したがってブローデルの方法は、可能な限り長い時間、可能な限り広い空間を通して歴史のダイナミズムを把握しようとするところにある。
======
【鳥巣注】
現代の日中の2項対立に米を加えた”政治”は、その地理は動かし難くーーブローデル流にいえばこれまたーー「循環する歴史の運動」。
その場合の日中米の歴史とは、政治・外交・経済・社会・文明をひっくるめた「全体史」となる。この3カ国の文明とは何か、政治、経済、外交、社会とはーこの未完の歴史書のタイトルは『太平洋』。

--私の初夢だったような気がするのですが・・。「日中米」という視点に立てば、何がその国の運命を最も変えてきたかは各自異なるのかもしれないが、共通点は「戦争(異なる同盟を含む)」と「経済(市場&競争を含む)」と「文化交流(日本が輸入過多だが)」。
【鳥巣注②】
ブローデルが最も重視するのが、とりわけ経済史。スペインとトルコとの覇権争いの場面でも、クライマックスの海戦はほんの一瞬で終わってしまう。代わりに、地中海の地理的条件や、当時の物流、金融の話に力点を置く。ブローデルの歴史観はーー「地理と経済が政治史をつくる」。
日本の歴史では以下のようになる。
| 戦国時代 | 1467年(1493年) – 1590年 |
| 安土桃山時代 | 1573年 – 1603 |
そしてヨーロッパでは、地中海の東西でスペインとトルコの2大帝国が覇を競った時代。
そんな16世紀の地中海を舞台にブローデルは革命的な歴史書『地中海』を書いた。

【フェルナン・ブローデル(Fernand Braudel)】
1902年8月24日 - 1985年11月27日)はフランスの歴史学者。経済状態や地理的条件が世界史において果たす役割に注目し、20世紀の歴史学に大変革を起こした。
『地中海』は「経済・社会史」の視点からの歴史研究
【訳者あとがき】
『地中海』がなぜこれほど多くの人々から賞賛される本であるかを知るた めには、この本が構想から出版までにたどった変遷、つまり『地中海』の歴史その ものをかいつまんで記しておく必要があるだろう。
ブローデルは学位論文のテーマを初めは「フェリーペ2世の地中海政策」(序 文、第I分冊、一九頁)としていた。この研究のモデルとなったのは、リュシアン・ フェーヴルが一九一一年に提出した学位論文『フランシュ・コンテとフェリーペ二 世』(一九一二年刊行)である。
【フェリペ2世(Felipe II, 1527年5月21日 - 1598年9月13日)】
ハプスブルク家のカスティーリャ王国・アラゴン王国(=スペイン)の国王(在位:1556年 - 1598年)。イングランド女王メアリー1世と結婚期間中共同統治者としてイングランド王フィリップ1世(Philip I)の称号を有していた。また1580年からはフィリペ1世(Filipe I)としてポルトガル国王も兼ねた。
スペイン帝国・スペイン黄金世紀の最盛期に君臨した偉大なる王で、絶対主義の代表的君主の一人とされている。彼の治世はスペイン帝国の絶頂期に当たり、ヨーロッパ、中南米、アジア(フィリピン)に及ぶ大帝国を支配し、地中海の覇権を巡って争ったオスマン帝国を退けて勢力圏を拡大した。
1580年にはポルトガル国王も兼任し、イベリア半島を統一するのと同時にポルトガルが有していた植民地も継承した。その繁栄の様は「太陽の沈まない国」と形容された。ポルトガルはイギリスの飛び地ともいえるような同盟国であったから、スペインの繁栄はイギリスにとって面白くなかった。1588年、イギリスはフェリペをアルマダ海戦で破った。
~~~~
現在フランスの一地方であるフランシュ・コンテ は十六世紀には神聖ローマ帝国の一部であった。フェーヴルがやった地域史を拡大 して、地中海地域全体での十六世紀スペインの外交を研究するつもりであった。一 九二三年、ブローデルが二十三歳のとき、つまりアルジェリアのコンスタンティー ヌにリセの教師として赴任する前年のことである。
アルジェリアには一九三二年ま で滞在した。その後、ブラジルのサン・パウロ大学に一九三五年から一九三七年ま で勤めた。ブラジルからフランスに帰る船にリュシアン・フェーヴルが乗り合わせ ていた。これが歴史学的に言って、運命的な転回点となった。 「地理学の成果はどうでもよく、経済や社会問題にはほとんど目を向けることも なかった」(同上)ブローデルが、歴史学の新しい形態、今までの歴史学とは別な かたちで歴史学を構築する。
それは一九二九年にマルク・ブロックとリュシアン・ フェーヴルによって創刊された『アナール』に始まると言ってよい「経済・社会 史」の視点からの歴史研究である。こうして博士論文の主題は地中海とフェリーペ 二世となった。フェリーペ二世と地中海でない点に注意を払っておこう。
「地中海」を巨大な登場人物として描いている
ブローデ ルは地中海を巨大な登場人物として描いているが、この二人の登場人物は、フェー ヴルの言うように、「偉大さは同じではない」(Combats pour l'histoire, 4 Armand Colin, 1992, p. 432)。しかも「地中海」を第一の登場人物とした点が 「すでに大変な新しさ」(同上)である。「フェルナン・ブローデルの博士論文は まったく新しい、ある意味で革命的な」(同上)歴史書であった。
(4) いかなる意味で革命的であったか、フェーヴルやその他の歴史家の所見を 参考にまとめてみよう。 (A) まずブローデルの歴史の理解の仕方ということにふれておく。リュシアン・ フェーヴルが一九五〇年に書いた書評「のびゆく本」(井上幸治編『フェルナン・ ブローデル』新評論、1989)に次のような記述がある。
「見事な腕前を徹底し て持っている歴史家のこの優れた書物、この完璧な著作が、どういう点で、専門家 の傑作とはまったく別のものであり、はるかそれ以上のものになっているかを、概 括的に述べてみよう。それは、歴史の理解の仕方における革命であり、我々が古く から持っている習慣をひっくり返したことである。すなわちきわめて重要な〈歴史 的突然変異〉である。」(三〇七頁)フェーヴルはテーマの選択の見事さもさるこ とながら、「方法、そこに大きな革命がある」(三〇八頁)と述べている。
アフリカ大陸が上で北極海が下の世界地図での地中海
ここで ブローデルの三分法による時間の問題が方法として強調されるが、私としてはブ ローデルが我々の習慣をひっくり返して見せた点を指摘しておこうと思う。本書第 一分冊281頁に「地中海とその他の世界」という図版がある。この地図は通常 我々が思い描く地球の姿と異なって、アフリカ大陸が上に、北極が下になってい る。この上下さかさまの地図で見ると、地中海の空間が真ん中にあって、その上に 人の住めない広大なサハラ砂漠があり、人の住んでいるところは、さらに上のアフ リカ大陸の一部と下の方のヨーロッパ大陸の一部に限定されていることが見えてく る。さらに地中海の半島部分の高地にはあまり人が住んでいないこともわかる。
地理的に見える「16世紀の世界の中心は地中海にある」
こ うして、さかさまの地図から自然の大きさに比べて人間がいかに小さいかといった ことも見えてくるはずである。また地中海を最大規模で考えた場合、陸上ならびに 海上の交通網の中心に地中海があり、十六世紀の世界の中心は、地中海にあるとい うことが地理的に見えてくる。
このことは現在の政治・経済・社会・文化などの諸 問題を考えるときにも大変有効な方法である。つまり普段見ている世界像はつねに 見る者の位置からしか見えないというわけで、たとえば第三世界の人々から現代の 世界を見れば、その世界像は必然的に我々の世界像とは異なるということである。
欧州から見るのではなく世界全体の動きから見る視点
このことはブローデルの地中海を見る視点に大変動があったことを示唆してい る。フランス北東部の出身であるブローデルは「地中海をこよなく愛した」と序文 を書き始めているが、南側のアルジェリアに住み、次いで南半球のブラジルで仕事 をした経験から、地中海をヨーロッパ中心の視点から見るのではなく、世界全体の 動きから見る視点を獲得したのであろう(ただし、現在の時点からブローデルの視 点にイスラム世界に対する配慮が少ないといった批判があることに対してあらかじ め弁護しておけば、ブローデルが本書のもとになる古文書の調査を行っていた時代 には、トルコ側の資料は整理されていないから「内側から迫ることは」できず、西 側世界に残されたトルコ関係の資料に限られていたという時代的制約があったこと を忘れないでいただきたいし、「トルコの古文書を徹底的に調査したとき、はじめ て事態の全体を掴むことができるようになる」と著者自身が述べている)。
政治・外交・経済・社会・文明をひっくるめた「全体史」
全体の動きというのは、ブローデルの言葉で言うなら「全体史」ということにな る。政治史だけでない。外交史だけでない。経済も社会も文明もひっくるめて一つ の世界を考察するということである。そういう視点から歴史を見れば、歴史に登場 する個々の人間の営為は「長期の時間」の展望のなかでは小さなものである。しか しながらいわゆる事件史が決してないがしろにされているわけでないことも本書の 記述からわかるだろうし、人名・地名索引に登場する人物の数を列挙してみれば、 本書に登場する人物がいかに多いかもわかるだろう。
個人の意志を超えた集団の「運命」が最後に勝利を収める
ただブローデルは個人の意志 を越えた集団の「運命」が最終的には勝ちを収めると考えているのだ。 (B) 方法の新しさとして指摘しておくべきことは、スペインの政治の大枠をその歴 史的、地理的な環境のなかで位置づけ直し、人間のさまざまな意志に働きかける 「恒常的な力」を研究したことである。これはブローデルが「構造」と呼ぶもので あり、この力はそれと知らずに人間の意志に作用を及ぼして、しかじかの方向に人 間を導いていくものである。(中略)
「地理」をブローデルは”ほとんど動かない歴史”と呼んだ
7 (C) ブローデル以前の歴史書のほとんどが地理を歴史の後景としてほんの序論程度 にしか扱っていなかったのとは大きく異なり、ヴィダル=ド=ラ=ブラッシュの 『人文地理学原理』の影響で、第I部は長大な地理学的試論となっている。これも大 きな特徴である。フランソワ・ドスは「ブローデルの仕事はすべてヴィダルの遺産 のなかで読むことができる」(Ibid., p. 134)とさえ述べているが、私は「地理学者 ブローデル」という一章を書いている地理学者イヴ・ラコストにならって、これは のちの『フランスのアイデンティティー』に当てはまる言葉だと思う (Yves Lacoste, Paysages politiques, le livre de poche, 1990, p. 108)。
歴史を考察する上で地理が果たす役割は非常に大きい
しかしながら、たとえば経済史が話題になる本書第II部で経済活動にとっての 「第一の敵としての空間」がニュースの伝播速度や地中海を航行する船の速度とい う時間との関係で問題になるように、ブローデルにとって歴史を考察する上で地理 が果たす役割は非常に大きいのである。
地理という概念そのものがヴィダル=ド= ラ=ブラッシュよりもはるかに広く、ダイナミックである。ダイナミックであると いうのは、たとえば地中海の交易が盛んになってガレー船の数が増えれば、まずガ レー船建造のための木材が大量に必要になって、森林乱伐がおこなわれ、その結果 洪水が起こりやすくなり、一方の繁栄が他方の破壊をもたらすというエコ・システ ムの構造を視野に入れているという意味である。
地中海の衰退は1650年か1680年以降ーと遅めの設定
ブローデルは「地理学的決定論」 という言い方さえしているけれども、「ほとんど動かない歴史」と呼んだ地理を考 える際に、この「ほとんど」という言葉は重要である。まったく動かないという意 味ではなく、たとえば三十周年の周期で氷河が移動しているように、あるいは気候 の変化には温暖化と寒冷化の繰り返しがあるように、徐々に変化している歴史をも つ地理、まさに「長期持続」と名付けられる長期の時間における「変化」を「新しい歴史」の対象としているからである。
こうして地中海の衰退がいつかという問題 が論じられるが、ブローデルはまさに長い物差しで測定した上で、十六世紀ではな く、一六五〇年か一六八〇年以降という遅めの日付にしている。
地中海の東西にスペインとトルコの2大帝国が覇権争い
(D) さらに、これはヨーロッパの思考法の根幹をなしているものだが、ブローデル の歴史研究の方法の基本に言語学では馴染み深い二項対立がはっきりと見られる。
十六世紀にスペインとトルコという二大帝国が地中海の東西にあって、覇権を争う 時代を考察する際に、思いつくままに列挙するだけでも、次のような二項対立があ る。山/海、陸路/海路、自然/人間、夏/冬、戦争/平和、地中海の東/西、キリス ト教世界/イスラム教世界、地中海/大西洋、大西洋/インド洋、北欧の小麦/トルコ の小麦、定住/遊牧、北ヨーロッパ/南ヨーロッパ、カトリック/プロテスタント、 人間の住む地中海地域/人の住めない砂漠、金/銀、都市国家/領土国家、繁栄/衰 退、など数えだしたら切りがないほどである。
2項対立を循環する”運動”というダイナミズムで描写
二項対立という古典的な比較の方法 を完全に我がものとしているが、それだけなら別に目新しいものではない。ブロー デルはこれらの対立、相補関係、相互干渉を、要するに景気循環に見られるような 運動を持つものというダイナミズムにおいて描き出しているのである。歴史はすべ てダイナミズムであるということであり、ブローデルの歴史の展望は必然的に世界 的規模となり、地中海世界の概念そのものも北はロシアのカスピ海、南はサハラ砂 漠の南まで、西は大西洋、東は黒海、さらにはシルクロードを経由して中国まで、 と大変広い範囲にわたるものである。
この空間的規模の大きさ自体、地中海を考える際に画期的なことであった。したがってブローデルの方法は、可能な限り長い時間、可能な限り広い空間を通して歴史のダイナミズムを把握しようとするところにある。
======
【鳥巣注】
現代の日中の2項対立に米を加えた”政治”は、その地理は動かし難くーーブローデル流にいえばこれまたーー「循環する歴史の運動」。
その場合の日中米の歴史とは、政治・外交・経済・社会・文明をひっくるめた「全体史」となる。この3カ国の文明とは何か、政治、経済、外交、社会とはーこの未完の歴史書のタイトルは『太平洋』。
--私の初夢だったような気がするのですが・・。「日中米」という視点に立てば、何がその国の運命を最も変えてきたかは各自異なるのかもしれないが、共通点は「戦争(異なる同盟を含む)」と「経済(市場&競争を含む)」と「文化交流(日本が輸入過多だが)」。
【鳥巣注②】
ブローデルが最も重視するのが、とりわけ経済史。スペインとトルコとの覇権争いの場面でも、クライマックスの海戦はほんの一瞬で終わってしまう。代わりに、地中海の地理的条件や、当時の物流、金融の話に力点を置く。ブローデルの歴史観はーー「地理と経済が政治史をつくる」。
2016-01-04 05:47:35
鳥巣清典の時事コラム1545「14~17世紀<明>李氏朝鮮救援(文禄・慶長の役)の出費で財政破綻
テーマ:日中米国交史明
明(みん、1368年 - 1644年)は中国の歴代王朝の一つである。明朝あるいは大明とも号した。
朱元璋が元を北へ逐って建国し、滅亡の後には清が明の再建を目指す南明政権を制圧して中国を支配した。
1368年~1644年
ー1580年の明国の領域(チベット・満州
は除くー
1368年明を建国、江南出の王朝が初の中国統一
モンゴル人が建てた元朝は14世紀に入ると帝位の相続争いが起こり、統治能力が低下した。さらに疫災が相次いだため、白蓮教徒が1351年に紅巾の乱を起こすと反乱は瞬く間に広がった。紅巾軍の一方の将領であった貧農出身の朱元璋(太祖・洪武帝)は南京を根拠に長江流域の統一に成功し、1368年に明を建国した。
洪武帝は建国するとただちに北伐を始め、順帝(トゴン・テムル・ハーン)は大都(北京)を放棄して北に逃れ、万里の長城以南の中国は明に統一される。江南から誕生した王朝が中国を統一したのは明が唯一である。1402年、永楽帝の即位により、政治の中心は再び北京へと移った。
大艦隊を派遣してアフリカ東海岸にまで大遠征
領土の拡大
永楽帝は北京に遷都し洪武帝の慎重策を改めて盛んに勢力を広げた。北に退いた元朝の余党(北元、明ではこれを韃靼と呼んだ)は1388年にトゴン・テムル・ハーンの王統が断絶していたが、永楽帝は遠征により制圧した。満洲では女真族を服属させて衛所制に組み込むことに成功した。南方ではベトナムを陳朝の内乱に乗じて征服した。
さらに海外の東南アジア、インド洋にまで威信を広げるべく鄭和に率いられた大艦隊を派遣し、一部はメッカ、アフリカ東海岸まで達する大遠征の結果、多数の国々に明との朝貢関係を結ばせた。
永楽帝の死後、モンゴルへの遠征、東南アジアへの艦隊派遣は中止され、ベトナムでは征服からわずか20年で黎朝が独立した。しかし永楽帝の子洪熙帝、孫宣徳帝の二代に明は国力が充実し、最盛期と評価される(仁宣の治)。
16世紀モンゴル勢力や倭寇に明は悩まされる
北虜南倭の危機
一方このころ、モンゴル高原では西モンゴルのオイラトが力をつけ、モンゴルを制圧したオイラト族長エセン・ハーンは明へ侵攻してきた。1449年、英宗は側近の宦官王振の薦めでオイラトに親征を行ったが、自ら捕虜となる大敗を喫した(土木の変)。
エセン・ハーンは内紛で殺され危機を免れたが、後に帰還して奪門の変で復位した英宗以来、歴代の皇帝は紫禁城から出ることを好まず、また政治を顧みない皇帝も多く、国勢はしだいに低調となった。また、同時期1448年、小作人鄧茂七が地主への冬牲や小作人負担による小作料運搬の免除を求めて反乱を起こし、鎮圧には成功したものの最終的に叛徒は数十万人に膨れ上がっている。
16世紀に入ると倭寇が中国人の密貿易商人と結びついて活動を始め、沿岸部を脅かすようになった(後期倭寇)。さらにモンゴルではクビライの子孫とされるダヤン・ハーンが即位し、オイラトに対抗してモンゴルの再統一を成し遂げた。オルドス地方に分封されたダヤン・ハーンの孫アルタン・ハーンは16世紀中ごろに頻繁に中国に侵入し、1550年には北京を攻囲した(庚戌の変)。
明を悩ませた、この時代の倭寇とモンゴルを併称して「北虜南倭」と呼ぶ。
李氏朝鮮救援(文禄・慶長の役)の出費で財政破綻
明の衰亡
1572年、わずか10歳の万暦帝が即位した。はじめの10年間は内閣大学士張居正が政権を取り、国政の立て直しが計られたが、張居正の死後親政が始まると帝は政治を放棄した。在位は48年に及ぶが、途中日本に攻撃された李氏朝鮮の救援(文禄・慶長の役)などの出費がかさみ、財政が破綻した。
【文禄・慶長の役】
文禄元年/万暦20年/宣祖25年(1592年)に始まって翌文禄2年(1593年)に休戦した文禄の役と、慶長2年(1597年)の講和交渉決裂によって再開されて慶長3年/万暦26年/宣祖31年(1598年)の太閤豊臣秀吉の死をもって日本軍の撤退で終結した慶長の役とを、合わせた戦役の総称
1644年、、清が李自成を破って北京を占領し、中国支配を宣言すると、中国南部にいた明の皇族と官僚は南明を建て清に抵抗したが、雲南からビルマに逃げ込んだ永暦帝を最後に滅ぼされた。南明は日本の徳川幕府に何度も援軍の派遣や物資援助を要請している。御三家や薩摩藩は出兵に対して乗り気であったとの記録がある。日本側は清への手前、公式に援助を行なうことが出来ないため鄭氏の交易利権(長崎貿易)を黙認することによって間接的に援助した。
1724年、明の代王朱彝の孫、朱之璉(注:中文)が清の雍正帝より一等延恩侯の爵位を授けられ、以後はその子孫に明の祭祀が引き継がれた。
(*参考資料ウィキペディア)
2016-01-04 04:25:46
鳥巣清典の時事コラム1544「13~14世紀<元>初めて”外敵”と戦った日本=1274年・元寇」
テーマ:日中米国交史元
元はモンゴル人が建国し中国を支配した征服王朝
元(げん)は、1271年から1368年まで中国とモンゴル高原を中心とした領域を支配した王朝である。正式の国号は大元(だいげん)で、元朝(げんちょう)とも言う。モンゴル人のキヤト・ボルジギン氏が建国した征服王朝で国姓は「奇渥温」である。
モンゴル政権では、モンゴル王侯によって自ら信奉する宗教諸勢力への多大な寄進が行われており、仏教や道教、孔子廟などの儒教など中国各地の宗教施設の建立、また寄進などに関わる碑文の建碑が行われた。モンゴル王侯や特権に依拠する商売で巨利を得た政商は、各地の宗教施設に多大な寄進を行い、経典の編集や再版刻など文化事業に資金を投入した。大元朝時代も金代や宋代に形成された経典学研究が継続し、それらに基づいた類書などが大量に出版された[9]。南宋末期から大元朝初期の『事林広記』や大元朝末期『南村輟耕録』などがこれにあたる。朱子学の研究も集成され、当時の「漢人」と呼ばれた漢字文化を母体とする人々は、金代などからの伝統として道教・仏教・儒教の三道に通暁することが必須とされるようになった。鎌倉時代後期に大元朝から国使として日本へ派遣された仏僧一山一寧もこれらの学統に属する。
高麗から欧州まで領土とする世界最大の国・蒙古
【元寇】
元寇(げんこう)とは、日本の鎌倉時代中期に、当時大陸を支配していたモンゴル帝国(大元ウルス)およびその属国である高麗王国によって2度にわたり行われた対日本侵攻の呼称である。1度目を文永の役(ぶんえいのえき・1274年)、2度目を弘安の役(こうあんのえき・1281年)という。蒙古襲来とも。
特に2度目の弘安の役において日本へ派遣された艦隊は、元寇以前では世界史上最大規模の艦隊であった。
主に九州北部が戦場となった。
「天に守られている大蒙古国の皇帝から日本国王にこの手紙を送る.昔から国境が接している隣国同士は,たとえ小国であっても貿易や人の行きなど,互いに仲良くすることに努めてきた.まして,大蒙古皇帝は天からの命によって大領土を支配してきたものであり,はるか遠方の国々も,代々の皇帝を恐れうやまって家来になっている. 例えば私が皇帝になってからも,高麗(こうらい=朝鮮)が蒙古に降伏して家来の国となり,私と王は父子の関係のようになり,喜ばしいこととなった.高麗は私の東の領土である.しかし,日本は昔から高麗と仲良くし,中国とも貿易していたにもかかわらず,一通の手紙を大蒙古皇帝に出すでもなく,国交をもとうとしないのはどういうわけか?日本が我々のことを知らないとすると,困ったことなので,特に使いを送りこの国書を通じて私の気持ちを伝えよう. これから日本と大蒙古国とは,国と国の交わりをして仲良くしていこうではないか.我々は全ての国を一つの家と考えている,日本も我々を父と思うことである.このことが分からないと軍を送ることになるが,それは我々の好むところではない.日本国王はこの気持ちを良く良く考えて返事をしてほしい.不宣 至元三年八月(1266年・文永三年)
|
これが元(蒙古=モンゴル)の皇帝「フビライ・ハーン」から日本に送られてきた蒙古の国書です.この中にもあるように蒙古は東は高麗・中国から西はヨーロッパまでを領土とする史上最大の国でした.
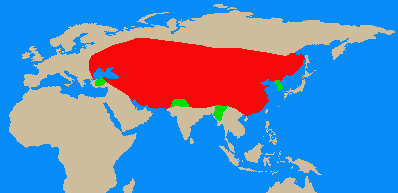
蒙古からの「国書」を無視した日本は国難を覚悟
国書を無視した日本
文永五年(1268年)国書は九州の太宰府にもたらされ幕府をとおして朝廷に届けられました.当時の太宰府は中国・朝鮮をはじめとする,アジアに向けられた日本の玄関で,今で言うなら「外務省」にあたるところです.朝廷では連日会議をかさねて「返事をしない」・・つまり無視をするという結論を出しました
.日本は国をあげて蒙古の侵略を防ごうとしましたが,外敵と戦った経験が無かったためにその恐ろしさがまだ分かりませんでした.このとき幕府は18歳という若さの北条時宗を執権にしてこの国難を克服しようとしました。
当時の蒙古軍は短くて強力な弓と,よく動く馬で戦いとても強かったのです.ところが高麗には三別抄(さんべつしょう)という抵抗組織(ていこうそしき)ができて蒙古はこれをなかなか鎮圧することができませんでした.さらに南宋(南中国)は蒙古と大々的に戦っていました.
こうした状況の中で,蒙古は南宋を支配するためには日本も属国にする必要があったのです.
【鳥巣注】
元は図式的には、高麗の抵抗組織と南宋に対して二股作戦を強いられていた。そこで戦略としては、日本を属国化し、敵(南宋)に対して前方(元)からと後方(日本)からの「挟み撃ち」にしたかった。この間に蒙古は国の名を「元」にかえ,首都を現在の北京である大都に移しました.
(おまけの話)
このころの日本は「金がでる国」と伝えられていました.事実,日本は当時としては大量の金の産出国だったと言われています.
ちなみに,「日本」という文字を中国の福建省では「ジップン」と発音します.この音を聞いたイタリアの商人マルコポーロが,イタリアに戻って書いた「東方見聞録」に「ジパング」と紹介しました.これが今日,日本のことジャパンとかジャポン.ヤーパン,ハポンと呼ばれるもとになったのです.
1274年北九州に高麗・元軍は上陸したが消えた文永11年(1274年)10月3日に高麗の合浦(がっぽ)をたった元・高麗軍は10月5日に対馬,14日に壱岐をおそい19日に博多湾に集結しました.対馬・壱岐の人々のほとんどは殺され,わずかに生き残った人(主に女性)は手に穴をあけられ,そこをひもで通して船のへりに鎖(くさり)のように結ばれたと言われています.こうすれば日本軍が矢を撃てないからです.このような蒙古の残虐な行為は世界の至る所で行われ大変に恐れられていました.蒙古の侵略を受けた東ヨーロッパには今でもその時の恐ろしさが伝えられています.。
朝鮮の歴史書には「夜半に大風雨があった」と記述
嵐は起きたのか?元・高麗軍が大量に上陸し,一方的に優勢な戦いをすすめていた次の日の朝「信じられない出来事」が起こりました.前日ひどい目にあった日本の武士や博多の市民の目の前に静まりかえった博多湾が広がっていたからです.湾内を埋め尽くしていた船が一艘も見あたらなかったのです.
一説によると大暴風がやってきて多くの船が沈みたくさんの敵兵が死んだ.この風は神がおこした風,すなわち「神風」と呼ばれ,その後,日本に敵が攻めてくれば神が守ってくれるという考え方をうえつけたと言われています.この説は長い間人々に信じられてきました.
ところが最近では,「文永の役で嵐は起きなかった」と言う説が有力になりつつあります.フビライははじめから今回の派兵を「おどし」のためにおこなったので,日本を本格的に侵略するつもりはなかったのではないか・・・「元軍は夜に船に戻って」そのまま帰ったのだ.だからこそ次の元寇である弘安の役までに何度も使者を送ってきたのだ,という考え方です.
そもそも文永11年の10月20日は現在の11月4日ですから台風はあまり考えられません.今回は「おどし」た後に短い期間で帰るつもりだったのではないかとも思えます.八幡愚童訓には嵐のことは一行も触れていないばかりか「朝になったら敵船も敵兵もきれいさっぱり見あたらなくなったので驚いた」と書いてあります。
ところが「東国通鑑」(とうごくつがん=高麗(こうらい=ちょうせん)の歴史書)には夜半に大風雨があったこと,多くの船が海岸のがけや岩にあたって傷んだことが書かれています.この違いはなんでしょう?一説によれば日本と本気で戦う気の無かった高麗軍が言い訳のために書いたのではないか・・・また一説には、博多湾で嵐にあって沈んだのではなく、波の荒い冬の玄界灘で悪天候に遭遇して沈んだのではないか・・とも言われています.文永の役で神風が吹いたと唱えたのは明治時代の学者で,それ以前の人々は一回目は何となく敵がいなくなって,2回目(弘安の役)には嵐が来て助かったと思っていたらしいのです.さて,どっちでしょう?とにかく,元の大軍は一夜にしていなくなり日本は助かりました。
(*参考資料=「元寇は何故起きたか」玉川学園・玉川大学・協同 多賀歴史研究所 多賀譲治)
2016-01-04 02:35:45
鳥巣清典の時事コラム1543「10~13世紀<宋>世界初の紙幣『交子』は有価証券にも使用」
テーマ:日中米国交史宋
宋(そう、拼音 Sòng、960年 - 1279年)は、中国の王朝の一つ。趙匡胤が五代最後の後周から禅譲を受けて建国した。国号は宋であるが、春秋時代の宋、南北朝時代の宋などと区別するため、帝室の姓から趙宋とも呼ばれる。国号の宋は趙匡胤が宋州(河南省商丘県)の帰徳軍節度使であったことによる[1]。通常は、金に華北を奪われ南遷した1127年以前を北宋、以後を南宋と呼び分けている。北宋、南宋もともに、宋、宋朝である。首都は開封、南遷後の実質上の首都は臨安であった。
北宋と南宋とでは華北の失陥という大きな違いがあるが、それでも文化は継続性が強く、その間に明確な区分を設けることは難しい。

11世紀の北宋ー960年~1279年ー
生産力の大幅な向上と全国的な市場形成と流通の活発化
経済・金融
宋代経済の概況
宋代において
- 生産力の大幅な向上と地域的偏差、および商品経済の確立
- 各地方における市場の成熟と市場間の流通の活発化
- それによる全国的な市場形成と市場における分業化
などが進み、宋代の経済状態を形作っていた。
生産力の大幅向上と品目の多様化
宋代に至り、各種生産力が大幅に向上した事は異論を挟む余地が無い。中でも重要なのが農業、特に米作の発展である。その他にも精銅・製鉄・窯業の技術的発展など宋代の発展は枚挙に暇が無い。
また因地制宜により、沿岸部では漁業や塩業を山間部では林業をといった具合に各地域の特性にあった物を生産するに至る。ただ、南高北低・東高西低を基調とする地域毎の経済力格差が拡大したのも宋代の特徴である。
”世界初の紙幣”交子は有価証券にも使用
貨幣
貨幣政策は経済に対して強い影響を及ぼすが、宋政府は歴代王朝の伝統を継承せず銅などの生産を厳格に把握・監理し貨幣鋳造を行った。宋の通貨は基本的に銅銭と鉄銭で、次いで銀錠や大型決済用の金が用いられ、紙幣の交子も登場する。
北宋代には銅銭や鉄銭の鋳造量が格段に増え、太宗の至道年間(995年-997年)80万貫(八億銭)から、真宗の景徳年間(1004年-1007年)には183万貫となり、神宗の元豊元年(1078年)には506万貫と最高点に達する。元豊年間の増産により一応の安定を見たため、その後は6割程度の鋳造量で推移した。
紙幣・為替・証券
銅銭・鉄銭は重く嵩張り、金銀は高価なため、どちらも持ち運ぶには不便な点がある。それを補うために便銭(飛銭)という為替制度があった。唐代長安の便銭務という役所では、銭を預けて預り証を受け取り地方の役所で換金出来たが、この制度は宋にもあった。民間の堰坊では、銅銭・金銀・布帛などを預かって交子(会子・関子)と呼ばれる預り証を発行していた。
四川や陝西・河東では鉄銭が使われたが、鉄銭は銅銭と比べても重く不評であった。そこで成都の商人が集って鉄銭を預かり交子を発行していた。交子は使い勝手が良く、四川や陝西では広く流通していた。この交子の利益に目をつけた政府は、商人の経営が傾くと商人に代わって交子を発行した。交子は世界最初の紙幣とされる。交子は始め四川や陝西でのみ流通していたが、やがて全国へと広がり、兌換の対象も鉄銭から銅銭へと替わった。交子には界と呼ばれる期限があり、その間に使用ないし兌換しなければ紙切れとなった。
専売の引換券である交引もまた一種の有価証券として扱われ、取引された。
1159年に出された規定では、1万貫以上の銅銭を保有する者は2年以内に会子や商品へ換える事が義務付けられ、銅銭は経過後に例外無く没収された。1168年までは、前述の界の期限内に銅銭又は銀又は新紙幣と交換出来たが、以降は新紙幣との交換のみになり不換紙幣へと変わった。(*参考資料ウィキペディア)
2016-01-04 01:24:00
鳥巣清典の時事コラム1542「7~9世紀<唐>遣唐使で中国に初めて『日本』『天皇』を使用」
テーマ:日中米国交史唐
唐(とう、拼音:Táng、618年 - 690年,705年 - 907年)は、中国の王朝である。李淵が隋を滅ぼして建国した。7世紀の最盛期には、中央アジアの砂漠地帯も支配する大帝国で、朝鮮半島や渤海、日本などに、政制・文化などの面で多大な影響を与えた。日本の場合は遣唐使などを送り、894年(寛平6年)に菅原道真の意見で停止されるまで、積極的に交流を続けた。首都は長安に置かれた。
遣唐使

ー上海万博で再現された遣唐使船ー

中国の先進的な技術や仏教の経典の収集が目的
遣唐使の目的
海外情勢や中国の先進的な技術や仏教の経典等の収集が目的とされた。旧唐書には、日本の使節が、中国の皇帝から下賜された数々の宝物を市井で全て売って金に替え、代わりに膨大な書物を買い込んで帰国していったと言う話が残されている。
第一次遣唐使は、舒明天皇2年(630年)の犬上御田鍬(いぬかみのみたすき)の派遣によって始まった。本来、朝貢は中国の皇帝に対して年1回で行うのが原則であるが、以下の『唐書』の記述が示すように、遠国である日本の朝貢は毎年でなくてよいとする措置がとられた。
- 貞観5年、使いを遣わして方物を献ず。太宗、その道の遠きを矜(あわれ)み、所司に勅して、歳貢せしむることなからしむ。(『旧唐書』倭国日本伝)
- 太宗の貞観5年、使いを遣わして入貢す。帝、その遠きを矜(あわれ)み、有司に詔して、歳貢にかかわることなからしむ。(『新唐書』日本伝)
遣隋使の『天子』を止め遣唐使では『天皇』号を使用
なお、日本は以前の遣隋使において、「天子の国書」を送って煬帝を怒らせている。遣唐使の頃には天皇号を使用しており、中国の皇帝と対等であるとしているが、唐の側の記録においては日本を対等の国家として扱ったという記述は存在しない。むしろ天平勝宝5年(753年)の朝賀において、日本が新羅より席次が下とされる事件があった。しかし、かつての奴国王や邪馬台国の女王卑弥呼、倭の五王が中国王朝の臣下としての冊封を受けていたのに対し、遣唐使の時代には日本の天皇は唐王朝から冊封を受けていない。
その後、唐僧維躅(ゆいけん)の書に見える「二十年一来」(20年に1度)の朝貢が8世紀ごろまでに規定化され、およそ十数年から二十数年の間隔で遣唐使の派遣が行われた。
遣唐使は200年以上にわたり、当時の先進国であった唐の文化や制度、そして仏教の日本への伝播に大いに貢献した。
回数
回数については中止、送唐客使などの数え方により諸説ある。20回説では、1回目630年~20回目894年。
***********
中国から技術を学ぶ(=遣隋使1回目が600年)事で、日本国内には建造物や歴史書などが作られていきます。
❶【法隆寺】
7世紀に創建され、古代寺院の姿を現在に伝える仏教施設であり、聖徳太子(574年~622年)ゆかりの寺院である。創建は金堂薬師如来像光背銘、『上宮聖徳法王帝説』から推古15年(607年)とされる。金堂、五重塔を中心とする西院伽藍と、夢殿を中心とした東院伽藍に分けられる。境内の広さは約18万7千平方メートルで、西院伽藍は現存する世界最古の木造建築物群である。
❷【古事記・日本書紀】
現存最古の歴史書の古事記は、8世紀初め(700年~)に編纂されたとされます。正史の日本書紀が出来たのも8世紀初頭。その日本書紀によれば、日本で歴史書といえるものが作られたのは推古28年(620年)。皇太子(聖徳太子)と嶋大臣(蘇我馬子)が力を合わせて「天皇記と国気」の編纂に取り組んだとあります。日本書紀の記述に従えば、その頃、聖徳太子は、世界に比肩しうる法制度(律令)をもった国家になることを初めて意識するようになり、史書を作り始めました。聖徳太子によるその史書は現存しませんが、以来、日本では歴史書作りが試行錯誤されるようになったと考えられます。
❸【遣唐使の廃止】
寛平6年(894年)遣唐大使に任ぜられるが、唐の混乱や日本文化の発達を理由とした道真の建議により遣唐使は停止される。なお、延喜7年(907年)に唐が滅亡したため、遣唐使の歴史はここで幕を下ろすこととなった。
【鳥巣注】
自国より優れた技術や制度があると思えば、迷うことなく人材を派遣し、目的を達したと判断すれば中止する。劣等感によるプライドは野暮。「己を知り、敵を知れば百戦危うからず」。”外から学ぶ”は、日本の伝統芸となっていきます。
逆に中国は長く、こうして技術や文化を与えるのみでした。
2016-01-04 00:50:28
鳥巣清典の時事コラム1541「7世紀<隋>いよいよ日本も技術や制度を中国に学ぶ旅に出た」
テーマ:日中米国交史中国の歴史
隋
隋(呉音:ずい、漢音:すい、拼音:Suí 、581年 - 618年)は、中国の王朝。魏晋南北朝時代の混乱を鎮め、西晋が滅んだ後分裂していた中国をおよそ300年ぶりに再統一した。しかし第2代煬帝の失政により滅亡し、その後は唐が中国を支配するようになる。都は大興城(長安、現在の中華人民共和国西安市)。国姓は楊。当時の日本である倭国からは遣隋使が送られた。

ー581~618年 隋の領域ー

ー7世紀初めの隋と周辺国ー
いよいよ日本も技術や制度を中国に学ぶ旅に出た
■遣隋使
隋
隋(呉音:ずい、漢音:すい、拼音:Suí 、581年 - 618年)は、中国の王朝。魏晋南北朝時代の混乱を鎮め、西晋が滅んだ後分裂していた中国をおよそ300年ぶりに再統一した。しかし第2代煬帝の失政により滅亡し、その後は唐が中国を支配するようになる。都は大興城(長安、現在の中華人民共和国西安市)。国姓は楊。当時の日本である倭国からは遣隋使が送られた。

ー581~618年 隋の領域ー

ー7世紀初めの隋と周辺国ー
いよいよ日本も技術や制度を中国に学ぶ旅に出た
■遣隋使
遣隋使(けんずいし)とは、推古朝の倭(俀國)が技術や制度を学ぶために隋に派遣した朝貢使のことをいう。600(推古8年)~618年(推古26年)の18年間に5回以上派遣されている。なお、日本という名称が使用されたのは遣唐使からである。
大阪の住吉大社近くの住吉津から出発し、住吉の細江(現・細江川)から大阪湾に出、難波津を経て瀬戸内海を九州博多津へ向かい、そこから玄界灘に出る。
倭の五王による南朝への奉献以来約1世紀を経て再開された遣隋使の目的は、東アジアの中心国・先進国である隋の文化の摂取が主であるが、朝鮮半島での影響力維持の意図もあった。この外交方針は次の遣唐使の派遣にも引き継がれた。
○第一回目
派遣第一回 開皇20年(600年)は、『日本書紀』に記載はない。
『隋書』「東夷傳俀國傳」は高祖文帝の問いに遣使が答えた様子を載せている。
「開皇二十年 俀王姓阿毎 字多利思北孤 號阿輩雞彌 遣使詣闕 上令所司訪其風俗 使者言俀王以天爲兄 以日爲弟 天未明時出聽政 跏趺坐 日出便停理務 云委我弟 高祖曰 此太無義理 於是訓令改之」
開皇二十年、俀王、姓は阿毎、字は多利思北孤、阿輩雞弥と号(な)づく。使いを遣わして闕(けつ)に詣(いた)る。上、所司(しょし)をしてその風俗を問わしむ。使者言う、俀王は天を以て兄と為し、日を以て弟と為す。天未(いま)だ明けざる時、出でて政(まつりごと)を聴く。日出ずれば、すなわち理務を停(とど)めて云う、我が弟に委(ゆだ)ぬと。高祖曰く、此れ大いに義理なし。是に於て訓(おし)えて之を改めしむ。
俀王(通説では俀は倭の誤りとする)姓の阿毎はアメ、多利思北孤(通説では北は比の誤りで、多利思比孤とする)はタラシヒコ、つまりアメタラシヒコで、天より垂下した彦(天に出自をもつ尊い男)の意とされる。阿輩雞弥はオホキミで、大王とされる。『新唐書』では、用明天皇が多利思比孤であるとしている。
開皇20年は、推古天皇8年にあたる。この時派遣された使者に対し、高祖は所司を通じて俀國の風俗を尋ねさせた。使者は俀王を「姓阿毎 字多利思北孤」号を「阿輩雞彌」と云うと述べている。ところが、高祖からみると、俀國の政治のあり方が納得できず、道理に反したものに思えたのであろう。そこで改めるよう訓令したというのである。
解釈
「倭王は、天を以て兄と為し、日を以て弟と為す。天未だ明けざる時、出でて政を聴く。日出ずれば、すなわち理務を停めて弟に委ぬ」
これは、これで一つの文章であり、倭国の大王による、隋の皇帝に対する謎かけなのである。
この答えは「明けの明星」である。天は常にあるから一番目の「兄」であり、夜明け前に輝く金星(明けの明星)は二番目であり、三番目の「弟」である太陽が昇ると、金星(明けの明星)は見えなくなってしまう。
結局、この謎かけは隋の皇帝には理解されず、第二回遣隋使での直接的表現へとつながるのである。
○第二回(607年)
第二回は、『日本書紀』に記載されており、607年(推古15年)に小野妹子が大唐国に国書を持って派遣されたと記されている。
倭王から隋皇帝煬帝に宛てた国書が、『隋書』「東夷傳俀國傳」に「日出處天子致書日沒處天子無恙云云」(日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙無しや、云々)と書き出されていた。これを見た煬帝は立腹し、外交担当官である鴻臚卿(こうろけい)に「蕃夷の書に無礼あらば、また以て聞するなかれ」(無礼な蕃夷の書は、今後自分に見せるな)と命じたという。
なお、煬帝が立腹したのは俀王が「天子」を名乗ったことに対してであり、「日出處」「日沒處」との記述に対してではない。「日出處」「日沒處」は『摩訶般若波羅蜜多経』の注釈書『大智度論』に「日出処是東方 日没処是西方」とあるなど、単に東西の方角を表す仏教用語である。ただし、仏教用語を用いたことで中華的冊封体制からの離脱を表明する表現であったとも考えられている。
小野妹子(中国名:蘇因高)は、その後返書を持たされて返されている。煬帝の家臣である裴世清を連れて帰国した妹子は、返書を百済に盗まれて無くしてしまったと言明している。百済は日本と同じく南朝への朝貢国であったため、その日本が北朝の隋と国交を結ぶ事を妨害する動機は存在する。しかしこれについて、煬帝からの返書は倭国を臣下扱いする物だったのでこれを見せて怒りを買う事を恐れた妹子が、返書を破棄してしまったのではないかとも推測されている。
裴世清が持ってきたとされる書が『日本書紀』にある。
「皇帝、倭王に問う。朕は、天命を受けて、天下を統治し、みずからの徳をひろめて、すべてのものに及ぼしたいと思っている。人びとを愛育したというこころに、遠い近いの区別はない。倭王は海のかなたにいて、よく人民を治め、国内は安楽で、風俗はおだやかだということを知った。こころばえを至誠に、遠く朝献してきたねんごろなこころを、朕はうれしく思う。」
「皇帝問倭皇 使人長吏大禮 蘇因高等至具懷 朕欽承寶命 臨養區宇 思弘德化 覃被含靈 愛育之情 無隔遐邇 知皇介居海表 撫寧民庶 境內安樂 風俗融合 深氣至誠 遠脩朝貢 丹款之美 朕有嘉焉 稍暄 比如常也 故遣鴻臚寺掌客裴世清等 旨宣往意 并送物如別」『日本書紀』
これは倭皇となっており、倭王として臣下扱いする物ではない。『日本書紀』によるこれに対する返書の書き出しも「東の天皇が敬いて西の皇帝に白す」(「東天皇敬白西皇帝」『日本書紀』)とある。これをもって天皇号の始まりとする説もある。また、「倭皇」を日本側の改竄とする見解もある。
なお、裴世清が持参した返書は「国書」であり、小野妹子が持たされた返書は「訓令書」ではないかと考えられる。 小野妹子が「返書を掠取される」という大失態を犯したにもかかわらず、一時は流刑に処されるも直後に恩赦されて大徳(冠位十二階の最上位)に昇進し再度遣隋使に任命された事、また返書を掠取した百済に対して日本が何ら行動を起こしていないという史実に鑑みれば、 聖徳太子、推古天皇など倭国中枢と合意した上で、「掠取されたことにした」という事も推測される。
○年表
- 600年(推古8年)第1回遣隋使派遣。この頃まだ俀國は、外交儀礼に疎く、国書も持たず遣使した。(『隋書』俀國伝)
- 607年(推古15年) - 608年(推古16年)第2回遣隋使、小野妹子らを遣わす。「日出処の天子……」の国書を持参した。小野妹子、裴世清らとともに住吉津に着き、帰国する。(『日本書紀』、『隋書』俀國伝)
- 608年(推古16年) - ? (『隋書』煬帝紀)
- 608年(推古16年) - 609年(推古17年)第3回遣隋使、小野妹子・吉士雄成など隋に遣わされる。この時、学生として倭漢直福因(やまとのあやのあたいふくいん)・奈羅訳語恵明(ならのおさえみょう)高向漢人玄理(たかむくのあやひとくろまろ)・新漢人大圀(いまきのあやひとだいこく)・学問僧として新漢人日文(にちもん、後の僧旻)・南淵請安ら8人、隋へ留学する。隋使裴世清帰国する。(『日本書紀』、『隋書』俀國伝)
- 610年(推古18年) - ? 第4回遣隋使を派遣する。(『隋書』煬帝紀)
- 614年(推古22年) - 615年(推古23年)第5回遣隋使、犬上御田鍬・矢田部造らを隋に遣わす。百済使、犬上御田鍬に従って来る。(『日本書紀』)
- 618年(推古26年)隋滅ぶ。
○遣使の『日本書紀』と『隋書』の主な違い
- 第一回遣隋使は『日本書紀』に記載がなく『隋書』にあるのみ。
- ここでは中国史に合わせて遣隋使として紹介しているが、『日本書紀』では「隋」ではなく「大唐國」に遣使を派遣したとある。
- 『日本書紀』では裴世清、『隋書』では編纂された時期が唐太宗の時期であったので、太宗の諱・世民を避諱して裴清となっている。
- 小野妹子の返書紛失事件は『日本書紀』にはあるが『隋書』にはない(『隋書』には小野妹子の名前自体が出てこない)。
- 『隋書』では竹斯國と秦王國の国名が出てくるが大和の国に当たる国名は記されていない。しかし、「都於邪靡堆」とあることから、都は「邪靡堆」にあったと推察される。
2016-01-04 00:06:24
鳥巣清典の時事コラム1540「5世紀<劉宋>413年~477年”倭の五王”の遣使9回」
テーマ:日中米国交史劉宋
宋(そう、420年 - 479年)は、中国南北朝時代の南朝の王朝。周代の諸侯国の宋や趙匡胤が建てた宋などと区別するために、帝室の姓を冠し劉宋(りゅうそう)とも呼ばれる。首都は建康(現在の南京)。


5世紀中頃
子が父を、弟が兄を殺す内紛の連続で衰退
宋(そう、420年 - 479年)は、中国南北朝時代の南朝の王朝。周代の諸侯国の宋や趙匡胤が建てた宋などと区別するために、帝室の姓を冠し劉宋(りゅうそう)とも呼ばれる。首都は建康(現在の南京)。


5世紀中頃
■倭の五王の遣使
5世紀に倭国(日本列島)の王のうち5人が相次いで南朝に使者を派遣して朝貢した。この5人の王を倭の五王という。倭の五王の遣使は413年から477年までに少なくとも9回が確認されるが、このうち413年の倭王讃による遣使は東晋に対してであるが、421年から477年までの倭王讃、倭王珍、倭王済、倭王興、倭王武の遣使はいずれも宋に対するものである。
宋の皇帝の一覧[編集]
| 廟号 | 諡号 | 姓名 | 在位 | 年号 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高祖 | 武帝 | 劉裕 | 420年 - 422年 | 永初 420年 - 422年 | |
| 2 | 少帝 | 劉義符 | 422年 - 424年 | 景平 423年 - 424年 | 武帝の子 | |
| 3 | 太祖 | 文帝 | 劉義隆 | 424年 - 453年 | 元嘉 424年 - 453年 | 武帝の子 少帝の弟 |
| (4) | (元凶劭) | 劉劭 | 453年 | 太初 453年 | 文帝の子 | |
| 4 | 世祖 | 孝武帝 | 劉駿 | 453年 - 464年 | 孝建 454年 - 456年 大明 457年 - 464年 | 文帝の子 劉劭の弟 |
| 5 | (前廃帝) | 劉子業 | 464年 - 465年 | 永光 465年 景和 465年 | 孝武帝の子 | |
| 6 | 太宗 | 明帝 | 劉彧 | 465年 - 472年 | 泰始 465年 - 471年 泰豫 472年 | 文帝の子 前廃帝の叔父 |
| 7 | (後廃帝) (蒼梧王) | 劉昱 | 472年 - 476年 | 元徽 473年 - 477年 | 明帝の子 | |
| 8 | 順帝 | 劉準 | 476年 - 479年 | 昇明 477年 - 479年 | 明帝の子 後廃帝の弟 |
子が父を、弟が兄を殺す内紛の連続で衰退
450年1月に文帝は国内の安定を背景にして貴族の賛同を得て北伐を行なう。だが宋軍は北魏軍に敗れて北魏軍50万の大軍の侵攻を建康の手前まで受ける事になった。この北魏の侵攻で宋の国力は衰退し、文帝も453年に皇太子劉劭の謀反により殺害された。その劉劭も弟の劉駿に敗れて子供4人とともに晒し首とされて長江に遺棄され、劉駿が孝武帝として即位した。
衰退・滅亡へ
文帝時代から始まった子が父を、弟が兄を殺すという皇族の内紛は後の南朝において常に続く内争の端緒となったし、また宋を大いに衰退させる一因となった[16]。孝武帝も自身の兄弟や一族を次々と殺戮した。また中央集権を図ったが失敗している[17]。孝武帝が464年に崩御すると、長男の劉子業が跡を継いだが、性格が凶暴・残忍で戴法興・柳元景・顔師伯ら重臣を殺したため、465年に寿寂之・姜産之により殺害された。
新しい皇帝には文帝の11男明帝が擁立された。だがこの明帝も残忍で孝武帝の子を16人も殺害した。またこの明帝の時代には北魏からの侵略が激しくなり、山東半島から淮北までの領域を完全に奪われた。明帝は寺院の建立や無謀な遠征を連年続けて濫費を繰り返し、宋の財政は悪化した。472年に明帝が崩御すると、長男の劉昱が跡を継いだが、この時にも孝武帝の遺児12人が殺戮される悲劇が繰り返されている。このように歴代が内紛を繰り返した結果、宋は衰退した。(*参考資料ウィキペディア)