マダイは?でも大漁
やっと、当ブログで釣りの報告ができる。
本日、友人のお仲間のお誘いを受け、金沢漁港「黒一丸」 からタイ五目に出かけた。
仕掛けは80号のサニービシ+6~8mの3号ハリス。
マダイをメインにイナダをサブターゲットにしている。
今日は仕立てなので、優雅な雰囲気。
730に金沢漁港を出港。
810に釣り場、多分剣崎沖についた。
天気は絶好。
晴れ、ナギ、波穏やか。
朝から昼に掛けるにつれ、「北風と太陽」の太陽の恩恵にあたったごとく、フィッシングウエア、フリースを脱ぎ、だんだん軽装になっていく。
さて釣り開始から入れ食いといきたいところだけど、なかなか最初のアタリはこなかった。
それでも、ガクガクとボクのアグリショット に反応が来た。
引きが弱かったので、アジかなと思いつつあがってきたのはオニカサゴの子供。

ちょっとがっかりだけど、最初の獲物なのでキープ。
それから少々静かなあたりのない時間を過ごした。
ハリス6m+2mコマセを振りながら棚にあわせる。
反応なし、、、
ためしにゆっくりと竿を上げ、ゆっくりとおろす。
そこでキター。
ギュインとしたアタリ。
久々に、ドラグを滑らせながらのやり取りで慎重に上げた獲物はイナダだった。

そこから、たびたびのアタリ、型のよいヒラソウダ、ビックなゴマサバ、イナダを追加でもう1本。
結果↓の釣果で大満足。

今回沖釣り3回目の友人Iさんもイナダを上げてうれしそう。

赤い魚は連れなかったけど、天気も釣果も大満足の一日でした。
本日、友人のお仲間のお誘いを受け、金沢漁港「黒一丸」 からタイ五目に出かけた。
仕掛けは80号のサニービシ+6~8mの3号ハリス。
マダイをメインにイナダをサブターゲットにしている。
今日は仕立てなので、優雅な雰囲気。
730に金沢漁港を出港。
810に釣り場、多分剣崎沖についた。
天気は絶好。
晴れ、ナギ、波穏やか。
朝から昼に掛けるにつれ、「北風と太陽」の太陽の恩恵にあたったごとく、フィッシングウエア、フリースを脱ぎ、だんだん軽装になっていく。
さて釣り開始から入れ食いといきたいところだけど、なかなか最初のアタリはこなかった。
それでも、ガクガクとボクのアグリショット に反応が来た。
引きが弱かったので、アジかなと思いつつあがってきたのはオニカサゴの子供。

ちょっとがっかりだけど、最初の獲物なのでキープ。
それから少々静かなあたりのない時間を過ごした。
ハリス6m+2mコマセを振りながら棚にあわせる。
反応なし、、、
ためしにゆっくりと竿を上げ、ゆっくりとおろす。
そこでキター。
ギュインとしたアタリ。
久々に、ドラグを滑らせながらのやり取りで慎重に上げた獲物はイナダだった。

そこから、たびたびのアタリ、型のよいヒラソウダ、ビックなゴマサバ、イナダを追加でもう1本。
結果↓の釣果で大満足。

今回沖釣り3回目の友人Iさんもイナダを上げてうれしそう。

赤い魚は連れなかったけど、天気も釣果も大満足の一日でした。
つくばの「蕎舎」(そばや)
今日は同僚4人と仕事でつくば市へ行った。
午前中に客先訪問を終え昼食は、「蕎舎」(そばや) で取ることにした。
藁葺屋根の古民家をそのまま使い、母屋の横には水車小屋があってそこで蕎麦搗きをしている。
期待大。
店内は平日のためか比較的空いていて落ち着いた昼休みを過ごすことが出来た。


同僚、3名は天もりそば(1,554円)、私はもりそば(819円)を2枚。
運転手は除いてビールを頼みたかったが、 午後も客先訪問を控えていたので断念。
追加で厚焼き卵(504円)を注文した。
待つことしばし・・
注文後すぐ出てくるような蕎麦屋ではたかがしれている。
注文後に蕎麦湯で、てんぷら挙げに着手してくれなきゃ。
ちょうどよい待ち時間で出てくる。


期待を裏切らない、
細めだが腰のしっかりとした蕎麦。
厚焼き玉子もうまい。
最後の蕎麦湯も結構。
久々にうまい蕎麦を仕事の途中で戴くことができ、本日はラッキー。
店のつくりからいってたぶん有名店だろうから休日は満員なんだろう。
値段も手ごろ、店の雰囲気もよし、味もよしで「☆みっつ」って感じでした。
最後に、仕事は仕事できちんと遂行してきたことを付け加えておく。
午前中に客先訪問を終え昼食は、「蕎舎」(そばや) で取ることにした。
藁葺屋根の古民家をそのまま使い、母屋の横には水車小屋があってそこで蕎麦搗きをしている。
期待大。
店内は平日のためか比較的空いていて落ち着いた昼休みを過ごすことが出来た。


同僚、3名は天もりそば(1,554円)、私はもりそば(819円)を2枚。
運転手は除いてビールを頼みたかったが、 午後も客先訪問を控えていたので断念。
追加で厚焼き卵(504円)を注文した。
待つことしばし・・
注文後すぐ出てくるような蕎麦屋ではたかがしれている。
注文後に蕎麦湯で、てんぷら挙げに着手してくれなきゃ。
ちょうどよい待ち時間で出てくる。


期待を裏切らない、
細めだが腰のしっかりとした蕎麦。
厚焼き玉子もうまい。
最後の蕎麦湯も結構。
久々にうまい蕎麦を仕事の途中で戴くことができ、本日はラッキー。
店のつくりからいってたぶん有名店だろうから休日は満員なんだろう。
値段も手ごろ、店の雰囲気もよし、味もよしで「☆みっつ」って感じでした。
最後に、仕事は仕事できちんと遂行してきたことを付け加えておく。
青春のガソリンスタンド(その3)
GSでのバイトのせいではないが、ボクは大学5年生になった。
卒業研究も4年生の時に終わらせ、落としたわずかな必修科目のためと就職情報を得るためだけに大学へ通っていたので、週一ほど大学へ行けばよいペースだった。
だから、大学5年生の一年間はほとんどこのGSでのバイトで過ごした。
18のころからこのGSで働いていたので(毎日ではないが)、ボクの名前も顔を覚えてくださるお客様もたくさんいらっしゃって、嬉しい思いをした。
就職活動もGSからリクルートスーツに着替えていくことも度々会ったので、励ましてくれるお客様も多かった。
「あなた社員じゃなかったの?」と勘違いされているお客様もいた。
そして就職が決まり、このGSを去るときあるお客様からご祝儀をいただいた。
きちんと祝儀袋に入っていたので、気まぐれなチップという感じではなかった。
このお客様は貿易の会社を営む社長さんで、ボクがバイトを始めたころからのお得意様だ。
多くのお客様の中でもこの社長は印象深い。
最初にこの社長がボクがバイトするGSに来られた時はチェイサー(トヨタ)に乗られていた。
その洗車やWAXがけをやらされた(やらせていただいた)ものである。
ドアモールに水滴が残ってるだの、ここにWAXの拭き残しがあるだの、厳しいお客様だった。
いやな客3本指にこの社長は入っていた。
社長の商売の様子は、乗られているクルマの変化でなんとなくわかった。
チェイサーからAUDI(新車)になり、もうかってるんだなあと思った。
その後、新車のGOLFに変わり、趣味がかわったのかなあ、と思った。
このGOLFのアルミホイールはボクの勧めで社長が買ってくれた。
そうこうするうちに、GOLFが中古のファミリアになってしまった。。。
けど、社長のボクらに対する態度は全く変わらず、クルマのグレードが下がってきてることにも意も介していない。
ボクが就職先に迷っている時、この社長に相談したことがある。
「公務員になるか、民間にいくか」
この命題に悩んでいたわけだが、社長は迷わず「民間に行け」といった。
親も含め他の人たちは「そりゃ公務員がいいよ」って言っていたのに。。
最後は自分の判断で民間企業への就職を決めたが、この社長のスタイル、言葉は今でも覚えている。
結局、バイトを辞め就職をし、それきりお会いすることも、就職祝いをいただいたお礼を改めてすることも出きていないことが悔やまれる。
卒業研究も4年生の時に終わらせ、落としたわずかな必修科目のためと就職情報を得るためだけに大学へ通っていたので、週一ほど大学へ行けばよいペースだった。
だから、大学5年生の一年間はほとんどこのGSでのバイトで過ごした。
18のころからこのGSで働いていたので(毎日ではないが)、ボクの名前も顔を覚えてくださるお客様もたくさんいらっしゃって、嬉しい思いをした。
就職活動もGSからリクルートスーツに着替えていくことも度々会ったので、励ましてくれるお客様も多かった。
「あなた社員じゃなかったの?」と勘違いされているお客様もいた。
そして就職が決まり、このGSを去るときあるお客様からご祝儀をいただいた。
きちんと祝儀袋に入っていたので、気まぐれなチップという感じではなかった。
このお客様は貿易の会社を営む社長さんで、ボクがバイトを始めたころからのお得意様だ。
多くのお客様の中でもこの社長は印象深い。
最初にこの社長がボクがバイトするGSに来られた時はチェイサー(トヨタ)に乗られていた。
その洗車やWAXがけをやらされた(やらせていただいた)ものである。
ドアモールに水滴が残ってるだの、ここにWAXの拭き残しがあるだの、厳しいお客様だった。
いやな客3本指にこの社長は入っていた。
社長の商売の様子は、乗られているクルマの変化でなんとなくわかった。
チェイサーからAUDI(新車)になり、もうかってるんだなあと思った。
その後、新車のGOLFに変わり、趣味がかわったのかなあ、と思った。
このGOLFのアルミホイールはボクの勧めで社長が買ってくれた。
そうこうするうちに、GOLFが中古のファミリアになってしまった。。。
けど、社長のボクらに対する態度は全く変わらず、クルマのグレードが下がってきてることにも意も介していない。
ボクが就職先に迷っている時、この社長に相談したことがある。
「公務員になるか、民間にいくか」
この命題に悩んでいたわけだが、社長は迷わず「民間に行け」といった。
親も含め他の人たちは「そりゃ公務員がいいよ」って言っていたのに。。
最後は自分の判断で民間企業への就職を決めたが、この社長のスタイル、言葉は今でも覚えている。
結局、バイトを辞め就職をし、それきりお会いすることも、就職祝いをいただいたお礼を改めてすることも出きていないことが悔やまれる。
青春のガソリンスタンド(その2)
「お前もおんなじ大学生なのになあ」
既に所長に昇格されていたFさんがボクにこう言った。
吉祥寺という場所柄、良家の子女の方々がよくこのGSに来られた。
お買い物の前に、BMWやSAABに乗ってこられ、
「これから買い物に行くからWAX掛けといて!」
って、吉祥寺の町に出かける近所の女子大のお嬢様も結構いらした。
「大学生ってのはああいうもんじゃねえのか?」
て言われても、こちらはクルマを磨く側、あちらは磨かせる側。
そして決まってお買い物からお帰りになったお客様は缶コーヒーをお礼にと渡してくれるのだ。
大きな川が両者の間には流れている。
吉祥寺にある有名な釣具店のご子息(今は社長様)も、よくボクらのGSにきていただいた。
いやみのないさわやかな方で、愛車(もちろん外車)を磨かせていただいた。
また、冬にはセントラルヒーティングで暖房されている家(もちろん邸宅)に1トン車のタンクローリーに灯油を詰めて配達に出かけた。
ポリタンを届けるのではなく、各邸宅にある灯油タンクに給油して回るのである。
狭い吉祥寺東町や北町の路地をタンクローリーを運転して、「こんばんは、灯油の給油に参りました」と訪ねるのだ。
冬は寒い、邸宅の中は暖かい。
向こう側と、こちら側の差を明確に感じたものである。
いつかはどこかのGSに乗り付けて、「WAX掛けといて、ちょいと買い物してくっから・・」
とオレも言ってやるぞ!と思ったのは言うまでもない。
で、現在、、、
GSでWAX掛けを頼めるようにはどうにかなれたが、セントラルヒーティングの家にはやはり住めていない・・。
既に所長に昇格されていたFさんがボクにこう言った。
吉祥寺という場所柄、良家の子女の方々がよくこのGSに来られた。
お買い物の前に、BMWやSAABに乗ってこられ、
「これから買い物に行くからWAX掛けといて!」
って、吉祥寺の町に出かける近所の女子大のお嬢様も結構いらした。
「大学生ってのはああいうもんじゃねえのか?」
て言われても、こちらはクルマを磨く側、あちらは磨かせる側。
そして決まってお買い物からお帰りになったお客様は缶コーヒーをお礼にと渡してくれるのだ。
大きな川が両者の間には流れている。
吉祥寺にある有名な釣具店のご子息(今は社長様)も、よくボクらのGSにきていただいた。
いやみのないさわやかな方で、愛車(もちろん外車)を磨かせていただいた。
また、冬にはセントラルヒーティングで暖房されている家(もちろん邸宅)に1トン車のタンクローリーに灯油を詰めて配達に出かけた。
ポリタンを届けるのではなく、各邸宅にある灯油タンクに給油して回るのである。
狭い吉祥寺東町や北町の路地をタンクローリーを運転して、「こんばんは、灯油の給油に参りました」と訪ねるのだ。
冬は寒い、邸宅の中は暖かい。
向こう側と、こちら側の差を明確に感じたものである。
いつかはどこかのGSに乗り付けて、「WAX掛けといて、ちょいと買い物してくっから・・」
とオレも言ってやるぞ!と思ったのは言うまでもない。
で、現在、、、
GSでWAX掛けを頼めるようにはどうにかなれたが、セントラルヒーティングの家にはやはり住めていない・・。
石焼ひつまぶし→残念
今日、仕事で三島のお客様へ同僚3人と訪問した。
午前中の商談は、結構よい感じに終わり雑談タイムとなった。
「今日は天気がいいからどこか観光でもしてくればいいんじゃないんですか」
と先方ご担当者。
「せっかくだから三島のウナギを食べてかえろうかと思っています。」
すると、
「うな重ではないけど、ひつまぶしの名店がある」
とのコト。特に「石焼ひつまぶし」がオススメらしい。
HPで調べてもらい、定休日は月曜であることを確認し、帰りのご挨拶を終えていざそのお店「うな繁」 へ。
お客様のオフィスからクルマで15分。
目指す「うな繁」へ着いた。

「昼時だから込んでるんだろうね」
などと同僚と会話していたが、駐車場ががら空き。
いやな予感がしつつ、店の前に立つと・・

ボクらと同様に店前でボーゼンとしているバイクツーリングの団体さんもがっかりの様子。
結局、この日の昼食はウナギから寿司に変更。
これはこれでうまかったけどね。
2週間後に、再度このお客様に訪問することになります。
その時は食うぞ「石焼ひつまぶし」。
次回は、うまそうな画像、アップしますよ。
午前中の商談は、結構よい感じに終わり雑談タイムとなった。
「今日は天気がいいからどこか観光でもしてくればいいんじゃないんですか」
と先方ご担当者。
「せっかくだから三島のウナギを食べてかえろうかと思っています。」
すると、
「うな重ではないけど、ひつまぶしの名店がある」
とのコト。特に「石焼ひつまぶし」がオススメらしい。
HPで調べてもらい、定休日は月曜であることを確認し、帰りのご挨拶を終えていざそのお店「うな繁」 へ。
お客様のオフィスからクルマで15分。
目指す「うな繁」へ着いた。

「昼時だから込んでるんだろうね」
などと同僚と会話していたが、駐車場ががら空き。
いやな予感がしつつ、店の前に立つと・・

ボクらと同様に店前でボーゼンとしているバイクツーリングの団体さんもがっかりの様子。
結局、この日の昼食はウナギから寿司に変更。
これはこれでうまかったけどね。
2週間後に、再度このお客様に訪問することになります。
その時は食うぞ「石焼ひつまぶし」。
次回は、うまそうな画像、アップしますよ。
青春のガソリンスタンド(その1)
ボクが車の運転免許を取ったばかりの18のころ、吉祥寺をぶらついたいた時に「アルバイト募集」の看板をとあるガソリンスタンド(GS)で見つけた。
バイトを探していたボクは、そのGSに飛び込み、
「あのー、バイトしたいんですけど・・」
と切り出した。
当時の所長に簡単な面接をされ、
「じゃ、明日から頼むよ!」と言われるまでに10分も掛からなかった。
次の日からGSでのバイトが始まる。
最初は、給油、窓拭き、洗車、など簡単な作業からはじめたが、慣れてくるにつれオイル交換やクーラント(ラジエーターに入れる液体)の交換などもやらせてもらえた。
もともとクルマ好きだったボクは、結構ここのGSでクルマのことも、そして働くことの意味も身に着けることが出来た。
何よりよかったのがメンバーだ。
所長、主任(25歳、後に所長になる)、社員のM君(18歳)に、東北から就職してきたK君(18歳)。
それからベテラン社員のIさん。
みんな個性的で楽しい思い出がたくさんある。
ここのGSは吉祥寺という土地柄か、老舗の商店や会社、そして周りの高級住宅地にお住まいの外車にのった方々・・。そう、一見のお客様より固定客が多かった。
そして、もう一つの特長は夜になると改造車に乗ったお客様(元族??)がよくいらっしゃった。
というのも、当時主任もIさんもクルマの改造が得意で、エンジンの載せ替えは当たり前。ボアアップやターボキットの装着。もちろん電装系の改造まで請負っていた。
さながら夜はレーシングガレージの様。
エンジンの分解や洗浄などを手伝うことも出来たし、寒い日や暑い日の洗車やワックス掛けはつらかったけど楽しいバイト先だった。
おかげで本業の大学の出席日数が減り、5年間通うことに。
GSではフルには働かなかったが、18から23まで、半分の日々はこのGSで過ごすことになった。
さて、こんな話を書き出したのは、つい先日当時の主任に再会したから。
何回かに分けて、この「青春のガソリンスタンド」のことを書いてみたい。
*本も、つりも最初は関係なさそうだけど、今に出てきます。
バイトを探していたボクは、そのGSに飛び込み、
「あのー、バイトしたいんですけど・・」
と切り出した。
当時の所長に簡単な面接をされ、
「じゃ、明日から頼むよ!」と言われるまでに10分も掛からなかった。
次の日からGSでのバイトが始まる。
最初は、給油、窓拭き、洗車、など簡単な作業からはじめたが、慣れてくるにつれオイル交換やクーラント(ラジエーターに入れる液体)の交換などもやらせてもらえた。
もともとクルマ好きだったボクは、結構ここのGSでクルマのことも、そして働くことの意味も身に着けることが出来た。
何よりよかったのがメンバーだ。
所長、主任(25歳、後に所長になる)、社員のM君(18歳)に、東北から就職してきたK君(18歳)。
それからベテラン社員のIさん。
みんな個性的で楽しい思い出がたくさんある。
ここのGSは吉祥寺という土地柄か、老舗の商店や会社、そして周りの高級住宅地にお住まいの外車にのった方々・・。そう、一見のお客様より固定客が多かった。
そして、もう一つの特長は夜になると改造車に乗ったお客様(元族??)がよくいらっしゃった。
というのも、当時主任もIさんもクルマの改造が得意で、エンジンの載せ替えは当たり前。ボアアップやターボキットの装着。もちろん電装系の改造まで請負っていた。
さながら夜はレーシングガレージの様。
エンジンの分解や洗浄などを手伝うことも出来たし、寒い日や暑い日の洗車やワックス掛けはつらかったけど楽しいバイト先だった。
おかげで本業の大学の出席日数が減り、5年間通うことに。
GSではフルには働かなかったが、18から23まで、半分の日々はこのGSで過ごすことになった。
さて、こんな話を書き出したのは、つい先日当時の主任に再会したから。
何回かに分けて、この「青春のガソリンスタンド」のことを書いてみたい。
*本も、つりも最初は関係なさそうだけど、今に出てきます。
仕立てでマダイ??
11月28日(土)。友人のお仲間が予約した仕立船、金沢八景の黒一丸
に乗せていただくことになった。

マダイ五目、って釣りものはたいていアジ、サバを持ち帰ることになりマダイの二段引きを堪能できる機会は過去の経験から確率が低い。
だが、一週間前ながらマダイを釣る気満々。
聞いた話によると、あんまり「釣ってやるぞ!」の気合を入れるぎるとそれがマダイに伝わり避けられるトカ。
マダイがかかればめっけもの、くらいでビシと仕掛けをゆっくりひそかに扱ってやるといいとか。
さて、週末によい報告がココでできるかご期待ください。

マダイ五目、って釣りものはたいていアジ、サバを持ち帰ることになりマダイの二段引きを堪能できる機会は過去の経験から確率が低い。
だが、一週間前ながらマダイを釣る気満々。
聞いた話によると、あんまり「釣ってやるぞ!」の気合を入れるぎるとそれがマダイに伝わり避けられるトカ。
マダイがかかればめっけもの、くらいでビシと仕掛けをゆっくりひそかに扱ってやるといいとか。
さて、週末によい報告がココでできるかご期待ください。
桐野夏生「OUT」
日本のサスペンス、ミステリーの傑作といえば桐野の「OUT」でしょうね。
エドガー賞のノミネートまでいって受賞できなかったのは残念だけど、海外でも高評価されてる。


この本は、釣り仲間のmasaさんから紹介され貸していただいて読んだもの。
「すごいよ、ぐいぐい行っちゃうよ」
の言葉に半信半疑になりながら、平日ほとんど眠らずに読了しました。
おまけに、その後2回読んだ。
実は、主人公(香取雅子)がかつて勤めていたというT信用金庫はどう考えても我が家のメインバンク。
毎月住宅ローンをこの信金に収めてます♪
てなことはさておき、ロケーションが我が家の近くなので東大和のデニーズも邦子が(?)を捨てた、K公園(小金井公園)も日常の生活範囲。
そんな意味もあって、一介のパートのおばさん(ごめん)の裏の顔。
金のためには、ここまでやる。
でも手にした金の価値は手をする前より変わってく。
桐野の作品はこの後何作か読んだが、残念ながらこれを超えられない(って無理か)。
ドラマ化、映画化されたらしいけど、見てないのでそのことは語れない。
「OUT」は読まれた人がほとんどだと思うけど、もし、まだだったら是非。
文学的な価値より、ドラマとしての価値は最大限あり。保証する。
エドガー賞のノミネートまでいって受賞できなかったのは残念だけど、海外でも高評価されてる。


この本は、釣り仲間のmasaさんから紹介され貸していただいて読んだもの。
「すごいよ、ぐいぐい行っちゃうよ」
の言葉に半信半疑になりながら、平日ほとんど眠らずに読了しました。
おまけに、その後2回読んだ。
実は、主人公(香取雅子)がかつて勤めていたというT信用金庫はどう考えても我が家のメインバンク。
毎月住宅ローンをこの信金に収めてます♪
てなことはさておき、ロケーションが我が家の近くなので東大和のデニーズも邦子が(?)を捨てた、K公園(小金井公園)も日常の生活範囲。
そんな意味もあって、一介のパートのおばさん(ごめん)の裏の顔。
金のためには、ここまでやる。
でも手にした金の価値は手をする前より変わってく。
桐野の作品はこの後何作か読んだが、残念ながらこれを超えられない(って無理か)。
ドラマ化、映画化されたらしいけど、見てないのでそのことは語れない。
「OUT」は読まれた人がほとんどだと思うけど、もし、まだだったら是非。
文学的な価値より、ドラマとしての価値は最大限あり。保証する。
エルマーとりゅう
ここ数回のブログで、昔語りをしてしまった。
読者には悪いが、この一連の話を書くにつれ昔を振り返る時間が深夜に流れた。
本好きになったのは、いつ頃か、、、?
昔何を読み何を思ったか、、?
ボクにとっては貴重な回想だと思ってる。
子供のころ、いろんな本を読んだ。
姉が二人いたし、親は本を買い与えるのに、今思えば寛容だった。
おもちゃはなかなかGETできなかったけどね。
思い出すのは「エルマーとりゅう」のシリーズ。

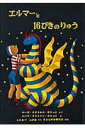
これが、絵本を超えた自分で読みふけた最初の作品だと思う。
「水の子トム」 のように、図書館で借りた本かもしれない。
時間を忘れて、読み込んだ。
エルマーが食べるオレンジが、やたらうまそうに感じたことを思い出す。
この本は、実はうちにある。
息子が小学校低学年の時に買い与えたのだ。
幸いにして、息子もちゃんと読了してくれた。
心に何が残ったかは知る由もないが・・。
読者には悪いが、この一連の話を書くにつれ昔を振り返る時間が深夜に流れた。
本好きになったのは、いつ頃か、、、?
昔何を読み何を思ったか、、?
ボクにとっては貴重な回想だと思ってる。
子供のころ、いろんな本を読んだ。
姉が二人いたし、親は本を買い与えるのに、今思えば寛容だった。
おもちゃはなかなかGETできなかったけどね。
思い出すのは「エルマーとりゅう」のシリーズ。

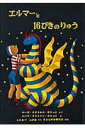
これが、絵本を超えた自分で読みふけた最初の作品だと思う。
「水の子トム」 のように、図書館で借りた本かもしれない。
時間を忘れて、読み込んだ。
エルマーが食べるオレンジが、やたらうまそうに感じたことを思い出す。
この本は、実はうちにある。
息子が小学校低学年の時に買い与えたのだ。
幸いにして、息子もちゃんと読了してくれた。
心に何が残ったかは知る由もないが・・。
