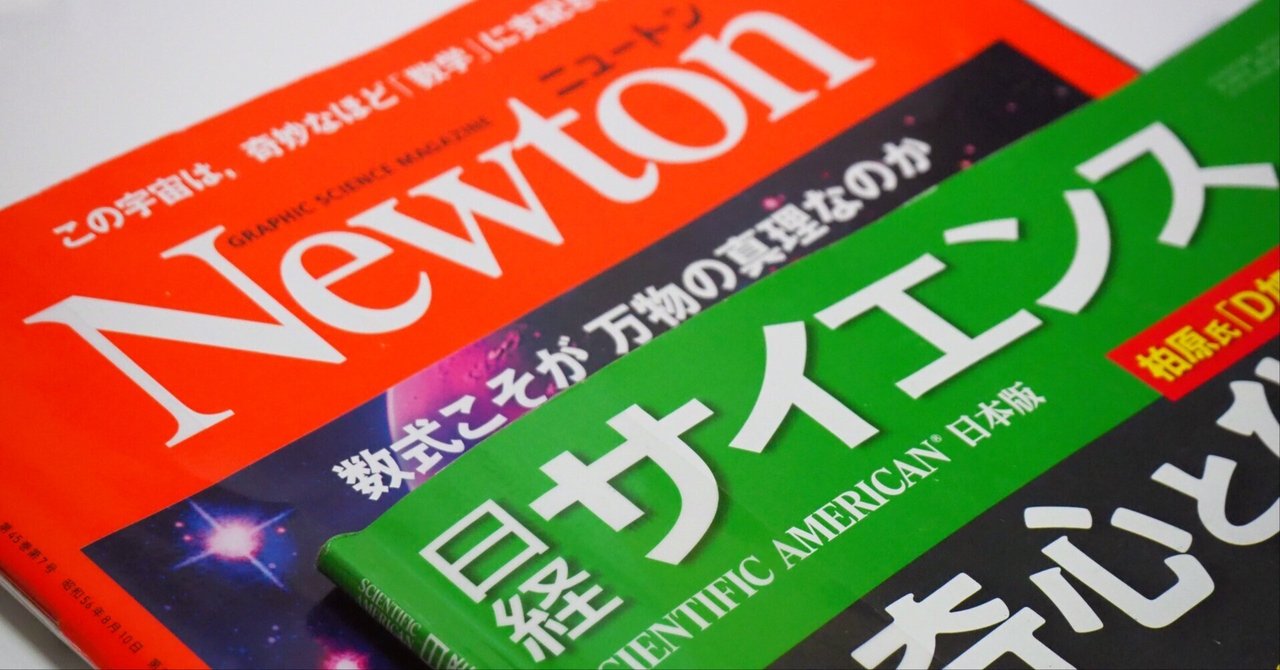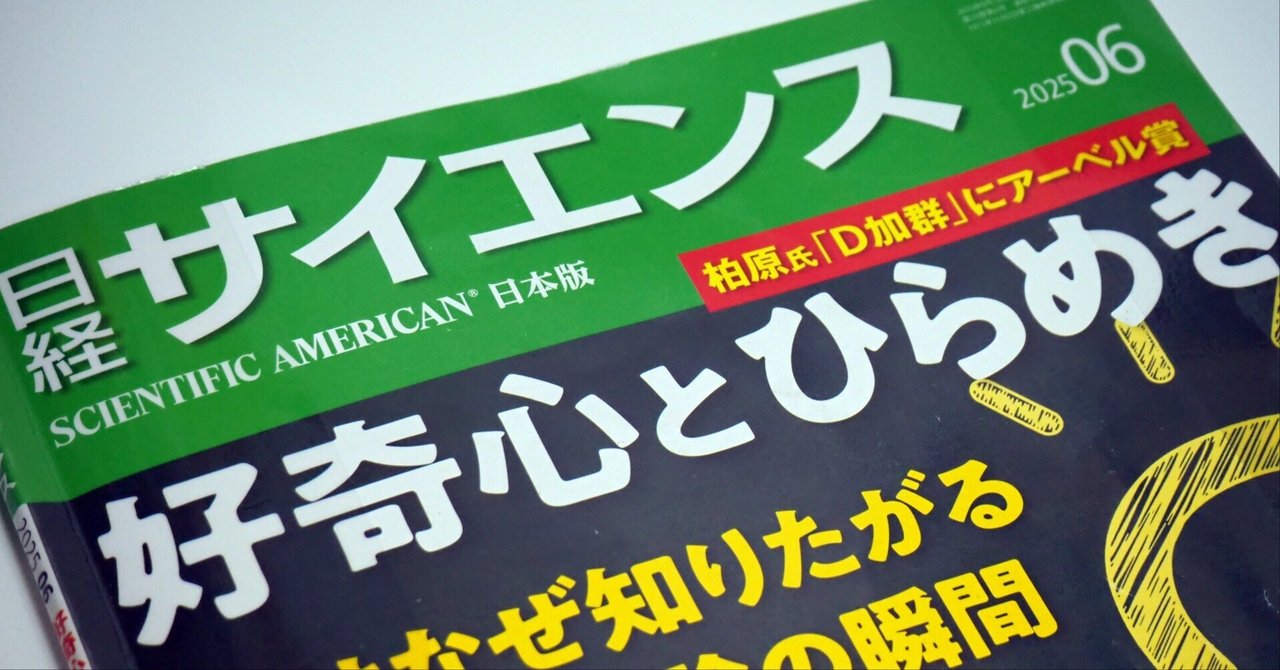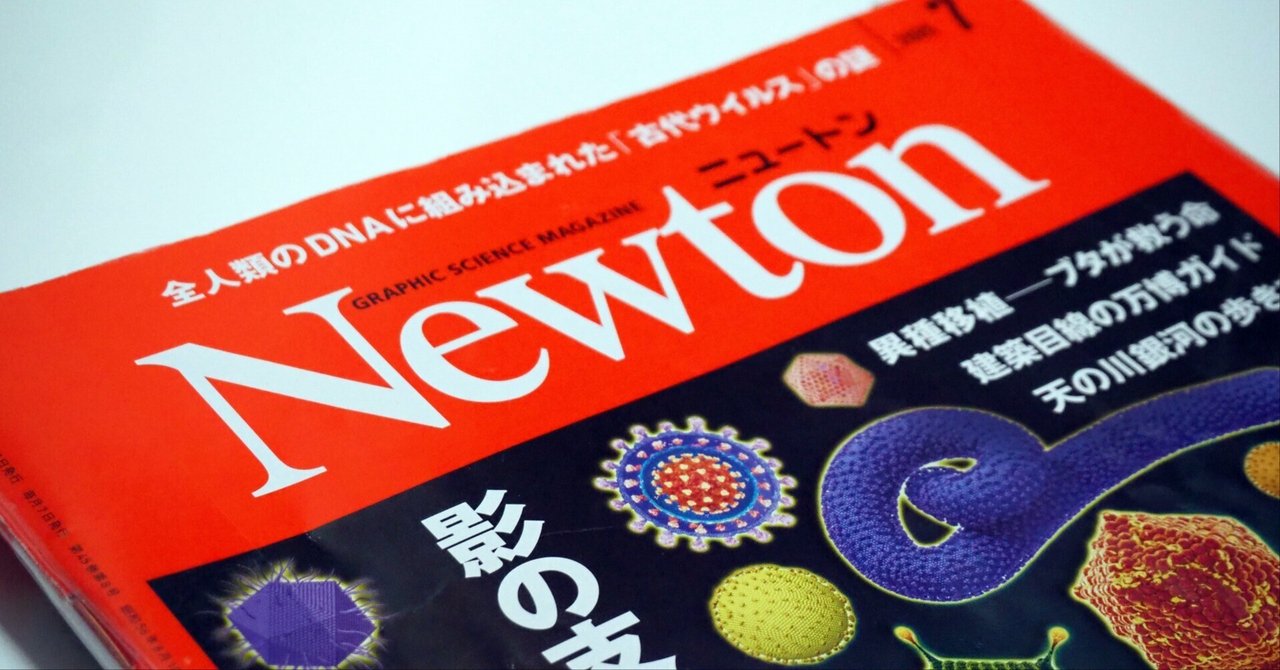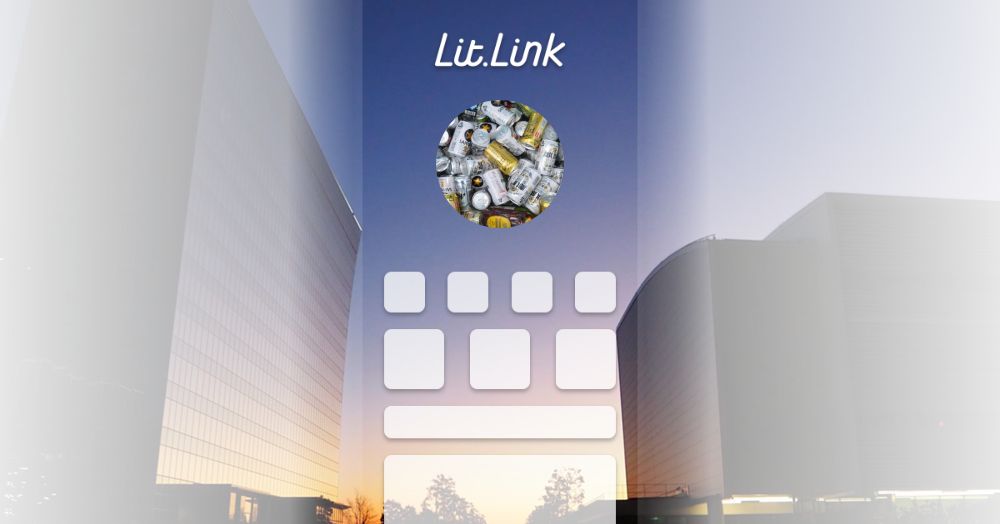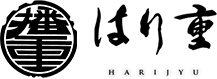すごろく×美術史
どうも遊木です。
前回の記事でもちょろっと触れましたが、2026年最初のミーティングは私が議長を務めました。
そこで扱った内容について、ざっくり記事にまとめたいと思います。
今回用意した議題は「一般教養レベルの美術知識」です。
10年以上活動している創作サークルが扱うには、“妥当”と“今更”がせめぎ合うテーマですが、今回は私の個人的な事情を優先させて貰いました。
というのも、私は今まで一度も、しっかりと美術の勉強をしたことがありません。
「あれだけ美術展に行ってるのに何言ってんだ」という感じですが、鑑賞、技術の習得は一旦置いといて、ここでいう“美術の勉強”は、つまるところ座学です。
高校はそもそも美術の授業がなく、大学では「一般教養レベル」を飛び越えて、より専門的な勉強をしていました。
つまり、私は「広く浅い一般教養としての美術」と一度も向き合ったことがなく、勤勉な性格でもないので、ここまでなあなあに済ませてしまっていたわけです。
見に行く展覧会が現代アート中心なのも関係しているでしょうが……当然歴史は繋がっているわけでして……。
現代アート展であっても、ふとした拍子に古典美術やルネサンス、近代美術の片鱗が、作品そのものやキャプションに出てきます。
そういうとき、知識の甘さが露見するのだ……!
……などという前置きがあり、去年の夏ぐらいから細々……とっっっても細々、美術の勉強をしていました。
なので今回のミーティングは、私にとっては成果発表の場、そして学習スピードを上げるためのブーストという面もありました。
ただ、問題は発表の仕方です。
講義形式は結局ウィキペディアの音読になりそうだし、自由研究のような一方的な成果発表は組織としての実りが薄い。
さてどうするか……。
色々悩んだ結果、年明けという開催時期をヒントに、以下の様な企画を考えました。
■美術史すごろく~時をかけるアーティスト~
▼コンセプト
「一般教養レベルの美術知識」の復習と再発見。
▼内容
・遊木が制作した双六『時をかけるアーティスト』をプレイする。
・盤面は古代~現代美術に関する内容。
▼狙い
・遊びを通じて直感的に美術の知識を学ぶ。
・代表的な「作品」「作者」「変革運動」「特徴」「世界的事件」などに触れつつ、美術史の大きな流れを知る。
・双六のプレイスタイルやビジュアルを活かし、“点”として独立している知識を“線”として認識できるようにする。
・2025年に学んだ「デザイン強化企画」の復習。(一部)
↓このような札を44枚用意しました。
それを歴史順に並べ、あとは普通の双六通り遊びます。
サイコロで止まった札の指示に従い、内容に合わせGM(私)が、補足説明を入れました。
↓盤面の全景。
本当は全マス丁寧に紹介したいのですが、引用資料を遠慮なくネットから拾っているので……断念。
著作権の関係でデータは載せられませんが、使用したメインテーマとキーワードだけご紹介します。(大体著作権切れてると思うけど、全部確認するのは手間……)
<メインルート>
①先史美術 (スタートマス)
②古代エジプト美術 写実より“意味の正確さ”。
③古代ギリシャ美術 人体の理想美、“美しい”とは。
④古代ローマ美術 写実性・個人の顔立ちを重視。
⑤初期キリスト教美術 迫害下の“隠れた美術”。
⑥ビザンティン美術 神がそこに“いる”ための媒体。
⑦ロマネスク美術 美しさより伝達力、“教えるための美術”。
⑧ゴシック美術 “体験”させる美術。
⑨分岐マス (サイコロの結果で日本美術史ルートへ)
⑩ルネサンスの幕開け “この世界”を描く絵へ。
⑪遠近法の発明 世界は“信じるもの”から“観測するもの”へ。
⑫レオナルド・ダ・ヴィンチ 万能の天才。
⑬もう一人の万能 圧倒的な人体表現。
⑭事件マス「信仰の分裂」
⑮バロック美術 “説得”のための美術へ。
⑯ロココ美術 “快楽と私生活”の美術へ。
⑰新古典主義 快楽から“徳”へ。
⑱ロマン主義 理性から“感情”へ。
⑲事件マス「産業革命×〇〇の発明」
⑳写実主義 理想ではなく“いま・ここ”を描く。
㉑印象派 モノではなく“見え方”を描く。
㉒ポスト印象派 超えるための実験。
㉓表現主義 見えたものより、感じたものを。
㉔キュビズム “一つの視点”の崩壊。
㉕抽象美術 「現実の代理」から解放。
㉖事件マス「第一次世界大戦」
㉗ダダイスム 戦争への絶望。
㉘シュルレアリスム “夢・狂気・欲望”こそが現実。
㉙抽象表現主義 “結果”ではなく“行為”。
㉚大量消費社会の美術 境界の破壊。
㉛コンセプチュアルアート 作品=アイデアへ。
㉜現代美術とは “問い”を立てる美術。
㉝美術館と国際展 場所と美術。
㉞時代と美術 芸術かテロか。
㉟AIと美術 “作者”の崩壊。
<日本美術史ルート>
<J1>飛鳥・奈良美術 国を作る力。
<J2>平安美術 美意識の完成。
<J3>鎌倉美術 生身を描く時代へ。
<J4>室町美術 “気配”の美。
<J5>桃山美術 権力で爆発した“美”。
<J6>江戸美術 美術は市場へ。
<J7>事件マス「鎖国」
<J8>ジャポニスム 日本美術が世界へ。(㉑印象派へ合流)
※双六の背景色
黄色…先史、古代
緑…中世
青…近世~近代
紫…近代
ピンク…近代~現代
オレンジ…戦後~現代
日本…年代を考慮するなら⑥ビザンティン美術で分岐するべきだったが、ゲーム性の都合上⑨で分岐。その代わり「世界との合流地点」(印象派合流)は史実通りに。
全員ゴール後は、未踏マスを中心に振り返りの時間を設け、それぞれ何が印象に残っているかなど感想会をしました。
流れの都合上、一般常識を逸脱している項目もありますが、まぁそこは創作サークルなので「ついでに学べ」というスタンスで。
ところでこの双六は、名前の通り「“時をかけるアーティスト”として、歴史を旅して美術史を学ぶ」という世界観です。
ゲーム開始時には次のようなナレーションを入れました。
あなたたちは、“時をかけるアーティスト”です。
世界の断片的な知識しか持っていない若い表現者。
洞窟壁画、モナ・リザ、印象派、現代アート……それらはまだ、バラバラの“点”にすぎません。
これからあなた達は、時代を旅しながら、人類が何を描き、なぜ作り、何を問い続けてきたのかを目撃します。
この旅を終える頃、点だった知識は“線”になり、自分たちもその一部であることを知るでしょう。
プレイ中にこの世界観が活きたかというと、大して活きてはいない。
私がフレーバーテキスト考えるのが楽しかっただけという……まぁ、ボードゲームの世界観なんてそんなもんよ。
ただ一応、ゴールは↓のようにしました。
スケジュールの都合上、約1週間で爆速のまとめ→双六制作をしました。
故に拾えていない項目は無数にあるし、そもそもネットとChatGPTを駆使したので、怪しい情報もあるでしょう。
可能な限りファクトチェックはしましたが、多分、おそらく、絶対漏れはある。
※サークルでChatGPTを使用したときは「詳しく知りたいなら自分でもう一度調べ直してね」が基本。
ただ今回の取り組みは、しっかり自分の美術知識の底上げになったなと感じます。
ひとマス作るごとに毎回、
・内容から核となるキーワードの抽出。
・代表作品、作者、特色の抽出。
・問題の選定と作成。
・正誤ギミック用に、時代ごとの長所と短所の抽出。
・補足説明の用意。
という過程が入るので、自然と情報を立体的に観察できました。
正直、準備は物凄く大変でしたが、関連書籍をただ読むより身になる勉強ができたと思います。
プレイしたメンバーの反応も、概ね狙い通りだったので、頑張って制作したかいがありました。
大人になると、何事も自学自習が基本です。
なので「リアルで学習を発表する場がある」「一緒に取り組んでくれる人がいる」という、“孤独の学習で終わらない環境”はとても貴重です。
今後も組織としての強みを活かしつつ、楽しい学びを心掛けていきたい。
のぞみん作の我々の立ち絵は、大変使い勝手が良いのである。
aki
「創作者のための科学雑誌レビュー」なるものを始めました。
須々木です。
2026年になってもう1か月だと・・・
そこそこ忙しい時期であるため、横浜創作オフ会関連でワーワーやってた以外はあまりできたことはない感じです。
というわけで今回は先月のネタです。
以前ブログで「リベンジ義務教育」(note版)を始めたという記事を書きました。
こちらは11月末の更新のあと少し新規記事をあげられていませんが、「スキ」を押しながら気長にお待ちください。
そして今回ご紹介するのは、noteにおける新シリーズ。
その名も「創作者のための科学雑誌レビュー」!!
12月からスタートし、現時点で以下の4つの記事があります。
例によって、このシリーズの概要、コンセプト等は最初の記事(#001)に書いてあります。
すごくザックリ言えば、「科学雑誌は創作ネタの宝庫! それを少しだけ紹介するよ!」というノリ。
偉そうなことが言えるほど深く知っているわけではないので、備忘録に毛の生えた程度のものと思ってほしいのですが・・・。
noteの方ではもう少し真面目に書いたのでそちらを読んでもらえると良いのです。
とりあえず今のところ、主に「日経サイエンス」、「Newton」という2つの科学雑誌を取り上げながら進めたいと考えています。
ただし、最新号からかなり遅れて扱っているのでご注意。
noteで紹介している号は本屋に並んでいないはずです。
「創作者のための科学雑誌レビュー」はどういう切り口が良いのか悩ましいところですが、試行錯誤しながら書いていくので、気が向いたらよろしくお願いします。
sho
食い倒れてきた!
どうもこんばんは霧島です。
ただいま大阪から神奈川に戻る新幹線の中でこれを書いています。
昨日京セラドームで行われたなにわ男子の初のドームコンサートに
駅に着いて周りから聞こえる関西弁がなんだか不思議な感じ。
今回新幹線とホテルを一緒に予約したんですけど、
チケットが12枚付いていて、
今回私はOSAKAたこ焼きマーケットというところでたこ焼きの食べ比
あ、【推しの子】のルビーちゃんもいた。
さて、今回は三か所のお店のたこ焼きをいただきました。
1つ目はたこ焼きの元祖という会津屋さん。
ソースやマヨネーズをかけないタイプのたこ焼きです。
2つ目は甲賀流。
今回私が頼んだのはしょうゆ味です。 もう、THE 大阪のたこ焼きという感じで外ふわふわの中トロトロで爪楊枝では
青のりは歯につくのが嫌なので省いてもらいましたが、
ちょうど私が大阪に着いたくらいのタイミングで雪が降り始めていて
そして最後はくくるさん。
こちらはクーポンで選べるお味はソースマヨのみ。
そういえば梅田に行く前にりくろーおじさんのチーズケーキも気に
新大阪はできたてを販売しているのですが、
焼きあがったタイミングで私はちょうどガラス窓の目の前に並んでいた
ちなみに釘付けになっていたので写真や動画は撮り忘れました。
こちら初めて食べたのですが、
さて、腹ごしらえをしたのでいざ京セラドームへ!
ドームにめちゃくちゃ近いホテルをとったわけでは無かったのです
大阪、
ただ、
せっかちという噂を聞いてはいたけど、なるほど…
そして会場に無事到着。人の映り込みがすごいので名前のところだけ…
中の売店でもたこ焼きを売っていたりして大阪感があってよかったです。
私はスタンド席だったんですが、
そして3時間近くずっとキラキラしたままパフォーマンスし続ける
今年は5周年イヤーということで、
あ…これはホテルに戻ってからコンサートの余韻を嚙み締めつつ飲んだクラフトチューハイ…
さて、
大阪松竹座が今年閉館するという事だったので、
かっこいい…建物…!
1923年に作られた歴史ある建物ですが、
こちらはデビュー前のなにわ男子含む関西ジュニアが日々通ってい
そしてそのとなりにあるはり重さんというお店で新幹線の中で食べ
受け取りに少し時間がかかるとのことだったので道頓堀周辺をブラ
なんだかテーマパークのような街並みで面白いです。
これは無事電車の中で頂いたお弁当。
上品な味付けで素材の味がしっかりわかる、とても美味しいお弁当で
結構量があるので、食べ切れるかな…
そしてこちらは新幹線の改札内で売っていた堂島ロール。
ロールケーキ自体をものすごく久しぶりに食べましたが
あとは551の豚まん…
これは帰宅して先ほど温めて食べてみましたが、めっちゃ好き~!
肉まんじゃなくて豚まん!て感じですね。(?)
とても豚肉の味がしっかりしているのと、弾力のある皮が絶妙だった…豚まんもめちゃくちゃ久しぶりに食べたな…
そんなわけで一番の目的はコンサートだったわけですが、
今回の旅では定番のところにお邪魔した感じですが、
さて、
したらば!
rin
2026年が始まりましたが、去年の活動報告です。
明けましておめでとうございます。
どうも遊木です。
2026年も、どうぞよろしくお願いいたします。
今年は午年ですね。
馬は古来より、縁起物として世界中で愛されてきました。
前進や成功、勝負、出世、人を結ぶ縁など、様々なものの象徴となっているようです。
さて、新年の挨拶をするには、年明けから大分時間が経ってしまいました。
というのも、個人の作業にプラスして、今年最初のミーティングが議長回だったので、その準備に追われていたら……あら不思議、もう月末だと……?
少ない議長回なので、回ってくると力入っちゃうんですよねぇ。 詳細は別記事にまとめる予定なので、良かったらそちらもご覧ください。
※数年前までミーティング議長はメンバーの持ち回り制だったが、個人活動を考慮して、現在漫画組は年2回程度に制限されている。
新年の挨拶をしておいてなんですが、今回は残していた去年の活動報告をまとめて行いたいと思います。
イベントが多い季節だったからな……さて、どのくらいのボリュームになるのか。
ということで、2025年10月~12月の活動報告です。
10月
■横濱コクーン・スクウェア2025
横浜市役所アトリウムで開催されたイベントです。
今年で10周年ということですが、初めてお邪魔しました。
横浜における生糸の立ち位置や関連遺跡の紹介、伝統工芸品であるスカーフにスポットを当てた催しで、大変興味深い内容でした。
私は1日目のダンスパフォーマンスとシンポジウムを見学したのですが、特にシンポジウムが印象的でした。
「横浜の生糸貿易と歴史的建造物」という切り口から、昔の生糸産業の様子や、現存する遺構をどう扱っていきたいかなど、過去から現在、そして未来に向けて“生糸の物語”をどう紡ぎ続けるのか、希望や課題などを聞かせて頂きました。
■ハマクリ YOKOHAMA CREATORS’ MARKET
初開催ということで、お邪魔してきました。
10月の一ヶ月間(祝・休日)に、スカイビルの10階中央広場で開催された創作系イベントです。
小規模のCOMITIAみたいな感じですね。
第2回も開催されるようで、12月に出展アーティストを募集していました。
今の所規模はかなり小さめですが、身近な場所でこのようなイベントが行われるのは嬉しいです。
■横濱JAZZ PROMENADE 2025
例年通りお邪魔しました。
今までで一番、しっかり演奏を聞けたと思います。
初日は生憎の悪天候で、屋外参加予定のアーティストさんは不憫でしたが……。
屋外イベントの難しい部分ですね。
ということで初日は屋内ステージ、二日目は屋外ステージを中心に回りました。
「横浜ジャズ100年」というテーマで開催されたので、天気に負けず、いつもより盛り上がっていたようにも思えます。
毎年この日は横浜がジャズに包まれます。
大規模会場も小規模会場もそれぞれの良さがあるので、是非一度覗きに行ってみて下さい。
■佐藤雅彦展 新しい×(作り方+分かり方)
横浜美術館リニューアルオープン記念ということで開催されていました。
巷でもかなり話題になったようで、特に会期の後半はすんごい行列が出来ていましたね。
横浜に来て10年以上経ちますが、横浜美術館があそこまで混んでるの初めて見た。
非常に刺激を受ける展覧会でした。
個人的には展覧会というより研究発表を見ている気分で、思わず「学生の頃にこの内容を知っていたら!」と考えてしまった。
とにかく創作活動をする人は、図録だけでも読むことをお勧めします。
むしろ図録がメインです。
佐藤雅彦の“始まり”やヒットメーカーである由縁、彼の思考回路の一端、展覧会名の「新しい×(作り方+分かり方)」も理解できるかと。
須々木氏が関連記事をあげているのでそちらもどうぞ。
■わくわく!こどもハロウィン in 横浜北仲フェス
横浜市役所アトリウムで開催されたイベントです。
基本は子供向けのコンテンツですが、イベントに合わせて31階のレセプションルームが開放されるということでお邪魔しました。
ちなみにレセプションルームはプリキュアとのコラボ。
流されてる映像に合わせて子供たちが踊ってて…めっちゃ…癒された……そのまま元気に踊り続けろ子供達よ。
子供向けと言いつつ、建築(大工)体験など大人でも楽しめそうなコンテンツがあったので、タイミングが合えばまたお邪魔しようかなぁと思ってます。
■ヨコハマきのこ大祭
毎年MMテラスで開催されている、キノコ好きのためのイベントです。
テラス内に個人ブースが並んで、雑貨から本物のキノコまで、様々な関連物が販売されています。
全体的にクオリティが高いので、キノコ好きさんだけでなく、クリエイティブな活動に興味がある人にもおススメのイベントです。
会場で買った巨大しめじが美味しかった。
■第10回 横浜よさこい祭り
馬車道、みなとみらいで開催されるイベントです。
存在は知っていましたが、直接見たのは初めてです。 思っていたよりもすごい迫力。
参加者もそうですが、衣装、小道具、振り付けも多種多様で、とても見応えがありました。
一括りに“よさこい”と言っても、いろんな表現があるんですね。
特にフィナーレにあった旗手の演舞は大迫力でした。
余談ですが、私は幼稚園の鼓笛隊でガードを担当しており、その経験から大旗を振るのが好きになりました。応援団とか。
■企画展示 BROKEN PROMISES 破られた約束 ―太平洋戦争下の日系カナダ人―
JICAで開催された企画展です。
第二次大戦中、あらゆるものを取り上げられた日系カナダ人たちがどのように生きたのか、そこにスポットを当てた内容です。
また、実際に送還され、敗戦後の日本を必死に生き抜いた中山信子・レナさんの公演を聞くことも出来ました。
書籍や映像の情報より“生っぽい”当時の様子や、実際にその時代を生きたが故の考え方、感情、それらを当人から直接聞けるとても貴重な経験だったと思います。
■その他のイベント
〇ワールドフェスタ・ヨコハマ2025
初めて歩行者天国部分を歩きましたが、めっちゃ雨でした。
〇オールドノリタケ展
BankPark YOKOHAMAのグランドオープン記念として開催されていました。
11月
■馬車道まつり
その名の通り、毎年馬車道で開催されるお祭りです。
馬車や人力車、鹿鳴館時代を再現したお祭りで、バッスルラインの煌びやかな洋装の人もおり、現場を見るだけでも楽しいです。
袴の試着体験や日本の在来馬と触れ合うこともできる、和洋が混在するイベントです。
ちなみに、今年の年賀絵はここで撮影した馬車をめちゃめちゃモデルにしました。
■旧東海道、ビジネスパーク散策など
数年前に洲崎大神から保土ヶ谷の本陣跡まで歩いたのですが、今回は戸塚区側から相鉄の天王町まで歩きました。
実はさらに昔、箱根の旧東海道を歩いたことがあるのですが、あれは普通にプチ登山でしたね。「昔の人すげぇー!」ってなる。
その後は星天qlayや横浜ビジネスパークを覗き、噂のパブリックアートを鑑賞しました。
最後に神明社を覗き、この日の散策は終わり。
まだまだ横浜には見どころがあります。
■第5回 横浜スタチュー・ミュージアム
日本大通りを中心に開催される屋外パフォーマンスイベントです。
これも須々木氏が記事をあげているので、気になる方はそちらもどうぞ。
毎年少しずつ作品が増えるのですが、第5回の新作目玉はクラーク博士でした。
ラストの全員集合では、みんながクラーク博士のポーズを!
以前にも書いたかもしれませんが、スタチュー・ミュージアムの面白さは「現場で直接知るしかない」というのがリアルな感想です。
写真や動画では、あの独特のエンタメは伝わらない。
「舞台を生で観るのとDVDで観るのとは違う」に似ているのかもしれませんが、個人的にはそれとも少し違う気がしていて、作品の設定、場所、通行人、パフォーマンスに気付く人、気付かない人、様々な要素が化学反応を起こして、初めてスタチュー・ミュージアムのエンタメは完成するのかなと思います。
まぁ結局「直接見に行ってくれ!」に帰結する。
■横浜ユーラシア文化館 企画展「山本博士コレクション 横濱東西文化のランデブー」
正確には「山本博士コレクション 横濱東西文化のランデブー ―眞葛󠄀焼、横浜写真から横浜彫刻家具まで―」です。
ランデブーには「艦隊の集結地点」という意味があり、横浜は「東西文化の集結、対峙した場所」という解釈から、この展覧会名になったようです。
1859年の開港以降、横浜は日本の代表的な貿易港として急速な発展を遂げました。
目新しい西欧文化が入ってくる場所、伝統的な日本文化が出ていく場所、両者が交錯する文化の玄関口として独自の“色”を生み出し、その形跡は、現在でも街に色濃く残っています。
その“色”が目に見える形となったものの一つに、輸出用の工芸品があります。
当時の作品は、日本の伝統技術を活用しながらも、外国人が好むよう独自にローカライズされていました。
眞葛焼きや横浜彫刻家具が共通して内包する「和洋折衷な芸術性」は、この結果誕生したものでしょう。
これらに魅了された山本博士氏は1000点以上の作品を収集し、今回の展覧会ではそのうちの約200点が紹介されたようです。
以前鑑賞した金子皓彦氏のコレクション展(横浜で発展した近代輸出漆器の展覧会)では、この頃の輸出用工芸品は、外国人に受けるよう「より日本らしいもの」を意匠にしていたと説明がありました。
人力車に傘を持った着物の婦人、背景に富士山……言葉にすれば、なるほど確かにザ・日本風のモチーフですが、不思議なことに日本の文化は“日本風”を押し出せば押し出す程、“日本らしさ”からは離れていく傾向にあります。
ワビサビ、余白の美、日本独自の美的感覚は、日本独自の価値観が伴わなければ、なかなか理解し辛いものなのかもしれません。
といっても、個人的には「日本風に憧れた外国人が、日本風につくったもの」とは明確な差があると思っています。
眞葛焼きや横浜彫刻は、当時の職人が「なるほど、外国人はこういうのが好きなのね」と改変していったものですが、あくまで日本人が日本人として生み出した芸術です。
華美な装飾に目を盗られがちですが、一つ一つの要素に目を向けると、隠れて息づく日本独自の“美”を感じることが出来ます。
そこが19世紀の西洋で興ったジャポニスムや、現在の日本風アニメとの相違点かなと思います。
表現の世界においては、これからもガラパゴス化を恐れず“日本らしさ”を追求して欲しいところ。
■YOKOHAMA URBAN SPORTS FESTIVAL’25
赤レンガで開催されたアーバンスポーツのイベントです。
今回は音楽だけでなく“食”も合わせて、もっと広い意味での“アーバン”を推しているようでした。
個人的に開催時期の変更が大変ありがたかったです。
元々は夏に開催されており、長時間の観戦はとてもじゃないけど不可能だったので。
普通に生活しているとアーバンスポーツを直接見る機会はないので、このイベントには毎回助けられています。
アクロバティックな動きを勉強するのにも、参考資料を得るのにも、とても良い場所。
■その他のイベント
〇日本丸 総帆展帆・満船飾
毎年この日は天気が良いですね。
〇第3回かながわ木づかいフェア
象の鼻パークで開催されていました。
12月
■湯河原紅葉狩り
これはサークルの恒例イベントとして行きました。
紅葉シーズンとしてはギリギリでしたが、当日は天気も良く、適度な運動、適度な散策、適度な甘味、ゆったり温泉と、心身をリフレッシュするには丁度良い行楽だったと思います。
個人的に万葉公園が近くに欲しい……。
川の音を聞きながらゆったり出来る空間は万人を癒します。
しかし、そろそろ日帰りできる紅葉狩りスポットが尽きてきましたね……今年はどうなるのか。
■イルミネーション関連
横浜の冬は各地でイルミネーションが展開されており、最近では日本新三大夜景都市にも選ばれました。
今年度は「THE YOKOHAMA ILLUMINATION」として各地域が引き続き連携し、冬の横浜を盛り上げているようです。
〇ヨルノヨ、ミライト、その他各地のイルミネーション
〇BALLPARK Xmas YOKOHAMA KANNAI 2025
初開催です。
以前は「BALLPARK FANTASIA」としてスタジアム内を活用するイベントでした。
「ここ最近マンネリ気味だなぁ」と思っていましたが、しっかりアップデートが入ったようです。
今回のアプデだったり、赤レンガのイベントと連携したり、DeNAはこういう取り組みが上手い気がします。
〇Pokémon Happy Holidays
これも初開催。ZAのDLC発売に合わせた感じでした。
事前告知があまりされていなかったので「開始直後が絶対一番すいてる!」と初日に突撃。
案の定、後ろに行くにつれて混雑したようです。
ポケモンと言えば『ポケパークカントー』オープンに向けて、諸々の情報が出始めましたが、ちらほら「内容に対して値段が高いのでは?」という意見を見かけます。
感じ方は人それぞれですが、個人的に、ピカチュウ大量発生チュウ、WCS、春節や今回のような突発ポケモンイベントを体験していると「いや、そのぐらい取らないとマジで大変なことになるぞ」とは思いますね。
〇イタリア山キャンドルガーデン
前回は同日に色んなイベントが重なっていたので、駆け抜けるように見てしまいましたが、今回はしっかり楽しみました。
ギリギリまで天気が怪しくて、何なら途中降られたりもしましたが、演奏なども合わせて楽しみました。
復活した外交官の家は、なかなかの映えスポット。
〇各地クリスマスツリー
MARINE & WALKではツリーだけでなくプロジェクションマッピングも取り入れたようです。
■横浜山手西洋館「世界のクリスマス2025」
これも恒例イベントです。
各国のクリスマス装飾だけでなく、パネルなどで文化の勉強が出来るのもこのイベントのポイントです。
今回はオーストラリアが参加しており、北半球に住む日本人には馴染みのない、南半球の、つまりは“夏のクリスマス”が印象的でした。
装飾も青でまとめられており、爽やかな雰囲気。
昔は教科書や資料集に、サーフィンに乗るサンタさんが載っていましたが今はどうなんでしょう。
あとクリスマスには関係ないのですが、文化紹介のパネルに、カンガルーとワラビーの中間に「ワラルー」という種類がいることが書かれており、「マジか」となりました。
それは知らんかった。
■横浜ランドマークタワースカイガーデン
改修工事のために閉じてしまうということで、滑り込みで登ってきました。
過去に一度だけ入場したことがありますが、その時は真っ昼間だったので、今回は夕方、日の入り、夜景が見られる時間帯に行きました。
トムジェリ85周年コラボも開催されており、展示、装飾、スタンプラリーなどが展開されていました。
個人的にはクッションが可愛くて、暫く抱きしめてぼーっとしてた……癒し……。
スカイガーデンの再開は2028年以降らしいので、暫く69階からの景色はお預けです。
今回撮影した風景と、次登ったときに撮影する風景にどのくらい変化があるのか、比べるのを楽しみに再開を待ちたいと思います。
■草凪みずほ画業20周年記念 暁のヨナ大原画展
アソビルで開催されたのを、会期ギリギリで乗り込みました。(ギリギリが多い人生)
12月発売の花ゆめで無事完結し、2月に47巻が発売されるそうです。
「暁のヨナ」は少女漫画の中では1、2を争うくらい好きな作品で、アニメも含め楽しませて貰いました。
貴種流離譚として読み応えのある物語で、血と泥臭さ、率いるものが置かれる厳しい環境など、少女漫画で扱うには難しそうな題材を、ギャグやトキメキと打ち消し合わないように描き切っているところが本当にすごいです。
こういうのもなんですが、初めてヨナを読んだときは「少女漫画でもこういうことして良いんだ!」と衝撃を受けました。
今回、大原画展ということで、初めて草凪先生の原稿を拝見しました。
繊細なペンタッチからはもちろん、特に修正箇所から「あぁ、ここの表情を決めるのに苦労したんだ」という制作の裏側を読み取れ、とても刺激になりました。
会場では「暗黒龍(以下略)の野営」のようなニッチなものから「等身大の一行」、扉絵の再現など、見ごたえのあるフォトスポットが設置されていました。
最後に「プッキューの森」がありましたが、ここで妙な既視感が……ハッ!これ、ベルセルク展のパック広場と同じ!?ハッ!どっちも白泉社…!?
となり帰宅後に写真を見返したら、コンセプトだけじゃなくて設置台も同一のものと発覚。
……同一、だよね?
↑ベルセルク展のパック大量発生
その他には、ようやく足に出来たイボが完治したり、遅れていたゲ謎の備忘録が届いたり。
多分、掘ればもっとあると思うんですがキリがないのでこの辺で……。
以上、長くなりましたが3ヶ月分の活動報告でした。
個人インスタに関連写真を載せているので、そちらもどうぞご覧ください。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
aki
小倉城行ってきた!
どうもこんにちは霧島です。
年末年始は山口の実家に帰省してるので、ぼちぼちお絵描きしながら地元の友達とご飯に行ったり飲んだりしています。
先日は小学生時代からの友人たちと福岡は小倉をブラブラしたんですが、初めて小倉城の中に入りました。外から眺めることはあったけど、そういえば中に入ったことはなかったなと…
「日本一おもしろき城」を目指しているそうで、5階までに歴史的な展示や体験型のアトラクション、ミニシアター、あと脱出ゲームなどもあったりしてなかなか盛りだくさんで面白かったです。小さい子連れの方々が多かったのですが、ちびっこ達も楽しそうでした。楽しく歴史を学べるのはいいね。
土曜の夜はバーなどもやってるそうです。(冬期は休業中のようですが)
城内を下から上まで見学したあとは、庭園にもお邪魔しました。
こちらは庭園から仰いだ天守閣。
庭園では茶道体験などもできるらしい。
そのあとは夕飯を食べ、初めて角打ちに行ってきました。
ここは駅ビルに入ってるお店。
立ち飲みは初めてだったのですが、お店の雰囲気もよく、お酒も美味しくて楽しかったです。年末というものあってか人もすごく多くて活気のある感じがとても良かった。
というわけで、1年の終わりにまた1つ新しい経験もできて、いい年の瀬を迎えられそうです。
多分この後はだらだらとお絵描きしつつ…日付が変わるんだろうな。
今年も一年大変お世話になりました。来年も楽しく充実した年にしていけたらなと思いますので、皆さま引き続きどうぞよろしくおねがいいたします。それでは良いお年を!
したらば!
rin