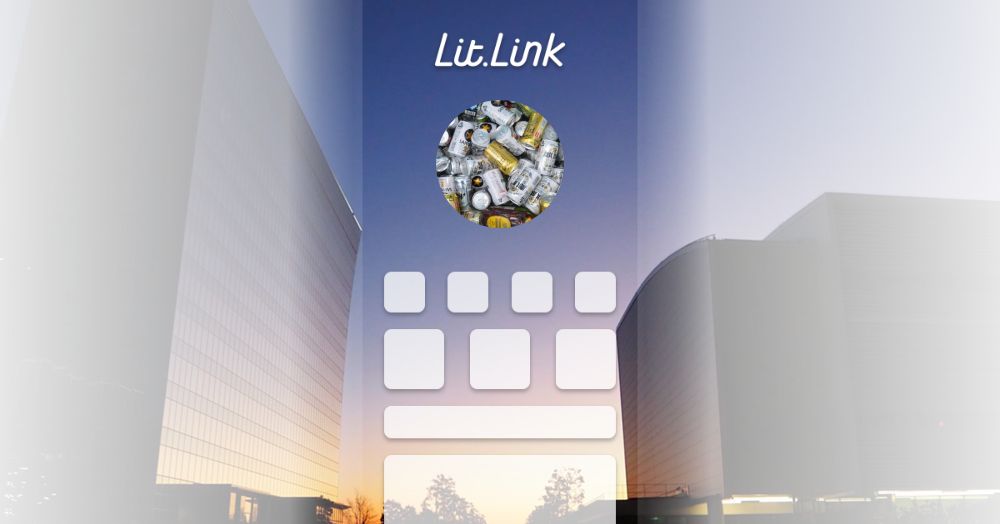横浜美術館「佐藤雅彦展」行ってきました。
須々木です。
先日、
横浜美術館リニューアルオープン記念展
佐藤雅彦展 新しい×(作り方+分かり方)
に行ってきました。
なかなか人気ということは聞いていたので、平日の開館30分前に行ったら・・・すでに長蛇の列!
横浜美術館には何度も入っていますが、いまだかつて見たことのない人気っぷり。
客層も「はじめて来ました」という雰囲気の人が多い気がしました。
今回の展覧会の内容的に、子供もとても多かったです。
わりとお堅いイメージのある横浜美術館がこんなに子供で溢れかえるなんて、ちょっとした事件です。
入場時間指定のチケットをゲットして、待ち時間は同時開催のコレクション展を見ていました。
昼頃『佐藤雅彦展』に入場して、結局、出たのは夕方でした。
もちろん中もそれなりに混んでいましたが、十分堪能して満足しました。
* * *
世の中的に佐藤雅彦の知名度がどれほどなのか少しわからないのですが、とりあえずその制作物のうち、一般の認知度が高そうなもの列挙しておきます。
TVCM 湖池屋「スコーン」/NEC「バザールでござーる」/TVCM サントリー「モルツ」/TVCM 湖池屋「ドンタコス」/TVCM 湖池屋「ポリンキー」/ゲーム「I.Q Intelligent Qube」/「だんご3兄弟」/TV番組「爆チュー問題」(企画)/TV番組 NHK「ピタゴラスイッチ」/TV番組 NHK「たなくじ」etc
YouTubeで「佐藤雅彦 作品」などと検索すると、雰囲気はわかるでしょう。
バザールでござ~る♪
ドンタコスったらドンタコス♪ ドンタコスったらドンタコス♪
ポリンキー ポリンキー 三角形のひみつはね♪ 教えてあげないよ ジャン!♪
串にささって だんご だんご♪ 3つならんで だんご だんご♪
もともと佐藤雅彦の制作物は、佐藤雅彦という名とは無関係にたくさん知っていました。
一方で、佐藤雅彦の名をそれほど明確に意識してきたわけでもなく、「だんご3兄弟とかの人」「ヒットメーカー」くらいの薄っぺらい認識でした。
数々の制作物についても「ドハマりした」とかいうわけでもなく。
でも頭の中にいつの間にかこびりついて、しかもそのままわりと残っています。
この絶妙な塩梅――夢中にならないけれど頭に残る――により、その背後に当然いるはずの制作者に対し意識が向かなかったのだと思います。
そんなわけで、“佐藤雅彦”という人物についての事前の知識をほとんど持たぬまま展覧会会場に足を踏み入れました。
展覧会をたっぷり堪能した後の印象などを好き勝手に書き記しておきましょう。
展覧会タイトルにある「新しい×(作り方+分かり方)」から何となくうかがい知ることはできますが、この展覧会は、ただ有形の作品を敷き詰める回顧展ではありません。
いや、ある意味で敷き詰めているのかもしれませんが。
「作り方」「分かり方」と彼が呼ぶ方法論こそが彼が生み出したものの本質であり、そのような無形の“作品”たちを、美術館がもつ物理的制約の中、もっとも効果的と思われる方法によって敷き詰めて披露したのが今回の展覧会でした。
全体を通して、とにかく彼の「思考する力」の強さを感じました。
ひらめきの質の高さは言うまでもなく凄まじいものがありますが、それを確信をもって整える論理がとにかく強固です。
根本を支えるのは数学的思考(抽象化)で、日常にパズル的要素を見つけるセンスの高さも感じます。
極限まで抽象化し、得られた概念をツールとして駆使するため、極めて汎用性が高く、媒体の制約を超越していきます。
ヒットの再現性が高い人は多かれ少なかれこのタイプが多いのではないかと思いました。
また、現在の「バズり」や「映え」に通じる先見性も随所に感じられました。
一定のクオリティーに達する型をあらかじめ用意してヒットを量産する手法は、現代のSNSでも追求されているものだと思います。
* * *
佐藤雅彦が生み出した制作物は本当に膨大ですが、その背後にある方法論はそれ以上に膨大です。
それらを意味のある形で我々が受け取るには、美術館がもつ物理的制約以上に、我々がそこに滞在するという時間的制約の方が大きいかもしれません。
だからこそこの展覧会はダイジェストにならざるを得ず、圧倒的な情報量を誇る海面下の氷山本体のボリュームを把握しようとするだけで精一杯になってしまいます。
必然的に、展覧会を補完するものが求められます。
それこそが公式図録。
すでに開催を終えてしまっていますが、かつて毎年開催されていた文化庁メディア芸術祭もまた、物理的、時間的制約を少しでも乗り越えるべく、充実した内容の図録を読み込むことがマストの展覧会でした。
展覧会を見て、図録を読んで初めて鑑賞体験が一応の完結をみるという感じです。
『佐藤雅彦展』に行ったあと図録もひと通り読みましたが、文化庁メディア芸術祭と同様の印象、もしくはそれ以上の感覚を覚えました。
図録こそが本体で、展覧会は図録のためのプロモーションの一環と捉えた方が適当かもしれないと思えるほどです。
展覧会を見て「学びを深めたい」という意欲が少しでも掻き立てられたなら、公式図録は必ず入手すべきだと思います。
この図録は、いわゆる「展覧会の図録」とは趣を異にするものです。
事前に何の情報も持たない人に概要を伝えるなら、「展覧会の図録」ではなく「佐藤雅彦の自伝」と言った方が適当でしょう。
しかし、『佐藤雅彦展』を見て図録を最後までしっかり読めば、これがまさに完璧な意味で今回の展覧会の図録なのだと納得できます。
展覧会を見ているときは、彼が提示する方法論の汎用性や再現性の高さにワクワクし、「すぐ何かに活かせるのではないか?」と感じた人も多いのではないでしょうか。
僕もそんな感覚で展覧会を見ていましたが、図録を読んで印象がガラリと変わりました。
確かに、佐藤雅彦が提示する方法論は、万人に通用する驚異的な汎用性や再現性をもっていると思います。
しかし、図録を読みながら冷静に考えると、こんな命題が浮かんできました。
「〈再現性があるような方法〉を生み出す方法自体にそもそも再現性はあるのか?」
感覚的ではありますが、これは「相当怪しい」と言わざるを得ません。
図録を読みつつ、知るほど佐藤雅彦の天才性が際立ってきているようにも思いました(奇しくも図録巻末掲載の美術館主席学芸員による論考でも同様の記述があります)。
図録を読むと理屈はクリアになりますが、同時に、再現できないことも身にしみてわかってきます。
凄腕のマジシャンのネタばらしを見せられた気分です。
一方で、サークルに還元できそうなものもたくさん得られました。
特に、漫画やアニメをはじめとするコンテンツの生まれ方、ヒットの仕方について、論理的に語れる部分が格段に増えた気がします。
「ジブリ作品とジブリの影響を受けた他作品の間の越えられない壁」、「ジブリっぽいと分かるけれど全然響かない生成AI画像の謎」、「異世界転生など昨今のトレンドの裏に潜むメカニズム」、「要素の量と物語性の発現の(非)相関」、「二次創作を励起するメカニズム」などは、かなり系統立てて語れそうです。
ただし、ここでその詳細には触れないことにします。
気が向いたらそのうち別記事として書くかもしれませんが。
* * *
今回の展覧会は、創作とはやや繋がりが薄く感じられる「リベンジ義務教育」との関連でも刺激となりました。
図録の第4章の章題は「本当にやりたかったのは教育だった」です。
佐藤雅彦の活動は、「教育」をやりたいと思いながら心折れたところがスタートで、電通に在籍しCM制作などで数々のヒットを飛ばす時代を経て、大学に招聘され研究に軸足をおく時代に至ります。
そして、大学における研究では、まさに「教育」がキーワードになっています。
広告でミッションを達成するために培った膨大なノウハウを携え、今度は斬新な教育コンテンツを生み出していくわけです。
とても同列に語れるようなものではありませんが、それでも「リベンジ義務教育」は教育コンテンツです。
ゆえに学べることだらけです。
この点については、以下のnoteの記事でこのブログの補足のような感じで少し書いていますので、興味があったらご覧ください。
* * *
横浜美術館は長期休館を経てリニューアルオープンしてこれが2つ目の展覧会です。
リニューアルを機に横浜美術館の在り方そのものを再定義しようという決意のようなものを感じていましたが、今回の『佐藤雅彦展』はまさにうってつけだったように思います。
いつも横浜美術館の前の広場でわいわい遊んでいる小さな子供たち。
この子たちを重厚な美術館の建物内に引き入れ、広場で遊ぶのとはまた違った楽しい体験を提供した功績はとても大きいと思います。
距離にして10メートル程度ですが、とても意義深い10メートルです。
横浜美術館が目指すところと、佐藤雅彦が目指すところがうまく嚙み合った結果が、展覧会でわいわいはしゃぐ子供たちの声なのでしょう。
こういう種蒔きを、今後も継続してほしいと思います。
sho