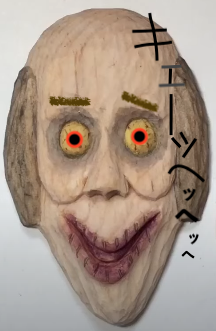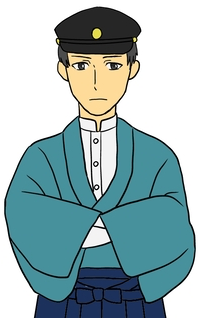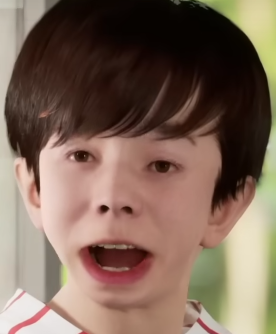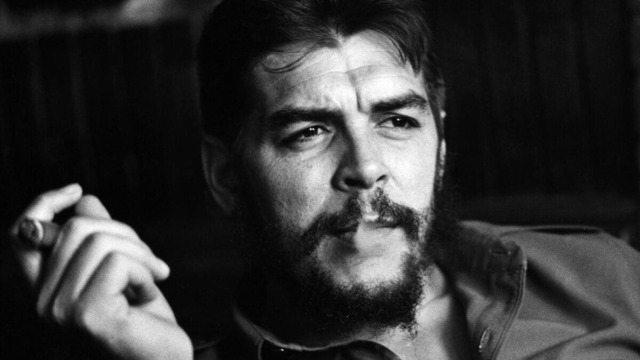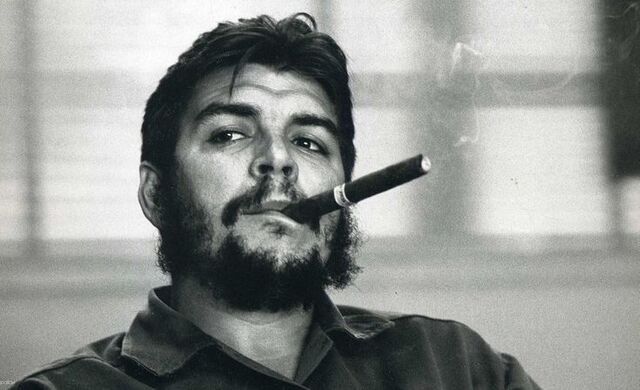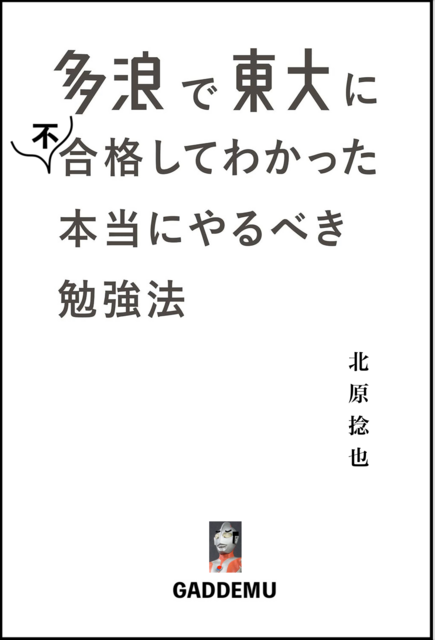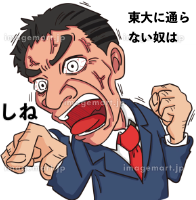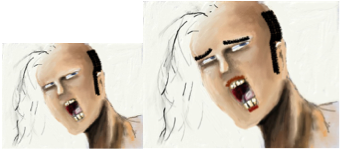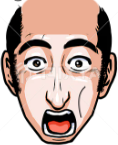新発売
(ガッデム汚腹著 第3弾)
第3回進路指導
希望は、
「どこだったっけ?」
と、すっとぼけた顔で聞いてきた。このあいだ伝えたはずのことを。ガッデムはまたしも職員室に呼び出した。
「国立を」
「国立大学です」
答えると、ふうむという顔をして下を向くと
「学部は?」
と聞いてきた。一応、聞いておこうといった態度だった。理学部か、工学部か、農学部か、といった調子で。それと共に、あれほど言ったのにまだ言い張るのか、といった呆れた様子が見て取れる。
この時点では、佐賀大農学部→広島大学生物生産学部→広島大学理学部生物学科と変遷を辿ってきたのだが、いちいちそんな説明はしない。今のところのことだ。だがこいつにとっては今のところだろうが最終的であろうが、僕の選択などどうでもよかった。
「理学部です」
この日はそれで終わった。
こいつに僕が生物学科を志望しているのを伝えたのは、ここから1年以上も先のことだった。それまでは聞こうともしなかったし、僕も言いたくなかった。難癖をつけさせる材料を与えるだけだからだ。ガッデム先生は自説を押し付けることに熱心なあまり、ありとあらゆる否定や植え付けを行ない、僕が生物系を志望しているのを知ったのは3年も6月になってからで、それまでは、国立受験を断念させることに専念していた。
学科まで聞いてきたのは、僕が志望を遂げるべく協力するためでなく、お買い得お勧めの私大をゴリおすために過ぎなかった。この人にとって生徒の意図や意思などどうでもよく、ただただ自分の命令に従わせることだけが命題だった。
付け加えておくが、2年生の5月の時点での僕は広大理学部どころか佐賀大農学部でさえ高嶺の花で、国立大学の門は高く聳えていた。
こいつが学部を聞いてきたのは、次の質問をするためだったと推測する。つまり国立を断念させるための作戦を練るための調査をしたまでだ。
第4回進路指導
学部を尋ねられてから数日経った昼休みのことだ。僕が商業科棟の講師室に英語の質問をしに職員室を通っていると、それを認めたガッデムが席から呼び寄せた。方向を変えて近づくと聞いてきた。
「逆に聞くが、なぜ国立の理学部でなければならないんだ?」
またいきなりの質問だ。この男は、いったい何をはしゃいでいるのか? と思った。
そんなことが客観的に証明できるものなのか? 僕は首をかしげた。ーー僕がそう思うから。それ以外に答えがあるだろうか。これが、受験数学の弊害というやつだ。他人を追い込むために背理法を使う。実際の人間関係で行使すれば屁理屈にしかならない論法。
理学部と聴くと僕は胸が躍る。工学部や農学部ではこんな高鳴りはない。しかも、生物学科と聴けばもう天にも舞い上がる面持ちだった。ーーあくまでなんとなく、だったが。化学とか物理とか、特に化学は嫌だった。ガッデムに対する距離感と近い距離感があった。人格障害や社会不適応者の香りがする。物理は電気より力学や地球物理学ならやってもいいかと思った。生物学科でないなら地学科だろうと思っていた。愛のない数学は数学ではない。屁理屈だ。屁理屈に数字を当てはめているだけのゴミ屑に過ぎない。ガッデム汚腹。こいつには3次元の平面思考すらなく、ひたすら左に伸ばしていくだけの直線思考しかない。2次元思考だ。しかも逆戻り。そんなものは詭弁にすぎない。
理学部の代わりに工学部でも農学部でも同じことだったろう。その答えを論破して、自分の勧めるお買い得大学とやらをゴリ押そうという魂胆だったののにちがいない。ところが僕の答えに、こいつは論破する気も失せた模様だった。いや、それが最初からの作戦だったのかもしれない。すなわち、なんと答えたところで同じ態度を取るつもりだった。
立ったまま僕はこう返した。
「学者になりたいからです」
なぜそう答えたか。もちろん、本心ではある。何をするにせよ、真理の探究をしていくことに変わりないからだ。
科学者になるのに、国立大学の理学部でなくてはならない必然性はないではないか、と反論してくるのかと思いきや、聞いたガッデムは真顔になり、ふと侮蔑の息をもらした。
「やめとけ。趣味にしておけ」
静かに彼はそう言った。そして、
「話にならん」
といった素振りでそっぽを向き、くるりと椅子を回して前に向き直ると、やってきたデスクワークの続きに取り掛かった。
「どうせ、勉強するのだから、いまから熱心に勉強するんです」
僕はそんな答えを用意していたのに、肩透かしを食らったような気がした。
こいつに本心を打ち明けると、もれなく否定と押し付けが返ってくる。この脊髄反射がルーズな大人のみすぼらしい姿なのだ。
とんだ道草だった。
グラマーの講師のところに足先を戻しながら、
燕雀焉んぞ鴻鵠の意を知らんや
すぐに僕はその言葉を思い出した。
そんな折り、おそらくクラスメイト全員に同じようなアプローチをしているのだろう。長渕が、
「ガッデムあいつ俗物」
と言った。
学者といえば、俗物のガッデムは即座に大学教授と決めつけたことだろう。
僕は大学程度の学問を超えた学門、真理の探究をしようと勉強をやっているのだ。探求した成果を分かち合うために、小説など何らかの著述はおこないたいと思っている。その在り方に、大学は通過経路だと位置付けていた。
ところが学者といえば大学教授が学者だと短絡しているこいつ。学者はむしろ大学には少なく、それ以外のところに多くいるものだ。
学者=悟り
この方程式が成り立つ。大学は、そうなっていくための体験すべき通路でしかない。この時にはすでに僕はそう思っていた。だが、そんなことはこの男にとって戯言、興味関心が皆無のことだったのだろう。
俗物のガッデムに僕の志はわかるべくもないし、解らなくて構わない。いや、俗物にわかるような志では低すぎるのだ。
ちょうどそんな頃だったか、関係副詞を使うこの言葉にでくわし、決意を固めたのだった。
Where there is a will,there is a way.
意志あるところに道はある
輝いて見えた。
willが助動詞でなく名詞として使われ意思でなく意志と訳す。人間の意思でなく神の意志。すなわち、神の道。Lord=road
詭弁の先には、道などあるはずもない。
科学者になりたい
しかしこれは言わば盾でもあった。かつてガッデムが目指し、中途で諦めたであろうことが彼の日常の話から手に取るように解っていたのだった。その後、僕は将来なにをやりたいか聞かれる度にある人には「学者です」と言い、ある人には「詩人です」と答え、ある人には「実業家です」と返し、またある人には「作家です」と話した。どれも質問者がなりたがっている、あるいはかつてなりたかったものであり、自分と同じ希望を持つ若者に対してどう答えるかで、その人の本音が聞ける。
人は若かりし頃、自分が志しながらも半ばで脇道に逸れ、まがいものでごまかし『立派な社会人』に身をやつしている自分をよく知っている。それをやり遂げられなかった後悔が、「やめとけ。趣味にしておけ」といった若者をバカにしきった言葉として現れてくるのだ。詭弁の先は行き止まりだ。詐術を弄する稚拙な詭弁家、ガッデム汚腹。
自分の道を進みたいという望みがあったが、こうして本命はしまっておいてブラフの方を出した。有言実行というが、やり始めてから宣言した方がいいのかもしれない。やる前に「やりたい」と言っても十中八、九否定が来る。自分の中に迷いがあるからでもあるだろう。だが、「やっている」に「やめとけ」は遅すぎる。やり始め、やり続けるしか道はない。また、I try to do.ではダメだ。I do it everymoment.でなければならない。
なぜ、若者の志をロートルが否定しにかかるか。たいていは、その人が若い頃、志したことと一致していたのだろう、過敏に反応する。彼は自分の若気の至りをさんざんけなして、僕のしたいことを潰しにかかった。けれど、僕の生命にはなんの損傷もなかった。彼が自分を責めさいなんでいる様子に悲しくなっただけだった。
後年、予定通り三十二になった僕が実際に自分で自分に命令を下してやり始めた時、一切の妥協も許さなかったし、またからみつき足をひっぱろうとする者があれば、なぎ倒し振り払った。
ガッデムは、勉強することにではなく、自分の思い通りに従わせるという、本筋とは異なるところで葛藤を作り出し、エネルギーを浪費させようとする。むりやりそれに乗らなければならないようにしているのに、まるでこちらが自分を知らぬ愚か者だから悪いかのような涼しげな小馬鹿にした表情をしている。彼がどう言ったところで、僕の命をかけた選択を変節するのは余計なお節介以上ではない。
そんなの僕の自由じゃないですか。
と僕が思ったと思ったのだろう。きっと、他の生徒の中には、押し付けに対してそんな反応をした者もいたにちがいない。次に会った時、ガッデムはつまらない質問をしてきた。おそらく、家に帰って夜通し考え、こう言って切り崩し、こう言って言い込めてやろうと算段したにちがいない
結論から言えば、ガッデム先生は、せっかく根づき成長して行こうとしている苗木の畑をしょっちゅう踏みにじって回ったので、本来収穫できた成果の一つとして得ることができなかった。眼が観えないというのは恐ろしいことだ。いや、恐れているから眼が塞がるのだろう。
この人は即座に職業と思ったのらしい。が、学者とは在り方であって、職業とイコールではない。
家に帰り、今日の進路指導とやらを思い返しながら考えた。
ーーあいつの娘なら、出資者である父親の言うことを聞き従わざるを得ないのだろうし、また、会社の部下なら査定に響くから渋々イエスと言うかもしれないが、僕らはこの男から金を出して頂くわけでもないし、給料の額に影響もない。プロ教師だかなんだか知らないが、担任というだけで僕らがそれにひれ従う謂れはないのではないか?。
むしろ、あいつが僕らの意向を実現させてナンボなのではないか。あいつの給料の大部分は僕らの授業料であるし、僕らが心から満足する進路に着き感謝されて初めて、こいつが給料分の価値ある仕事をしたというわけだ。前払いをしてもらっているのだから、もししくじれば、再起は難しくなるだろう。この学校に勤めている限り。
ーーどうやって切り崩していこうか?
とでも思案しているのにちがいない。彼には彼なりの攻略順序があるようで、ともかく、僕が「国立はやめました」と降参し承服してからでなければ、お勧めの大学は提示しないのだろう。このあと、躍起になって策を仕掛けてきた。
ところが僕は私立大学は眼中になかったし、まさか教育者ともあろう者が、大人のあざとさを満腔から噴出させているなど夢にも思わなかったので、彼がなぜそんなことをしているのか理解できなかった。
ただ、こいつが段階を追ってはいたが、僕に対してはそれなりに柔和に接していたのは、僕の頭脳がずば抜けてよかった、からではなく学研の偏差値が50の生徒にすぎなかったからだろう。僕より偏差値の高かった、例えば桐川などにーー味噌糞に言いやがったのは、彼の偏差値がクラスで上位、もしかすると1番だったかもしれないからだ。目標が高いからケチをつけただけでなく、ガッデムの持論を達成する最も近い生徒だったからでもあったろうと思う。
第5回進路指導
休み時間、ガッデムが息せききって階段を昇ってきたところ、ちょうどそこにいた僕の前に立ちはだかり、いきなりこんな質問をしてきた。
僕はこれは子供を舐めた大人が中学生にする質問だと思っていた。まさか17歳の高校2年生に向かって放たれるとは。ガッデム先生は教科書やら指し棒やらを携えたまま腕組みをして僕の返答を待った。
「ええっと・・・」
「どうなんだ、ええ?」
と詰め寄るガッデ。僕はちょっと考えて答えた。
「素晴らしい世の中になるんじゃないですか?」
それを聞いたガッデムが模範解答をばらした。
「馬鹿きゃ?」
「みんなが好きなことばしたら、世の中が大変なことになっとぢぇ」
呆れ口調で言った。
だとしても、それがお前の言うことに従わなくてはならない理由にはならないではないか。ガッデは、話しならん、と言った素振りで踵を返した。そして階段を降りて行った。僕は、なに幼稚なことを聞いてくるんだと思いながら、後頭部を見送った。
そんな折り、
「ねえ、なんかあいつ、勉強のできる中学生みたいじゃね?」
休み時間にうしろの方で固まって話していると、桐川が歩いてこっちに来ながら言った。僕は黙っていたが、腰野たちはうなづいて応対した。僕の中学時代の同級生で勉強のできる者は周囲より相対的に大人びた者ばかりだったが、言いたいことは解る。桐川がそう評した背景には、これまでもちょっと首をかしげるような問いかけや、ホームルーム中のおたけびやくだらない自慢話が重なってきたからだったし、桐川個人にもいろいろ幼稚なアプローチを仕掛けていたものと推測できる。その具体的なことはもしかすると私鉄帰宅組は聞いていたのかもしらないが、詳細を僕は知らなかった。とにかく、ガッデム先生はあっちゃこっちゃで愚かなアタックを繰り広げていた模様だ。まさに、中坊が高校生の中に紛れ込んでいるの図だった。ガキが必死で盾ついている。それもハゲオヤジの仮面をかぶり格好だけは大人の男に扮装した。
こうして振り返れば、この男の失敗はもう、この5月の時点でほぼ確定していたと言っても過言ではない。それでもゴリ押し続けた2年間700日の地獄。
僕はこいつの話を聞くたびに、あれを思い出す。プロクルステスの寝台Procrustean bed〉英語の勉強していると出てきて、実感をもって解った。自分の理論が正しくなるよう、無理やりに生徒の方を理屈に当てはめ、嵌め込もうとする。狭いベットに合わせて足と頭を切り取るようなことだ。

さっきのやり取りをもう一度振り返ってみよう。
「馬鹿きゃ?」
「みんなが好きなことばしたら、世の中がたいへんなことになっとぢぇ」
「あ、そう」
「ええっと、ガッデムくんだったかな? いいことを教えてもらったよ、感謝する」
「君のママにも何か贈っておこう」
とでも返しておきたいところだ。
しょうもないことに合わせさせようとしたり自己犠牲を強いたり、横暴な未熟者が。こいつ、高校生にこんなことを言って納得するとでも思っているのか。桐川の言う通り『ちょっと勉強のできる中坊』が高校生の中に紛れ込んでいるふうだ。
僕はガッデがーーぢぇとほざいても、答えた以外答えず黙って立っていた。すると、通用しないか、といった素振りで踵を返したガッデのその背中には、他の方法を考えなければ、というのがにじみ出ていた。
仮にそうだったとして、どうしてお前の考え通りにする義務が僕にあるか? 権限もないし、命令系統もないし、徳もない。なのにどうして受け入れなければならないか。アホの言うことを聞き入れるやつはアホ。アホの言う通りにやればアホな結果を経験するだけのこと。
たしかに、人間のエゴや獣性を剥き出しにして、やりたいようにやるとか好きなことをやるとか迷惑かけていないからいいとか、全員がやり始めれば争いが絶えないだろう。
だが、こいつの考えはどう譲歩しても、賢明だとも達観だとも斬新だとも、とても思えない。
むしろ権力をもったつもりになったエゴと我欲が噴出しているのみのだ。
こいつにできるのは、親身さや誠実さが受け入れられた後のサポートだけではないか。そうでないことを受け入れる謂れは僕にはない。
つまらぬ社会的通念を信じている奴が手前勝手な理屈をこねくり回しているだけなのに、こいつは、自分は頭がいい、理性的な上等な人間だくらいに思っているのだろう。
「時に、ちょっとだけ、異見してもいいかな、ええっと、ーーガッデムくん」
「きみは、革命の対象だ」
「え?」
「僕の目指す共産革命はみんなが好きなことを好きなだけやれるようにすること。それなんだ」
「え?」
「いやなあに、気にすることはないさ」
「まあ、ちとばかり痛いがね」
「・・・・・・!」

主体性や自律性をなくせば、世間に流されるつまらない大人になるだけだ。それにしても結局、人は自分の好きなことにおさまっていくものではある。このガッデム先生にしてもそうだ。ただ、自覚があるかないか。他人のせいでここに押しやられて糞づまっていると感じている者が多いのだろうが。自分のやりたいことをやりたいようにやれるようなって行くために、僕らは勉強するのだし、その要諦を掴まない限り、いつまでも奴隷から抜け出せない。
起こすべくは集団での共産革命でなく個々人の自己革命だ。
こいつは、自分が好きなことをやっていることに気づかず、義務で犠牲になっているくらいに思い上がっている。かわいい娘のために嘘をつきハッタリをかまし、生徒を煙に巻いてまでせっせと働いているではないか。
ガッデム先生の生い立ち
ガッデムは、背筋を伸ばし、まるでクラウチングスタートでもきるように両手を教壇の机のこちらがわの両隅に広げて置き、自信満々に言った。
「成績に見合わない大学を志望して多浪するのは、愚の骨頂ですよ」
この愚の骨頂という言葉は彼のよく使う言葉だ。それから続けて、
「なにが、国立大か、ふざけんな!」
と言った。このふざけるなという言葉も多用する。
誰に言っているのか知れなかった。今にして思えば、僕を始めとする、社会科教師の問いかけに挙手していた者たち全員に向けていたのだろう。いつまでも変節しない僕を始めとするクラスメイトの大半に向け、例のオルグがまた始まった。
「予備校に行けば、年間百万くらいかかります。しゃにむに国立に行こうなどとして、2年も3年も通うくらいなら、さっさとどこか私立大学に行って就職すれば、余計な出費をおさえられます」
余計な出費をおさえてやっている。そんな自負があるのだろう。彼が学費の高い私立大学を押しつける背景には。
「一見高額に見える私大の授業料は、多浪するくらいなら、かえって、安上がりなんです」
彼の計算はすべて金だ。無視できない問題だが、それが先に立つのは悲しい。安上がりな人生を歩むために生まれてきたわけでもないだろう。あとから小出しにしてくるが、彼が勧めているお買い得な私大が現役でスパスパ通るようなところではないのだ。時代錯誤も甚だしい。
どういうわけだか、僕は自分の人生がどんなふうに進むのか、ほとんど確信に近いように知っていた。まるで根拠はない。けれども、知っていたのだ。明確な理由はない。だれが止めようが、金がなかろうが、自分は国立大学に行く。それ以外の選択肢を僕はなぜだか、持っていなかった。人によって、この確信めいた人生の青写真は異なっていることだろう。だから、ガッデムが秘訣として校長に売り込んだ彼のテクニックが、東京あたりでささやかれている受験の常識であり、正攻法であったとしても、僕にはまったく通用しない。そのことは、確実だ。
神をも凌駕するガッデム汚腹先生は、自分の言っていることに従わないのはおかしい、間違っていると思っている。自分の考えが絶対に正しいと思っているからだ。
だが、絶対に正しいなら、従う前に従っている。法則に例外はないし、差別もない。法則を自覚する前にそのようにやっているものだ。
国立大学が、確実で運の好い人材を欲しているのは解った。けれども、僕はそれを聞いて気が引けることはなかったし、躊躇、再考することもなかった。大体、この人はどこを想定して言っているのか? 国立と一言で言ってもピンからキリまであるではないか。それに、今の僕の現状から抜け出すには、すでに昨年、十分に観察・考慮した末に、国立大学に行くしかないと結論づけられていて、それを覆す納得のいく理由が提示されない限り、変更はあり得なかった。こいつの言っているのは、現実の厳しさでなく堕落の押し付けであって、僕の決意を変節させるには説得力が乏しかった。いや。皆無である。怠慢なジジイの姑息でセコい人生観を鼻をつまんで呑み込むわけにはいかない。
などと考えていると、
「おれを信じろ!」
ガッデムが雄叫びをあげた。この言葉はこのあと、何度も繰り返された。
誰かをあるいは神ですら外側にあるものをを信じるのは、己の責任を放棄することだ。自分自身を信じる時、責任を認めているのだ。自分以外の誰かを信じさせようとする行為は、責任を奪う行為だ。
「俺の言うことを聞け! 俺を信じろ!」
「お前らは、俺の犬だ」
ついに本性を現した。
ガッデムがこう叫んだ時、うしろの方で、わぉーんという鳴き声がした。すかさず松居が反応したのだった。
それにしてもこの人がこんなことを主張する要因はいくつか考えられる。①生育過程 ②受験失敗 ③お買い得大学合格者の出た場合のボーナス
まずは、なぜこいつが自分の行った高校について一言も触れないか。そのあたりからみていこう。
(姉妹編も同時出版)
彼がもし僕らと同じ非進学校というか底辺校の出身だったとしよう。それが農学部とはいえ国立1期の東京教育大に受かれば、ばんばいざい。逆転合格を自信にして、僕らにもそれが可能だと励まし、勧めるにちがいない。だが、それをしない。決して明かさない。とすると、逆に進学校だったのかもしれない。東京教育大では不服、それも農学部なら恥ずかしい。同じ東教大でも理学部科学科か生物学科あたりならまだ示しがつく。東大に行かなければ落ちこぼれと見なされる高校だった可能性が高い、もしかするとガッデムは、関東の中高一貫、たとえば麻布や武蔵や学芸大附なんかの名門校に受かったのかもしれない。
ーーまさかと思うが、東京教育大学附属高校に行っていた? それも駒場にある。
つまり、現在のツッコマ。筑波大学附属駒場高校。その学校がどこにあるかといえば、東大の駒場キャンパスのまん前なのである。
とすれば、すぐ目の前に東大の駒場があり、毎日時計台を見ていたことになる。地獄だね。
そこに入ったのも、できるだけ東大の近くにという父親の計らいだった。ここは国立の高校なので、都立のような『学校群制度』の煽りを受けることもなく、昭和22年の設立後、まだまだ教育大附属高校には及ばないものの、1960年代には東大進学者数を順調に伸ばしていった。しかも、元は東京農業教育専門学校の附属なのだ。
ガッデはしかし僕らに自分がどこの出身かも一切、口にしなかった。ただ、ーーキャない、とかーーカない、という特徴的な言い回しと、ふざけるなを多用し、また東北・関西・九州の方言のなさからして、顔は九州人の醤油顔そのものであったが、関東あたりに長くいた者ではないかと思われる。それがどうして大牟田、三池あたりにいるのか?
① 退職して戻ってきた
② 勤めていた会社の研究所なり工場がそのあたりにあり、家を建てた後に退職して居残った。
そういう事情は、蒲池と鮎川はよく知っていたのかもしれないが、聞いたことはない。だが、ガッデム先生の足跡がどんなものであっても関係ない。将来のビジョンの明確な者たちにとっては、それを邪魔するくらいなら、手も口も出してこないで欲しい。それだけだ。
ともかく、彼は方言が出ないほど幼少期以前から東京に住んでいたと推測する。
当時、1期校2期校と分かれていた時代にガッデム先生は東京教育大の農学部を受験し、めでたく合格された。東大と東教大は同じ1期校であり併願はできなかった。3浪目の先生は東教大を受けた。それまでどこを目指していたのか?
あれだけ東大と多浪を悪様に言う理由は?
推して知るべしだ。
受験熱が過熱していた時代だったので僕らの頭をクールダウンさせる目的で言ったとは思えない。あつものに懲りて膾を吹いていただけなのではないかと推測される。すなわち、ガッデム先生ご自身が東大を目指され、現役・1浪・2浪と3度チャレンジなさったが叶わなかった。仕方なく、次の年には東教大に鞍替え。しかしそれは、東大駒場キャンパスにある学校だったのだ。それが『東京農業教育伝習所』であった。名前は『東京教育大農学部』と変わっていたが、内実は相変わらず伝習所そのままだった。
『お買い得な東大』は駒場キャンパスに彼は4年間通い続けたのだ。(大部分の東大生が2年しか在籍しないところを)
駒場に通う若き日の北原捻也
敗北感に打ちひしがれながらも自己を正当化するために編み出したのが「今の偏差値で行けるお買い得な大学でいい」だったのではないか。どうして彼が東大にこだわったのか? 父親に強制された。同級生に優越しようとした。彼のレベルにまつわる動機はいくつかあるだろう。
第一、筑波大と東教大はちがうのだ。ガッデムは、学園闘争を尻目に、バリケートを蹴って中に入っていた、と話していた。まるで、東教大の運動学生を敵のように言ったのが引っかかっていた。彼は茨城県つくば山には移動していない。そのご、筑波大学となり第2学群に組み入れられたことで労せずして学歴ロンダリングがなされた形となった。
ともかく彼の入った時は紛れもなくまだ東京教育大学の農学部だったのだ。そこは、農業指導者を養成する元東京農業教育専門学校で、帝大付設だった校舎は東大駒場の敷地にあった。4年間、東大の敷地に通いながらも、東大生とは別枠。
彼の通っていた頃の東教大の農学部が東大の駒場キャンパス内にあったとすれば、彼の言った学生運動とは70年代半ば以降の『移転反対運動』ではなく、1967から69年にかけての東大紛争であったことになる。すなわち他の大学の学生がやっていることだ。それで「知るか!」と言ってバリ封を蹴り倒して中に入っていた。そう考えると辻褄が合う。年齢的にも一致する。2浪、都合3回東大を受験して落ちたので、3浪目には同じ一期校だった東教大を受け、晴れて合格。東大には入れなかったが『東大構内』の大学には入学しえたことになった。
たとえそこだったとしても東大と似たようなことはやれるし、就職の時にもよほどのことがない限り、東大卒と別扱いになることもなかっただろう。けれども、ガッデム本人の中ではぬぐいきれない何か、人生コンプレックスがつきまとっているのかもしれなかった。3回も落ち続け、別の大学なのに4年間も東京大学構内に通い続けた屈辱は計り知れない。
しかし、仮に東大の理科2類に入っていたとして、それが彼の何を解決しえたのだろう?
東教大だった彼は東大全共闘を敵のように言っていたのだった。農学部は東京教育大の前身の東京高等師範学校でなく、農業伝授所だった。それが東教大に組み入れられ、果ては筑波大学の第2学群となって、難関校づらをするようになったのだ。農林学部は、第2学群の中でも際立って偏差値が低く、穴場中の穴場だった。まさに、ガッデムの主張する通り、学歴ロンダリングの最たるところだ。あとの時代の人たちにしてみると、大学そのものの名声や格がそのまま浸透したように見える。いわば、お得な、お買い得な学部であったということだ。
1969年(昭和44年)度は、関東大震災があろうが東京大空襲を受けようが原爆が落ちようが行われた大学入試が中止になった空前絶後の年である。その年は東大と共に東京教育大も入試がなかった。なぜなら、ガッデムの通う東教大農学部はまだ東大駒場キャンパス内にあったからだ。実験があるのでバリ封を蹴り飛ばして入ったという話からして、1969年にガッデは3年か4年。すると入学は1965年か66年ということになる。受験期間は現役時が1961年か62年。
ともかく、彼が自分の学歴を実際よりもフヤかしてアピールするところからして、ツッコマだったかどうかは知らないが、東大進学校だった可能性が高い。
彼の背後に教育熱心な父親が想像される。
ーー今の偏差値でいけるお買い得な私立大学でいいんだよーー
いかにも、こんな家庭環境で育まれた考えとすれば、筋が通るのではないだろうか。
必死で膾を吹き始める。
曽野綾子が昭和48年に書いた『太郎物語ー高校編ー』には、こういう一節がある。
ーー皆が行きたがり、しかもむずかしいから東京大学を受ける。それも一つの若気のあやまちだ。しかしそのような行為がおろかしいから、藤原おやじのようなものの考え方をする連中の鼻をあかすために、わざと別のところを受ける。それも一つの若気のあやまちだーー
ガッデム先生がしばし化学の実験やデータ処理から離れ、こうした三文小説のひとつでも手にとる余裕があれば、己の愚かさを省みる機会も得られたかもしれない。
『北の海』昭和43年 井上靖
『赤頭巾ちゃん気をつけて』昭和44年 庄司薫
『青葉繁れる』昭和48年 井上ひさし
『春の道標』昭和56年 黒井千次
これらの作品にも学校、学歴に関するスノビズムを超えた観方が提示されている。ガッデム先生は先生になる前に、自分の考えや行動が積極的な意思かそれとも反抗かの区別くらいはつけておいた方がよかった。
したがってこの人のこの『羹に懲りて膾を吹く』は自分の体験に依拠しているものと思われる。
3浪という膨大なサンク・コストをかけた割には、たいした結論に達していないお粗末なやつだ。開き直りに欠ける。中途半端。結局はエゴイズムの結論に至った。諦観に達していない。ただの馬鹿ナマス。
こうしてガッデム先生の劣等感は醸造された。親の強烈な考えを反対にしただけで良くなったと思いあがっている。それが最高の考えだとして他人の押し付ける。
ついでに、父親にはこんなことも言われ続けていたのかもしれない。
「東大に通らんやったおまえのような出来損ないは」
こんな、他人に恨みを返すような奴を観ると、伝習所というところは、教授どころか帝大生の助手扱いだったのではなかろうか。旧制の頃の帝大生は高等学校を経ているので20歳以上で、附設伝習所は16歳以上だったのだろうが、その伝統は帝大が本郷に移転した後も、新制になってからも引き継がれ、あーしろこーしろとアゴで指示され、昼夜問わずデータを取らされるが、成果は全部上に持っていかれる。それを見て、大人のやり方はこうだとでも習得したのに違いない。愚かなことだ。それを会社でも教室でもやれば、それはそれなりの齟齬と弊害が生じるのは目に見えている。浅ましい輩が浅ましいやり口を真似して回す。
この男の最終学歴は東京農業教育伝習所だ。
伝習所。
便所の所と同じであって、大学でもなければ、学問追求の『学部』でもないのだ。のちに専門学校と名を変えたが、貫かれている精神は同じ。待合所。停留所。喫煙所。ゴミ収集所。「ところ」とは読まない「ジョ」。のちに、オウム真理の麻原に心酔しサリン製造を喜んでやった男を生み出すことになる。
うまいことネームロンダリングが生じたのだろうが、この人は入った時には、元農業教育伝習所の資産がそのまま継承されていたのである。教師、器具、思想、雰囲気、そして級友たちはみな、そのつもりで入ってきた、そのつもりの人たちであった。そういう雰囲気の中で人格を形成したのだ。良くも悪くも。それが後から人気が出ようが、偏差値が上がろうが、この人が20代の自分に与えた環境育成プログラムが変わることはない。この人は入ったその時の難易度であり、雰囲気であり、教育方針であり、学生の自意識である。
ガッデム先生が自分自身をどのように見なしているか、それは『今の偏差値で入れるお得なところ』をベースにした程度なのだろう。
この男は仏頂づらでいかにも理屈っぽく話すが、その実、感情論ばかりだ。
感情は女子供のもの。大の男はリクツでビシビシ切るものだ、と思っている。感情に高低のあることを知らない。メソメソだけが感情だと思っている。これはこいつお得意のデータ解析でも理屈でもなく、ただの迷信。データを直視し洞察するなら、そんな認識は導かれない。
安い、さげすんだ感情から物事を発想し、導き出し、数字や理屈で武装する。つまらぬ持説を押し付け、押し付ける。これは頭の悪い証拠。こいつとは話し合いが不可能だ。なにを言ったところで、答えは決まっている。持説が正しい。だから従えだ。知能指数が低く、魂の幼い者の特徴を現している。論理的に見せかけているだけで、押し付けたいだけ。
向上心を否定し、たいした学歴でもないのに学歴にすがるさもしい奴。それがガッデム汚腹。
万一、この男が逆にまかり間違って東大に受かっていたとしたら、どんな人生観になったのか? おそらくきっとこうだ。
「世の中、なんのかんの言っても学歴ですよ」
「東大に行かないやつは人間じゃなーい。全員、東大を目指すのが動物の義務だー、わかったなー」
ここで字数制限が来てしまいました。続きはseesaaブログで。