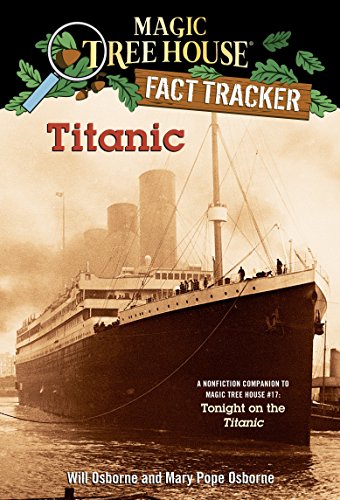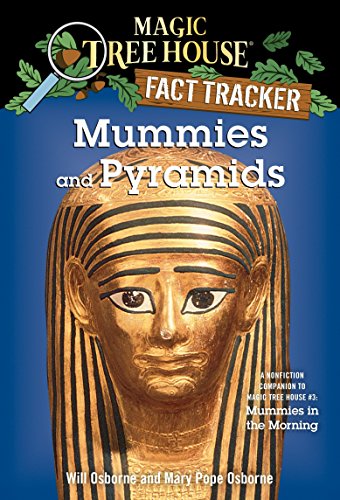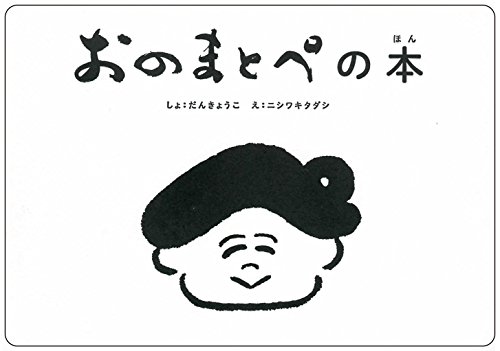小学校では あと数年で
英語が教科化されるなど、
英語教育がますます低年齢化する中、
ここ数年、
早期英語教育の弊害
が より声高に
叫ばれるようになったと感じます。
そういった内容の記事や報道も
目にするようになりました。
早期英語教育をすると....
![]() 思考力が育たない
思考力が育たない
![]() 日本語も英語も中途半端になる
日本語も英語も中途半端になる
中にはそんな主張もありますが、
こういった記事や報道は
極端に一般化している例が多いと
感じてしまいます。
「早期英語教育」という言葉も
定義が曖昧になってきて、
単に、「中学より前に英語教育を取り入れること」だけを指さない場合が多いと感じます。
もし仮に、
日本に住みながら、
日本語にほとんど触れさせず、
英語だけに触れさせていたら、
上で挙げたような弊害が
起こり得るのは想像はつきます。
インターナショナルスクールに
通わせている家庭や、
子どもが帰国子女で
幼少を海外で過ごした家庭や、
家庭内の言語を英語に
している家庭は、
日本語を維持する取組みは
必要になると思うし、
色々と工夫をしている家庭も
多いと思います。
でも そうでない場合は、
多くの場合が
日本語に囲まれる生活をしています。
そんな中で、
早期英語教育 = 思考力が育たない
という図式は
論点がずれてしまっていると
感じています。
英語教育をするから思考力が育たない
のではなくて、
思考力を育てるような教育
(あるいは育児)をするから
思考力は育つもの
ではないでしょうか?
英語教育(育児)をしていても
していなくても、
日頃から 子どもと どう接しているか
どんな会話をしているか
その積み重ねが思考力を育てると
思っています。
日本語も英語も中途半端になる
という主張も、もちろん
行き過ぎた英語教育や
質の悪い教育をすれば
そのようなリスクも伴うと思います。
でも、質の高い教育内容だったり、
バランスの取れた英語育児であれば、
日本語の成長に悪影響を
与えるとは考えにくいし、
むしろ 思考力の成長を
助けるのではないかと考えています。
上の![]() のように
のように
「両言語ともに中途半端」と言ってしまうと
とてもネガティヴに聞こえますが、
そもそも日本語の環境で
生まれ育った人が
「日本語と同じレベル」の
英語力を身に付けること自体、
とても大変なこと。
早期に英語を取り入れるのは、
日本語も英語も
完全にバランスの取れたバイリンガルを
目指すためではないと思っています。
英語は、日本語と同じ言語。
コミュニケーションのツールです。
早期に英語を始めるメリットは、
英語を「教科」として学習するのではなく、
コミュニケーションのツールとして
英語という言葉を
自然に身につけることができる点。
(関連記事『早期に英語を始めるメリットは?』)
英語力(日本語力)もつけつつ
思考力や人間力もつけていく。
早期英語教育をしながらでも
それは十分に可能だし、
英語を使えるようになることで
子どもの世界も広がると思っています。
【参考文献】