あいまいな言葉
京都の舞妓さんのお話を伺った時のこと。「舞妓さんのお給料ってどの程度ですか?」と初老男性の質問。すると「お小づかい程度どすなぁ」とのお答。この「どすなぁ」が、「ドゥふなぁ」と、はんなりした余韻を残し、雅びな風情を感じました。ずばり金額を答えるのは野暮。あいまいな言葉は、直球の相手を旨くかわす言葉であり、人間関係の潤滑油にもなるのでは…と余韻に反芻しました。
向田邦子さんの文章に、乗り合わせたタクシーの運転手さんに著名なシナリオライターと知られ、貯金の額を問われたくだりがあります。「たくさんありません。親の死んだ年齢くらいかしら」と向田さん。それを正しく把握できないのに正比例するほど、シナリオライターとは一律で計れない不思議な職業であり、あげく尋ねても無駄であることにゆきつきます。絶妙のかわし方です。
人との摩擦の多い向うみずな若者を、心配されたあるご高齢の方が、「かわし方を知らない」と諭されたことがありました。例えば、同様に運転手さんに問われたら、その若者ならまずムッとするのでしょう。それでもまだ問われたら、「どうしてそんなこと聞くんですか? 放っといてください」なんて云うのでしょう。でも、こんなセリフの繰り返されるシナリオは、面白くもありませんし、機微も描けません。
今、世をあげてあいまいさは否定され、明確に主張する人物の方が理知的であると好印象にとらえられがちです。しかしあいまいな言葉は人間味のある言葉です。関西に多いとも云われます。わたしたちにしか描けないあいまいな言葉と、そこに密かに息吹くやさしさやしたたかさ、たくましさを今一度、丁寧にふり返り、表現してみませんか?
リアリティのある女
好きになる必然性が練られていないラブストーリーを読んだ時、「きっとこの女の人は美人なんだろうなぁ」と思ってしまいます。でも、それでは説得力として弱いですね。
先日、シナリオとは無関係の女友達に、「リアリティのある女がいい」などと口走ると、彼女はあらためて、「リアリティのある女っていい言葉ねぇ」と云いました。そう云われると、私もあらためていい言葉だなぁと思いました。で、リアリティのある女って、どんな女なんでしょう?
心の中が綺麗なだけじゃない女。人を傷つけたこともあって、ストレスも一杯かかえていて、格好良く見られたい見栄っ張りで、人に嘘はついても自分に嘘はつけないエゴイストで、人に嫌われると気になるくせにシニカルにポーズするのが癖で、そんなこんなでストレスがたまると、発散にはショッピング、美味しいものも大好きで、ワインなんて目がなくて…どうやら誰かさんのことを並べたみたい。でも、よく考えると、リアリティのある女とは欲望のある女? 一理はありそう。
欲望を女が持つことは、どうやら日本では昔から良くないと考えられていたようです。動物の欲望に雄も雌もありません。人間の女だけが欲望を抱いてはヒロインらしくないなんて、変です。でも、むつかしいのは、欲望もあって魅力もある女。男でも女でも欲望が服も着ないで往来を歩いていたら、それこそ大変。魅力のない世界観です。
谷崎潤一郎の『陰影礼賛』に「西洋には『聖なる淫婦』『みだらな貞婦』というタイプがあるけれど、日本にはこれがありえない」とありますが、女が欲望を抱くことをふしだらと見る時代は終わりました。それでも古い考えはいまだ蔓延っています。可愛くてヒューマンな「生きている女」の欲望が観たいです!
西中島はグルメの変異地帯?
シナリオ・センター大阪校のある西中島(南方)から新大阪というエリアは新幹線の大阪への入口となるので、従来から出張族のための居酒屋や風俗店が多いところです。
センター御用達食堂?であるジャッキーと紅梅ちゃんの美味しい中国料理店「蓬莱閣」もそんな一角にある繁盛店なのですが、この春からこの近辺のグルメ状況にちょっとした異変が?!
既にご存知の方も多いと思いますが、超有名芸能人の名前を冠した店が相次いで2軒オープンしたのです。
両店とも未だ予約がなかなか取れないようですが、吉本芸人の店ならいざ知らず、東京系のタレントの店がなぜこの西中島に?
ゆうこりんであれば、出張族達がよもや本人に会えるかなと淡い期待をもって食べに行きそうですが、失礼ながら和田アキ子に会いたいと思う粋な出張族はこの辺りにはいなさそうです。
しかも、大阪に住んでいても西中島に降りたことがある人って、とっても少ないのですから!
飲食店って共存共栄が原則ですから、今後西中島にどんな店が増えていくのか、密かに楽しみにしています。
大阪しゃれ言葉
最近はテレビや新聞のニュースを見るのが嫌になるくらい、短絡的で残忍な事件が連日起きています。
いつからこんな世の中になってしまったのか、そしてそれらの原因は何なのかというようなことは識者に任せておいて、ただ言えることは言葉が暴力的になり、加害者・被害者共に想像力が欠如していることが多いということではないでしょうか?
また、些細な日常の其処此処に、加害者、被害者の双方になりかねない危険があるように思えます。
※「今そこにある危機」というハリソン・フォード主演の映画がかつてありましたね。
この映画で衣装デザインを担当したバーニー・ポラックとは前回ご紹介したシドニー・ポラックの実の妹さんなのですよ。
肩が触れただけで睨みつけて大声で怒鳴りつけるAと、それに負けじとくってかかる女性連れのB。
ちょっと詰めれば数人が座れる満員電車で、電車内で携帯や音楽に夢中で大股を開いて素知らぬ顔で座っているAと、それを腹立たしそうに注意するB。
注文した料理が遅いと大声で怒鳴るAと、マニュアル通りの対応しているのにこんな言い方をされるいわれは無いと切れかかるアルバイトのサービス係B。
AもBも想像力が欠如しているので、互いに発する言葉によってその後何が起きるか理解できないようです。
互いにもう少し婉曲的な表現ができれば、不愉快な思いをすることもないのにと思ってしまいます。
※もちろん何の理由も契機も無く、一方的に被害者にされてしまう不条理な事件が増えていることも事実ですが・・・。
そこで今回ご紹介したいのが、かつて大阪でよく使われていた「大阪しゃれ言葉」です。
そこには商業の中心地として永く栄えてきた大阪ならではの、相手を怒らせない、そして相手に一呼吸おかせて考えさせるための、なにわ商人ならではの知恵がたくさんあります。
例を挙げると、こんなもんがおまっせー。
あかごのしょんべん(赤子の小便) ⇒ ややこ(赤ん坊)しい(小便)
うさぎの逆立ち ⇒ 耳が痛い
うしのおいど ⇒ 物(もう)知り(尻)
竹屋の火事 ⇒ ポンポン言う
花火屋の火事 ⇒ ドンくさい(臭い
うどん屋の釜 ⇒ 言う(湯)ばっかり
夏の火鉢 ⇒ 人気がない(誰も手を出さない)
雪隠(トイレ)の火事 ⇒ やけくそ
やかんでゆでたタコ ⇒ 手も足も出ない
いかがですか?こんなこと言われたら、ちょっと面食らってしまうかもしれませんが、頭の回転が速いAはその意味がわかるや拍子抜けしてしまうでしょうし、鈍いBも何か変なこという奴やから関わらない方が良いと退散することでしょう。
みなはん、どないでっか?
シナリオ習作にも、ぜひこんな表現を応用してみてください。
- 大阪人の「うまいこと言う」技術 (PHP新書)/福井 栄一

- ¥800
- Amazon.co.jp
- 大阪ことば事典 (講談社学術文庫 (658))/牧村 史陽

- ¥2,048
- Amazon.co.jp
- 今そこにある危機/ハリソン・フォード
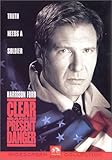
- ¥1,460
- Amazon.co.jp
涼しくなりたい!
夏と言えば恐怖映画、ホラー、怪談…。とにかくとにかく涼しくなりたい猛暑がこれからつづきますね。
子どものころに見た四谷怪談、今もそのときの恐怖を覚えています。田舎の映画館に満員のお客。立ち見で親戚のだれかにおんぶしてもらって見たお岩さん。せっかくおんぶしてもらっているのに、ずっと掌で目をふさいでいました。
ジャパニーズホラー映画の特徴はつぎのようなものだそうです。
●「怖い」と感じさせる部分では沈黙をあえて長くとり、登場人物が絶叫するシーンは少ない。この沈黙のために、急な効果音(扉の閉まる音、水滴の音など)を挿入することで観客を驚かすことができる。
●水を使ったシーンが多い(例:雨、水滴、床に残る濡れた足跡等)。これは、四方を海に囲まれ、湿潤な気候を過ごして水(湿気)が常に身近にある日本人独自の感覚による物かもしれない。
●日常生活に欠かせない、身近なものを利用する頻度が高い(例:電話、テレビ、ビデオ、鏡、トイレ、車、旧家など)。これにより、観客に「映画のような怖いことが、自分の身にも起るかも知れない(だが、使わざるを得ない)」と言う心境を与える。
●幽霊等、恐怖の対象であるクリーチャーのデザインは、海外のようなグロテスクなものではなく、女性や手だけのものが多い。特に「長い髪をたらした女性の幽霊」はJホラーの代名詞として親しまれている。
●残虐なシーンを避ける傾向にあり、電車に轢かれる・投身自殺する等のシーンであっても、直接的な描写はされないことが多い。
●舞台の規模が小さく(”町一つ””家一軒”等)、全国や全世界という規模にまで展開するような作品は少ない。
シナリオで涼を…。
- 新釈 四谷怪談 (前・後篇) (2枚組) [DVD]/田中絹代,上原謙,瀧沢修
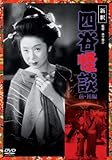
- ¥3,990
- Amazon.co.jp
- 東海道四谷怪談 [DVD]/天知茂,若杉嘉津子,江見俊太郎

- ¥3,990
- Amazon.co.jp
- 四谷怪談 [DVD]/長谷川一夫,中田康子,鶴見丈二
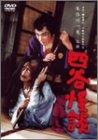
- ¥4,935
- Amazon.co.jp
- 四谷怪談 [DVD]/竹中直人,広末涼子,高嶋政伸

- ¥7,140
- Amazon.co.jp
めりはり
女性誌に「めりはりのあるお洒落をしましょう」との記事。「めりはりのあるお洒落」とは、ポイントを決めたお洒落であり、調和と変化を計算したお洒落のことのようです。全身の映る姿見を見て、全体像がうまく調和するようにポイントを要所要所で計算。至る処ゴテゴテはダメ。ポイントのないのもなんとなくヴィヴィッドでなくてダメ。そんなことのようです。
辞書より。
○めりはり(滅張・乙張)「ゆるむことと張ること。特に邦楽で音の抑揚をいう」
○抑揚「或いは抑え、或いは揚げることの相互関係。高低。音楽の調子、文勢などにいう」
さて、シナリオでめりはりは計算されているでしょうか?
よく長篇を読ませていただいていて、シーンシーンは魅力があるのに、「めりはり」がないために全体として損をされていると思うことがあります。同じ調子で続くシナリオです。その反論として、小津作品を「淡々と」ととらえ、「敢えて淡々と…を狙いました」との意見をゼミで耳にします。しかし小津作品では、表面化しなくとも内にある心情のめりはりがいかに計算し尽くされているかをよぉく観てください。安易に「淡々と」と云うのはどうなのかな…と思います。
決してテクニシャンにと云う意味でなく、謙虚に「めりはり」を意識してみましょう。テンポ、日常・非日常、感情の起伏、セリフの抑揚、キャラクターの対比、シーン展開、ロケ・セット…シナリオでのめりはりの表現方法はたくさんあります。
シナリオが全身映る姿見を、作者の視線の部屋に置いてみてはいかがでしょう?
シドニー・ポラック賛歌
5月26日(月)、都会風なセンスと洒脱な会話で男女の愛を美しく描き、また印象的なシーンで女優の魅力を見事に引き出してきたアメリカの映画監督兼俳優のシドニー・ポラック氏が亡くなられました。
監督作品としては、センター所長の後藤先生も大好きな映画の一つにあげておられるバーブラ・ストライサンドとロバート・レッドフォードの「追憶」、メリル・ストリープとロバート・レッドフォードの「愛と哀しみの果て」、プロデュース作品としてはミシェル・ファイファーとブリッジス兄弟の「恋のゆくえ/フォビュラス・ベイカー・ボーイズ」、そしてスーザン・サランドンとジェームス・スペイダーの「ぼくの美しい人だから」…。
「追憶」では、苦学生で学生時代に政治運動に積極的に関わり、やがて政治家となるケイティ(バーバラ・ストレイザンド)の解けた靴紐を、ノンポリのスポーツマンでキャンパスのヒーロー、そして後に映画脚本家となるハベル(ロバート・レッドフォード)が自分の膝に足を載せて結びなおすシーン、「愛と哀しみの果て」では奔放な主人に振り回されながらケニアで農場を経営するデンマーク人のカレン(メリル・ストリープ)が冒険家のデニス(ロバート・レッドフォード)と出会い、お互い惹かれあう中、ケニアの大地でデニスに髪を洗ってもらうシーン。いずれも映画の正確なストーリーを忘れてしまってもいつもでも心に深く残るものです。
映画でも音楽でも小説でも、そして料理でも、一部の人にしかわからないような難解な表現にしてしまうことは簡単です。
当事者しかわからないような専門語や共通語、テクニックを多用しさえすれば良いわけですから。
でも難しいことをあえてわかりやすく、そして心に染み入るように表現できることこそ、真のプロにしかできない芸当なのではないでしょうか。
そういう意味で、日本では作品以上にもっともっと評価されるべき監督だったと思います。
彼の作品を観たことがない方はぜひこの機会に!
追悼の意を込め、バーブラ・ストライサンドがシドニー・ポラックの訃報に接し、応えた言葉を記しておきます。
"He knew how to tell a love story - he was a great actor's director because he was a great actor." singer Barbra Streisand said.
追記:「トッツィー」のダスティン・ホフマンも彼に女性としての魅力を最大限に引き出してもらった一人なのでしょうね(笑)
- 追憶/バーブラ・ストライサンド
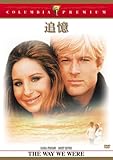
- ¥2,441
- Amazon.co.jp
- 愛と哀しみの果て/メリル・ストリープ
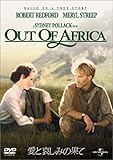
- ¥1,280
- Amazon.co.jp
- 恋のゆくえ
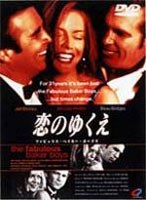
- ¥3,591
- ぼくの美しい人だから
- (ユニバーサル・セレクション2008年第3弾) 【初回生産限定】
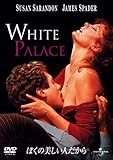
- ¥1,350
- Amazon.co.jp
- トッツィー/ダスティン・ホフマン

- ¥2,600
- Amazon.co.jp
惚れる
…辞書でひくと「心を奪われるまでに相手を慕う」とあります。
かつて大阪校の5枚シナリオコンクールで「惚れた瞬間」という課題を出しました。「今どきの若い人に惚れるという意味が分かるのだろうか?」とご年配の先生からの心配のお声も。確かに死語の範疇。
心を奪われるとはどんなこと?
平常心を失うこと。理性で判断できなくなること。とにかく理屈じゃないこと。寝ても覚めても無我夢中。
恋はもちろん仕事でもいい。勉強でもいい。心を奪われるほど夢中になれる人生でありたい。奪い奪われることに臆病な人はケチな人。お金にケチより心にケチは寂しい。惜しみなく奪い奪われる…創作者ならそうありたい。
そこで思うのは大人のルール。例えば恋にしぼって考えて、闇雲に奪い奪われてヘトヘトに疲れ、根こそぎ果てたのでは洒落にならず醜悪。危なっかしくて、「迷惑な人」。大人のルールを守り、なおかつ上手く惚れられるには、相手への思いやりが必要。しかし、そこに到達できるのには、いっぱい失敗を繰り返すことが必要なのでは? 失敗を恐れていては、いつまでたっても大人のルールが守れる人にはなれなくて、グラスに浪漫の滴る芳醇な赤ワインに似た、真の「惚れる」醍醐味も味わえないような。
これ、シナリオに置き換えます。失敗を恐れていては、いつまでたっても大人になれません。観客の心を奪えるシナリオが描けるようになるには、まず失敗を恐れず無我夢中になれるかどうかです。
シナリオに惚れましょう。
そしてお客さんを惚れさせましょう。
「愛している」というセリフ
21世紀、死語となる日本語はたくさんあるそうです。久世光彦氏の『ニホンゴキトク』(講談社)の目次を繰ると、「辛抱・じれったい・冥利に尽きる・できごころ・うすなさけ・邪慳・夢ん中」他が記されています。「惚れた」の感覚が少なくなり、「愛している」というセリフがドラマで頻繁に使われるようになったことと近いことのようです。
従来の日本語の「愛」という言葉は仏教的な意味から、執着する、貪るといった否定のニュアンスが強かったそうです。「色」を恋愛ととらえていた男尊女卑思想故かと思えます。
「愛」が、今日のような肯定的な意味に変化したのは、聖書の翻訳が契機であったそうです。文章としての「愛」に違和感はないものの、セリフとしての「愛」には、空々しさを感じます。崇高なこの言葉をおいそれと口に出すことにはストイックになり、有り得ないのではないかと思い、結果的には英語を日本語に訳し、そのまま抵抗なしに使っているデリカシーの無さを感じてしまうのです。
若い人は普段「愛している」と言うのでしょうか? 多分言う人は少ないと思うのですが、一度、伺ってみましょう。さりとて「惚れたゼ」なんてセリフを現実の生活で言う人も、いよいよ少ないでしょう。しかしドラマではキャラクターによってOKです。そこがフィクションのむつかしさです。さすれば「愛している」もOK。有り得ないセリフだからこそ、陶酔して聞いてみたい、あのスターに言わせたい、それもドラマの効役です。
ただ、もし無神経に一行の「愛している」というセリフを書くのなら、「どのように愛しているのか?」を丁寧にエピソードとして考えて頂きたいとは思うのですが…。
大阪風男と女の愛し方…
とはどんなことでしょう?
「夫婦善哉」に象徴されるような、しっかりモンの女と頼りない男のペア。近松作品にみられるような色香に惑う男と、社会的には薄幸であるが心の汚れていない女とのペア。そして21世紀、どんな男と女の物語が大阪から生まれるのでしょう?
恋愛感情のなかに人情が大きなシェアを占めるのが、大阪風男と女の愛し方の特徴ではないでしょうか。相手が落ち込んでいるときにこそ相手にしかと寄り添う…。親の人情を子が見て育っているからかもしれません。
江戸ッ子には、大阪風の人情が同情と取り違えられて、東西間の人間感情の誤差が生じることもあるようです。得てして気風がよくて粋を尊ぶ江戸ッ子は、同情されては自分らしくリアクションができないから拒むのでしょう か。東京大阪間に限らずこの誤差は、悲しい人間関係の結果を生んでしまいがちです。
「可哀想ったぁ惚れたってことよ」と云うコトバもあり、同情もさほど低い感情ではないと思うのですが、日ごろ触れるシナリオから推察して非常に乱暴に区分けすると、一番古いのは人情、受ける側があまり喜ばしくないのは同情、新しい都会的感覚は共感性へと、人への感情移入の糸口は移り変わっていると思えます。
人がこぞって新しいと思いそうな都会風に流されては、それはもうその時点で新しいことではありません。また古いことばかりいくら巧く飾りたてて並べても、それはオタクにすぎず、後世へのメッセージ性に欠けます。
わたしたちは大阪に住んでいます。
大阪に住むあなたはどの糸口から愛し方を描きますか?