父もの
6月には父の日が。いずこも父の日商戦はあの手この手。
ネットショップの目的で探すという欄に、一緒に楽しみたい、唯一無二のギフトを贈る、元気にしたい、癒してあげたい、アッと驚かせたい、オリジナル性をだしたい、お母さんとペアであげたい、配偶者のお父さんに贈る、と種別わけがあるのが面白いと思いました。
クリックでぽんぽん!なんとスピーディに目的をかなえられる世の中でしょう。すこしあたたかみがないような気もしないではありませんが…。
父もので思い出すのは、向田邦子さんのエッセイ、「父の詫び状」をはじめ、一連の向田父ものドラマです。森繁久弥さんがむかしのお父さんを名演されていました。そしてなんといっても小津映画の笠智衆さん演じるお父さん。ほんと、泣けてきます。わたしはヨンさまよりもリュウさま派です。
父ものとしてわたしが今までで一番じぃんとしたのは、文楽でみた、「伊賀越道中双六」の「沼津の段」です。年老いた父親の情けがつたわり、しぃんとしずまりかえった文楽劇場の観客席では、お客さんたちの啜り泣きがあちらでもこちらでもひびいていました。
むかしの日本のお父さんはあまり多くを語らないというイメージが強くて、お芝居では、語らない人だからこそ心がみえたときに、心がうたれるのかもしれません。母ものを描くより、父ものを描いたときには、その多くを語らないというアンチが効果的なのかもしれません。それにしてもいつのころから、日本のお父さんのイメージは変わっていったのでしょう?
ときは昭和…の切り口がおおい昨今ですが、ときは平成の、みおわったあとお父さんのたいせつが伝わってきて、感謝の気持ちがいっぱいになったり、心があたたまってきたりするような、そんな父ものドラマがみたいなぁと思います。
- 父の詫び状 <新装版> (文春文庫)/向田 邦子

- ¥530
- Amazon.co.jp
- 小津安二郎 DVD-BOX 第一集/原節子,司葉子,岡田茉莉子

- ¥24,675
- Amazon.co.jp
- 小津安二郎 DVD-BOX 第二集/原節子,笠智衆,淡島千景

- ¥24,675
- Amazon.co.jp
- 小津安二郎 DVD-BOX 第四集/結城一朗,高田稔,斎藤達雄

- ¥24,675
- Amazon.co.jp
- 小津安二郎 DVD-BOX 第三集/佐野周二,田中絹代,村田知英子

- ¥24,675
- Amazon.co.jp
- 伊賀越道中双六「沼津の段」 [DVD]/竹本住大夫(七代目),山川静夫

- ¥6,300
- Amazon.co.jp
飛田の百番
先日、小説クラスの方たちと飛田の料亭、百番で宴会をしました。
そういえばずいぶんむかしに長研クラスでも百番でチョー昭和的宴会をしたことがありました。いやはや光陰矢のごとし…。うン十年前のことであったやら…。
飛田百番は飛田遊郭のなかにあります。飛田遊郭は難波新地乙部遊郭が1910年に全焼したのにつづいて1916年に生まれたそうです。1912年に完成した旧通天閣を中心とした新世界が第一次大戦後の好景気で大いに賑わい、そこから近い飛田遊郭も昭和初期には200軒を越える妓楼が軒を連ねたそうですが、戦災でほとんどの店が消失。その後ふたたび赤線としてよみがえり、1958年の売春防止法以降は料亭に転じ、現在も伝統的な雰囲気をかもしだす町並みが保たれている地区です。百番は大正初期1918年頃に遊郭として生まれ、戦後は内部が大改築され、現在は料亭として営業されています。
むかしロックや前衛アートに意気揚々な外国人の貧乏アーティストたちと、飛田裏手に軒並ぶ狭い狭い呑み屋長屋で呑んでいたことがありました。彼らは飛田に大いに創意を触発され、なかには亡くなった友人もいるのですが、才能溢れるステキな作品を残しました。今はそのエリアも綺麗なマンションが並ぶ再開発地区へとすっかり姿を変えていて、とても淋しく感じました。
またむかし、パリの遊郭街をひとりで歩いたことがあります。ハラリと纏ったふかふかの黒い毛皮のコートの下に赤いシュミーズだけを着ている、それこそリズ・テーラーばりのグラマーな娼婦が煙草を吹かしながら街角に佇んでいました。
それから一年も経たない頃に、そのエリアもビッグなファッションタウンへと様変わりしました。消えてゆくもの。消えないもの。形は消えようとも消えはしないものとは。そんなことを想いつつ…。
- 飛田ホテル (1971年) (角川文庫)/黒岩 重吾

- ¥840
- Amazon.co.jp
- 飛田残月 (1980年)/黒岩 重吾

- ¥1,029
- Amazon.co.jp
春の横顔
今年の桜のおとずれは早かったようですね。あわただしい天候のうつろいに体調もくずしがちです。どうぞみなさん、ご自愛くださいね。
今年は少し変わったお花見を二回しました。
一回目は、雨の降る日の大川遊覧船から、天満、都島、大阪城へ、船のガラス窓越しにうすぼんやり雨に濡れる満開の桜のゲートを見ました。お天気の日の満開の桜とまたことなり風情のある景色でした。
それからもう一回は、棲んでいるマンションの裏手の小さな公園で、ひとときの夜桜見物をしました。枝から枝へ連なっているぼんぼりに灯が燈っていて、だれもいない公園の、見てくれる人もいない桜から、春の空気が静かにただよっていました。
満開の桜のしたにシートを敷いて、たくさんの料理にお酒を並べた会社の人たちの大宴会。名所にてライトアップされた樹齢ウン年を誇る桜の大木。テレビでそんな光景を映していましたが、こんな風変わりな春の横顔もまた風流と思いつつ、こんな状況でどんなラブストーリーが描けるのかしらと思いをめぐらせました。取るものも取りあえずギターだけ掴んで家出してきた主婦が、だれもいない夜桜公園でギターを爪弾いていたら、これもまた風変わりな男がギターの音色に惹かれて公園へ… そんなラブストーリーが浮かんできました。その主婦は昔の映画「フォロー・ミー」のミア・ファーローのようなタイプの女性かな?
真正面と横顔とが全然ことなる女優さんがいると聞いたことがありますが、人間を描くのにも、真正面と横顔はちがいますね。物書きには人間観察眼がたいせつ。
いつも人を観察していて気が許せないと、周囲から嫌がられるのは物書きの宿命です。嫌がられてちょっと淋しいけれども、その分ステキな人物を描いてみましょう。そこで真正面からではなくて横顔を観察してみるのも、一味ちがうかしらと思いました。
- フォロー・ミー FOLLOW ME [DVD]/ミア・ファロー,トポル

- ¥4,935
- Amazon.co.jp
読みかえして
先日は市川崑監督が亡くなられました。みなさんも心に残る映画がおありでしょうね?
「木枯らし紋次郎」のかっこいい男の翳り。「犬神家の一族」のおどろおどろしさ。「細雪」の豪華絢爛な桜のシーン。「四七人の刺客」の健さんの鋭い視線。たくさんの名シーンが蘇ります。映画監督の仕事というのはシーンを観客の人生に影響させてゆく、ものすごい仕事なのだとあらためて… 人は映画の名シーンとともに墓場まで登場人物と共有した人生観や浪漫を抱いてゆくのでしょうね。
わたしが市川監督の作品で一番好きな映画は「おはん」です。とくにラストの無人駅での吉永小百合の不思議な笑顔が好きです。原作ではどのように描かれているのかと原作を読みかえすのですが、笑顔について描写はありません。それなのに鮮烈に刻みこまれたあのラストの素晴らしさにつくづく… ひとつの映画をどのようにとらえるかは観る人によってまちまちなのでしょうし、またわたしひとりにしても同じ映画を数回観ても、観るときの状況によってとらえ方がことなります。作品から投げかけられた問いへの応えは、そのときどきの明日からの人生に反映してゆくものですね。
先日、ある方からお話を伺っていて、いいお話を伺ったと心にのこりました。その方の知人のお母さまはご高齢になられ、昔はあちこちへと出かけていらしたのがそれも思うに侭ならなくなられ、家に篭ることばかり。そのときにその方がなさったこととは、昔読まれた本を何度も読みかえされることだったそうです。
現代は情報過多で書物も溢れています。あれもこれも読まなくちゃ、と窒息しそうです。
そんな時代に、好きな本をじっくり丹念に読みかえして、自分の人生の来し方を視つめるときとは、本当に至福のときのようです。
- おはん [DVD]/吉永小百合,大原麗子,石坂浩二

- ¥4,725
- Amazon.co.jp
- 犬神家の一族 デジタル・リマスター版 [DVD]/石坂浩二,高峰三枝子,あおい輝彦

- ¥2,940
- Amazon.co.jp
- シネアスト 市川崑 (キネ旬ムック シネアスト)/キネマ旬報社
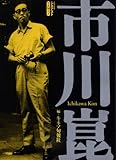
- ¥2,100
- Amazon.co.jp
妖怪ものがたり
私の棲んでいる東中島には「雨月物語」の作者の上田秋成が暮らしていたことがあったそうです。
調べていくうちに上田秋成がとても風変わりでユニークなおじいさんであったことがわかってきて、わくわく胸をときめかせています。
秋成は享保十九年に大阪に生まれ、自叙伝によれば、実父がだれか自分が生まれた時に生きていたかどうかもわからず、実母はというと商人の娘さんのヲサキさんという人で、もの心つかない四歳のときにヲサキさんに棄てられて堂島の商家の養子になり、青春時代はインテリの浮浪子(のらもの)として巷を荒れ放題に彷徨い、つぎは文筆家になり滑稽本をたくさん描いて、つぎは火事で家を失うと医者になり、その後、誤診をしてしまい幼い子どもが亡くなり、それを悔いて悔いて医者をやめ、晩年は極貧の生活のなかで知人への厭味や悪口を描いた「肝大小心録」を発表して非難轟轟の酷評を浴び…。それでもそんなことはどこ吹く風で、この東中島で世の中を真正面から拗ねて生きていた、風変わりな意地悪おじいさんだったそうです。
秋成の生涯の主題は、「常識から逸脱した人間を描くことによって、人間のなかにある妖異性と世界の不条理を描く」ことだったそうです。
単に不思議なおどろおどろしい妖怪変化がでてくるだけでは、奇異なものを登場させたのにすぎません。なぜこの人間には妖怪が見えるのか? その人間のなかになにが棲みついているのか…。
このところ和風ホラーが外国でリメイクされ関心をよんでいるようですね。また、ホラーを書きたいという声もよく聞きます。お化けや妖怪がでてきても、でてきたということだけにびっくりさせられるのではなくて、やっぱり人間が描かれている作品を読みたいなぁと思います。
- 改訂版 雨月物語―現代語訳付き (角川ソフィア文庫)/上田 秋成

- ¥820
- Amazon.co.jp
- 雨月物語 (ちくま学芸文庫)/上田 秋成
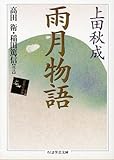
- ¥1,470
- Amazon.co.jp
- 雨月物語―マンガ日本の古典〈28〉 (中公文庫)/木原 敏江
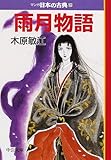
- ¥620
- Amazon.co.jp
遊覧船のお爺ちゃん
秋晴れの祭日、ぶらり天保山へ遊覧船に乗りに行きました。船内は家族連れやカップルなど老いも若きもさまざまに、大変な賑わいでした。
そんななか、デッキにひとりで来られているお爺ちゃんがいました。お爺ちゃんがなにかの拍子にジャンパーに手をやられたときに百円ライターがポケットから落ち、すぐ前のベンチから眺めていたわたしは教えてあげようかと思ったのですが、人生をかさねるように海を見つめているお爺ちゃんの邪魔をするのも気がひけて、そのまましばし見やっていました。
するとお爺ちゃんの前に立っていたモジャモジャのレゲェヘヤーのカップルの女の子がライターを拾いあげてお爺ちゃんに渡そうとしました。お爺ちゃんは思わず反射的に手で違う違うとサイン。
わたしの勝手な想像では、多分お爺ちゃんは連れあいのお婆ちゃんに先立たれた人。全然違うかも知れませんが…。秋晴れの日に思い立って海へ来て、海が大好きだったお婆ちゃんと心だけは道連れだけれど、なにせ賑やかすぎる遊覧船、やっぱりちょっとひとりは淋しいなぁと思っていた矢先に、お爺ちゃんにとってはチョー訳のわからないレゲェヘヤーのカップル。思わず反射的に知らん顔をしたのでしょうね?でも、よく見ると自分のライターなので、お爺ちゃんは「ありがと」ともいわず受けとりました。そのとき、お爺ちゃんの口元はちょっとだけはにかんでいました。モジャモジャの女の子は、彼氏にニカッと笑っていました。
高峰三枝子と上原謙がフルムーンの広告に出ていたのはずいぶん前ですが、天保山にもお洒落でダンディなフルムーンファッションのシルバーカップルがちらほら。でも着古したジャンパーから百円ライターを落として拾ってもらい、ちょっとはにかむだけのお爺ちゃんのために、大きな大きな口をあけて、お腹の底から楽しく笑える、あたたかい喜劇を書いてみたいなぁ…。
- 日本全国 日帰りフルムーン―12万円で100万円乗れる (講談社SOPHIA BOOKS)/小林 克己

- ¥1,680
- Amazon.co.jp
京都の運転手さん
先日来、所用で京都へ週に一回かよっています。
その折、よくタクシーを利用するのですが、観光タクシーが多いことも関係しているのか、お話の上手な運転手さんにしばしば出会います。京都の町では乗るわたしもエトランゼ気分。運転手さんのお話にときめきます。ただし恋のときめきではなくて、取材ができそうなときめきなので、ちょっと残念…
扇の職人さん一家で大きくなられた運転手さんと出会いました。住んでいらっしゃった町も職人さんばかりだったそうで、そこでは芸者さんをやめられた女の人を奥さんにする職人さんが多かったとのこと。彼女たちは既にいわゆる適齢期をこしたのちに嫁いでこられるので、もらい子をする家が多かったと伺いました。その町ではみんながそうなので、あのお嫁さんは元芸者だとか、あの子はもらい子だなどとだれもいわず、近所の人みんなが本当の親のような気持ちで、とても子どもたちを可愛がったそうです。
児童虐待のニュースが心にささってくる時代に、ほっこりあたたまるお話。山本周五郎の「ちいさこべ」の世界がかさなってゆきました。大阪といえば人情というドラマの発想はもう古いといわれ久しく経ちますが、このせちがらい現代では、同じ良かれと思ってとった人情のある行ないでも、結果の良し悪し、人間の身勝手さにより、人情ともとられたり、はたまたハラスメント呼ばわりされたり。でもやはり、人情のたいせつさを描いた、ステキなシナリオに出会いたくなりました。
やがてタクシーは目的地に着いたのですが、運転手さんは早々にメーターをおろしていて、わたしはわたしで、もっと運転手さんのお話を伺いたくなり、料金を払ったあともしばらく車から降りず、すっかり身をのりだして、つづきに聞きいりました。
- ちいさこべ (新潮文庫)/山本 周五郎

- ¥660
- Amazon.co.jp
- 青べか物語 (新潮文庫)/山本 周五郎

- ¥540
- Amazon.co.jp
- さぶ (新潮文庫)/山本 周五郎

- ¥660
- Amazon.co.jp
団塊の世代をシナリオに
この秋、センターの開講説明会にも、団塊世代の方がちらほらお見えになりました。映画館へも団塊世代の方がたくさん足を運ばれることになるでしょうね。
ある資料によりますと、団塊の世代の人の特徴として、競争心、自己主張が激しいのに関わらず、自立心が薄い指示待ち症候群であり、周囲から認められない理由を周囲に押しつける傾向が強いとありました。
血液型で一概に性格を決めつけられると納得がいかないのと同じことのようですが、面白い二面性だと思います。
かつて向田邦子さんは昭和と明治のギャップをホームドラマで書かれていましたが、今なら、どのような新しい関係でギャップが描かれるのかが楽しみです。
団塊の世代の人たちが成人したころの流行語。1967年/中流意識/アングラ/グループサウンズ/ボイン/ハプニング/核家族/1968年/ハレンチ/断絶/失神/1969年/エコノミックアニマル/フォークゲリラ/1970年/歩行者天国/ウーマンリブ/鼻血ブー/1971年/脱サラ/ピース/日本株式会社/へンシーン!/1972年/日本列島改造/ナウ/同棲時代/恍惚/1073年/四畳半フォーク/石油ショック/コインロッカーベビー/「ちょっとだけよ」「あんたも好きねえ」/1974年/狂乱物価/超能カ/中ピ連/ベルばら/金脈と人脈/1975年/あんたあの娘のなんなのさ/乱塾/落ちこぼれ。
懐かしいようでいて、少しも進歩していないようでいて、このころに流れははじまったようでいて…。
若い方は、こりゃなんや?と思われるような語彙もあるでしょうね。
「あなたってハレンチね」と、もし今、言われたら、怒るよりも、にんまり平和な気分になれそうです。
センターが年齢に分け隔てなく、いつもみんながワイワイ青春であるように、分け隔てなく、楽しめて、感動できるシナリオに出会いたいものです。
- 父の詫び状 <新装版> (文春文庫)/向田 邦子

- ¥530
- Amazon.co.jp
- 阿修羅のごとく (新潮文庫)/向田 邦子

- ¥700
- Amazon.co.jp
- 団塊の世代 (文春文庫)/堺屋 太一
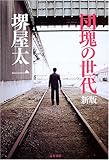
- ¥500
- Amazon.co.jp
今がわからないから
猛烈な残暑がつづきます。お元気でおすごしですか? 秋の到来まであと少しです。お元気にのりきってくださいね。
先日、テレビを見ていたら、ふだんドラマに見入らない私なのですが、つい見入りました。
桐野夏生さん原作の「魂萌え!」でした。
深夜の弁当工場で働く主婦が友人の死体をバラバラに。名門女子高を卒業したエリートOLが売春のため街角に。幸せな専業主婦が夫の死後に思いもかけない愛人の存在を突きつけられる。現代人の心の闇。人間が持つ嫉妬や悪意、孤独や淋しさをグサリとえぐる。
桐野さんが書かれている小説です。
「現代人の心の闇・桐野夏生さんに聞く」(日本経済新聞)より桐野さんの言葉。
「(中略)私は自分が持っている嫌な部分を総動員して、その先にあるものを描いている。そうでなければ今がわからないから。現代人はかつての人が持っていた規範意識を捨て、一線を越えてしまったのではないか」
その要因として、テレビの慎みのなさや、ネットを通して世界中、手に入らないものはなくなったという欲望の放流が。しかしいかに欲望が叶おうと、手に入らないもの。それは人間関係と。私がドラマに見入った訳は、今への視線が、映像に、言葉に、演技になり、その都度、リモコンへの指をストップさせたからだと思います。
心中したくても相手のいない人は、相手をサイトで手に入れられるでしょうが、愛する人ではない。当たり前のことが見えなくなるほど、現代人の心の闇は深くて慎みなく…。
男と女の間には深くて暗い河があると歌われた時代の河の深さと、現代人の心の闇の深さとでは、種類が異なり、「昼顔」のカトリーヌ・ドヌーブと、現代の売春願望とでは、種類が異なる。リモコンへの指にストップをかけさせてみたいものですね。
- 魂萌え!〈上〉 (新潮文庫)/桐野 夏生

- ¥580
- Amazon.co.jp
- 魂萌え!〈下〉 (新潮文庫)/桐野 夏生
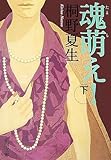
- ¥540
- Amazon.co.jp
- 昼顔 [DVD]/カトリーヌ・ドヌーブ
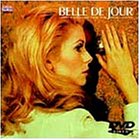
- ¥6,090
- Amazon.co.jp
大阪のおばあちゃん
先日テレビを見ていると、浅草でお好み焼き屋さんをやっていたおばあちゃんのことが。
ソースがたっぷりのった、大きな大きな、具もはみだしているお好み焼き。「風流お好み焼き 染太郎」というお店の崎本はるさんという方です。東京でお好み焼き? と不思議に思うと、大阪上本町出身の方でした。東京で生きぬかれた大阪のおばあちゃんのことを知りたくて調べてみました。
漫才師であった夫を戦争にとられ、昭和十二年、四十二歳のとき、浅草の家の一階で元手のかからないお好み焼き屋を開業。染太郎は夫の芸名で、店の安普請も風情として味わってもらおうと、開店後の常連客であった作家の高見順氏が屋号を命名。高見氏の小説「如何なる星の下に」にこの店はしばしば登場しています。
昼は仕事のない芸人やレビューガール、夜は演出家、踊り子、仕事帰りの芸人、文士たちが、「おばちゃん、元気!」の挨拶とともに訪れては我が家のようにくつろぎ、はるさんは有名無名問わずどんなお客さんも、わけへだててなく温かくもてなされたそうです。
お客さんの送別会やお祝い会のときには、はるさんは、「わたしにもお祝いさせて」と、当時は手に入らない豪華な食材の料理をだして、お金はとられません。はるさんのわけへだてのない愛情は人間に限らずそそがれて、二階の空き室は多いときで二十匹もの野良猫たちの棲家と化しました。
八十歳もすぎた晩年、店の思い出をぜひ本にとの依頼があり、そのときはるさんは、「本を書くとしたなら、お客さんを選んで書くことになってしまう。お客さんは一人残らず大事だから選べない」と断られたそうです。お好み焼きの気取らない満腹感。飾らない店と人柄とお客さんへの感謝の気持ち。ステキな大阪のおばあちゃんです。
- 如何なる星の下に (新潮文庫)/高見 順

- ¥489
- Amazon.co.jp
- 生としての文学―高見順論/小林 敦子

- ¥2,625
- Amazon.co.jp
- 大阪のおばちゃん学 (PHP文庫)/前垣 和義

- ¥620
- Amazon.co.jp