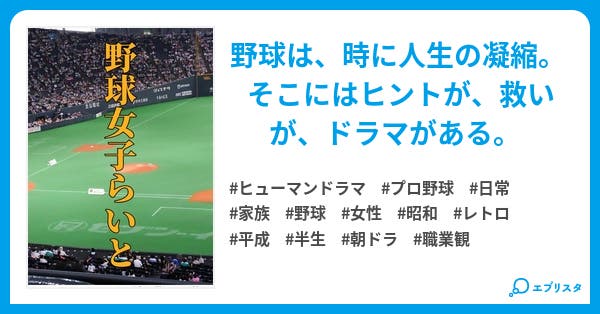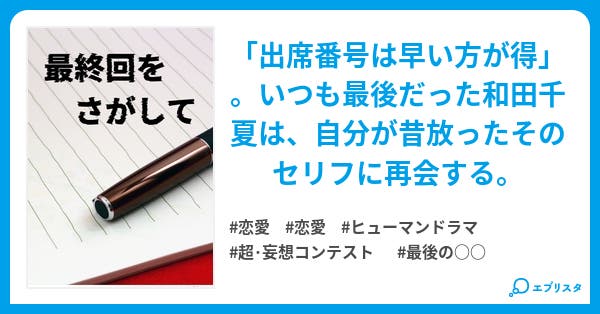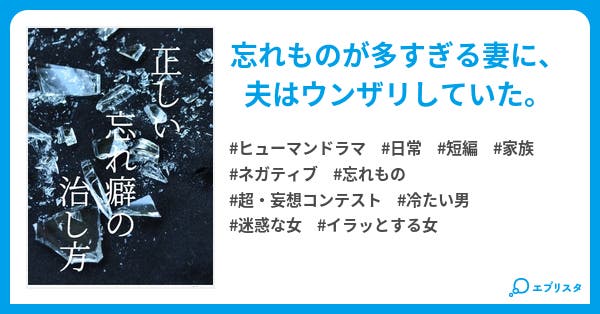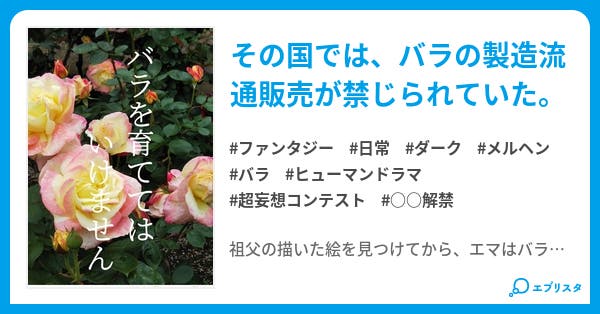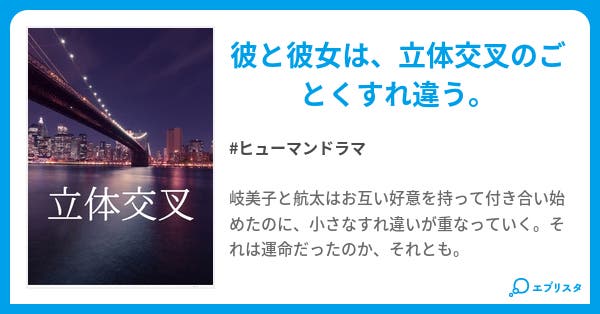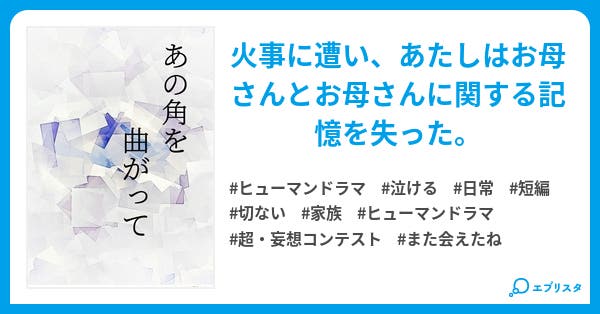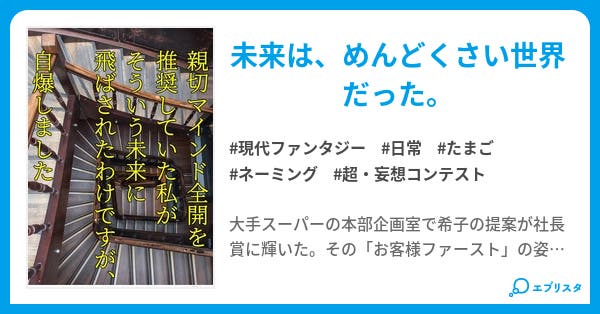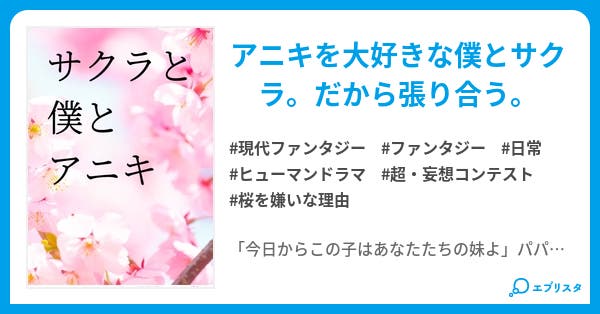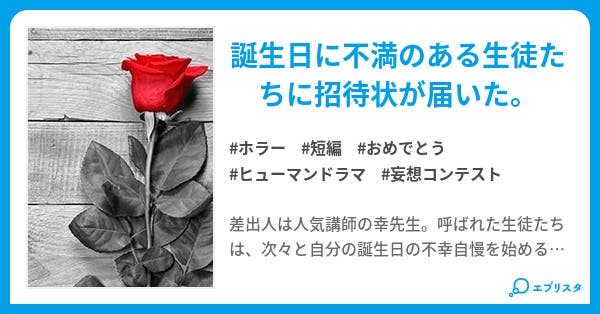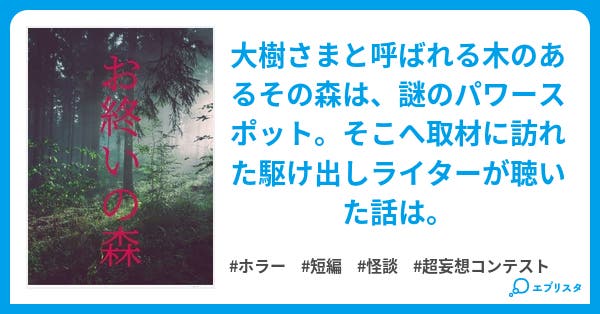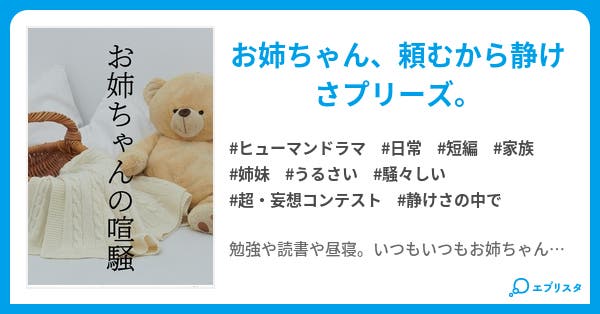私が文章を書くのは、しゃべるのがヘタクソだから。
言葉足らずで、瞬時に最適な単語が出てこなくて、気の利いたことが言えなくて、そもそも相手の言ったことをすぐに理解できる頭がないので、反応も遅いしトンチンカンな回答ばかり。
だから、「文章ならページを戻れば何度でも直しがきくからいい」と言ったことがあって、それが心からの本音だったせいか、そのときの相手が「いいこと言うね」と感心してくれた覚えまである。
と、そんなことを思い出したのは、このほどコロナが5類に移行し、用心モードながらの集まりに、そろりそろりと参加し始めたせい。
久しぶりでお互いの近況報告に盛り上がったり時間を忘れるほどにしゃべったり。そもそもこのまま会うのを躊躇していたら、会わずに一生終えてしまうかもという危機感もある、そんな年頃で。
なのに、そんな気安い仲間内でも私の場合、ホンットに疲れてしまうことがある。もちろん悪いのは自分。それがこの1ヶ月に2度もあった。
先に述べたように生来しゃべるのがヘタクソ。でも相手に退屈と思われたくない。それでちょっとカッコつけた言い回しとか、笑いを取ろうと変なこと言ってみたりとか……それをやめろっつーに! と過去何百回後悔してきたことか。
そう、コロナ禍の長い間人に会えなかったから、こういう気まずい自分を忘れていた。
言葉足らずゆえに、場を持たそうとして余計な一言を発してしまう……それが致命傷。
言ってしまったことは取り消せないし、相手に嫌な思いをさせただろうことに深く深く自己嫌悪を覚える。もうその帰り道から鬱々としてしまった。何であんなことを言ってしまったのか。それまですごく楽しかったのに。
もしかしたら相手はそう気にしていないかもしれない。でも、私としては気になって気になって「自分のバカバカバカ」と延々低空飛行。何もする気が起きず、必要最低限のマスト事項をこなすのがやっと。
一番効く復活方法は、もう一度その相手と会って笑い飛ばすことだとわかっているのだが、こんなご時世だし、この度久しぶりに会ったということは普段そう会わない昔馴染みだということが多い。なので次に会うのはもしかしたら年単位先。とすると、「あのときはあんなこと言っちゃって」などとわざわざ持ち出そうものなら、逆にまた雰囲気を壊すだろう。
とかとかずっと悶々とする。おそらく誰かが私にそういう相談を持ち掛けてきたら「もう取り消せないことじゃん。どうしようもないんだからさっさと忘れるしかない」と言うだろう。
でもそれができればこんなに悩まない。すぐに思考がそのことに戻ってしまい、ぐるぐる回って落ち込んでいくばかり。
こういうの、毎日そこそこ人と話すのに慣れていた時分には減っていた。このコロナ禍で3年もそれが遮断されていたせいで会話力が退化してしまった……ということなのかも。
そして、こういう思いをすると、ますます人に会うのが怖くなる。
で、私の場合の復活方法その2。
文章で書いて吐き出して頭から追い出す。
というわけで、本日のブログはそういうはけ口となっております。。。
(了)
↓ただいま連載中。
野球女子らいと (朝ドラ風長編ヒューマンドラマ)
↓第193回コンテストで、優秀作品に選んでいただきました✨
最終回をさがして (恋愛)
「最後の〇〇」がお題の短編です。11分で読めます。
↓第187回優秀作品に選んでいただきました✨
正しい忘れ癖の治し方 (ヒューマンドラマ)
「忘れもの」がお題の短編です。14分で読めます。
↓第185回コンテストで入賞作に選んでいただきました♡
バラを育ててはいけません (ファンタジー)
「○○解禁」がお題の短編です。14分で読めます。
↓「道」がお題の新作短編です。10分で読めます。
立体交叉 (ヒューマンドラマ)
↓「また会えたね」がお題の短編。13分で読めます。
あの角を曲がって (ヒューマンドラマ)
↓「たまご」がお題の短編です! 13分で読めます。
親切マインド全開を推奨してきた私がそういう未来に飛ばされたわけですが、自爆しました (現代ファンタジー)