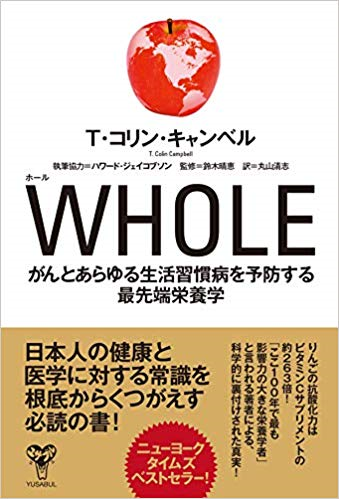翻訳で食べていく方法★プロの翻訳者養成所
リブログ、コメントは自由にどうぞ。その結果生じたトラブル等については関知いたしませんのでご容赦ください。このサイトでは副業としてお小遣いを稼ぐための翻訳者を養成するための情報ではなく、専業翻訳家として本気で1000万円以上稼ぐための方法やヒントを綴っています。
プロフィール
このブログのフォロワー
連載第6回で取り上げた「フリーランス」、この働き方の本質を言葉の定義と語源から紐解いてみた
テーマ:翻訳の一科事典
私がENGLISH JOURNALに連載させていただいている記事の第6回が本日公開されました。
すでにお読みくださってみなさん、ありがとうございます。
まだの方は、是非こちらからお読みください↓
フリーランスは本当にフリーなのか?~真に自由に働くためにすべきこと【翻訳者のスキルアップ術】 - ENGLISH JOURNAL ONLINE (alc.co.jp)
今回は翻訳に限らず、フリーランスという働き方について書きました。このブログでもたびたび題材にしている話題です。
この働き方は、いろいろな制約もありますし、思ったとおりにいかないという方も多いのではないでしょうか。
そんな「フリーランス」の「自由」について考えてみました。自由な働き方を本当に実現するヒントとなれば幸いです
![]()
![]()
![]()
ところで、この「フリーランス」という言葉、あらためて定義を考えてみると、少し本質めいたものが見えてきました。
まあ、定義もいろいろあると思いますが、今回は私らしく、英語の定義から考えてみたいと思います。
【Freelance】
doing particular pieces of work for different organizations, rather than working all the time for a single organization:
FREELANCE | 意味, Cambridge 英語辞書での定義
何が「本質めいた」ものかというと・・・
私個人的な話ですが、以前から「フリーランス」には、ちょっと「かって気まま」とか「自由人」とか、悪く言うと「ちょっと宛てにならない」といったイメージがつきまとっていたのでした。
それは、もしかしたら自分自身に対する自信のなさからかもしれませんが・・・
ともかく、会社などの組織に入って仕事をしている人に比べて、その社会的なものから少し外れている人たちの働きから・・・といった印象を(勝手に!)持っていたのでした。
しかし、今回定義から見つめ直してみて、そこが払拭されてたというか、今までの捉え方が間違っていたことに気づきました。
上のCambridgeの定義を端的に言い直すと・・・
フリーランスは職業に特化した人
と言えると思うのです。
これに対して、フリーランスではない会社員は「会社の業務に特化した人」だと思います。
どちらが良いとかスゴイとかいう話ではなく、「どこに軸を置いて仕事をしているか」ということだと思うのです。
たとえば、フリーランスの翻訳者は、「翻訳」という仕事に特化して、どこの組織に所属するかは関係のない人。所属している人もいれば、していない(私のような人)もいると思うのです。
一方で、会社員の翻訳者は、所属する「会社」の仕事に特化して、翻訳という仕事を中心に業務をしている人。もしかしたら、翻訳以外の業務も、会社の都合によってはやることもある、という人。
要するに、視点(軸)がどこにあるかということだと、改めて思いました。
で、ここが大事なのですが、ENGLISH JOURNALの記事でも書いたような「自由」という概念は、フリーランスの定義の軸にはならないということを、あらためて認識したのでした。
つまり、フリーランスが自由か自由でないかは、特に問題ではないということ。
フリーランスの定義において、「自由」は問題ではないということだと思います。
そう考えると、職業に特化して、その仕事をさまざまな組織に提供するフリーランスというのは、究極のスペシャリストといった感じがして、ちょっとかっこいいなと思えるのでした。
UnsplashのEmber Navarroが撮影した写真
では、この「フリーランス」(freelance)という言葉自体は、どういう語源なのでしょうか?みなさんご存じですか?
「フリーランス」という言葉が使われている最初の印刷物は、1819年発行のウォルター・スコット卿という、スコットランドの小説家が書いた『アイヴァンホー』という小説だそうで、その中で中世の封建領主がお金を支払って雇った傭兵団(free company)の雇われ槍騎兵(lancer)のことが、free lancer(所属なしのランサー)と記述されていたようです。
やはりもともとは「所属なし」「自由な」といった意味合いでの「フリー」だったようで、語源を辿るならば、やはり「フリーランス」を語るときに「自由」の概念は切っても切り離せないものだということになるようです。
しかし、当時の「フリーランサー」も、槍騎兵の業務に特化した、いわばスペシャリストだったわけで、そういう意味では現代のフリーランスと同じなわけで、高度な専門性を買われて雇われたと言えるでしょう。
現代のフリーランスも、中世のフリーランスを見習って、専門性を磨いて、大きな組織や国にも雇ってもらえるようにがんばらないといけませんね。
フリーランスの凄腕外科医が、権威ある(?)大病院に破格の報酬をもらうテレビドラマがありましたが、まさのあの外科医も腕だけを買われて仕事をしていた、フリーランスの鏡なのかもしれません。
ただ、あの外科医を雇う大病院の幹部たちが、どうも「フリーランス」という考え方が気に入らないよで、かなりバカにしたような態度を取っていたのが気になりましたが。
中世の時代はどうだったか分かりませんが、専門家としてその業務に関して頼りにされるという点では、その歴史を継承しているのかもしれません。
私たちフリーランスの翻訳者・通訳も、業務のスペシャリストとしての能力を買ってもらえるように、日々精進していかなければなりませんね。
「社員よりも安いから」という理由で雇われるのではなく。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
このブログは、にほんブログ村のランキングにも参加しています。下のバナーをクリックするだけで投票できますので、よろしければぽちっとお願いします。
![]() ランキングに参加しています!クリックして投票をお願いします。
ランキングに参加しています!クリックして投票をお願いします。
このブログでは、私の体験や実例を通して翻訳者が日々の業務をどのようにすすめ、どのようにリスク管理をすれば収入や効率のアップや翻訳者として成功することができるかのヒントやアイデアをご紹介しています。
フォロー、いいねなどもよろしくお願いします。
励みになります。
━─━─━─━─━─
丸山のプロフィールはこちらをご覧下さい。
━─━─━─━─━─
![]() ENGLISH JOURNAL ONLINE (alc.co.jp) 連載中
ENGLISH JOURNAL ONLINE (alc.co.jp) 連載中
Vol. 6 フリーランスは本当にフリーなのか?~真に自由に働くためにすべきこと【翻訳者のスキルアップ術】 - ENGLISH JOURNAL ONLINE (alc.co.jp)
◆Twitter◆
丸山清志 🇯🇵『WHOLE』(コリン・キャンベル著)翻訳者/Seishi Maruyamaさん (@marusan_jp) / Twitter
◆Instagram◆
拙訳書『WHOLE がんとあらゆる生活習慣病を予防する最先端栄養学』
T・コリン・キャンベル、ハワード・ジェイコブソン 著 鈴木晴恵 監修 丸山清志 翻訳
絶賛発売中!