神がいるなら、出て来て下さい! 私は、お正月の末に、
お店のお客にけがされました。
新潮文庫 太宰治『ヴィヨンの妻』より『ヴィヨンの妻』
122ページ
私は太宰フリークを自称していながら、自分のなかで依然として
すんなりで消化できない作品がある。それはまさにこの晩年の
短編集『ヴィヨンの妻』に収められた作品に集中している。
特に『ヴィヨンの妻』『桜桃』『家庭の幸福』の3作品は、
どう理解したらよいのか未だにわからない。「太宰フリークを
語っていながらずいぶん情けないじゃないか?」と言われそう
だが、わからないものはわからないのだ。
しかし、私が高校生の時から40歳代半ば(太宰より長命)に
なった今も、太宰フリークでいられるのは、これらの自分に
とって難解な作品の存在があってこそかもしれない。十全を
理解しきれない限り、私は太宰の作品を読み続けるしかない
のである。
手元にある文庫本の表紙は、現在店頭に並んでいるものとは
何世代も昔のものになり、活字の大きさも現在のものと比べると
ずいぶんと小さいし、本の黄ばみも甚だしくなったが、それでも
何度も読み返さずにはいられないのは、自分と太宰治の隙間を
埋めたい一心である。それが終わったとしたなら、私は太宰治へ
の興味を失うのかもしれない。でも、それはいやだ。
『ヴィヨンの妻』について採り上げよう。私はこの作品を書いた
太宰治の意図がわからない。
●これは道徳劇なのか?
太宰の分身である主人公の夫・詩人の大谷はまさに罪人である。
だが、道徳を破壊しようと意図していないし、否定もしていない。
苦々しく思っているだろう。むしろ道徳があってはじめて自分の
立ち位置が決まっているという存在ではないか。
なんだか奇妙に可笑しくて、いつまでも笑いつづけて涙が出て、
夫の詩の中にある「文明の果ての大笑い」というのは、こんな
気持の事を言っているのかしらと、ふと考えました。
(108ページ)
十日、二十日とお店にかよっているうちに、私には、椿屋のお酒
を飲みに来ているお客さんがひとり残らず犯罪人ばかりだという
事に、気がついてまいりました。
あんな上品そうな奥さんでさえ、こんな事をたくらまなければ
ならなくなっている世の中で、我が身にうしろ暗いところが一つ
も無くて生きて行く事は、不可能だと思いました。トランプ遊び
のように、マイナスを全部集めるとプラスに変わるという事は、
この世の道徳には起こり得ない事でしょうか。(122ページ)
妻は夫の借金を返済すべく小料理屋椿屋で働くことになるが、
働いているうちに、というか、「働くことを通じて」この世の
「悪徳の栄え」のようなものを理解していく。これが「警察沙汰
になるのを避けるため」というきわめて道徳的で社会的な動機に
よる、という設定が太宰らしいところである。
太平洋戦争の敗戦によって日本の旧体制とともに古い道徳観が
葬り去られた。その後「民主的」な新しい道徳観がもたらされる
ことになるのだが、太宰はこの空隙を見逃さなかった。
僅かにこの国に生じた道徳的な「無政府状態」、太宰の傑作の
多くはこの時期に生まれている。太宰文学を理解するにはこの
時代の空気が理解できなければならないのではないだろうか。
そしてそれはすでにむずかしい作業となってしまった。
非道徳のススメ。
そう読んでいいのだろうか? わからない。しかし妻は自らの
幸福を勝ち得ている。道徳的な弱者であった女性が、古い価値観
から逃れ、自由に生きることを労働や自由な性関係から得る。
これに驚愕するのは男性ではないか。
現在私たちを縛り付けている道徳観は「民主的」とは程遠いもの
であるが、人と人との関係をルールづける道徳の役割は、非人間
的な側面と、きわめて「人間くさい」側面を併せ持っている。
「不倫」を道徳的に排除することによって、家族が維持され、
それによって家族の構成員は安心感を手にする。「嫉妬心」と
いう魔物から逃れることが期待できるのだ。
私は現在の道徳に毒され、馴致され、またすがりついている哀れな
人間である。だからこの「非道徳のススメ」という恐ろしいテーマ
を理解できないのだ。
●これは女性の自立劇なのか?
「なぜ、はじめからこうしなかったのでしょうね。とっても私は
幸福よ。」
「女には、幸福も不幸も無いものです。」
「そうなの? そう言われると、そんな気もして来るけど、
それじゃ、男のひとは、どうなの?」
「男には、不幸だけがあるんです。いつも恐怖と、戦ってばかり
いるのです。」
「わからないわ、私には。でも、いつまでも私、こんな生活を
つづけて行きとうございますわ。椿屋のおじさんも、おばさんも、
とてもいい方ですもの。」(120~121ページ)
イプセンの『人形の家』における有名なノラのセリフ、
ノラ:いいえ、あなた、ーー私が今するように、妻が夫の家を
捨てて出てしまえば、法律上、夫は妻に対する一切の義務を解除
されると聞いています。ともかく私は、あなたから一切の義務を
解除してさしあげます。あなたもこれであたしと同じように、
何にも束縛はないものと思って下さい。どちらも完全に自由に
ならなくてはいけません。さあ、あなたの指輪をお返しします。
私のをくださいまし。
新潮文庫 イプセン『人形の家』第三幕 142ページ
私の短絡的な思考回路だと、どうしてもここに行き着いてしまう。
私はそうではないと思う。でも、この作品を少しでも「道徳的」
に理解しようと試みるとこうせざるを得ないのだ。
しかしノラのように法律的な自由を得ようとする姿勢は、妻から
は見ることができない。それに、夫婦はお互いのフリーセックス
みたいな状態を受け入れて、子供を保護し、家庭を維持しようと
努めている。妻と夫という個人の関係を切り、個人の自由と快楽
と幸福を尊重していながら、家族を維持しようとする。矛盾して
いないか。
これこそ、この時代の雰囲気を知らないものが踏み込めない考え
方のような気がするのだ。
ラストの夫婦間のセリフは、形としてはノラのように自由を勝ち
取った妻の・女性の勝利に見える。
「ここから五千円持って出たのは、さっちゃんと坊やに、あの
お金で久し振りのいいお正月をさせたかったからです。人非人で
ないから、あんな事も仕出かすのです。」
私は格段うれしくもなく、
「人非人でもいいじゃないの。私たちは、生きていさえすれば
いいのよ。」
と言いました。(127ページ)
この後に及んで道徳をかざすみじめな男の姿がある。日本の女性は
「自分で壊しておいてよくもそんな道徳じみたことが言えるわね!」
と、ノラのようには言わない。むしろ心の中で笑うのだ。どちらが
恐ろしいだろうか。
戦後の女性を襲った過酷な運命に関する本を読んだが、それは
理不尽な古い道徳観との戦いという側面も大きいと思う。古い
道徳観というのは洋の東西を問わず女性に過酷なものであった。
そして古い道徳観が消えても次の古い道徳観が生まれる、という
ことの繰り返しを体験してきた。これは男も女も同様だ。
『人形の家』が女性解放運動の先駆的作品と言われながらも、
その処方箋を示すに至らなかったことは重要だ。ヴィヨンの妻は
解放されていない。「救い」を見つけただけだ。ノラだってそう
なのだ。
ノラは自分が頼りにした法律によって解放されたかもしれないが、
次の瞬間から法律によって制限される運命にあったのだ。女性は
いつだって解放されていないと思う。
結論がない。わからないのだから、当然、ない。
ヴィヨンの妻 (新潮文庫)/太宰 治

¥380
Amazon.co.jp
人形の家 (岩波文庫)/イプセン
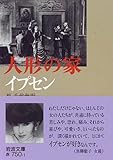
¥483
Amazon.co.jp


お店のお客にけがされました。
新潮文庫 太宰治『ヴィヨンの妻』より『ヴィヨンの妻』
122ページ
私は太宰フリークを自称していながら、自分のなかで依然として
すんなりで消化できない作品がある。それはまさにこの晩年の
短編集『ヴィヨンの妻』に収められた作品に集中している。
特に『ヴィヨンの妻』『桜桃』『家庭の幸福』の3作品は、
どう理解したらよいのか未だにわからない。「太宰フリークを
語っていながらずいぶん情けないじゃないか?」と言われそう
だが、わからないものはわからないのだ。
しかし、私が高校生の時から40歳代半ば(太宰より長命)に
なった今も、太宰フリークでいられるのは、これらの自分に
とって難解な作品の存在があってこそかもしれない。十全を
理解しきれない限り、私は太宰の作品を読み続けるしかない
のである。
手元にある文庫本の表紙は、現在店頭に並んでいるものとは
何世代も昔のものになり、活字の大きさも現在のものと比べると
ずいぶんと小さいし、本の黄ばみも甚だしくなったが、それでも
何度も読み返さずにはいられないのは、自分と太宰治の隙間を
埋めたい一心である。それが終わったとしたなら、私は太宰治へ
の興味を失うのかもしれない。でも、それはいやだ。
『ヴィヨンの妻』について採り上げよう。私はこの作品を書いた
太宰治の意図がわからない。
●これは道徳劇なのか?
太宰の分身である主人公の夫・詩人の大谷はまさに罪人である。
だが、道徳を破壊しようと意図していないし、否定もしていない。
苦々しく思っているだろう。むしろ道徳があってはじめて自分の
立ち位置が決まっているという存在ではないか。
なんだか奇妙に可笑しくて、いつまでも笑いつづけて涙が出て、
夫の詩の中にある「文明の果ての大笑い」というのは、こんな
気持の事を言っているのかしらと、ふと考えました。
(108ページ)
十日、二十日とお店にかよっているうちに、私には、椿屋のお酒
を飲みに来ているお客さんがひとり残らず犯罪人ばかりだという
事に、気がついてまいりました。
あんな上品そうな奥さんでさえ、こんな事をたくらまなければ
ならなくなっている世の中で、我が身にうしろ暗いところが一つ
も無くて生きて行く事は、不可能だと思いました。トランプ遊び
のように、マイナスを全部集めるとプラスに変わるという事は、
この世の道徳には起こり得ない事でしょうか。(122ページ)
妻は夫の借金を返済すべく小料理屋椿屋で働くことになるが、
働いているうちに、というか、「働くことを通じて」この世の
「悪徳の栄え」のようなものを理解していく。これが「警察沙汰
になるのを避けるため」というきわめて道徳的で社会的な動機に
よる、という設定が太宰らしいところである。
太平洋戦争の敗戦によって日本の旧体制とともに古い道徳観が
葬り去られた。その後「民主的」な新しい道徳観がもたらされる
ことになるのだが、太宰はこの空隙を見逃さなかった。
僅かにこの国に生じた道徳的な「無政府状態」、太宰の傑作の
多くはこの時期に生まれている。太宰文学を理解するにはこの
時代の空気が理解できなければならないのではないだろうか。
そしてそれはすでにむずかしい作業となってしまった。
非道徳のススメ。
そう読んでいいのだろうか? わからない。しかし妻は自らの
幸福を勝ち得ている。道徳的な弱者であった女性が、古い価値観
から逃れ、自由に生きることを労働や自由な性関係から得る。
これに驚愕するのは男性ではないか。
現在私たちを縛り付けている道徳観は「民主的」とは程遠いもの
であるが、人と人との関係をルールづける道徳の役割は、非人間
的な側面と、きわめて「人間くさい」側面を併せ持っている。
「不倫」を道徳的に排除することによって、家族が維持され、
それによって家族の構成員は安心感を手にする。「嫉妬心」と
いう魔物から逃れることが期待できるのだ。
私は現在の道徳に毒され、馴致され、またすがりついている哀れな
人間である。だからこの「非道徳のススメ」という恐ろしいテーマ
を理解できないのだ。
●これは女性の自立劇なのか?
「なぜ、はじめからこうしなかったのでしょうね。とっても私は
幸福よ。」
「女には、幸福も不幸も無いものです。」
「そうなの? そう言われると、そんな気もして来るけど、
それじゃ、男のひとは、どうなの?」
「男には、不幸だけがあるんです。いつも恐怖と、戦ってばかり
いるのです。」
「わからないわ、私には。でも、いつまでも私、こんな生活を
つづけて行きとうございますわ。椿屋のおじさんも、おばさんも、
とてもいい方ですもの。」(120~121ページ)
イプセンの『人形の家』における有名なノラのセリフ、
ノラ:いいえ、あなた、ーー私が今するように、妻が夫の家を
捨てて出てしまえば、法律上、夫は妻に対する一切の義務を解除
されると聞いています。ともかく私は、あなたから一切の義務を
解除してさしあげます。あなたもこれであたしと同じように、
何にも束縛はないものと思って下さい。どちらも完全に自由に
ならなくてはいけません。さあ、あなたの指輪をお返しします。
私のをくださいまし。
新潮文庫 イプセン『人形の家』第三幕 142ページ
私の短絡的な思考回路だと、どうしてもここに行き着いてしまう。
私はそうではないと思う。でも、この作品を少しでも「道徳的」
に理解しようと試みるとこうせざるを得ないのだ。
しかしノラのように法律的な自由を得ようとする姿勢は、妻から
は見ることができない。それに、夫婦はお互いのフリーセックス
みたいな状態を受け入れて、子供を保護し、家庭を維持しようと
努めている。妻と夫という個人の関係を切り、個人の自由と快楽
と幸福を尊重していながら、家族を維持しようとする。矛盾して
いないか。
これこそ、この時代の雰囲気を知らないものが踏み込めない考え
方のような気がするのだ。
ラストの夫婦間のセリフは、形としてはノラのように自由を勝ち
取った妻の・女性の勝利に見える。
「ここから五千円持って出たのは、さっちゃんと坊やに、あの
お金で久し振りのいいお正月をさせたかったからです。人非人で
ないから、あんな事も仕出かすのです。」
私は格段うれしくもなく、
「人非人でもいいじゃないの。私たちは、生きていさえすれば
いいのよ。」
と言いました。(127ページ)
この後に及んで道徳をかざすみじめな男の姿がある。日本の女性は
「自分で壊しておいてよくもそんな道徳じみたことが言えるわね!」
と、ノラのようには言わない。むしろ心の中で笑うのだ。どちらが
恐ろしいだろうか。
戦後の女性を襲った過酷な運命に関する本を読んだが、それは
理不尽な古い道徳観との戦いという側面も大きいと思う。古い
道徳観というのは洋の東西を問わず女性に過酷なものであった。
そして古い道徳観が消えても次の古い道徳観が生まれる、という
ことの繰り返しを体験してきた。これは男も女も同様だ。
『人形の家』が女性解放運動の先駆的作品と言われながらも、
その処方箋を示すに至らなかったことは重要だ。ヴィヨンの妻は
解放されていない。「救い」を見つけただけだ。ノラだってそう
なのだ。
ノラは自分が頼りにした法律によって解放されたかもしれないが、
次の瞬間から法律によって制限される運命にあったのだ。女性は
いつだって解放されていないと思う。
結論がない。わからないのだから、当然、ない。
ヴィヨンの妻 (新潮文庫)/太宰 治

¥380
Amazon.co.jp
人形の家 (岩波文庫)/イプセン
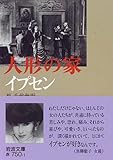
¥483
Amazon.co.jp


