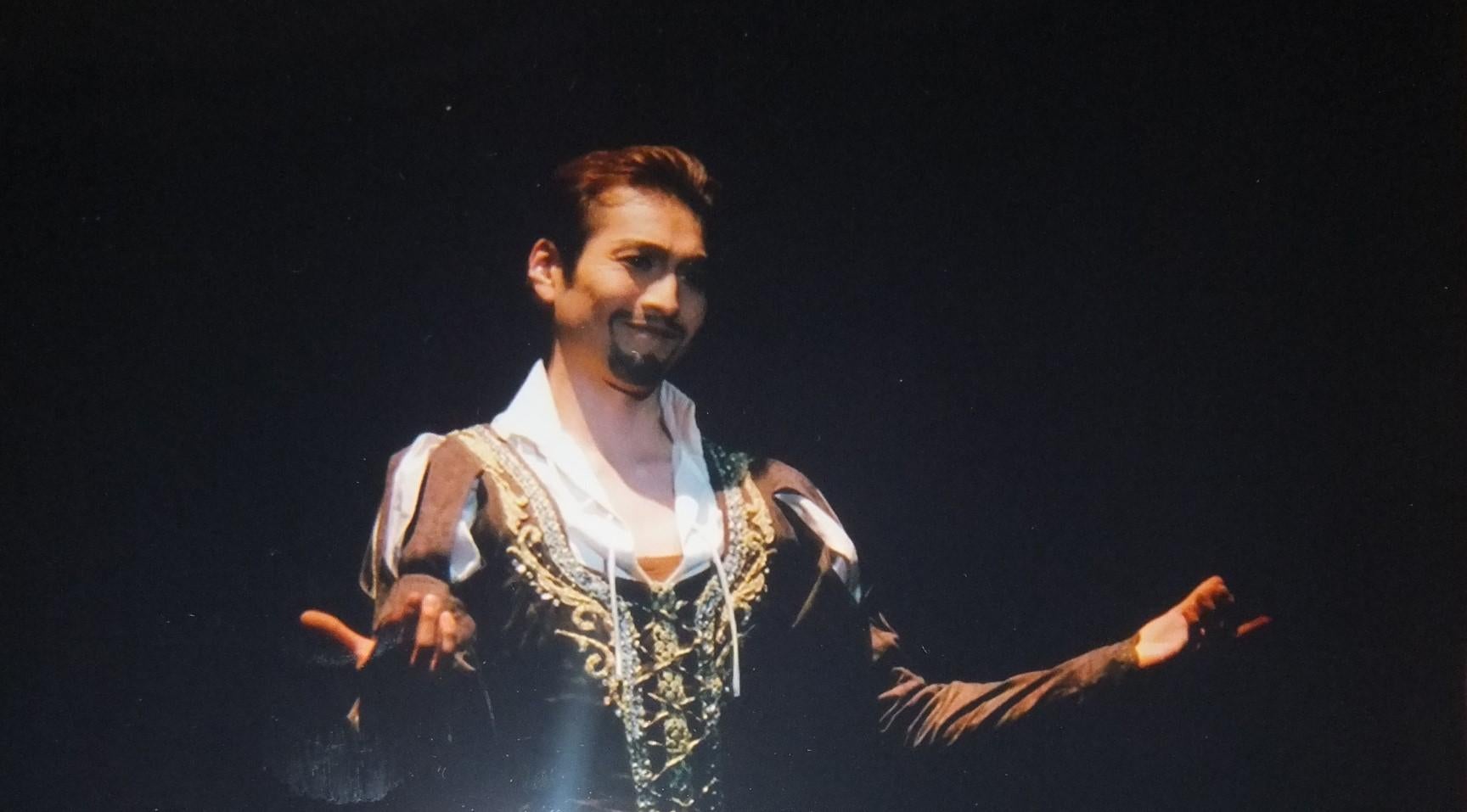バランスは両端から支える!
パッセのバランスにせよ、アラベスクのバランスにせよ、片脚でポワントに立ってバランスを取る事はあまり難しい事ではありません。 原理さえ理解していれば至極簡単に出来る事です。 そしてバランスが取れない理由は原理を間違って解釈しているからに他なりません。
バランスの取り方の原理について説明しますので指導者やプロダンサーの方々もレッスンで試して下さい。
バランスを取ると云うのは『トレイの両端を持ってトレイを水平に支える』様な物です!
トレイを骨盤に置き換えて考えて下さい。
例えばトレイに飲み物を乗せて運ぶとします。 この時にトレイを支える方法としては、トレイの両端を両手で支える、トレイの中心を手のひらで支えると云う二つの方法が考えられます。
更にポワントに立ってバランスを取るとは指先しか使えないと云う事なのでトレイの支え方も指先だけに限定します。
ではトレイの中心(重心位置)を指先だけで支えるのとトレイの両端を指先で支えるのとでは、どちらがより安定するでしょうか?
答えは一目瞭然でトレイの両端を支えた方が遥かに安定しますしコントロールも簡単です。 他方で中心の一点だけでトレイを安定させるのは非常に難しく重心位置を探すだけで物凄く時間が掛かります。
それに飲み物と云うのは液体なので微妙に揺れ動いて、その度に重心位置が変わります。 しかし、トレイの両端で支えていれば重心位置の変化にも簡単に対応出来ますが中心の一点で支えている場合は対応が困難です。
体幹も液体の様に無意識の内に細かく揺れていますので同じ様に重心位置の変化も絶えず起きています。 ですから中心軸の一点でバランスを取る事はとても難しい事なのです。
パッセバランス等で中々バーが離せないのは、一点でバランスを取る方法を選択している為です。
上記の様にバランスを取る為には骨盤を両端から支えて上げれば良く、パッセのバランスでは膝を骨盤の延長として考えて膝を支えて上げるのです。 アラベスクやアティテュードも同じ様に考えて骨盤と膝を下から支えて上げればバランスは簡単に取れる様になります。
またピルエットの時にパッセを下げては駄目なのは、それが両手で支えていたトレイの片端を放す様な行為だからです。
片端を放したらトレイはひっくり返りますが、パッセを下げたら骨盤も同じ様に急激に傾いて軸脚ごと崩れ落ちてしまいます。
そして骨盤やパッセの膝を両端から支えて上げられるのならば、そこを回して骨盤を直接回転させる事も可能です。 つまりピルエットやプロムナードではバランスを取る事と回転力を生み出す事を同じ場所でコントロールが出来るのです。
これはアラベスクやアティテュードのターンでも同様で回転原理もバランスを取る原理も同一なので至ってシンプルで本当に簡単だし無駄な力を使わないのでとても省エネになります。
実はバットマンタンデュ等の脚を上げない時でもこれと同じ考え方でコントロールすると身体の引き上げも脚の張りも格段にレベルが上がるのでレッスン全般において左右から骨盤を支えると云う意識でトレーニングをしてみて下さい。
https://ameblo.jp/hidecchi-1967/entry-12687291933.html
https://www.ballet-arts.jp/
https://ballet.mermo72.com/