剱岳(標高2999m)は富山県立山連峰に属していて、登山を趣味とする人にとっては大変有名な山です。剱(つるぎ)という字のごとく、その大変峻険な山容は近代まで一般人を寄せ付けず、1907年まで国内で唯一残された未踏峰とされてきました。
その剱岳に挑んだ男たちの2009年公開の映画です。
梅之助も登山とかトレッキングは好きですが、「趣味」のレベルを超えて、命の危険を伴う未踏峰や未踏破ルートを目指すクライマーやアルピニストの気持ちまでは理解できません。この映画もその手のものなら、梅之助は観なかったと思います。
しかしこの物語で剱岳に挑戦した人たちの目的は、登る事だけではありませんでした。
1906(明治39)年、国防の観点から日本地図最後の空白地帯を埋めるべく、陸軍参謀本部陸地測量部(後の国土地理院)に、未踏峰とされた剱岳への登頂と測量が命じられた事から物語は始まります。当時、剱岳は立山山岳信仰の対象でもあり、測量の為とはいえ登頂を目指す柴崎芳太郎測量官らを快く思う地元民はいませんでした。
そして翌年実施された山岳測量プロジェクトは案の定、厳しい岩場や雪崩などで作業行動は困難を極めます。結成されたばかりの日本山岳会との剱岳登頂争いという要素も加わる中、測量隊は遂に未踏の山へと歩を進めますが。。。
この映画で梅之助が最も強く感じたのは、当時の未発達かつ貧弱な登山装備で険しい山々一つ一つを測量していった先人たちへの畏敬の念です。この作品は新田次郎の「剱岳 <点の記>」という史実をもとにした小説が原作なので、尚更その想いを強く持ちますね。
ただし、映画作品としては何点か気になった事が。
登場人物の何人かは、会話の口調が全く明治らしくありません。特に測量手・生田信を演じた松田龍平さんの現代的な軽い口調には、強い違和感が残りました。
実直な柴崎測量官を演じた浅野忠信さんも、上手いのか物足りないのかよく分かりません。ただし案内人・宇治長次郎の香川照之さんは上手ですね。彼はアクの強い役柄をやらせるとピカイチですが、謙虚な人柄の長次郎を演じさせても難なくこなしていたのは流石です。
ストーリーは全体的に単調なので、脚本にもうひと捻りあっても良かったと思いました。映画と原作小説には日本山岳会との登頂争いが描かれていますが、史実としてはそのような競争は無かったのだそうです。ならば、どうせフィクションとしての登頂争いを映画ではもう少し工夫して描いて、ストーリー上の強いアクセントとした方が良かったでしょう。
空撮、CGなしで撮られたというカメラワークは、監督が名映画カメラマンだったという事で、現代の先端技術を使用せずとも満足出来るレベルでした。個人的には空撮・CGありの方が、ダイナミックさが出て好きなんだけれどね。
- 劔岳 点の記 メモリアル・エディション [DVD]/ポニーキャニオン
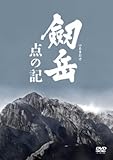
- ¥2,999
- Amazon.co.jp



