「血液型と性格」論文レビューをするにあたって
あちこちでも言われているし、このブログでも何度も繰り返し述べていることだが、「血液型と性格」の関係は以前から詳しく調査されており、万を越える人数を対象にした統計調査から、「血液型と性格に相関があるとは言えない」という結論が得られている。間違いでない範囲でもう少し強く言えば、「血液型と性格の間には、日常生活で使えるほどの関係はない」ということだ。
それを示した画期的な論文が、松井豊(1991)である。これはその筋では有名で、血液型性格判断を取り上げた一般向けの書籍ではかなりの割合で引用されているだろう。もちろん、心理学のプロが、心理学の論文を正しく取り上げているわけだから、我々素人としては、特に変に感じる部分がなければ、基本的にはその結論を(科学的な意味で)信じれば良い。
しかし、ネットの発達は、そのような論文や書籍の存在をちょっと検索すれば認識できたりその内容までかいつまんで教えてくれたりする反面、一部では(まだ一部であると思いたいが、今後増えると予想している)、ネットにない文献は存在しないのと同じ、と(意識するかどうかは別にして)みなす傾向がある。そして、そのことは、プロの間ではどれだけ見解が一致していても、素人が唱える妙ちくりんな主張も対等の主張であるとし、正しいと言うならソースを示せ、と安易に言う風潮がひろまりつつあるような気がしている。
そのような傾向自体は科学的知識を獲得する上で問題があると思われるが、その一方で、やはりオリジナルの論文を見てみたい、という欲求は、どうしても出てくるだろう。色々調べていけば、そう思うのもある意味当然である。
かく言う私も全く同じで、この論文を見てみたくて仕方なかった。ところが、これがネットでは公開されていないのである。
文献表記を正しく書いておこう。
松井豊「血液型による性格の相違に関する統計的検討」、1991、立川短大紀要,、24、51-54
だ。で、見たくてしょうがなかったので、図書館でコピーしてきた。「立川短期大学紀要」で検索して全然見つからなくて諦めかけたのだが、念のため「立川短大紀要」で探したらすぐ見つかったというのは秘密だ。
この論文、たった4ページである。しかし、サンプルが良いだけに、決定的な意味を持っている。そこで、心理学の素人である私が、無謀にもレビューをしようというのが今回の試みである。心理学のプロの方のツッコミをぜひともお願いする次第である。
なお、統計学の初歩を学んでいれば理解できるように書くつもりである。統計学の初歩、というのは、たとえば標本の数サイズをnとすれば、その誤差は√n程度である、というような。「程度である」という理解で十分だろう。わからないことがあれば、私に答えられる範囲ではあるがなるべく返答していきたい。
本当は論文のPDFを公開していただきたいところだが、まあ紀要だし、なかなか難しいのだろう。
トンデモ論文の紹介とは違って書くにも気をつかうので時間がかかるが、できればもう一つ二つ、重要な論文が紹介できればと考えている。とりあえずは、基本ということで、松井(1991)から紹介する。
「血液型と性格」論文レビューをするにあたって(本エントリ)
1.はじめに
なお、血液型性格判断肯定論者としては、かの有名なABO FAN氏をおいて右に出る者はいないだろう。当然、彼も松井論文についてはコメントをしている(このページ )。こちらがスキャンで済ました表を、わざわざ打ち直しているなどその労力のかけかたは敬服に値するが、端的に言って、論理展開が滅茶苦茶である。あちこちに詭弁が存在し、ページの上の方と下の方で分析の基準が違い、また帰無仮説の取り方もわかっておらず、都合のいい結果と文章のつまみ食いのオンパレードだ(ABO FAN氏に都合の悪い話も少し書いてはあるのだが)。
ABO FAN氏のページにもデータは載っているし、松井氏の文章も引用されてはいるので、丹念に読み解けば、松井氏の主張は読み取れるだろう。原理的には。しかし、それはあまりにも多大な労力を必要とする。そこで、ABO FAN氏の分析に挑戦したい方は、このブログでの紹介をもとにアタックされたら良いのではないかと思う。
追記(5/8)
次の論文についてのレビューを掲載しました。
山崎賢治、坂元章「血液型ステレオタイプによる自己成就現象-全国調査の時系列的分析-」、1991、日本社会心理学会第32回大会発表論文集、288-291
1. 問題と目的
2. 方法
3. 結果(この章の前半までその1 、後半以降はその2 )
4. 考察
それを示した画期的な論文が、松井豊(1991)である。これはその筋では有名で、血液型性格判断を取り上げた一般向けの書籍ではかなりの割合で引用されているだろう。もちろん、心理学のプロが、心理学の論文を正しく取り上げているわけだから、我々素人としては、特に変に感じる部分がなければ、基本的にはその結論を(科学的な意味で)信じれば良い。
しかし、ネットの発達は、そのような論文や書籍の存在をちょっと検索すれば認識できたりその内容までかいつまんで教えてくれたりする反面、一部では(まだ一部であると思いたいが、今後増えると予想している)、ネットにない文献は存在しないのと同じ、と(意識するかどうかは別にして)みなす傾向がある。そして、そのことは、プロの間ではどれだけ見解が一致していても、素人が唱える妙ちくりんな主張も対等の主張であるとし、正しいと言うならソースを示せ、と安易に言う風潮がひろまりつつあるような気がしている。
そのような傾向自体は科学的知識を獲得する上で問題があると思われるが、その一方で、やはりオリジナルの論文を見てみたい、という欲求は、どうしても出てくるだろう。色々調べていけば、そう思うのもある意味当然である。
かく言う私も全く同じで、この論文を見てみたくて仕方なかった。ところが、これがネットでは公開されていないのである。
文献表記を正しく書いておこう。
松井豊「血液型による性格の相違に関する統計的検討」、1991、立川短大紀要,、24、51-54
だ。で、見たくてしょうがなかったので、図書館でコピーしてきた。「立川短期大学紀要」で検索して全然見つからなくて諦めかけたのだが、念のため「立川短大紀要」で探したらすぐ見つかったというのは秘密だ。
この論文、たった4ページである。しかし、サンプルが良いだけに、決定的な意味を持っている。そこで、心理学の素人である私が、無謀にもレビューをしようというのが今回の試みである。心理学のプロの方のツッコミをぜひともお願いする次第である。
なお、統計学の初歩を学んでいれば理解できるように書くつもりである。統計学の初歩、というのは、たとえば標本の数サイズをnとすれば、その誤差は√n程度である、というような。「程度である」という理解で十分だろう。わからないことがあれば、私に答えられる範囲ではあるがなるべく返答していきたい。
本当は論文のPDFを公開していただきたいところだが、まあ紀要だし、なかなか難しいのだろう。
トンデモ論文の紹介とは違って書くにも気をつかうので時間がかかるが、できればもう一つ二つ、重要な論文が紹介できればと考えている。とりあえずは、基本ということで、松井(1991)から紹介する。
「血液型と性格」論文レビューをするにあたって(本エントリ)
1.はじめに
なお、血液型性格判断肯定論者としては、かの有名なABO FAN氏をおいて右に出る者はいないだろう。当然、彼も松井論文についてはコメントをしている(このページ )。こちらがスキャンで済ました表を、わざわざ打ち直しているなどその労力のかけかたは敬服に値するが、端的に言って、論理展開が滅茶苦茶である。あちこちに詭弁が存在し、ページの上の方と下の方で分析の基準が違い、また帰無仮説の取り方もわかっておらず、都合のいい結果と文章のつまみ食いのオンパレードだ(ABO FAN氏に都合の悪い話も少し書いてはあるのだが)。
ABO FAN氏のページにもデータは載っているし、松井氏の文章も引用されてはいるので、丹念に読み解けば、松井氏の主張は読み取れるだろう。原理的には。しかし、それはあまりにも多大な労力を必要とする。そこで、ABO FAN氏の分析に挑戦したい方は、このブログでの紹介をもとにアタックされたら良いのではないかと思う。
追記(5/8)
次の論文についてのレビューを掲載しました。
山崎賢治、坂元章「血液型ステレオタイプによる自己成就現象-全国調査の時系列的分析-」、1991、日本社会心理学会第32回大会発表論文集、288-291
1. 問題と目的
2. 方法
3. 結果(この章の前半までその1 、後半以降はその2 )
4. 考察
mizuden
どーでもいいことなんですが。
H.I.M.のこのページ のURLをふと見たら、mizuden なんですね。つまり、発行元が、「水からの伝言」を「mizuden」と読むように略している、と。
いやホントにどーでもいいんですが、以前、kikulog で昔こんなエントリ があったのを思い出したからなんですが。
というわけで、「水伝」は「みずでん」だった、と。(^^)
これだけではなんなので、^^;;
このページに載っている「感想」なるものにちょっとツッコんでおきましょう。
この短い文章で、そのあたり真っ向から書いているのに完璧に論理矛盾した文章が同居している。自分が書いている文章の意味も把握していないんだろうなあ。自分が発した言葉さえも、その耳当たりの良い断片だけに酔って、全体が意味するところを無視できてしまうところがスゴイと思う。
もっとも、それがフツーであるからこそ、これだけ拡まっているのだろう、とは思いますが…。
H.I.M.のこのページ のURLをふと見たら、mizuden なんですね。つまり、発行元が、「水からの伝言」を「mizuden」と読むように略している、と。
いやホントにどーでもいいんですが、以前、kikulog で昔こんなエントリ があったのを思い出したからなんですが。
というわけで、「水伝」は「みずでん」だった、と。(^^)
これだけではなんなので、^^;;
このページに載っている「感想」なるものにちょっとツッコんでおきましょう。
水の力でもありますがもちろん、「美しい意味」ってどういう意味?とか、「科学だ、どうだと」って適当に使い分けてるのはどっちだ、とか基本的な問題もあるわけですが、それ以前に、「水伝」というものが、人の心云々とは関係なく、水が言葉を判断するというロジックで展開されている以上、「言葉というものを使う人という存在」が美醜を判断するプロセスには介在しえない、「水伝」に従う限り、我々は「お水様」の御託宣に従う以上のことはできない、それはつまり「人」の存在価値を不当に貶めていることになっているんですが、わかってるんですかね。
言葉の力とは何かを感じます。
シンプル化された
美しい意味を込めたものが
美しい像を結ぶ、結晶を結ぶ
あらためて
言葉とは何かを再認識してしまいました。 つまり
感動してしまったんです・・・
言葉というものを使う人という存在にです。
科学だ、どうだと
賛否両論に分かれているそうですが
それはね
愛とは何かを科学できたときに
言うことかもしれません。
否定する言葉は、
醜く結晶にもならないそうですもの。
英国在住のK・J様からの感想
この短い文章で、そのあたり真っ向から書いているのに完璧に論理矛盾した文章が同居している。自分が書いている文章の意味も把握していないんだろうなあ。自分が発した言葉さえも、その耳当たりの良い断片だけに酔って、全体が意味するところを無視できてしまうところがスゴイと思う。
もっとも、それがフツーであるからこそ、これだけ拡まっているのだろう、とは思いますが…。
『Love & Thanks』3月号
再び出張で東京へ行きまして、『Love & Thanks』の3月号を入手。
しかしなんですな、Hado からリニューアルしたと思ったら、紙質だけでなく内容も薄くなっちゃって。論評に値しない記事ばかり。まあソフト路線ちうことで、エコでロハスな人々は手に取りやすいのかもしれないけど。でも新宿紀伊国屋本店と大阪梅田の旭屋でしか見ないもんなあ。
どんどんスピリチュアルに近付いていってますね。ということはまあアレだ、まさにオカルトということで、科学っぽい理論武装をしようという姿勢が見られなくなりつつある。と言ってももちろん客観的事実であるという姿勢に揺らぎのないことは、(今号にも載っているが)江本勝自身の発言の中にも表れている(既にあちこちで言われているのと同内容なので、ここで引用したりはしませんが)。
ところが、一つだけ面白い記事がある。「スピリチュアルステップ」という連載だ。誰が書いているのかはわからないけど、アキーとマサーオの二人の掛け合い漫才風の対話でスピリチュアル的な「何か」を解説していくのだ。で、わかりやすい説明っていうのはその対象に限らず難しいもんで、往々にして馬脚を表しやすい。
今回のテーマは「意識のちから」。イヤなニオイがプンプンしますね。最初の言葉が「アキー、『量子』って何?」ですよ。臓器も細胞も、ずーっと細かく見ていくと、
というツッコミはおいといて。頭クラクラしますが、まあでも許容範囲かもしれん。ここまでは。たとえば量子が原子を指しているのだとすれば、理解できなくもない。いや、「光のように点滅する粒」って。光だって光量子と言ったりもするし、粒でもあり(正しい意味で)波動でもある。で、「点滅する」ってなんなんだ。とツッコミたくなるがそこはおさえて(おさえられてないですね、ハイ)。
このあとが少々いやらしい。ついでなのでもうちょい引用。
量子力学と意識の関係といえば、以前このブログでも取り上げた奥健夫氏が最近何冊かまた困った本を出しているのですよね。この界隈での理論的支柱となっていくのか、ちょっと様子を見ておく必要がありそう。
ちなみに奥氏について(ちょっとでも)取り上げたエントリはこちら。
トンデモ本:『意識情報エネルギー医学』
奥健夫氏続報
どうして量子力学を齧ったサイエンスライターは観測問題とスピリチュアルを結び付けたがるのか
『懐疑論者の事典』と並んで@阪大図書館
さて、記事の続きである。
こういうあたりに、都合よく相対主義が利用され、また彼らが相対主義というもの、量子力学というものを理解していないということが端的に示されるのだな。
ちなみに対話はこのあと、だったら壁を通り抜けられても不思議じゃない、とか、スプーン曲げの人も割り箸をグニョグニョに曲げることはできないので意識の限界じゃないか、とか、しかし毛虫が刺すということを知らずにこの間毛虫を素手でつかまえてくれて助かった、それは無意識の意識の可能性だ、とかなんとかわけのわからん話になっていく。
もう一つ面白いのがイラストに添えられているセリフ。
***
精神世界コーナーに行くと、ついニヤニヤしてしまうのですが、この季節は花粉症でマスクをしているのでニヤニヤしていてもバレないですね。目でバレてるかな。もっとも若者が真剣に爬虫類型宇宙人の本を見ていたりするのはやりきれないですが。というか、爬虫類とかプレアデス星人とかの本が最近異様に増殖しているけど、本気で信じているのか?信じているんだろうな、たぶん…。
しかしまあ前回も書きましたけど、東京にいると花粉症はひどくなりますなあ、やっぱり。今回も、夜中に目が痒くて起きてしまったことが何度か。困ったもんだ。
しかしなんですな、Hado からリニューアルしたと思ったら、紙質だけでなく内容も薄くなっちゃって。論評に値しない記事ばかり。まあソフト路線ちうことで、エコでロハスな人々は手に取りやすいのかもしれないけど。でも新宿紀伊国屋本店と大阪梅田の旭屋でしか見ないもんなあ。
どんどんスピリチュアルに近付いていってますね。ということはまあアレだ、まさにオカルトということで、科学っぽい理論武装をしようという姿勢が見られなくなりつつある。と言ってももちろん客観的事実であるという姿勢に揺らぎのないことは、(今号にも載っているが)江本勝自身の発言の中にも表れている(既にあちこちで言われているのと同内容なので、ここで引用したりはしませんが)。
ところが、一つだけ面白い記事がある。「スピリチュアルステップ」という連載だ。誰が書いているのかはわからないけど、アキーとマサーオの二人の掛け合い漫才風の対話でスピリチュアル的な「何か」を解説していくのだ。で、わかりやすい説明っていうのはその対象に限らず難しいもんで、往々にして馬脚を表しやすい。
今回のテーマは「意識のちから」。イヤなニオイがプンプンしますね。最初の言葉が「アキー、『量子』って何?」ですよ。臓器も細胞も、ずーっと細かく見ていくと、
A: 「量子」と呼ばれる、光のように点滅する粒になるんだ。…江本先生!!この世のものは「波動」でできてるんじゃなかったでしたっけ!!
M: 何それ! じゃ、僕はその光の粒子の集合体ってこと?
A: そうなるね。マサーオだけじゃない、木だって、そこにあるコップも椅子も、細かく、細かく見ていくと「量子」にたどり着くんだ。
M: それは、みんな同じ「量子」なの?
A: 同じ「量子」だよ。
M: 同じ材料でできてるってこと?
A: そうだよ。
M: この世界のものは、みんな粒々、点々でできてるの?
A: そうだよ。
というツッコミはおいといて。頭クラクラしますが、まあでも許容範囲かもしれん。ここまでは。たとえば量子が原子を指しているのだとすれば、理解できなくもない。いや、「光のように点滅する粒」って。光だって光量子と言ったりもするし、粒でもあり(正しい意味で)波動でもある。で、「点滅する」ってなんなんだ。とツッコミたくなるがそこはおさえて(おさえられてないですね、ハイ)。
このあとが少々いやらしい。ついでなのでもうちょい引用。
M: う~~ん。じゃ、その粒々、点々だらけの世界で、僕が僕で、コップがコップとして存在しているのはなぜ?でた~「意識」!!電磁気力と核力という単語の意味を調べた方がいいと思うし湯川秀樹にも失礼だろうと思うがそれは置いといて。
A: 意識のちからだよ。
量子力学と意識の関係といえば、以前このブログでも取り上げた奥健夫氏が最近何冊かまた困った本を出しているのですよね。この界隈での理論的支柱となっていくのか、ちょっと様子を見ておく必要がありそう。
ちなみに奥氏について(ちょっとでも)取り上げたエントリはこちら。
トンデモ本:『意識情報エネルギー医学』
奥健夫氏続報
どうして量子力学を齧ったサイエンスライターは観測問題とスピリチュアルを結び付けたがるのか
『懐疑論者の事典』と並んで@阪大図書館
さて、記事の続きである。
M: どういう意味?悪しき相対主義から都合のいいところだけつまみ喰い。最初は意識が物体を構成していると言っておきながら、後半は「事実上存在しないも同じ」という話に飛躍している。飛行船なんて概念のない原始人はそりゃ「飛行船だ」とは認識しないだろうが、この話し方だと、アキーは、原始人は「あれは飛行船だ」とは思わなくても、我々が飛行船だとして見ているものと同じものを見ていると考えているとしか思えない。そして、それは前半の話とは矛盾する。
A: マサーオの世界は、マサーオが粒々、点々の中からマサーオが認識したものでつくられている。
M: 僕の意識が粒々や点々を、僕やコップに定着させている。
A: そうなるね。もし、原始人が空を飛んでいる飛行船を見たら、飛行船ってわかるかな?人が乗ってるってわかるかな?
M: 無理だよ。原始人は、飛行船なんて知らないもの。
A: だよね。おそらく、存在自体気づかないと思うよ。
M: あ! 認識できないものは、存在しないと同じ?
A: そう。原始人にとっては飛行船は存在しないんだよ。粒々、点々の中から、マンモスなんかは認識できるんだろうね。
こういうあたりに、都合よく相対主義が利用され、また彼らが相対主義というもの、量子力学というものを理解していないということが端的に示されるのだな。
ちなみに対話はこのあと、だったら壁を通り抜けられても不思議じゃない、とか、スプーン曲げの人も割り箸をグニョグニョに曲げることはできないので意識の限界じゃないか、とか、しかし毛虫が刺すということを知らずにこの間毛虫を素手でつかまえてくれて助かった、それは無意識の意識の可能性だ、とかなんとかわけのわからん話になっていく。
もう一つ面白いのがイラストに添えられているセリフ。
僕は存在している。存在させられているんじゃない。これって、この手の人々の発想と反対ですよね。「我々は生かされているんだ」的な。だから感謝しよう、みたいな。「愛・感謝」と整合するのだろうか。
そう。世界に存在しているすべてのものみーんな。
***
精神世界コーナーに行くと、ついニヤニヤしてしまうのですが、この季節は花粉症でマスクをしているのでニヤニヤしていてもバレないですね。目でバレてるかな。もっとも若者が真剣に爬虫類型宇宙人の本を見ていたりするのはやりきれないですが。というか、爬虫類とかプレアデス星人とかの本が最近異様に増殖しているけど、本気で信じているのか?信じているんだろうな、たぶん…。
しかしまあ前回も書きましたけど、東京にいると花粉症はひどくなりますなあ、やっぱり。今回も、夜中に目が痒くて起きてしまったことが何度か。困ったもんだ。
『彼らの犯罪』樹村みのり
異色の作品である。そして、読み終わった後、とても気分が重い。そういう名作である。割り切れない。いや、割り切れちゃいかんのだろう、と理屈ではわかる。しかし、割り切れないものを受けとめるのがいかに大変か、ということをも示している。
復刊ドットコム で復刊(というより新刊として出版されているが)された、樹村みのりの作品集。裁判を傍聴し、実際の事件をセミ・ドキュメンタリーという形でマンガにした『彼らの犯罪』『親が・殺す』『夢の入り口』、そして性教育の雑誌に連載されていたという短編集『横からの構図』を掲載したもの。
表題作は、いわゆる「女子高生コンクリート詰め殺人事件」を題材にしている。裁判を傍聴する中で、どのようにして少年達が非道な犯罪に走っていったのか、そして親達は何を考えていたのか、彼らの言葉から丹念に描かれる。もちろん完全なドキュメントではないので、裁判を傍聴する主人公と、その中で知り会った友人との会話を通して、作者の思考が伝えられる。
私は「彼ら」とは同世代で、リアルタイムで衝撃をもってこの事件を眺めていた。無論リアルタイムで見ていたからと言って真実を知っていたわけではなく、ニュースで報道される程度に知っていただけだ。だから、今回、このマンガで知ったことはとても多かった。しかし、だからといって何かを納得できたわけでもない。やはり、どうしようもなく割り切れなさが残るのだ。しかし、割り切れてはいけないのだろう。紋切り型に言えば「心の闇」ということになるのだろうが、それが簡単に割り切れるわけはないのだ。
…とまあ自分でも何を書いているのかわからない程度に全然整理できない。しかし、当時、漠然と予想していたことで、今回わかったことの一つは、「そう簡単にわかることではない」ということだろう。
本の帯には「人は、どのようにして裁かれるのか-!? "裁判員制度"を予感する著者渾身の作品群!!」とある。裁判員制度が動き出してしまった以上、我々誰もが人を裁くという経験をする可能性がある。そのときに、安易にヤッチマエ的な発想で動くのではなく、冷静に、背景まで想像しながら判断したいものだと思う。もっとも、そこまで考えたときに、プロでもない自分にどこまで判断できるのだろう、という気はするのだが。有罪か無罪か、ではなく、量刑まで判断するのが今回の制度だものね。
『夢の入り口』は、洗脳というものがどう実行されるかを、カルト集団の「講習会」に参加し、帰るなり精神科に入院した人の経験を描いたもの。洗脳というものがどのように行われ、多くの人々がどうして洗脳されてしまうのか、その一端がよくわかる作品。いろいろと勉強になる。
短編集も面白い。どうしてミスコンが批判されるのかが実にわかりやすく説得的に描いてあったりもする一方で、いかにも樹村みのりらしく、自分の幼少期をふりかえりつつ、大人になっていく様を詩的に描く作品もある。
そういうわけで、作品自体が異色だが、樹村みのりの作品として見た場合も異色であって、樹村みのりを知らない人がこれを読んで「これが樹村みのりなのか」と思われてもなあ、と思いつつ、しかしやはりこれは樹村みのりだからこその作品なんだろうなあ、という気もして、「良い後味の悪さ」を味わったのでした。
復刊ドットコム で復刊(というより新刊として出版されているが)された、樹村みのりの作品集。裁判を傍聴し、実際の事件をセミ・ドキュメンタリーという形でマンガにした『彼らの犯罪』『親が・殺す』『夢の入り口』、そして性教育の雑誌に連載されていたという短編集『横からの構図』を掲載したもの。
表題作は、いわゆる「女子高生コンクリート詰め殺人事件」を題材にしている。裁判を傍聴する中で、どのようにして少年達が非道な犯罪に走っていったのか、そして親達は何を考えていたのか、彼らの言葉から丹念に描かれる。もちろん完全なドキュメントではないので、裁判を傍聴する主人公と、その中で知り会った友人との会話を通して、作者の思考が伝えられる。
私は「彼ら」とは同世代で、リアルタイムで衝撃をもってこの事件を眺めていた。無論リアルタイムで見ていたからと言って真実を知っていたわけではなく、ニュースで報道される程度に知っていただけだ。だから、今回、このマンガで知ったことはとても多かった。しかし、だからといって何かを納得できたわけでもない。やはり、どうしようもなく割り切れなさが残るのだ。しかし、割り切れてはいけないのだろう。紋切り型に言えば「心の闇」ということになるのだろうが、それが簡単に割り切れるわけはないのだ。
…とまあ自分でも何を書いているのかわからない程度に全然整理できない。しかし、当時、漠然と予想していたことで、今回わかったことの一つは、「そう簡単にわかることではない」ということだろう。
本の帯には「人は、どのようにして裁かれるのか-!? "裁判員制度"を予感する著者渾身の作品群!!」とある。裁判員制度が動き出してしまった以上、我々誰もが人を裁くという経験をする可能性がある。そのときに、安易にヤッチマエ的な発想で動くのではなく、冷静に、背景まで想像しながら判断したいものだと思う。もっとも、そこまで考えたときに、プロでもない自分にどこまで判断できるのだろう、という気はするのだが。有罪か無罪か、ではなく、量刑まで判断するのが今回の制度だものね。
『夢の入り口』は、洗脳というものがどう実行されるかを、カルト集団の「講習会」に参加し、帰るなり精神科に入院した人の経験を描いたもの。洗脳というものがどのように行われ、多くの人々がどうして洗脳されてしまうのか、その一端がよくわかる作品。いろいろと勉強になる。
短編集も面白い。どうしてミスコンが批判されるのかが実にわかりやすく説得的に描いてあったりもする一方で、いかにも樹村みのりらしく、自分の幼少期をふりかえりつつ、大人になっていく様を詩的に描く作品もある。
そういうわけで、作品自体が異色だが、樹村みのりの作品として見た場合も異色であって、樹村みのりを知らない人がこれを読んで「これが樹村みのりなのか」と思われてもなあ、と思いつつ、しかしやはりこれは樹村みのりだからこその作品なんだろうなあ、という気もして、「良い後味の悪さ」を味わったのでした。
- 彼らの犯罪/樹村 みのり

- ¥630
- Amazon.co.jp
『環境教育 善意の落とし穴』田中優
タイトルからして気になるでしょう。
著者の問題意識は、ニセ科学問題に継続的にコミットしてきた人々が共通して抱えるものと同じである。「はじめに」で、
具体的にはどういうことか。例えばゴミ問題では以下のように述べる。
要するに、環境教育において、身近なことも大事だが、それだけでは問題は全く解決しない。問題の本質をつかみ、それを解決しようと行動することが大切だというわけだ。CO2を削減したいなら、どこが最も多く排出しているかを理解する。省エネに興味があるなら、どこが一番電力を消費しているかを理解する。
それだけではない。たとえばリサイクル。我々が良かれと思ってリサイクルをする。しかし、国内では消費しきれない。そこで、たとえば紙ゴミが東南アジアに安く輸出され、そこで活用される。するとどうなるか。ゴミあさりでかろうじて生計をたてていたその国の最下層の人々の生活がたちゆかなくなる。無論、ゴミあさりをしなければ生きていけない状況を批判するのは簡単だし、批判しなければならないのもまたそうなのだ。健康にも関わるわけだし。しかし、とりあえず彼らの目の前の生活を破壊はするだけの威力があるわけだ、リサイクルによる輸出というものは。
そこまで考えた上での取り組みが必要だ、というわけ。ここに必要なのは、「論理的な想像力」なのだろう。そこにはエコでロハスな自己満足的ライフスタイルは登場しない。いや、表面的、部分的にはもちろん一致するところはたくさんあるだろう。しかし、ライフスタイルが問題ではない、というところに気付くことが、環境教育の最も重要な点ではないか-ということだ。
著者の主張にはただちには頷けない部分もある。たとえば「化学物質過敏症」「電磁波過敏症」のくだりは特にそうだ。WHOの報告についてのコメントなどは、若干恣意的な感じもする。しかしまあそれは本質ではない。それ以上に重要なことをこの本は教えてくれる。
著者は言う。「援助の前に、同じ人間として見ること」-これは、環境教育が持つ射程を示唆するものだろう。自己満足に陥らないことは、環境問題に限らず、あらゆる場面で重要だと思う。それを学ぶという意味も、持ち合わせているのだ。
この本は、もともとは『クレスコ』という雑誌での連載だったそうである。これは、全教(全日本教職員組合)が発行している雑誌だ。こういう視点が現場の教師に確立すれば、環境教育に限らず、相当な範囲の進歩が見込まれると思うのだが。とりあえずは、教師集団自らの発信ということで、応援したい。
***
慣性がついちゃって、久々にこういうエントリを書くのはかなり労力が必要ですね。うーむ。まだまだリハビリ中…。
著者の問題意識は、ニセ科学問題に継続的にコミットしてきた人々が共通して抱えるものと同じである。「はじめに」で、
しかし現状の環境教育は、身の回りの心がけのように非常に狭いものにされている。生活の細々したところの心がけも大事だが、それだけでは解決しない。解決につながらないままでは環境教育の名に値しなくなってしまう。しかし一方で、環境教育に携わる人々の努力と熱意には頭が下がる思いがする。この、実現したい解決策と、している対策のギャップを何とかしたい。それが、本書の元となった連載執筆の動機だった。と著者は述べる。
具体的にはどういうことか。例えばゴミ問題では以下のように述べる。
環境教育が問題解決をめざすものであれば、全体像で、自分たちの位置をつかむことが重要だ。「やっぱりゴミは産業が出すものが圧倒的だから、こういう企業を変えていかなければなりませんね」という結論なら理解できるのだが、「やっぱり私たちのライフスタイルが大事ですね。心がけで地球を守りましょう。がんばれば不可能はありません」では、竹槍でB29爆撃機に立ち向かおうとした、どっかの国民のようではないか。
要するに、環境教育において、身近なことも大事だが、それだけでは問題は全く解決しない。問題の本質をつかみ、それを解決しようと行動することが大切だというわけだ。CO2を削減したいなら、どこが最も多く排出しているかを理解する。省エネに興味があるなら、どこが一番電力を消費しているかを理解する。
それだけではない。たとえばリサイクル。我々が良かれと思ってリサイクルをする。しかし、国内では消費しきれない。そこで、たとえば紙ゴミが東南アジアに安く輸出され、そこで活用される。するとどうなるか。ゴミあさりでかろうじて生計をたてていたその国の最下層の人々の生活がたちゆかなくなる。無論、ゴミあさりをしなければ生きていけない状況を批判するのは簡単だし、批判しなければならないのもまたそうなのだ。健康にも関わるわけだし。しかし、とりあえず彼らの目の前の生活を破壊はするだけの威力があるわけだ、リサイクルによる輸出というものは。
そこまで考えた上での取り組みが必要だ、というわけ。ここに必要なのは、「論理的な想像力」なのだろう。そこにはエコでロハスな自己満足的ライフスタイルは登場しない。いや、表面的、部分的にはもちろん一致するところはたくさんあるだろう。しかし、ライフスタイルが問題ではない、というところに気付くことが、環境教育の最も重要な点ではないか-ということだ。
著者の主張にはただちには頷けない部分もある。たとえば「化学物質過敏症」「電磁波過敏症」のくだりは特にそうだ。WHOの報告についてのコメントなどは、若干恣意的な感じもする。しかしまあそれは本質ではない。それ以上に重要なことをこの本は教えてくれる。
著者は言う。「援助の前に、同じ人間として見ること」-これは、環境教育が持つ射程を示唆するものだろう。自己満足に陥らないことは、環境問題に限らず、あらゆる場面で重要だと思う。それを学ぶという意味も、持ち合わせているのだ。
この本は、もともとは『クレスコ』という雑誌での連載だったそうである。これは、全教(全日本教職員組合)が発行している雑誌だ。こういう視点が現場の教師に確立すれば、環境教育に限らず、相当な範囲の進歩が見込まれると思うのだが。とりあえずは、教師集団自らの発信ということで、応援したい。
***
慣性がついちゃって、久々にこういうエントリを書くのはかなり労力が必要ですね。うーむ。まだまだリハビリ中…。
- 環境教育 善意の落とし穴 (クレスコファイル)/田中 優
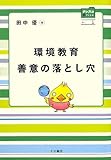
- ¥1,050
- Amazon.co.jp