『環境教育 善意の落とし穴』田中優
タイトルからして気になるでしょう。
著者の問題意識は、ニセ科学問題に継続的にコミットしてきた人々が共通して抱えるものと同じである。「はじめに」で、
具体的にはどういうことか。例えばゴミ問題では以下のように述べる。
要するに、環境教育において、身近なことも大事だが、それだけでは問題は全く解決しない。問題の本質をつかみ、それを解決しようと行動することが大切だというわけだ。CO2を削減したいなら、どこが最も多く排出しているかを理解する。省エネに興味があるなら、どこが一番電力を消費しているかを理解する。
それだけではない。たとえばリサイクル。我々が良かれと思ってリサイクルをする。しかし、国内では消費しきれない。そこで、たとえば紙ゴミが東南アジアに安く輸出され、そこで活用される。するとどうなるか。ゴミあさりでかろうじて生計をたてていたその国の最下層の人々の生活がたちゆかなくなる。無論、ゴミあさりをしなければ生きていけない状況を批判するのは簡単だし、批判しなければならないのもまたそうなのだ。健康にも関わるわけだし。しかし、とりあえず彼らの目の前の生活を破壊はするだけの威力があるわけだ、リサイクルによる輸出というものは。
そこまで考えた上での取り組みが必要だ、というわけ。ここに必要なのは、「論理的な想像力」なのだろう。そこにはエコでロハスな自己満足的ライフスタイルは登場しない。いや、表面的、部分的にはもちろん一致するところはたくさんあるだろう。しかし、ライフスタイルが問題ではない、というところに気付くことが、環境教育の最も重要な点ではないか-ということだ。
著者の主張にはただちには頷けない部分もある。たとえば「化学物質過敏症」「電磁波過敏症」のくだりは特にそうだ。WHOの報告についてのコメントなどは、若干恣意的な感じもする。しかしまあそれは本質ではない。それ以上に重要なことをこの本は教えてくれる。
著者は言う。「援助の前に、同じ人間として見ること」-これは、環境教育が持つ射程を示唆するものだろう。自己満足に陥らないことは、環境問題に限らず、あらゆる場面で重要だと思う。それを学ぶという意味も、持ち合わせているのだ。
この本は、もともとは『クレスコ』という雑誌での連載だったそうである。これは、全教(全日本教職員組合)が発行している雑誌だ。こういう視点が現場の教師に確立すれば、環境教育に限らず、相当な範囲の進歩が見込まれると思うのだが。とりあえずは、教師集団自らの発信ということで、応援したい。
***
慣性がついちゃって、久々にこういうエントリを書くのはかなり労力が必要ですね。うーむ。まだまだリハビリ中…。
著者の問題意識は、ニセ科学問題に継続的にコミットしてきた人々が共通して抱えるものと同じである。「はじめに」で、
しかし現状の環境教育は、身の回りの心がけのように非常に狭いものにされている。生活の細々したところの心がけも大事だが、それだけでは解決しない。解決につながらないままでは環境教育の名に値しなくなってしまう。しかし一方で、環境教育に携わる人々の努力と熱意には頭が下がる思いがする。この、実現したい解決策と、している対策のギャップを何とかしたい。それが、本書の元となった連載執筆の動機だった。と著者は述べる。
具体的にはどういうことか。例えばゴミ問題では以下のように述べる。
環境教育が問題解決をめざすものであれば、全体像で、自分たちの位置をつかむことが重要だ。「やっぱりゴミは産業が出すものが圧倒的だから、こういう企業を変えていかなければなりませんね」という結論なら理解できるのだが、「やっぱり私たちのライフスタイルが大事ですね。心がけで地球を守りましょう。がんばれば不可能はありません」では、竹槍でB29爆撃機に立ち向かおうとした、どっかの国民のようではないか。
要するに、環境教育において、身近なことも大事だが、それだけでは問題は全く解決しない。問題の本質をつかみ、それを解決しようと行動することが大切だというわけだ。CO2を削減したいなら、どこが最も多く排出しているかを理解する。省エネに興味があるなら、どこが一番電力を消費しているかを理解する。
それだけではない。たとえばリサイクル。我々が良かれと思ってリサイクルをする。しかし、国内では消費しきれない。そこで、たとえば紙ゴミが東南アジアに安く輸出され、そこで活用される。するとどうなるか。ゴミあさりでかろうじて生計をたてていたその国の最下層の人々の生活がたちゆかなくなる。無論、ゴミあさりをしなければ生きていけない状況を批判するのは簡単だし、批判しなければならないのもまたそうなのだ。健康にも関わるわけだし。しかし、とりあえず彼らの目の前の生活を破壊はするだけの威力があるわけだ、リサイクルによる輸出というものは。
そこまで考えた上での取り組みが必要だ、というわけ。ここに必要なのは、「論理的な想像力」なのだろう。そこにはエコでロハスな自己満足的ライフスタイルは登場しない。いや、表面的、部分的にはもちろん一致するところはたくさんあるだろう。しかし、ライフスタイルが問題ではない、というところに気付くことが、環境教育の最も重要な点ではないか-ということだ。
著者の主張にはただちには頷けない部分もある。たとえば「化学物質過敏症」「電磁波過敏症」のくだりは特にそうだ。WHOの報告についてのコメントなどは、若干恣意的な感じもする。しかしまあそれは本質ではない。それ以上に重要なことをこの本は教えてくれる。
著者は言う。「援助の前に、同じ人間として見ること」-これは、環境教育が持つ射程を示唆するものだろう。自己満足に陥らないことは、環境問題に限らず、あらゆる場面で重要だと思う。それを学ぶという意味も、持ち合わせているのだ。
この本は、もともとは『クレスコ』という雑誌での連載だったそうである。これは、全教(全日本教職員組合)が発行している雑誌だ。こういう視点が現場の教師に確立すれば、環境教育に限らず、相当な範囲の進歩が見込まれると思うのだが。とりあえずは、教師集団自らの発信ということで、応援したい。
***
慣性がついちゃって、久々にこういうエントリを書くのはかなり労力が必要ですね。うーむ。まだまだリハビリ中…。
- 環境教育 善意の落とし穴 (クレスコファイル)/田中 優
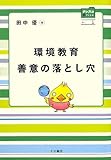
- ¥1,050
- Amazon.co.jp