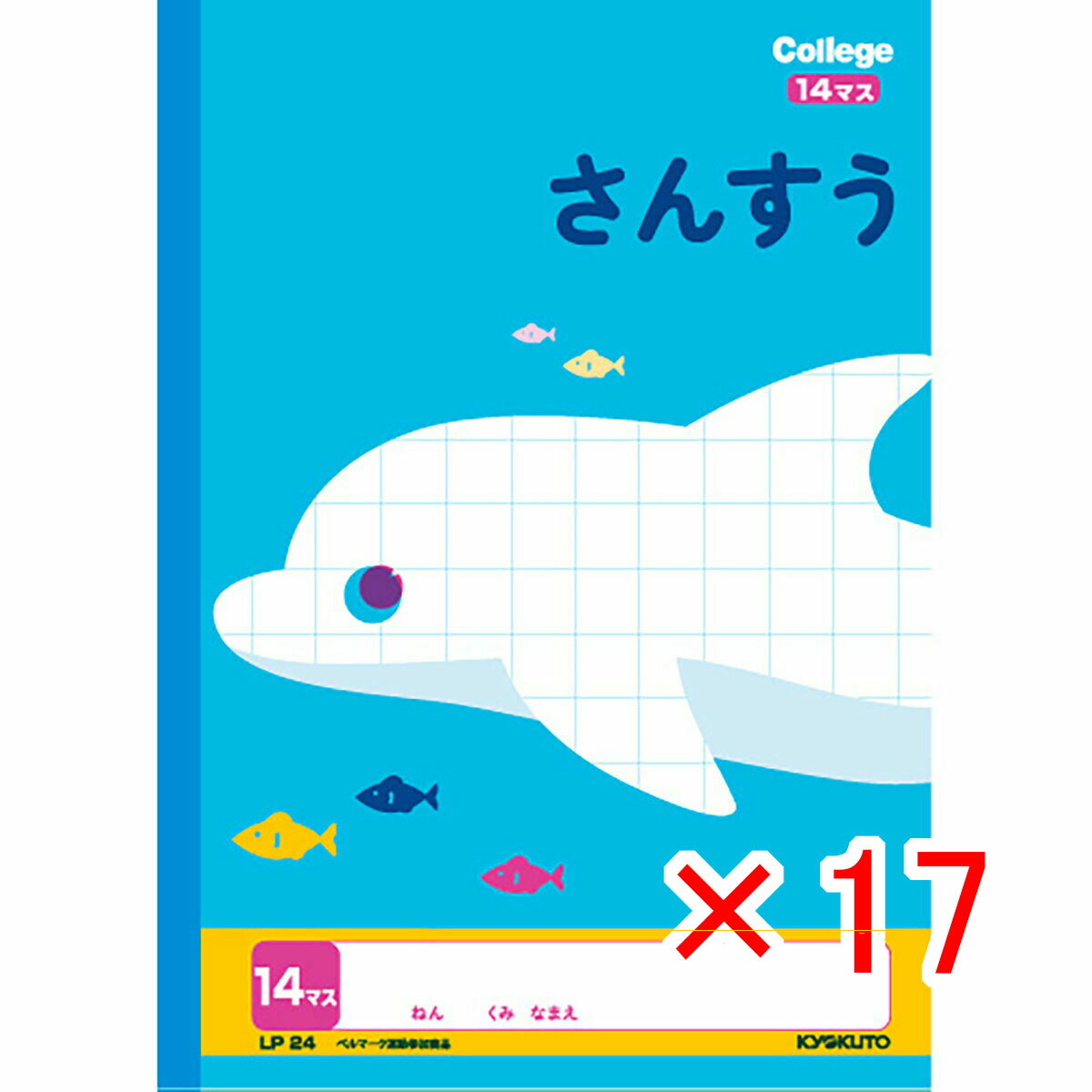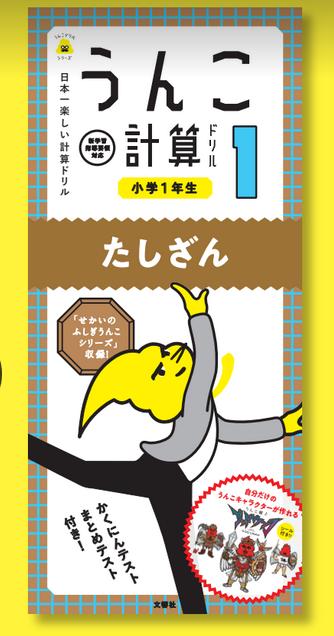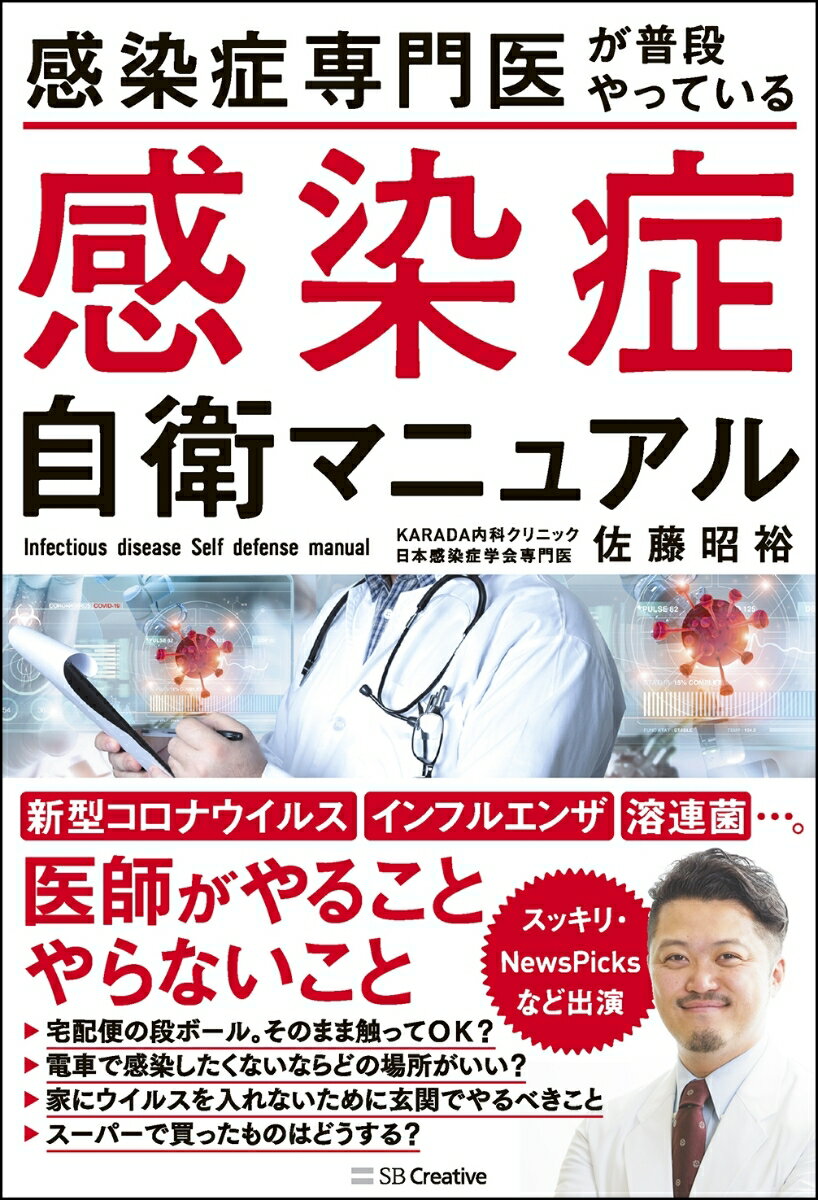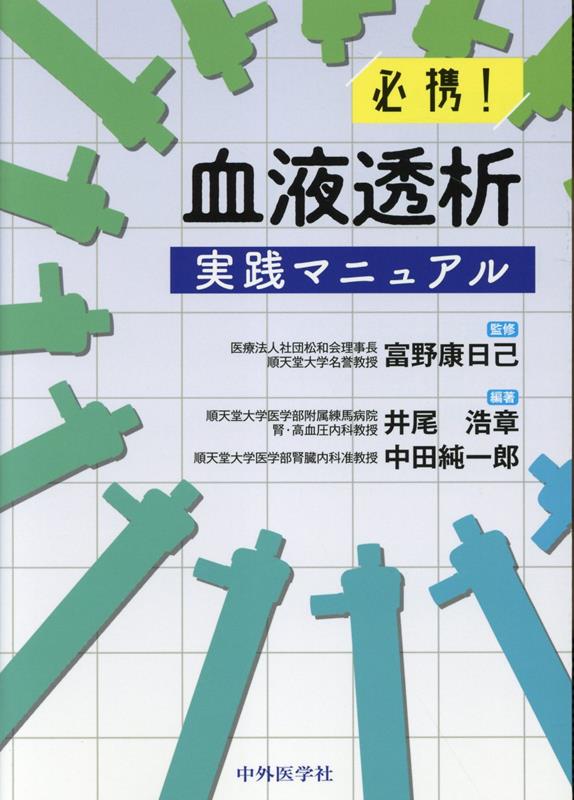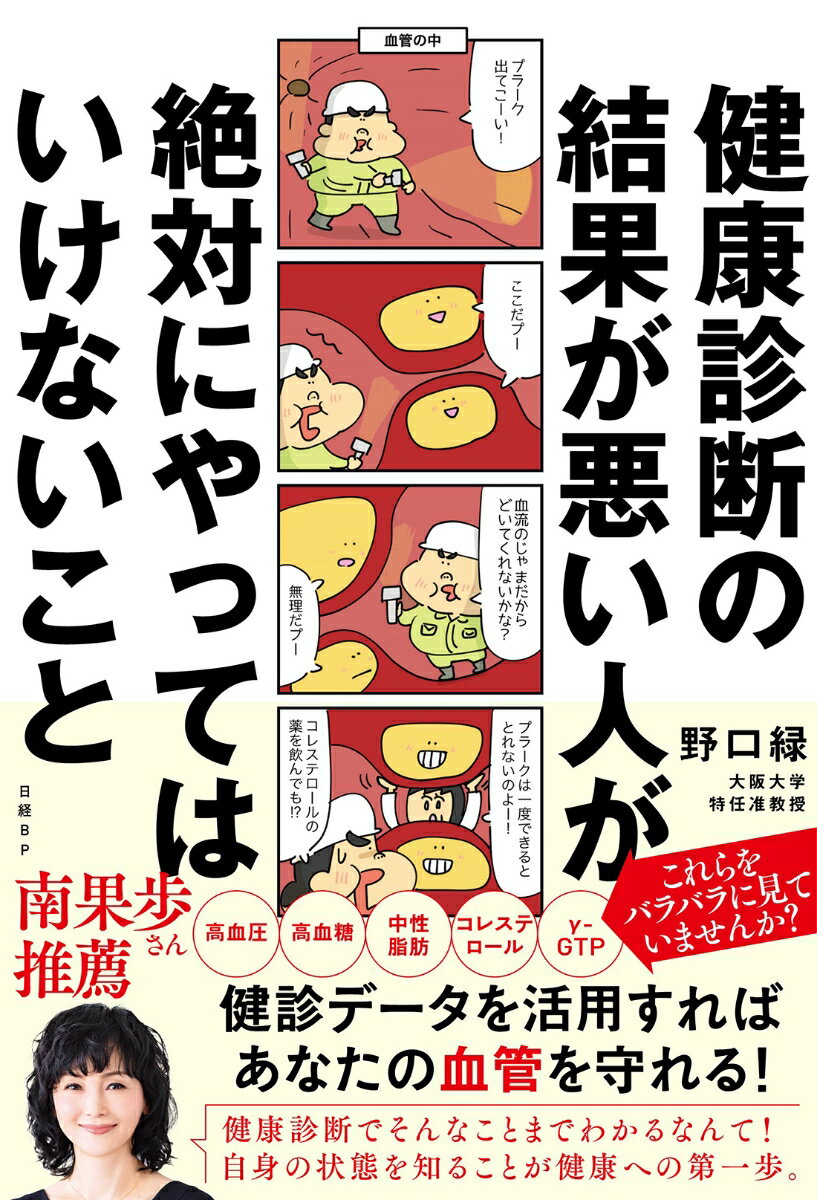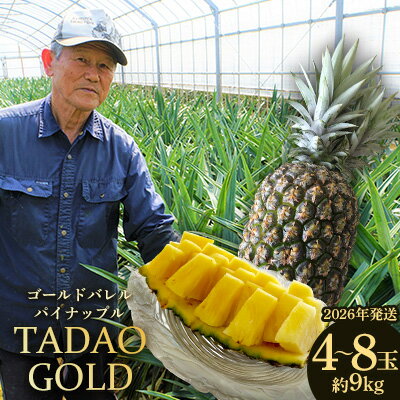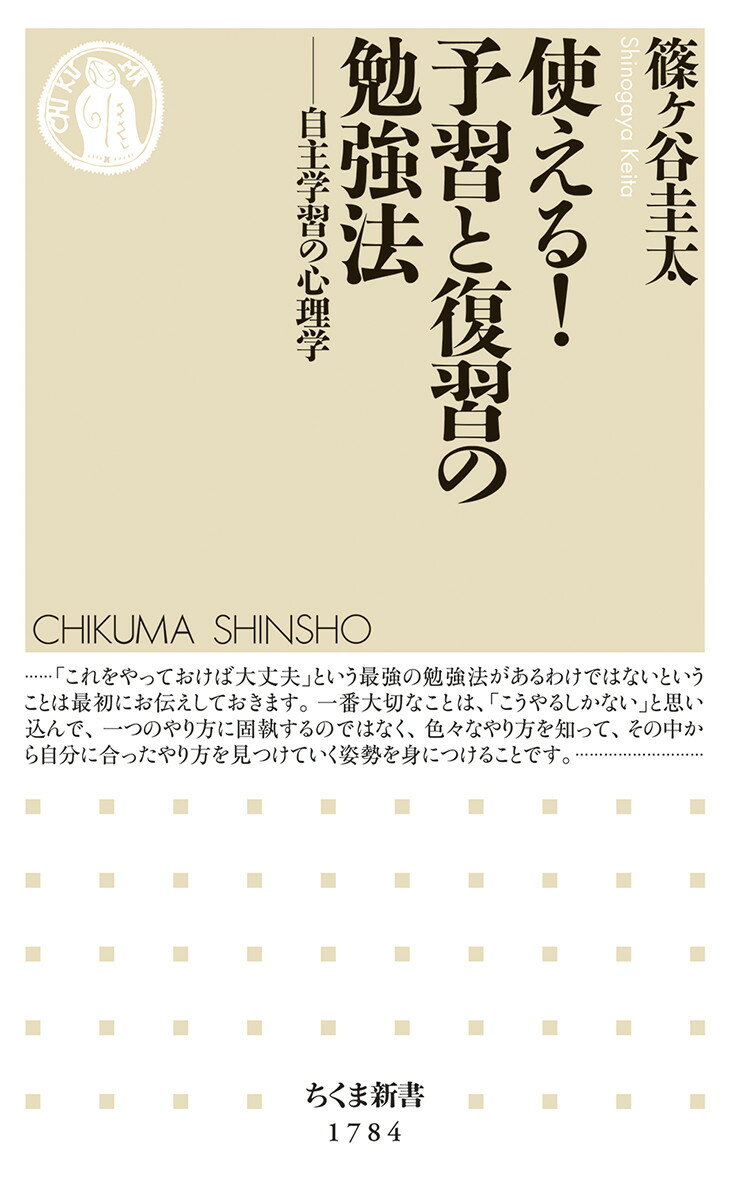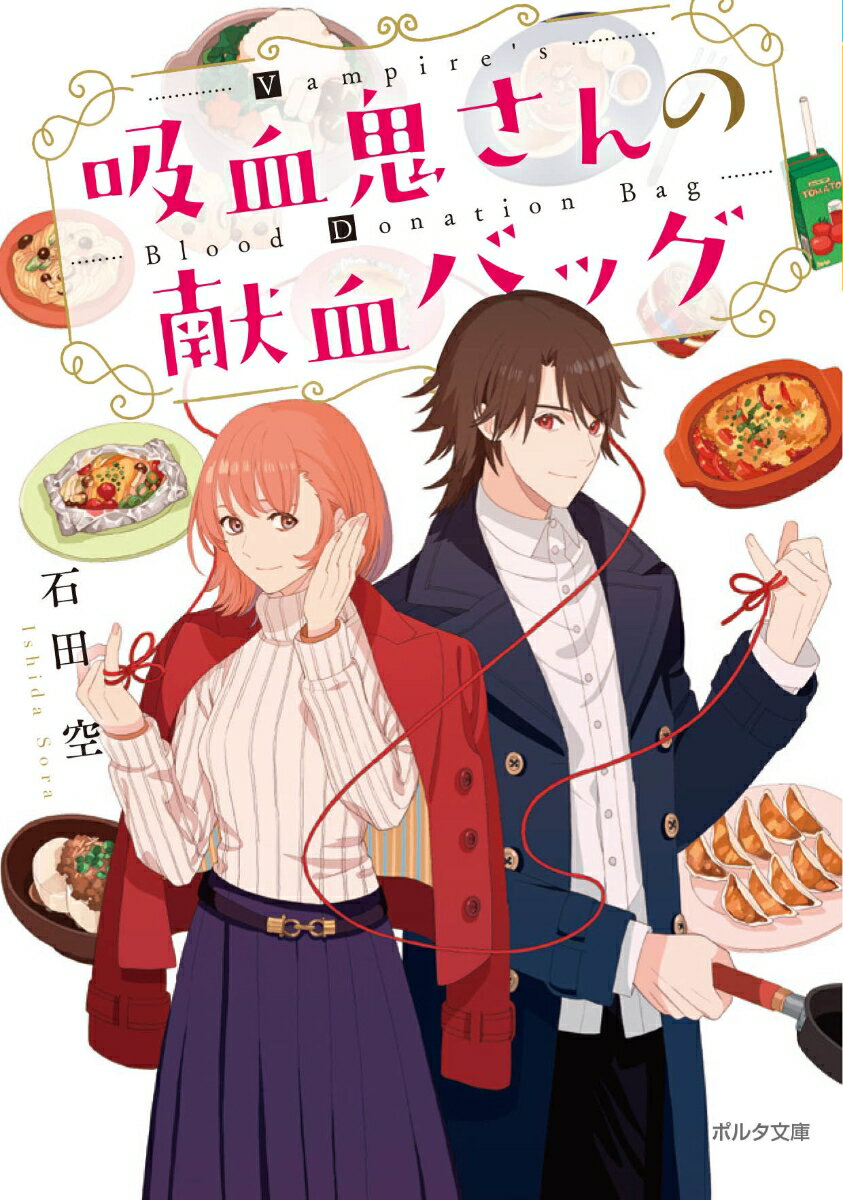【うちの子天才?】「9+2+3」を「10+5-1」で解く、小1息子の神業計算に感動!
こんにちは!毎日、子育てと格闘している父親です。
小学校に入学して数ヶ月、日々のお勉強で「あれ、今の学校ってこう教えるんだ?」と戸惑うことってありますよね。特に算数。
先日、小学1年生の息子(6歳)が 9+2+3 の計算をしているのを見て、思わず二度見してしまいました。
普通なら、
9+2=11
11+3=14
と計算しますよね。でも、うちの息子ときたら...
-
まず足す数どうしを足して 2+3=5。
-
残りの 9 と合わせて 9+5 を計算するとき、なぜか 10+5=15 を先に計算!
-
最後に「9 じゃなくて 10 にしちゃったから」と、1 を引いて 14 に。
「え、そんな回りくどいことするの?」と思いつつも、計算自体はめっちゃ早い!そして、この方法、実は私自身も無意識にやっていたんです。
この「計算のカロリーを減らす」ようなテクニック、これぞまさしく**「補数計算(ほすうけいさん)」**の考え方です。
このユニークな計算方法が、実は子どもの「数のセンス」を伸ばしてくれる理由と、学校で習う**「さくらんぼ計算」**との関係について、親目線で解説しますね!
補数計算(キリのいい数化)の3つのメリット
「10 や 100 といったキリの良い数を基準にする」という補数的な考え方は、一見遠回りですが、計算処理の負荷を劇的に下げてくれます。
1. 暗算(あんざん)力が劇的にアップする
息子のように 9+5 を 10+5−1 で計算する方法は、**「9足しは、10足して1を引く」**という定石が頭に入っている証拠です。
-
8+7 → 10+7−2(15)
-
19+8 → 20+8−1(27)
のように、繰り上がりを意識するより、**「10の位をどう操作するか」**に集中できます。暗算は、いかに「10のまとまり」を意識できるかがカギなんです!
2. 学校で習う「さくらんぼ計算」の基礎力になる
「補数計算」という言葉は学校では習いませんが、その考え方は小学1年生で習う**「さくらんぼ計算」**そのものです。
「さくらんぼ計算」は 8+5 のとき、足す数 5 を**「8 の補数(あと 2 で 10 になる数)」**の 2 と残りの 3 に分解します。
8+5 → 8+(2+3) → (8+2)+3=10+3=13
つまり、息子がやっているのは、さくらんぼ計算の応用編。「10 のまとまりを作ると計算が楽」という本質を理解しているからこそ、独自の工夫ができるんです。
3. 計算の「ケアレスミス」を減らせる
大きな数の計算や暗算をするとき、繰り上がりや繰り下がりで指がもたつき、間違えることがよくあります。
しかし、「キリの良い数」で一時的に計算を単純化すると、処理ステップは増えても、一つ一つの処理の難易度が下がるため、ミスの確率が減ります。特に時間制限のあるテストなどでは大きな武器になりますよ。
補数計算(工夫)を強要するデメリット
この計算方法はメリットが多い反面、**「学校のルール」**との兼ね合いで注意が必要な点があります。
過程を求められるテストで減点されるリスク
学校のテストや宿題では、**「さくらんぼ計算を使って解きなさい」**のように、指定された途中過程を求められることがあります。
そんなとき、うちの子のように「10に繰り上げてから1引く」という独自の方法で答えだけ合っていても、「考え方が違う」としてバツをつけられたり、△にされたりする可能性があります。
**「工夫できるのは素晴らしいけれど、今は学校で習った方法で解く練習も大切だよ」**と伝えてあげましょう。最終的には自分で最適な方法を選べるようになるのが理想ですね。
まとめ:親の知らない「数のセンス」を褒めて伸ばそう!
今の算数教育は、単に「答えを出す」だけでなく、「どういう考え方で答えにたどり着いたか」を重視しています。
息子さんの計算方法(10+5−1)は、まさに数の構造を直感的に理解し、「いかに楽するか」を追求した結果です。
親世代が習っていないからといって否定せず、「面白いね!どうしてその方法でやったの?」と聞いてあげてください。その会話が、お子さんの**「数のセンス」**を育む最高の栄養になりますよ!