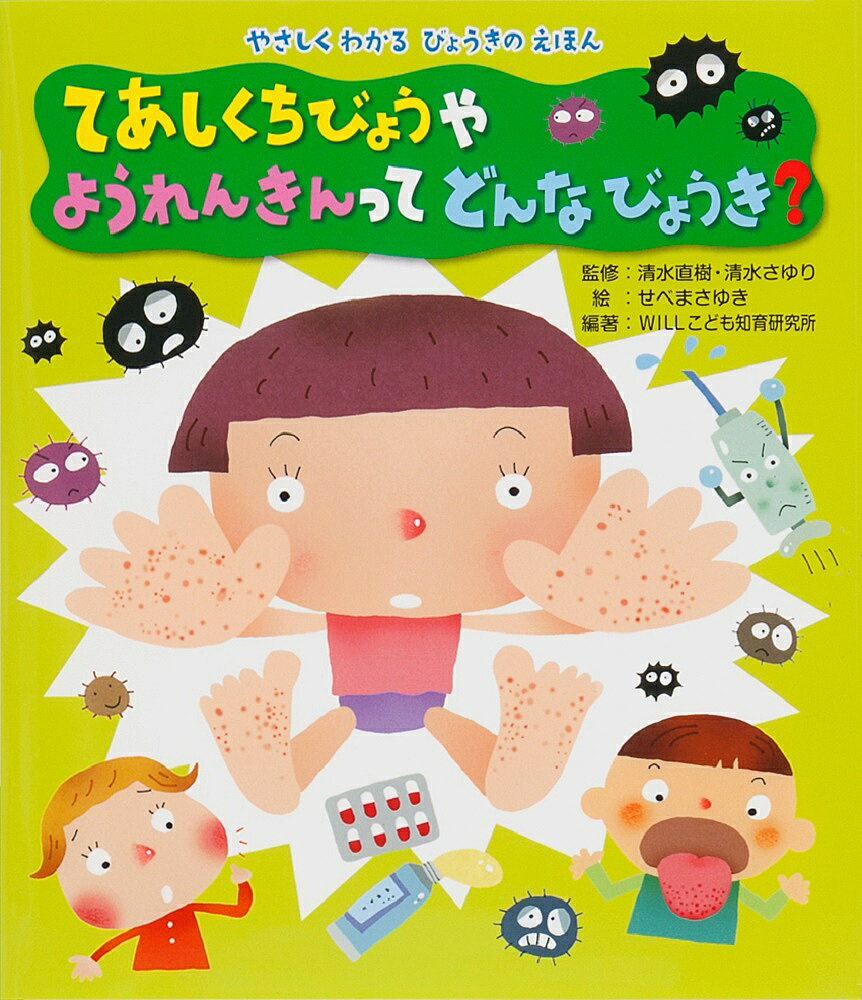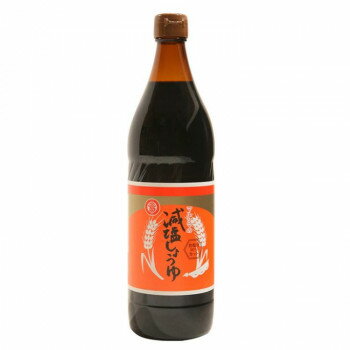知ってる? レギュラーとハイオク、何が違うの? セルフスタンドで隣のクルマが気になった話
先日、いつものようにセルフのガソリンスタンドで給油していた時のこと。
隣に止まったクルマが、僕とまったく同じ車種だったんです。なんだか嬉しくなってチラッと見ると、なんとそのオーナーさんは「ハイオク」を選んでいるではありませんか。
「あれ?このクルマ、レギュラーじゃなかったっけ…?」
僕自身、教習所でガソリンの種類について詳しく習った記憶もなく、
何となく「レギュラー=普通」「ハイオク=高いクルマ用」というイメージしかなかったので、なんだかとても気になってしまいました。
今回は、僕と同じように「ハイオクって何?」と思っている方のために、レギュラーとハイオクの違いについて、少し掘り下げて調べてみました。
そもそも、レギュラーとハイオクは何が違うの?
結論から言うと、一番大きな違いは**「オクタン価」**です。
オクタン価とは、ガソリンの「ノッキング(異常燃焼)」のしにくさを示す数値のこと。
この数値が高いほど、ガソリンは燃えにくく、エンジン内で予期せぬタイミングで爆発してしまう現象(ノッキング)を起こしにくくなります。
-
レギュラーガソリン: オクタン価は89以上。一般的な乗用車は、このレギュラーガソリンでの使用を前提に設計されています。
-
ハイオクガソリン: オクタン価は96以上。「ハイオク」は「ハイ(高い)オクタン価」の略です。レギュラーよりもノッキングが起こりにくいため、高出力なエンジンや高い圧縮比のエンジンに適しています。
つまり、同じガソリンでも、配合されている成分や添加剤が違うんです。
【メリット1】 エンジン本来の性能を引き出す
ハイオクガソリンは、高いオクタン価を活かして、エンジンの持つ本来のパフォーマンスを最大限に引き出すことができます。
特に、高性能なエンジンを搭載したスポーツカーや高級車は、高い圧縮比で燃焼させることでパワーを出しています。
この時、レギュラーガソリンだとノッキングが起きやすくなるため、車のコンピューターが自動で点火時期を遅らせてノッキングを防ぎます。しかし、これではせっかくのエンジンの性能がフルに発揮されません。ハイオクを使用することで、ノッキングを気にせず、エンジンの設計通りのパワフルな走りが実現できるというわけです。
【メリット2】 エンジン内部をクリーンに保つ
多くのハイオクガソリンには、エンジン内部を洗浄する効果を持つ「清浄剤」が添加されています。
この清浄剤が、インジェクターや吸気バルブなどに付着したカーボンなどの汚れを落とし、エンジンのコンディションを良好に保ってくれます。
エンジン内部がきれいだと、燃料の噴射効率が良くなり、結果的に燃費の向上や、エンジンの寿命を延ばすことにも繋がります。
【メリット3】 レスポンスが良くなり、静粛性も向上
ハイオクガソリンを使用することで、アクセルを踏み込んだ時のレスポンスが滑らかになったり、加速時のモタつきが改善されたりすることがあります。
また、ノッキングが起こりにくくなるため、エンジンの振動や騒音が低減され、より静かで快適なドライビングが楽しめることも、隠れたメリットと言えるでしょう。
【デメリット】やっぱりコストはかかる
良いことずくめのように感じるハイオクガソリンですが、最大のデメリットはやはり**「価格」**です。
レギュラーに比べて1リットルあたり約10円ほど高価になることがほとんど。日常的に長距離を運転する方にとっては、年間で考えると無視できない差額になってしまいます。
また、「レギュラー指定のクルマにハイオクを入れても、特にメリットはない」という点も知っておくべきです。
レギュラーガソリン用に設計されたエンジンでは、ハイオクの持つ高いオクタン価を活かしきれないため、性能向上は期待できません。場合によっては、かえって燃費が悪化するケースもあるため、注意が必要です。
まとめ|大切なのは「指定燃料」を守ること
僕の隣のクルマのオーナーさんがなぜハイオクを入れていたのかは分かりませんが、もしかしたら、エンジンのコンディションを保つためにハイオクを選んでいたのかもしれませんね。
今回の件で改めて分かったのは、自分のクルマに合ったガソリンを入れることが何よりも大切だということ。給油口のフタや取扱説明書に必ず「指定燃料」が記載されているので、まずはそこを確認してみましょう。
-
レギュラー指定のクルマ → 基本はレギュラーでOK!
-
ハイオク指定のクルマ → ハイオクを入れないとエンジンの性能が発揮できない!
「ハイオクは高いからレギュラーでいいや」と安易に考えてしまうと、エンジンの寿命を縮めてしまう可能性も。愛車を長く大切に乗り続けるためにも、ぜひ今回の記事を参考に、正しいガソリンを選んでみてくださいね!