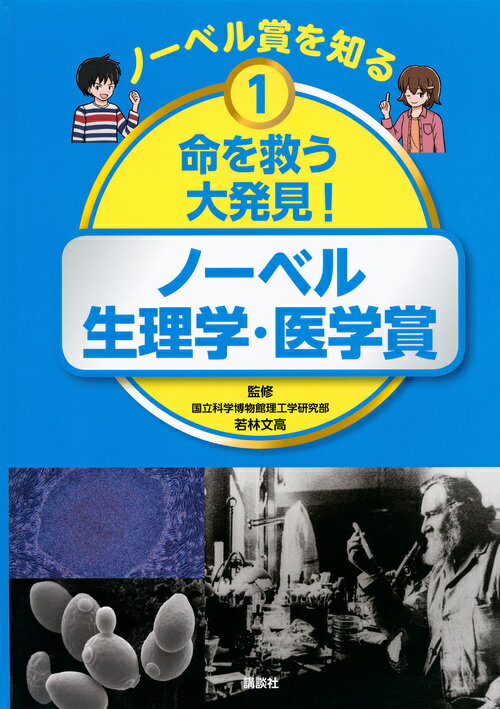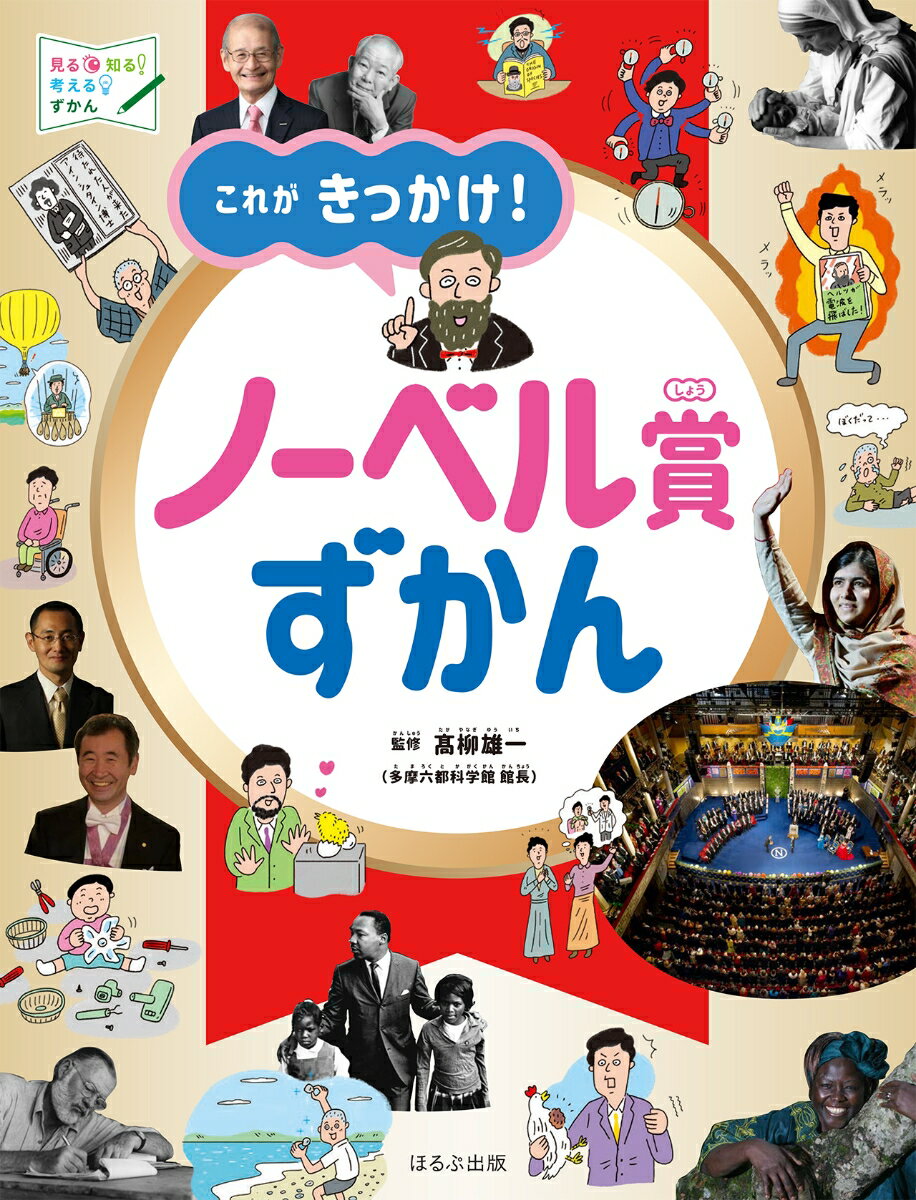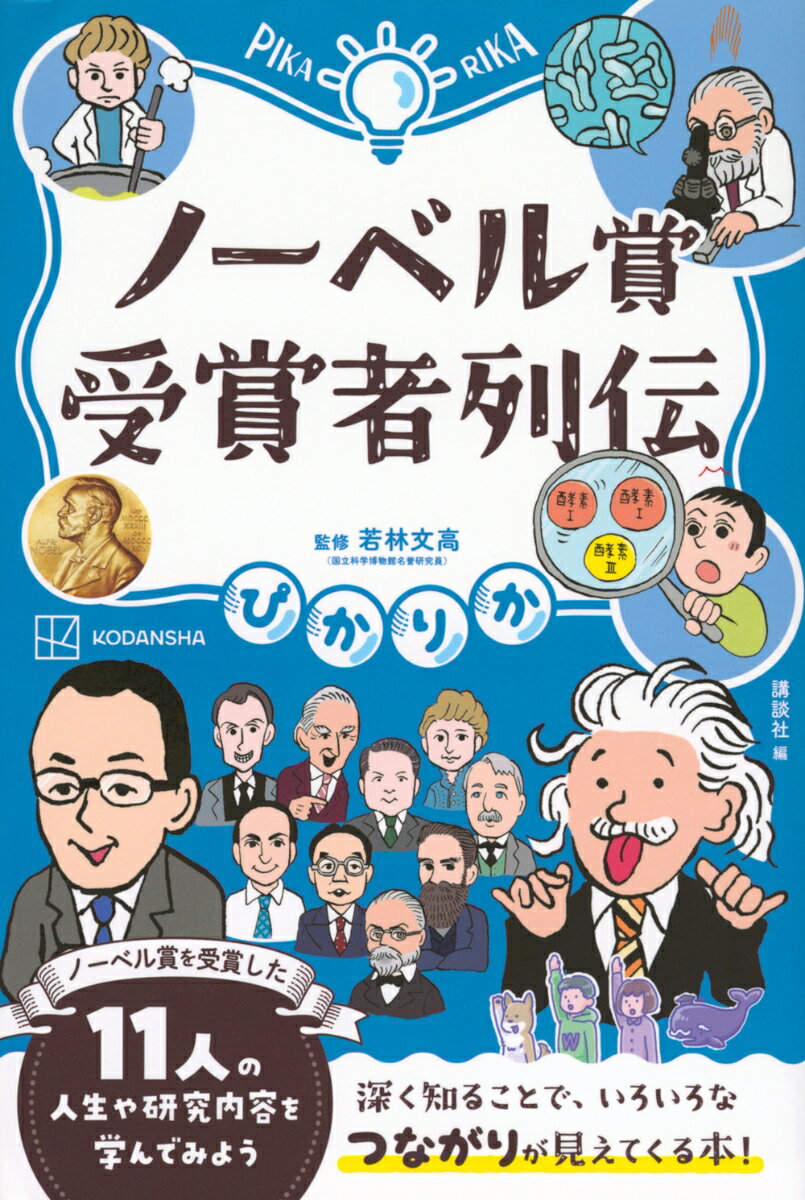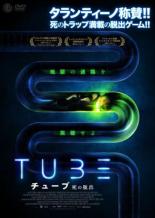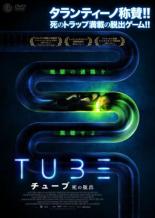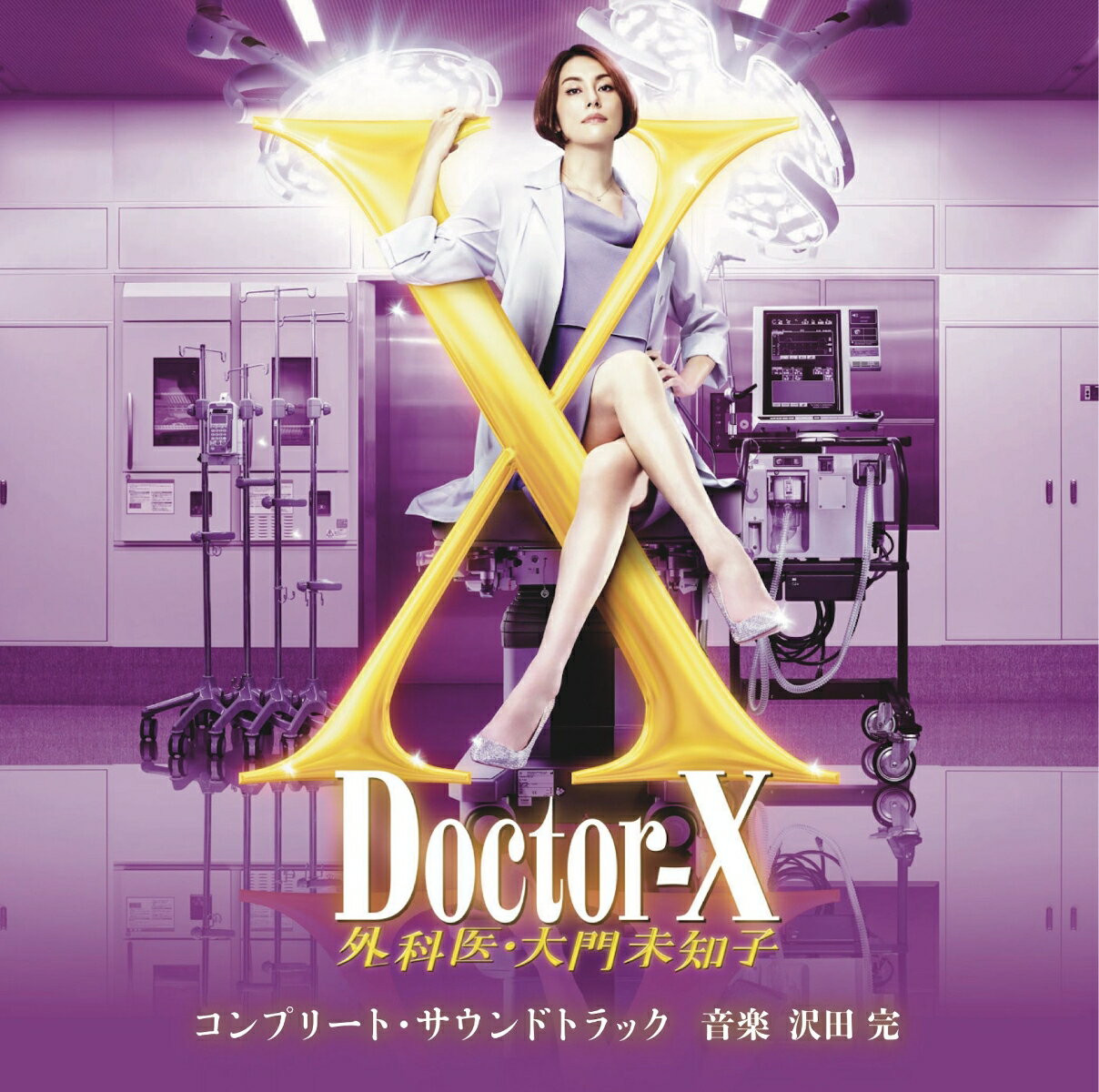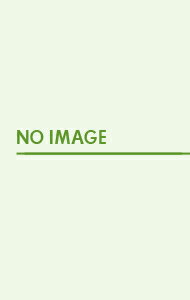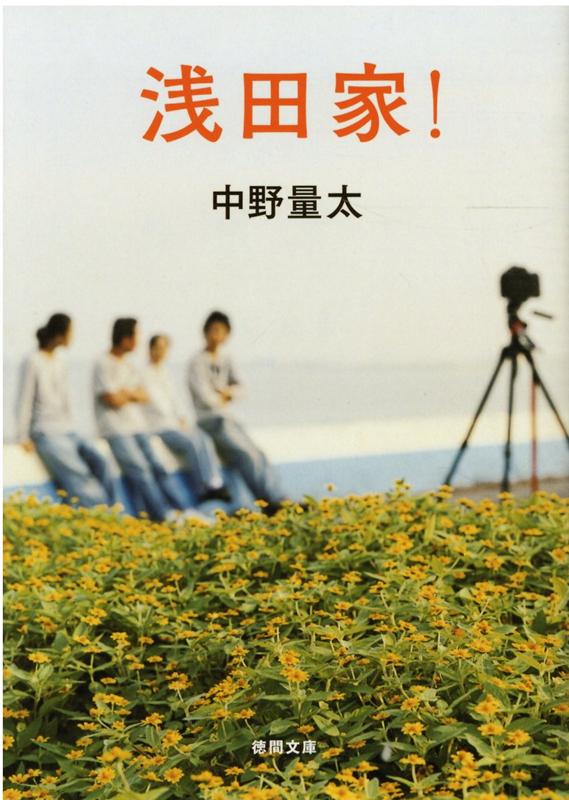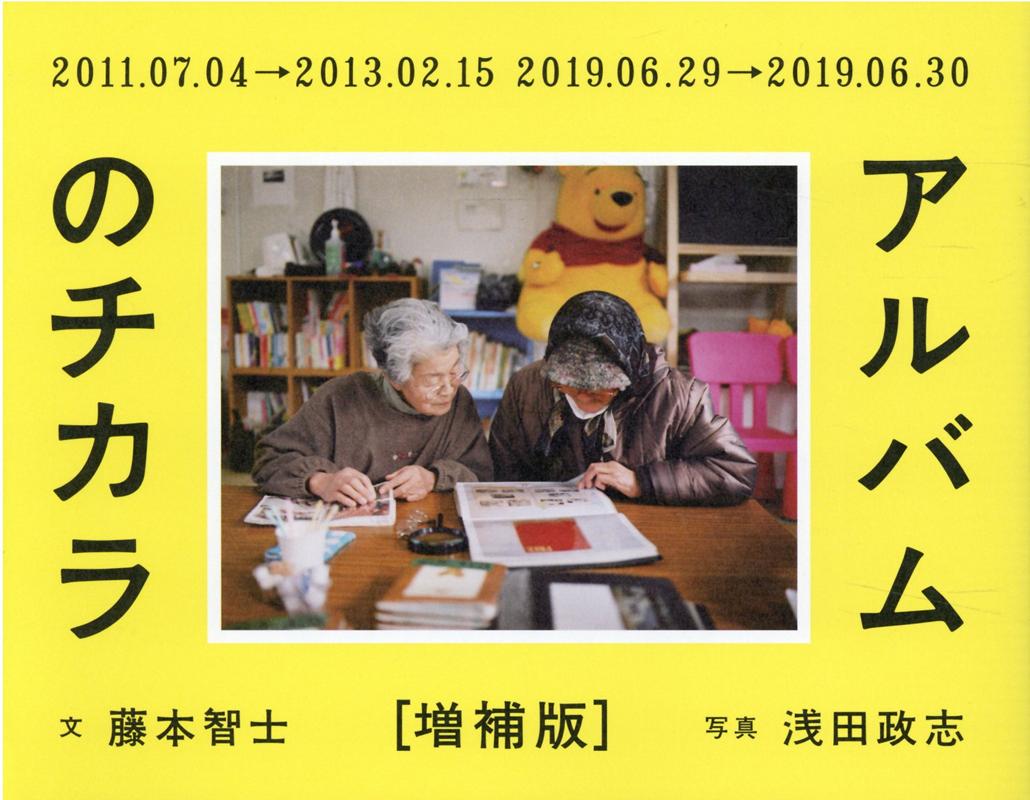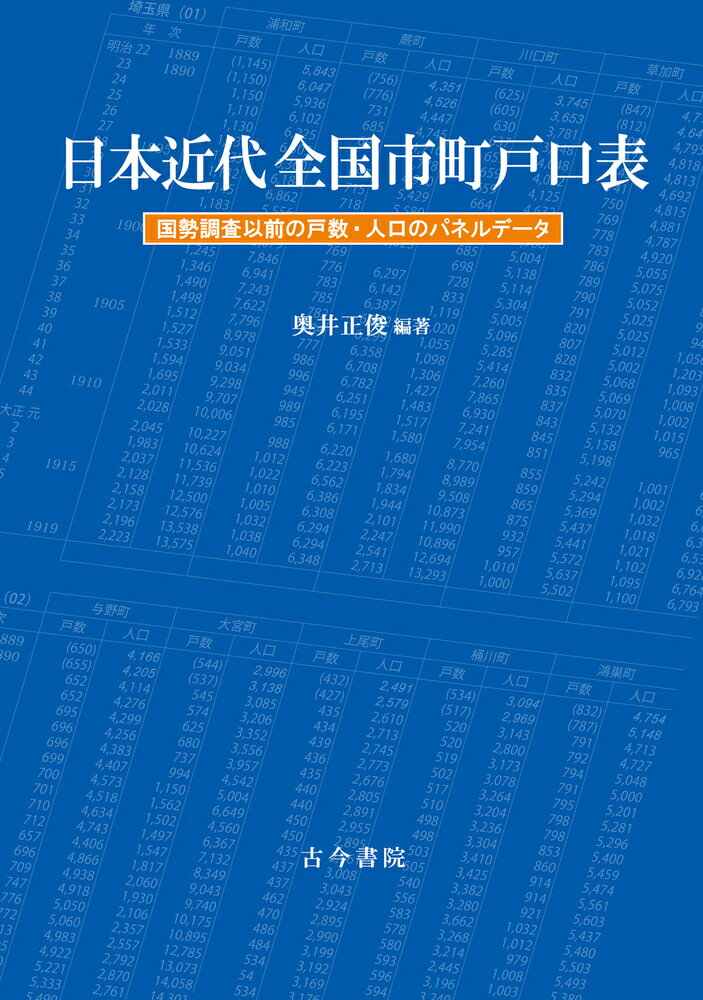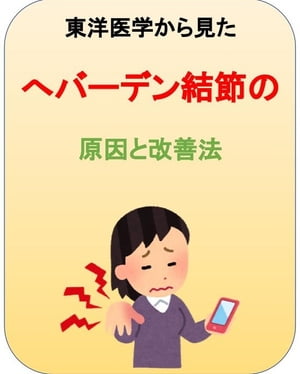【ノーベル賞2025】日本人が快挙!「暴走する免疫」にブレーキをかけた"静かなヒーロー"Treg細胞って何?
科学のニュースって難しそうだけど、実は私たちの子育て世代の生活や健康に直結することばかり。特に今年は、私たち日本人の先生が受賞されて、すっごく身近な話題になりました!
早速ですが、今年のノーベル生理学・医学賞に輝いた、坂口志文(さかぐち しもん)先生の偉大な発見について、お子さんにも説明できるくらい簡単に、面白おかしく僕なりに解説していきますね!
1. 免疫システムの「暴走」を止めたヒーロー!
今年のノーベル生理学・医学賞の受賞理由は、
坂口先生が発見した「制御性T細胞(Treg:ティーレグ)」の存在と、
その機能の解明です。
簡単に言うと、私たちの体を守っている免疫細胞の**「静かなるブレーキ役」**を見つけたんです。この発見が、これまで治りにくかった多くの病気の治療を根本から変える可能性を秘めていると評価されました。
ちなみに坂口先生は、京都大学医学部を卒業して医師免許も持っているのですが、ご自身で「病気を治すには、その裏にあるサイエンス(メカニズム)を知らないと!」と考えて、臨床ではなく基礎研究の道に進んだ、熱い情熱を持った科学者なんです。
医師としての視点も持ち合わせているからこそ、この発見の重要さに気づけたのかもしれませんね。
2. 免疫の「お行儀の悪さ」を正す
私たちの体の免疫システムは、**外から入ってきた敵(ウイルスや細菌)**を見つけると、T細胞などの攻撃部隊を送り込んで一掃してくれます。これは頼もしい防衛隊ですね。
ところが、この防衛隊が時々暴走して、自分の体の細胞を敵と間違えて攻撃し始めるという、大変お行儀の悪い行動に出ることがあるんです。これが、自己免疫疾患(関節リウマチ、I型糖尿病、アレルギーなど)の原因です。
坂口先生の発見以前は、「なんで免疫は自分の体を攻撃しないんだろう?」という疑問(自己寛容のメカニズム)は、謎に包まれていました。
3. 簡単に言うと:「制御性T細胞」は、免疫の交通整理係!
この難しかった謎を解き明かしたのが、**制御性T細胞(Treg)**です。このTregの役割こそ、今回のノーベル賞の核となる部分です。
お子さんに説明するなら、Tregは「免疫パトロール隊の交通整理係」のようなイメージです。
まず、体内の攻撃部隊(T細胞など)を、街を守るパトカーに例えてみましょう。パトカーは「敵だ!」と思ったらすぐに追いかける、頼もしい存在です。
そして、**制御性T細胞(Treg)**こそが、免疫パトロール隊の「交通整理係」であり、「ブレーキ役」です。「ちょっと待った!それは味方だから攻撃しちゃだめだよ!」と静かに指示を出し、パトカーの暴走(自己攻撃)を食い止めているのです。
Tregがきちんと働いていれば、パトカーが味方を攻撃するのを防ぎ、体は平和に保たれます。逆にTregが弱ったり少なくなったりすると、パトカーが暴走して味方(自分の体)を攻撃し始める、というわけです。
4. 今後、医療にどう関わってくる?(将来の「儲かる」話)
この発見が素晴らしいのは、治療法がガラッと変わる可能性があるからです。Tregは、薬そのものではありませんが、これを操作することで様々な病気を治そうという研究が進んでいます。
まず、自己免疫疾患やアレルギーの場合。これは免疫の**「暴走」**なので、治療戦略としてはTregを増やしたり、強化したりして、免疫の「ブレーキ」をしっかり効かせます。これが成功すれば、副作用の少ない根本的な治療につながります。
次に、がん治療の場合。がん細胞は、このTregを味方につけて免疫の攻撃から逃れています。そのため、Tregの機能を一時的に弱めたり、排除したりすることで、免疫の「ブレーキ」を外し、がんを攻撃する力をアップさせます。
また、腎臓移植などの臓器移植の場合も重要です。
移植後の拒絶反応は免疫の過剰な攻撃なので、Tregを投与し、拒絶反応だけをピンポイントで抑える研究も進んでいます。
透析患者さんの腎臓移植の予後改善に大きく貢献する可能性があり、これが成功すれば、移植後の強い免疫抑制剤の使用量が減り、患者さんの生活が一変します。
このように、Tregの働きをコントロールする薬や細胞療法は、「次世代の治療法」として巨大な製薬会社が開発競争を始めています。この発見は、私たちの子どもたちが大人になる頃には、多くの難病を治すための**「当たり前の技術」**になっているかもしれませんね。
5. まとめ
坂口先生の発見は、地道な基礎研究が、いかに人類の健康に大きな貢献をするかを教えてくれました。
「免疫細胞のブレーキ役」である制御性T細胞の発見は、私たち自身の体を深く理解し、病気と闘うための新しい武器を与えてくれた大偉業です。
この素晴らしいニュースを、ぜひお子さんとの理科の話題や、お友達との雑談に取り入れてみてくださいね!