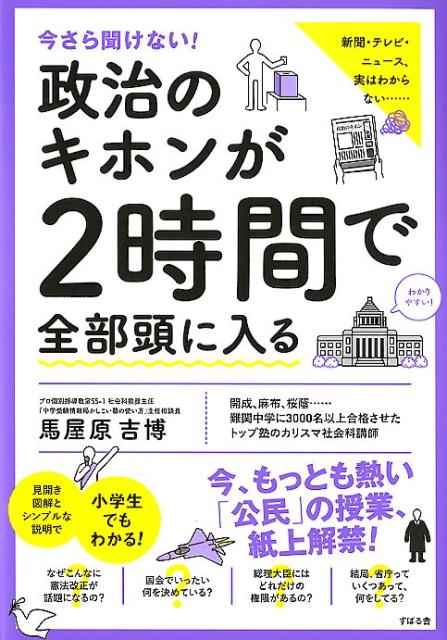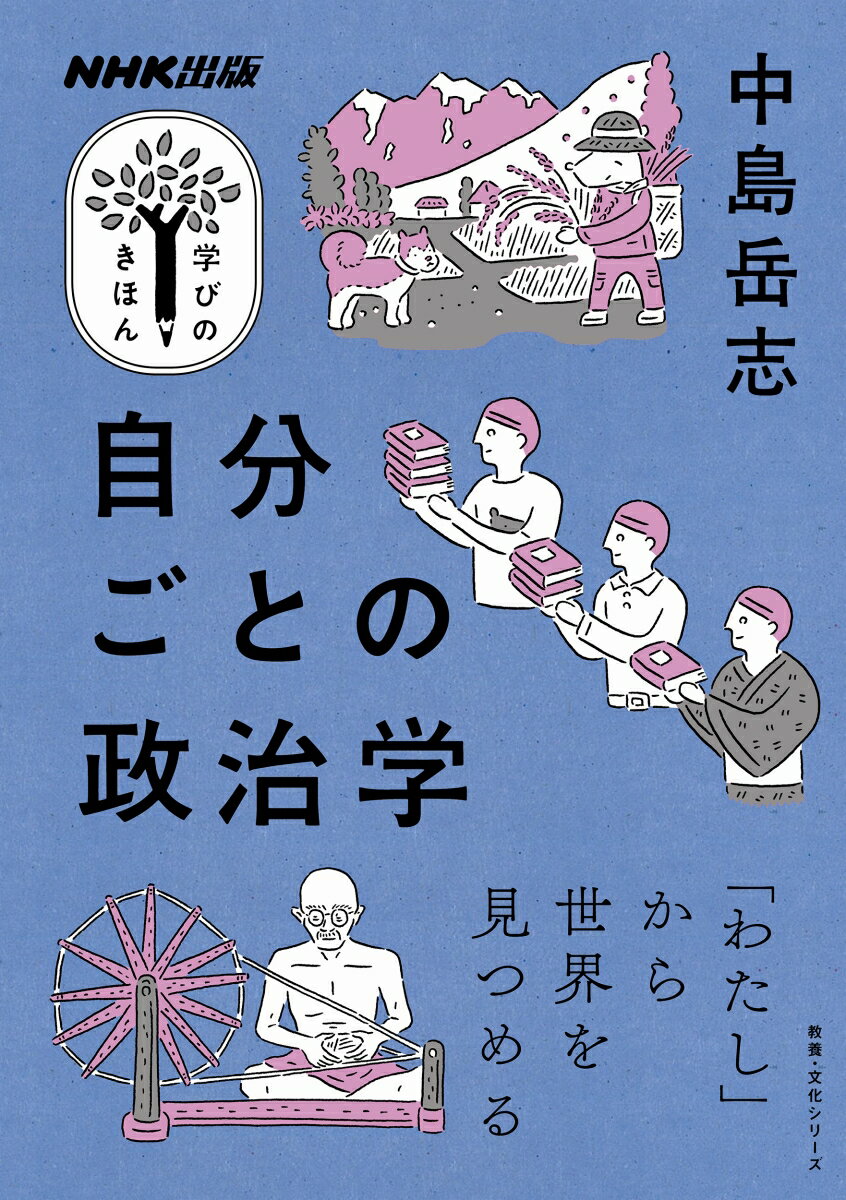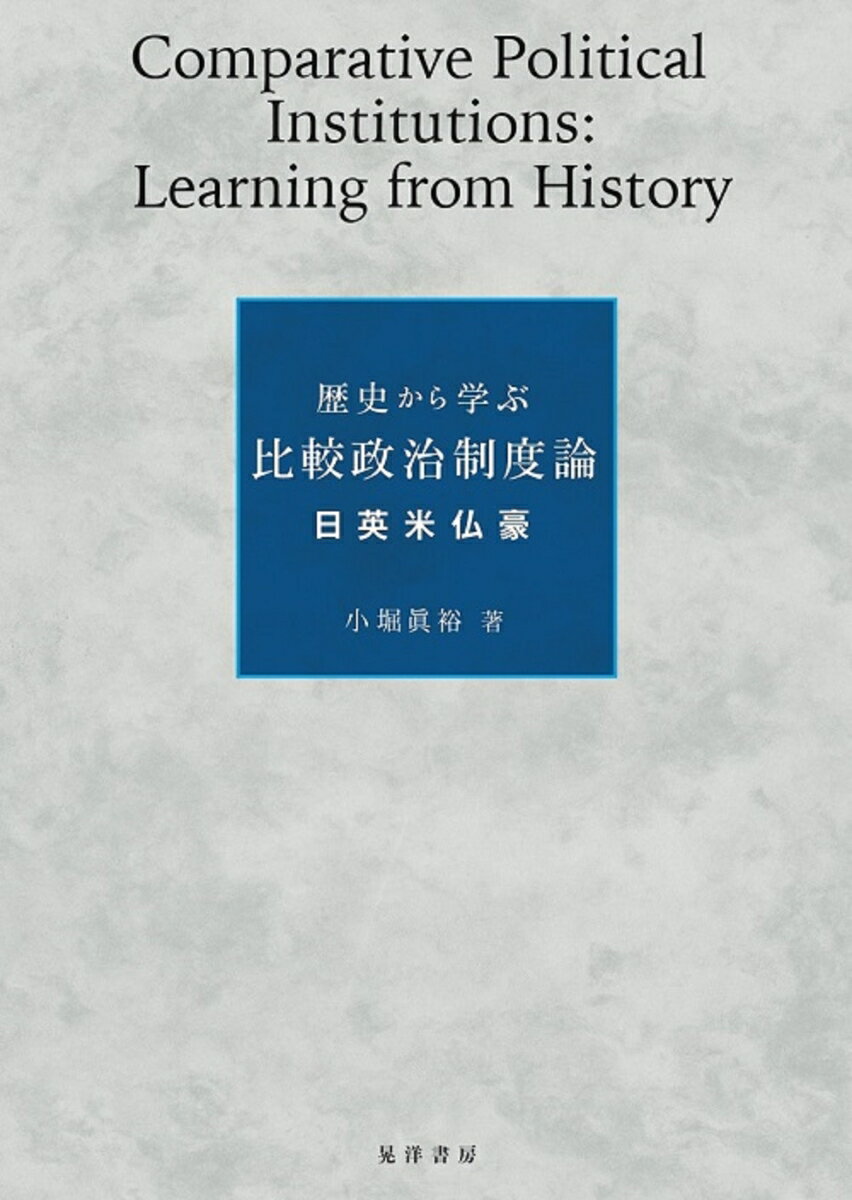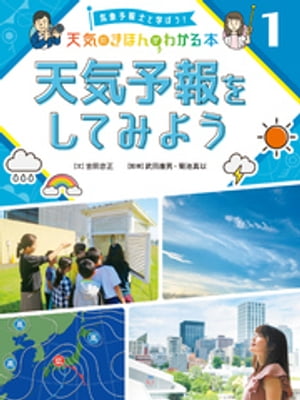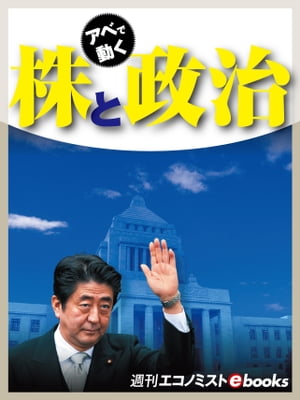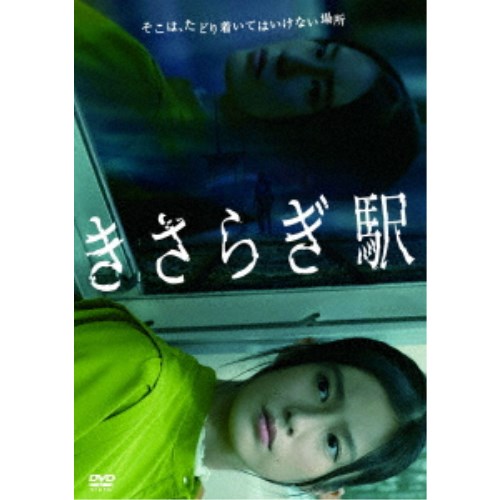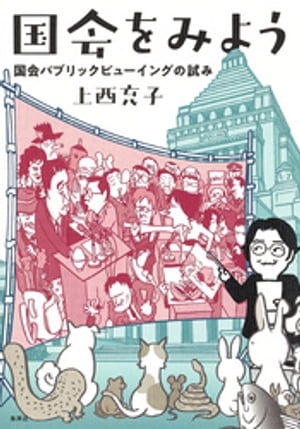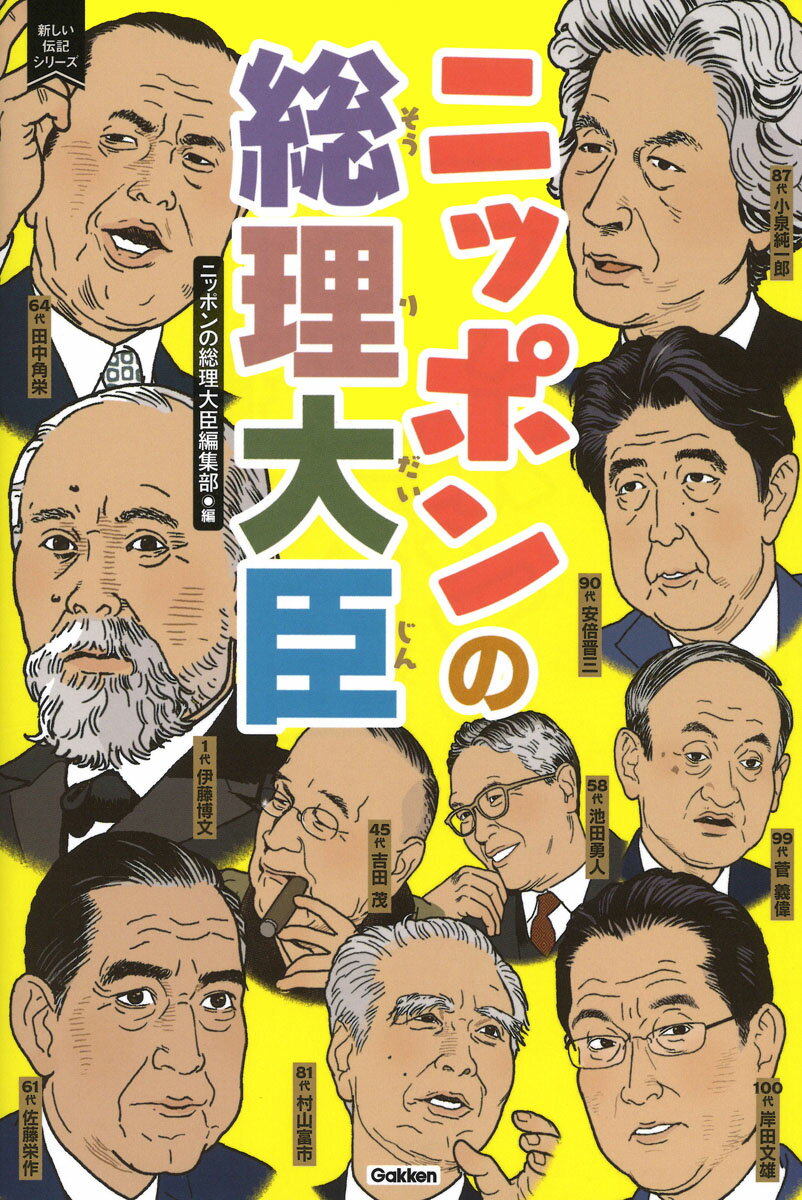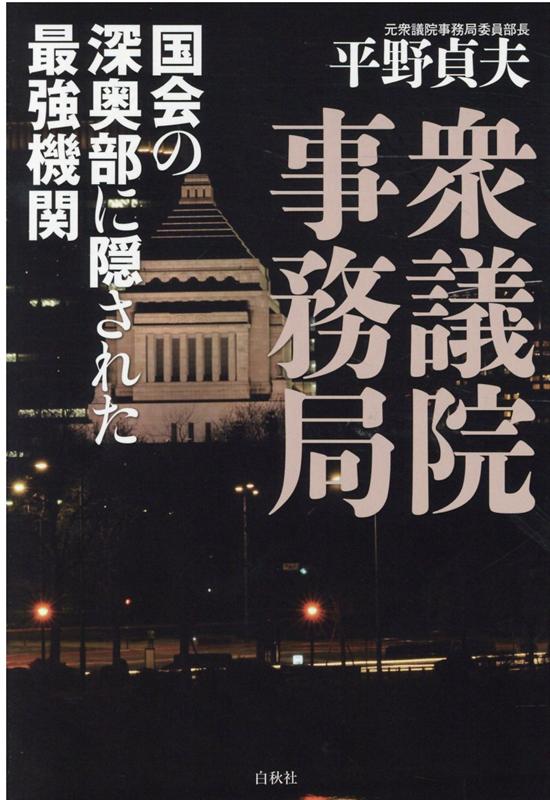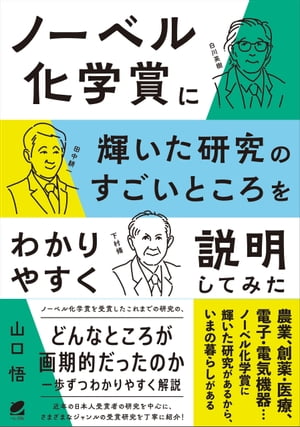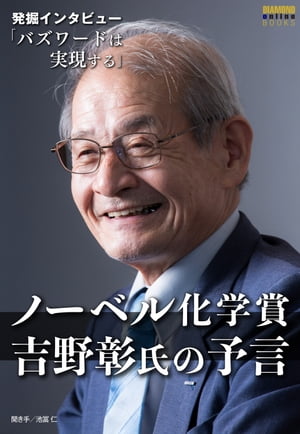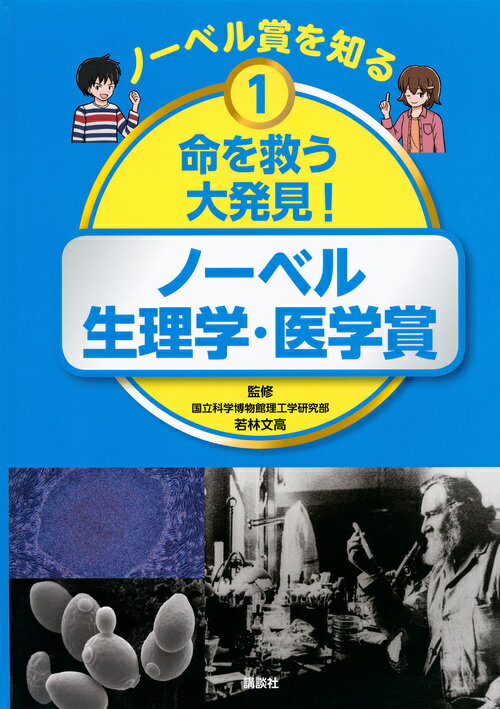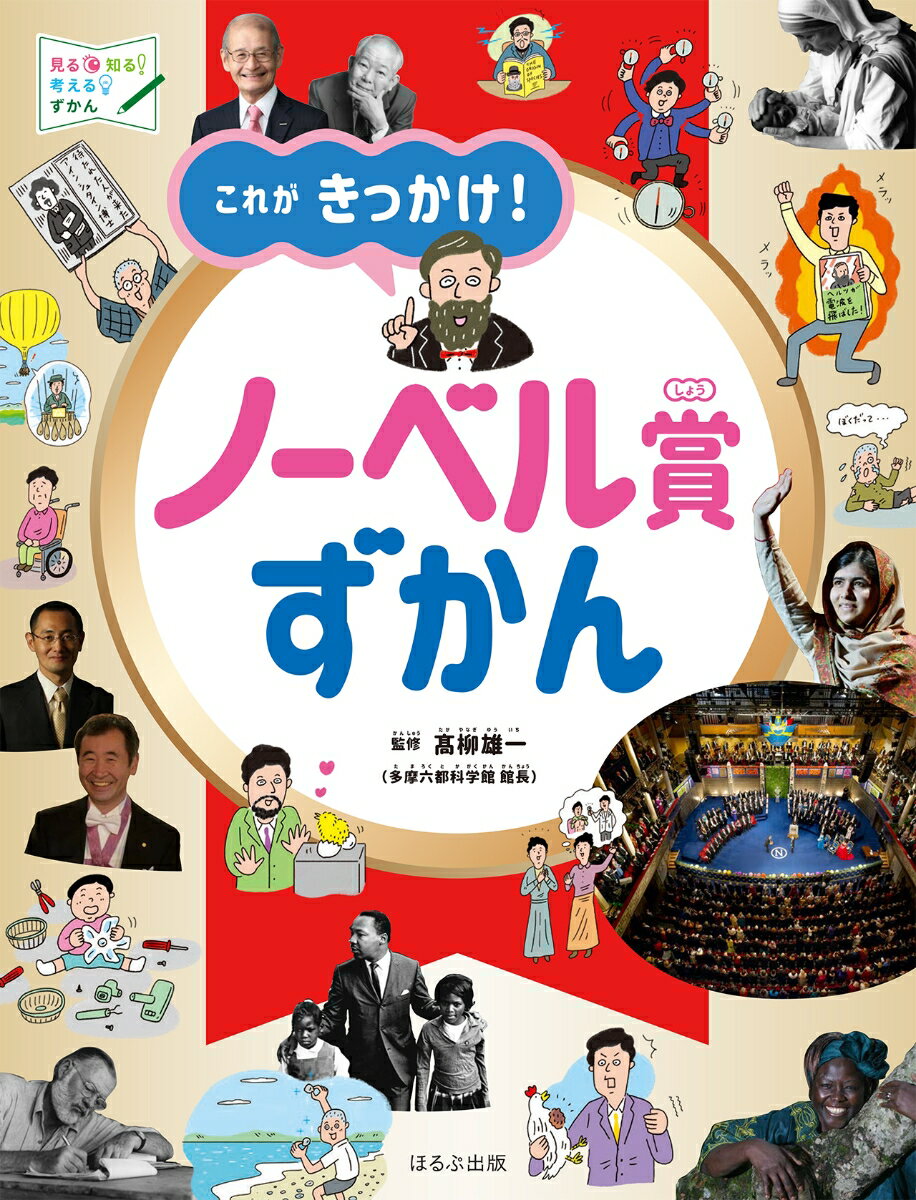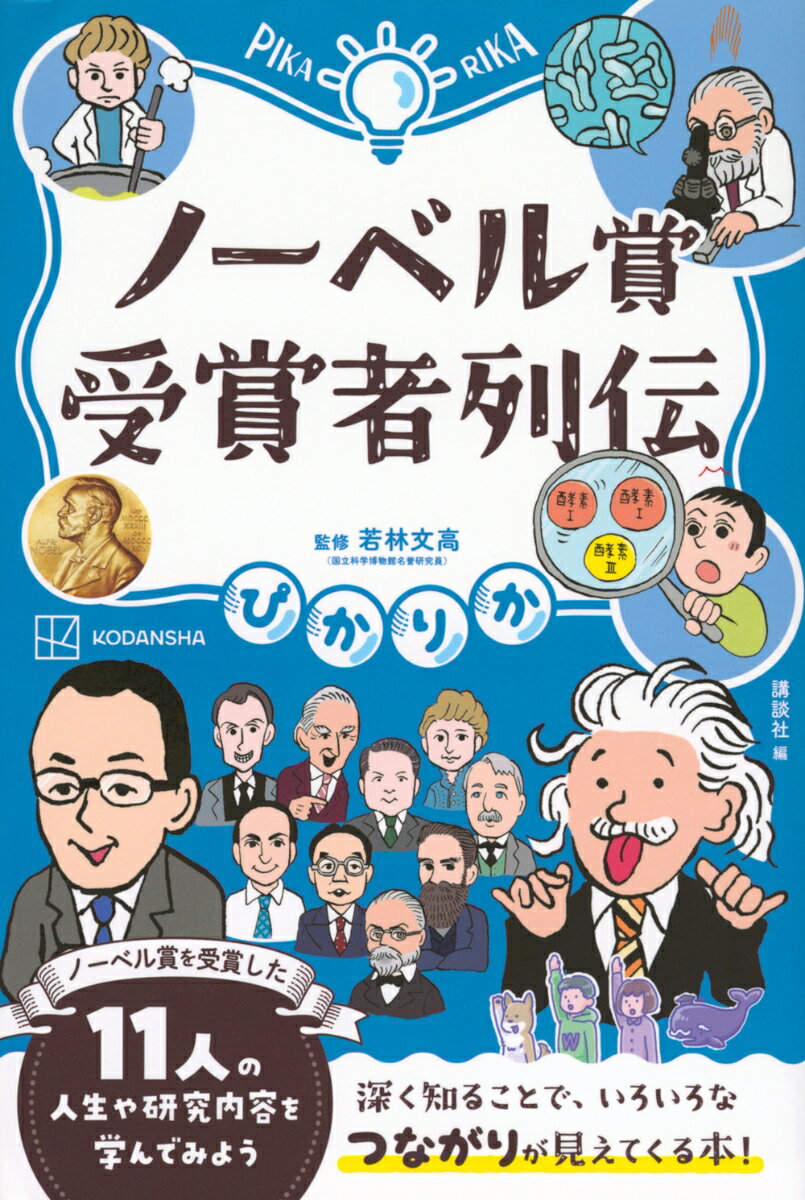【ゾクッ】都市伝説『きさらぎ駅 Re:』は「子育て世代の呪い」?意外とゲーム感覚で楽しめる理由
皆さん、こんにちは!週末の夜にこっそりホラー映画を見がちな僕です。
今回ご紹介するのは、
ネット掲示板発の超有名都市伝説を映画化した**『きさらぎ駅 Re:』**です。
「ホラーなんて怖くてムリ!」というママさんも多いと思いますが、ちょっと待って!この映画、**ホラーの皮をかぶった「現代社会の縮図」**なんですよ。
子育てや仕事で「時間がない!」と感じる私たちにこそ響く、**「専門家っぽくも語れる」**この作品の魅力をお伝えしますね。(もちろん、ネタバレはしないのでご安心を!)
きさらぎ駅って?「知らない」で済まされない現代のホラー
まず「きさらぎ駅」を知らない方のために簡単に解説。「はすみ」と名乗る女性がネット掲示板に投稿した、**「実在しないはずの駅に迷い込んだ」**という体験談が元になった都市伝説です。映画はその続編。
前作で奇跡的に生還した主人公、宮崎明日香(本田望結さん)が、今度は自分を助けてくれた先輩・堤春奈(恒松祐里さん)を救うため、再び呪われた異世界に足を踏み入れます。
<タイムリープと異世界>
本作の舞台となる異世界は、**「誰か一人が生還すると、残った人たちの記憶がリセットされて最初からやり直し」という、非常に残酷なルールで動いています。
これはホラー映画というより、まるで「セーブ&ロード機能」を持つゲームの世界。一見非科学的ですが、心理学でいう「記憶の再構築」**や、過去の過ちを何度も繰り返してしまう人間の業のようにも見えてくるのが怖いんです。
「子育てタイムライン」に似た異世界ルール
この映画の異世界、実は子育て中のママやパパにこそ共感できる部分があるんです。
-
終わりが見えないループ: 異世界では「全滅」すると記憶を持ったままやり直しに。これはまるで、「寝かしつけが成功したと思ったらまた最初から…」「家事を終わらせたと思ったら、すぐ次の家事が…」と終わりが見えない日々の家事育児のよう。
-
経験値の蓄積: 何度も失敗し、死んで(リセットされて)覚えることで、登場人物たちは「ここは危ない!」「次はこう動く!」と効率よく立ち回れるようになります。これって、初めての子育てで失敗しながら、だんだん「最短ルート」を見つけ出す私たちの姿に重なりませんか?
主人公たちが**「ホラーなのに、もはや笑える」**くらい攻略に熱中する姿は、毎日を乗り切る私たちへのエールにも見えてきますよ(笑)。
一番怖いのは「怪異」じゃなくて「現実の人間」
しかし、この物語が単なる脱出ゲームで終わらないのがミソ。
主人公・明日香は、きさらぎ駅での真実を訴えたことで、現実世界ではネット上の誹謗中傷にさらされます。「嘘つき」「頭がおかしい」—―。
異世界で襲ってくる目玉の怪異よりも、顔の見えない他人の悪意、つまり**「言葉の暴力」**の方が、よっぽど主人公を追い詰めます。
<子育て世代へのメッセージ>
これは、ママ友同士のSNSトラブルや、子育てに関する心ないネットコメントが問題になる現代への強烈な風刺です。
この映画は、「信じてもらう難しさ」「人を傷つける言葉の軽さ」という、私たちが日常で直面する**「人間ホラー」**を突きつけてきます。
ユーモアとシリアスの絶妙なバランス
「怖い話は苦手だけど、話題にはついていきたい!」という方でも大丈夫。
本作は、記憶を引き継いで何度もやり直すため、登場人物たちが怪異に慣れすぎてしまい、だんだんコミカルな言動が増えてきます。「また全滅かよ!」「次はこうするぞ!」と、まるで仲間と協力するRPGのようです。
この、シリアスとユーモアが混ざり合った独特なトーンこそ、映画に引き込まれる理由。最後まで「どうやったらクリアできるの?」という、知的好奇心が勝る作りになっています。
まとめ:「きさらぎ駅 Re:」は現代の教科書かも
『きさらぎ駅 Re:』は、都市伝説の恐怖を超えて、**「ネット社会の不寛容さ」と「終わらない日常からの脱出願望」**を描いた作品です。
ホラー映画ですが、観終わった後に残るのは、「私たちは普段、誰かの痛みを想像できているだろうか?」という社会的な問いです。
子どもの心を守りたい私たち親世代こそ、この映画を見て、現代社会の**「見えない恐怖」**について、少し考えてみるのも良いかもしれませんね。