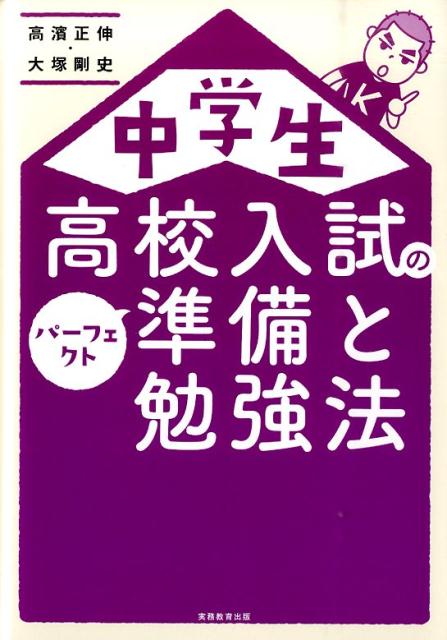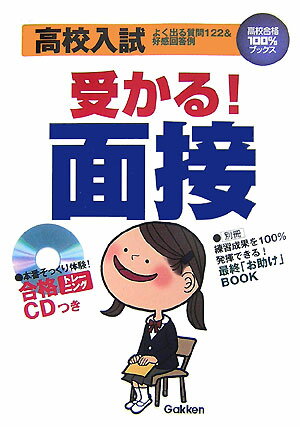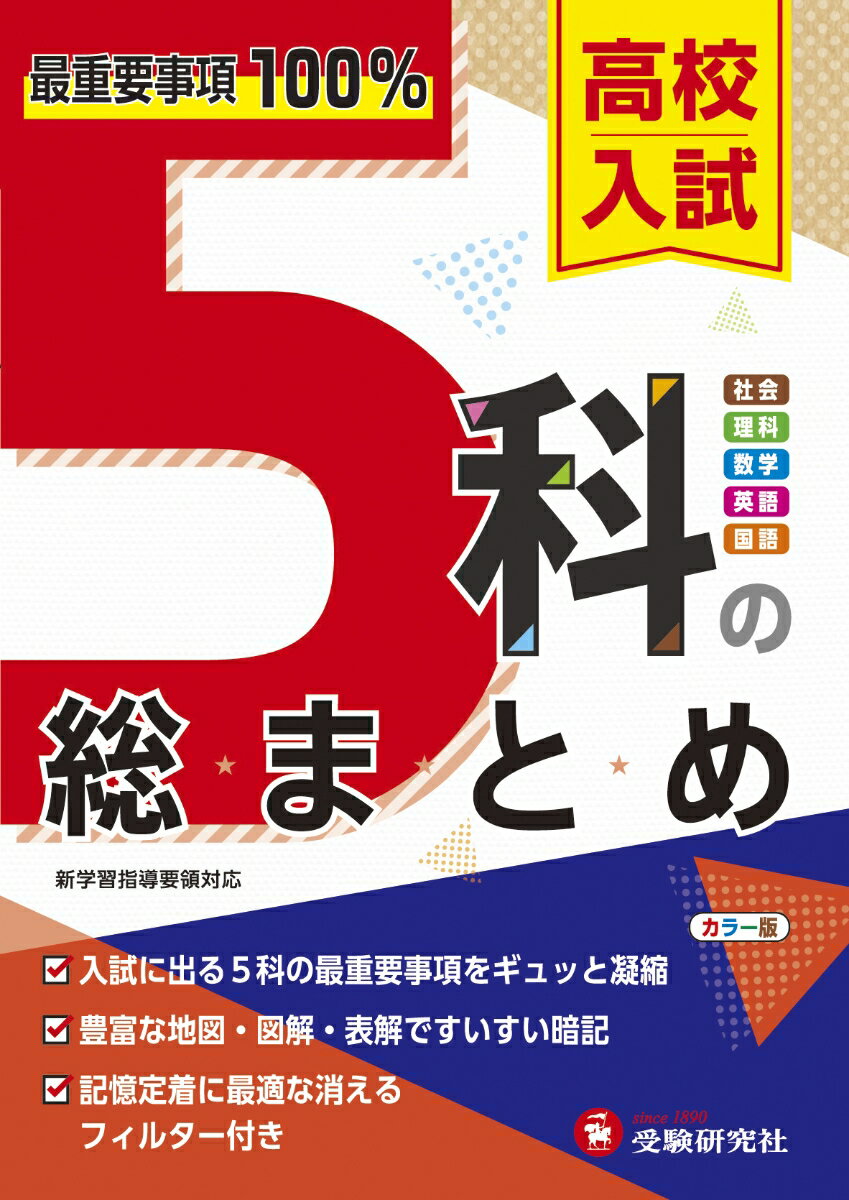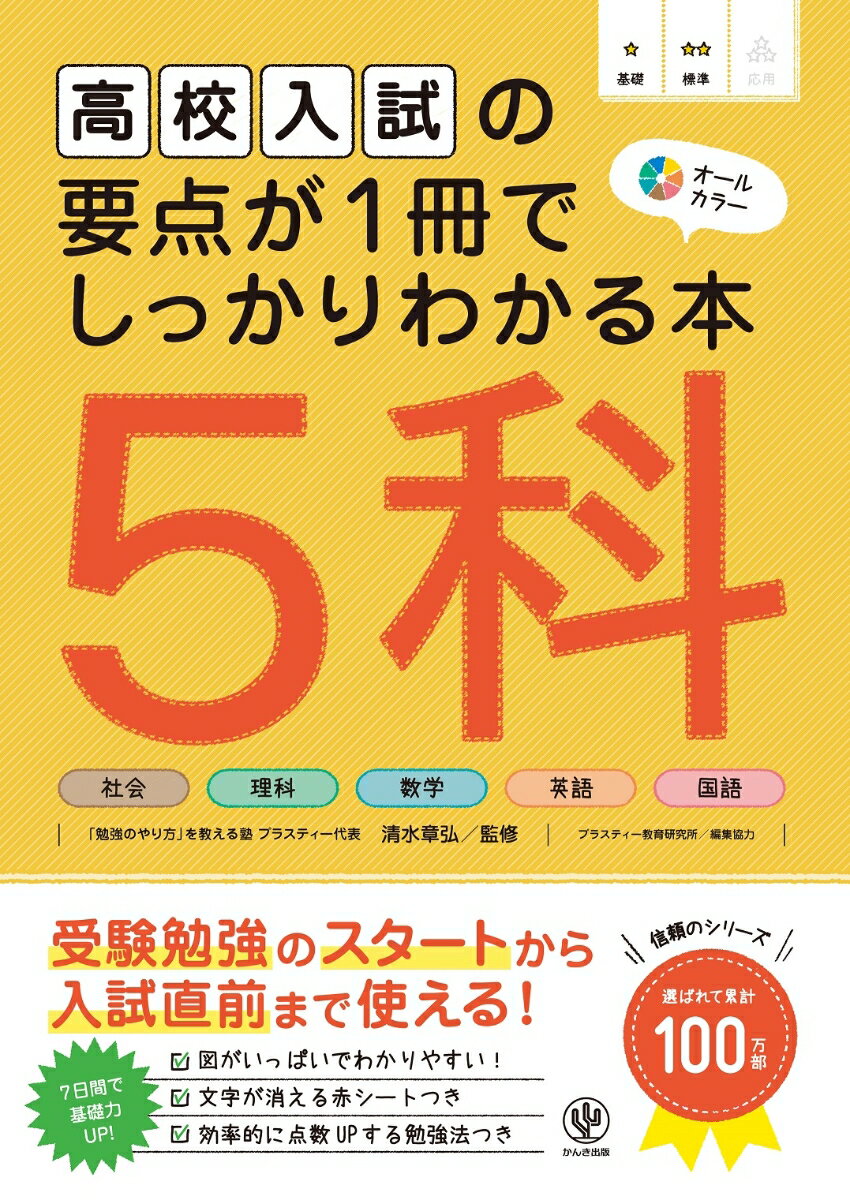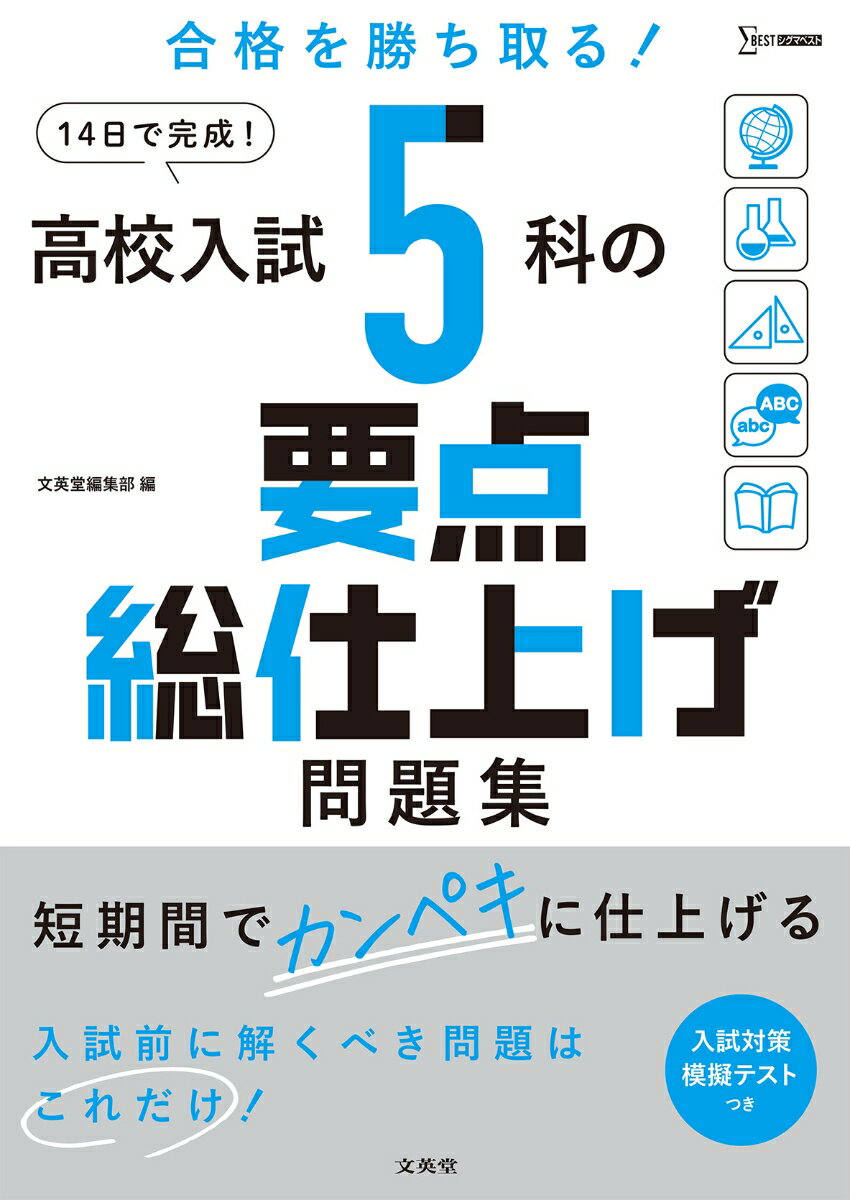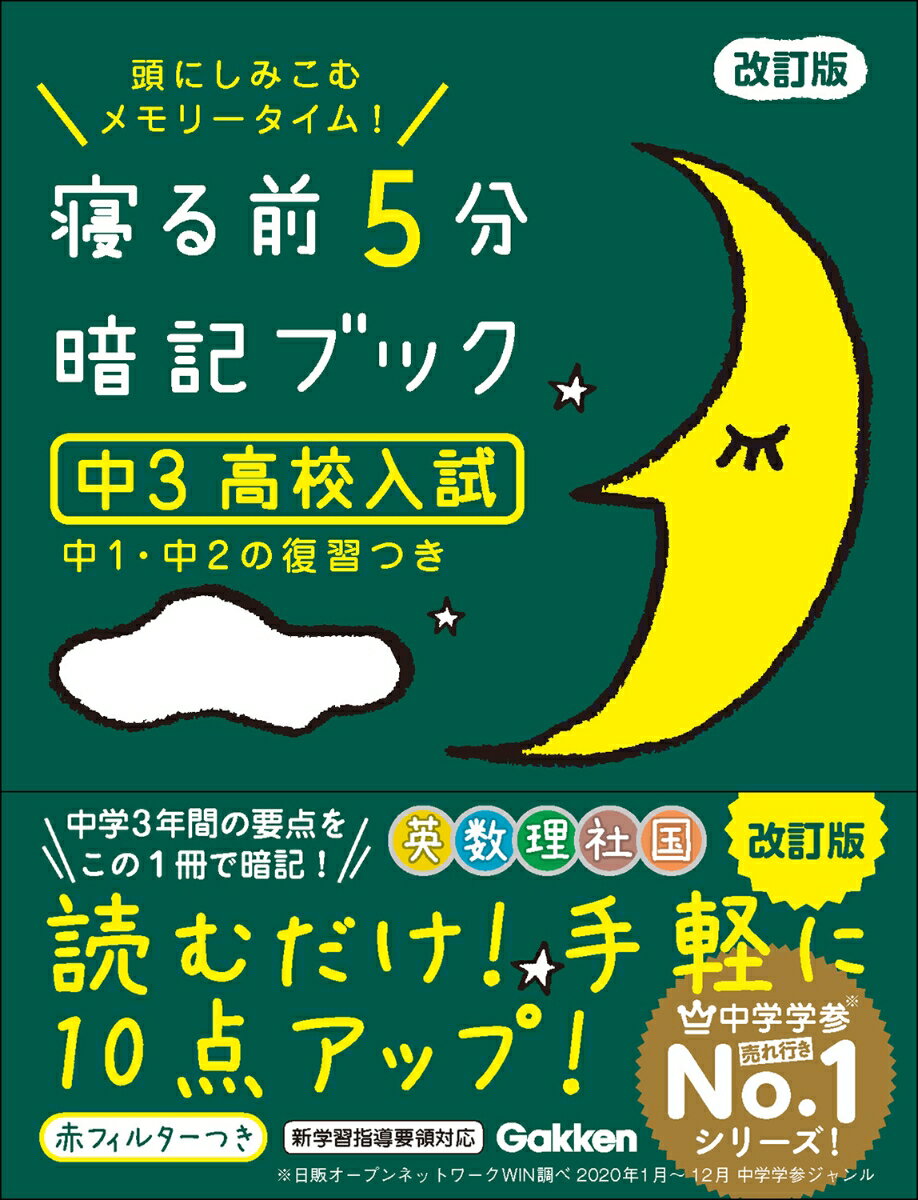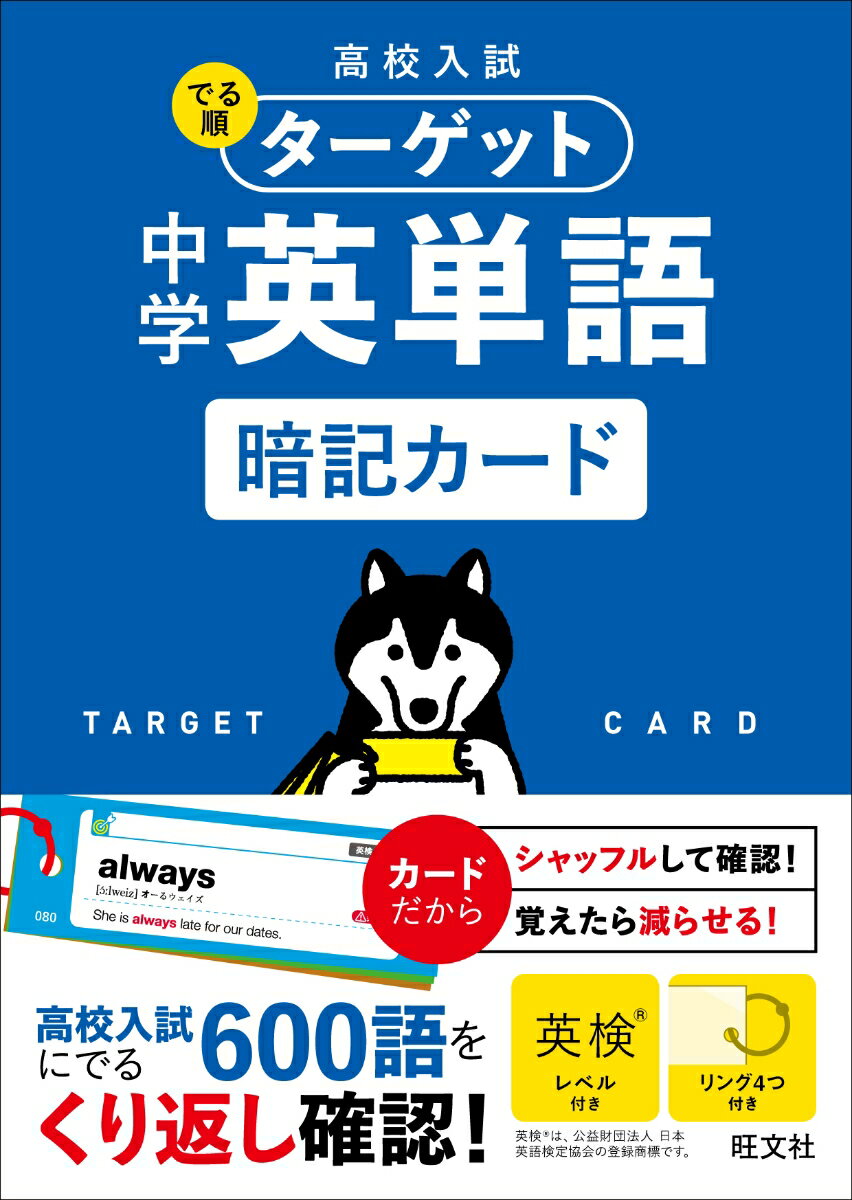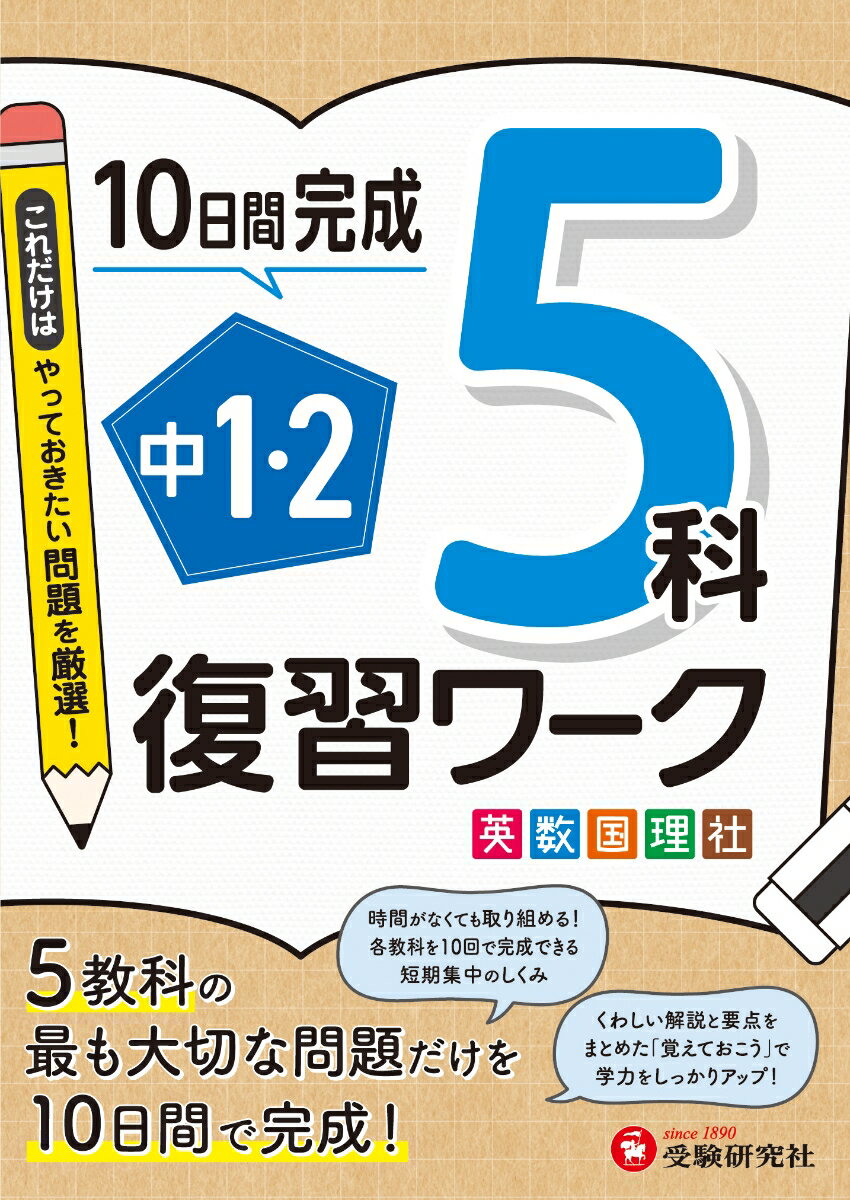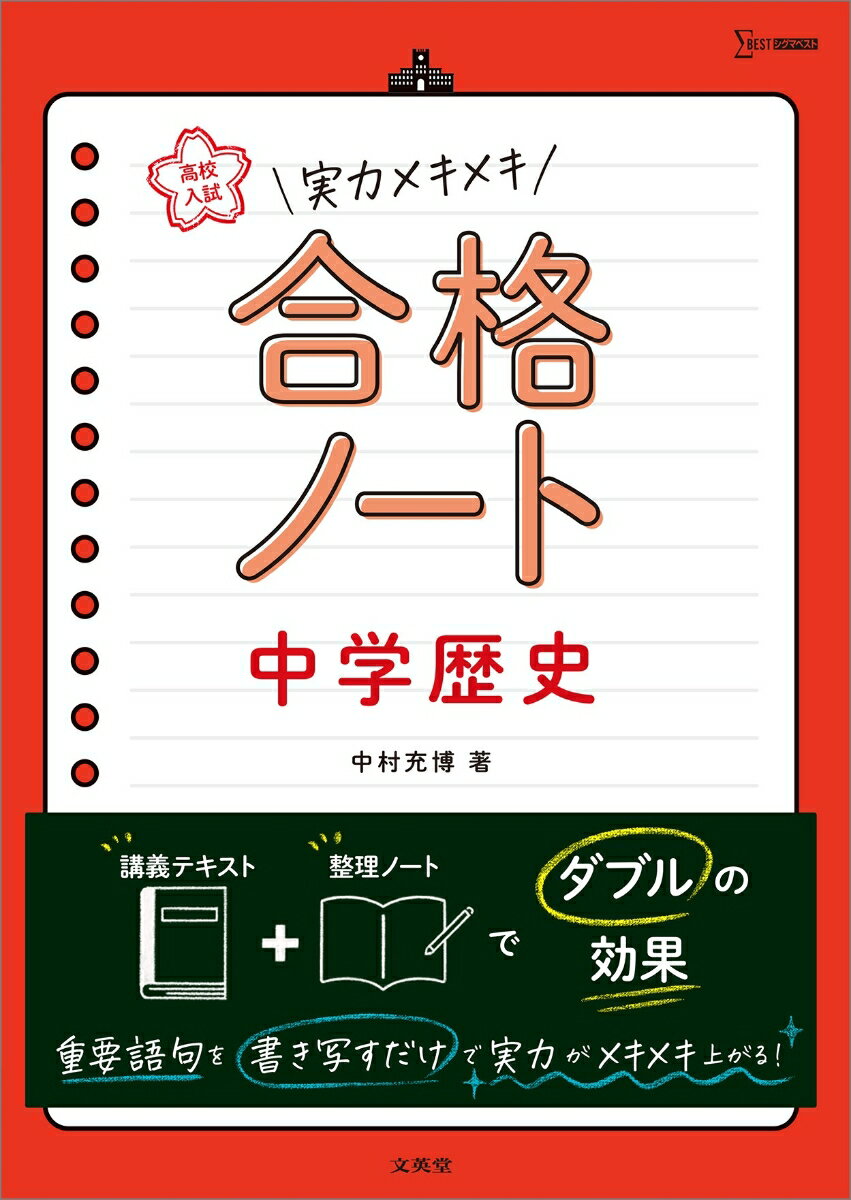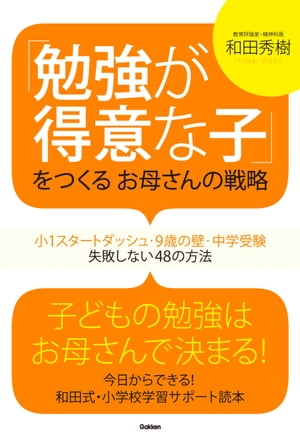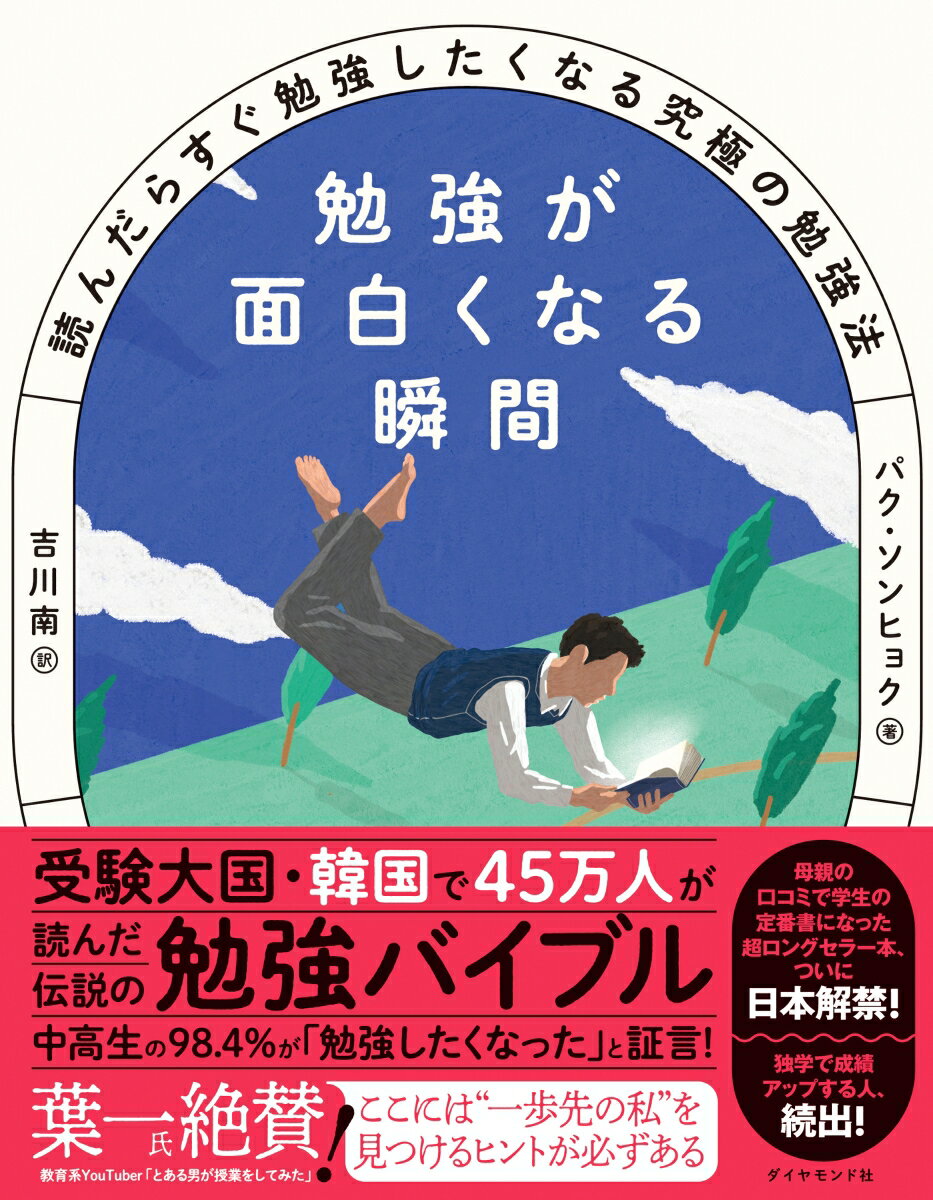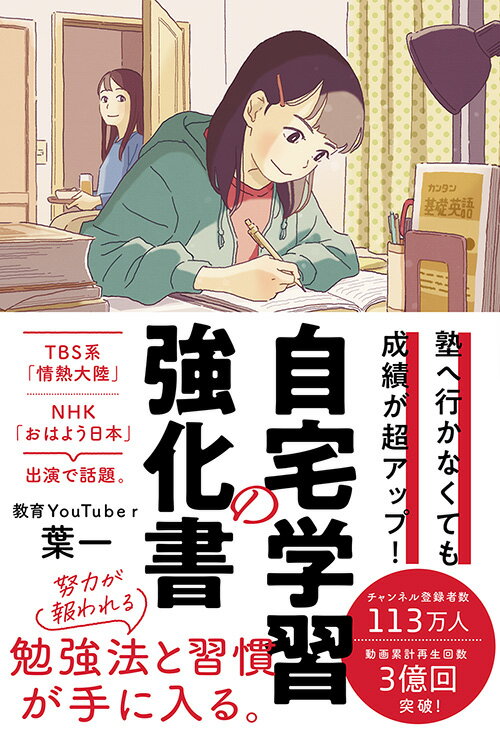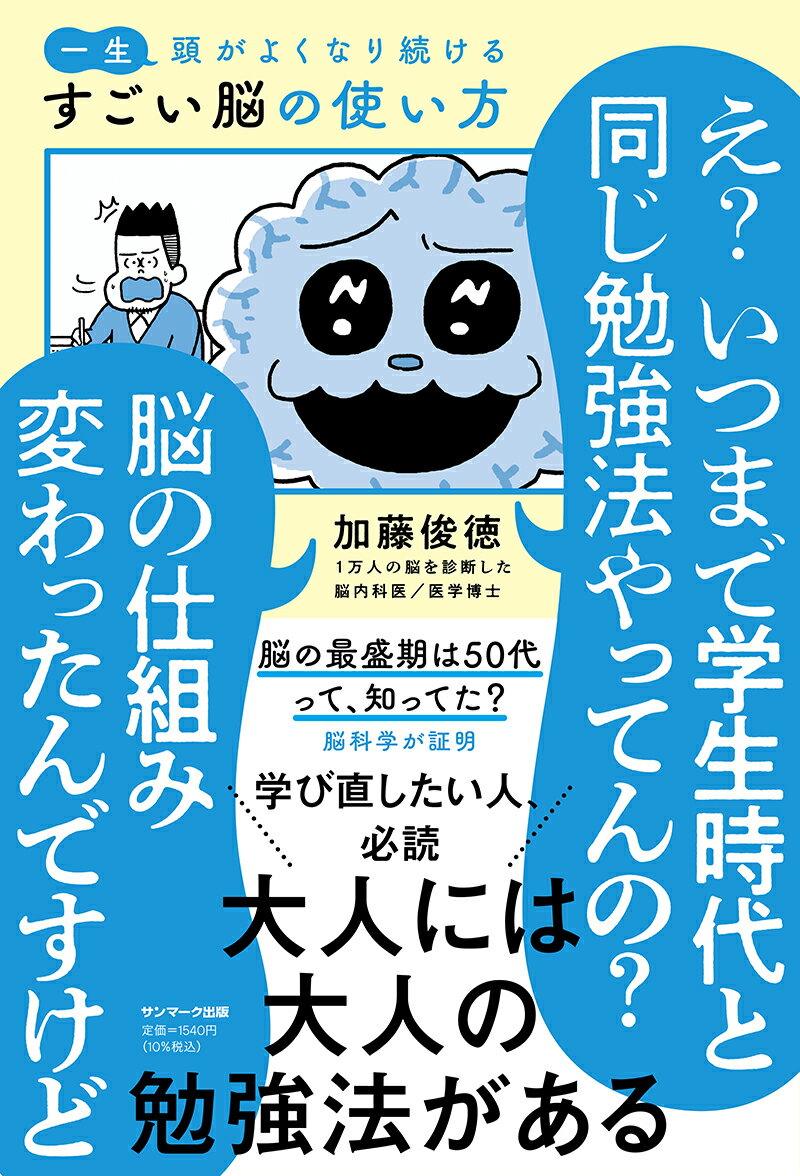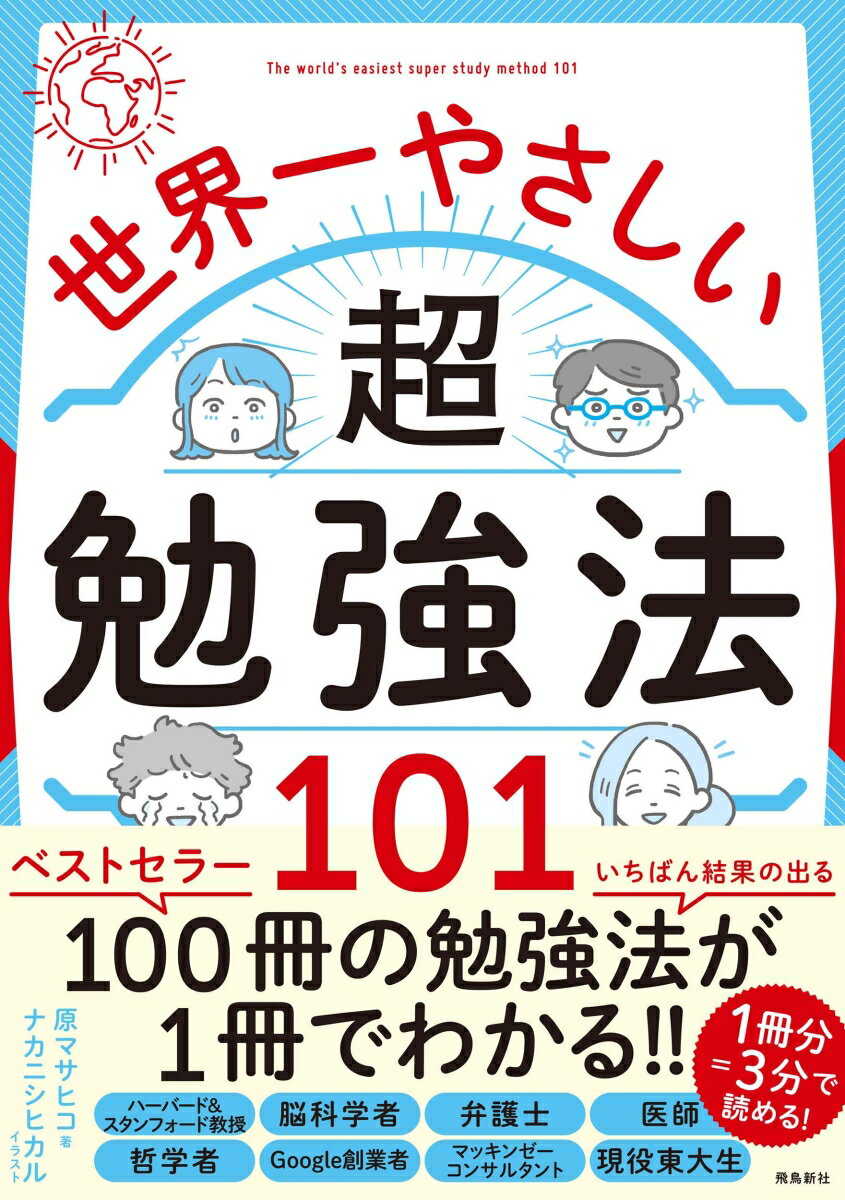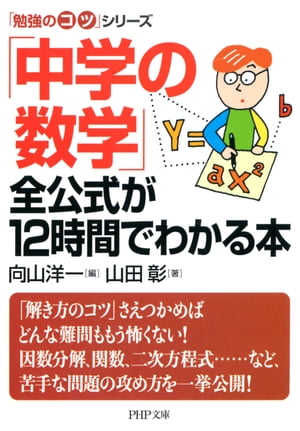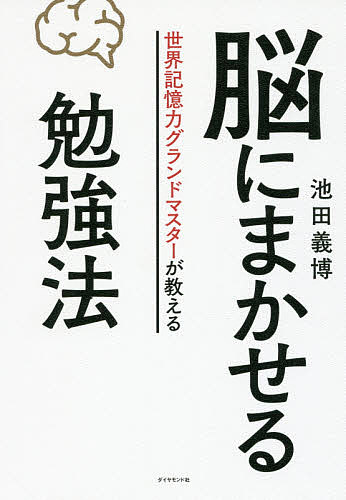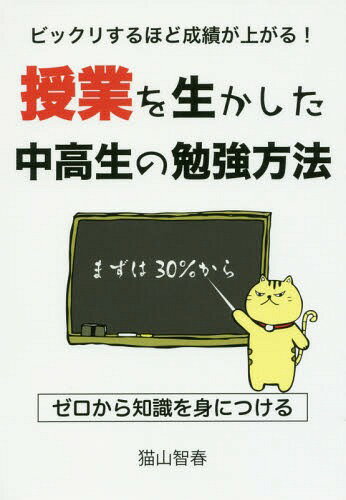いよいよ受験が始まります。
当日に持参するものや、事前に準備するものなどを記載してありますので、チェックしてみてください。
↓↓
▼試験前のチェックは何をする?
※これすごく大事です!!
▼高校受験日までに行うこと4:ポモドーロテクニック
※ここに、1~3までの内容を載せています。
▼過去問の活用方法
最後まで諦めずに、とにかく埋められるものはしっかり埋めましょう!(笑)
--------------
さて、直前にやっておくことを整理しましょう。
焦っていても仕方ありませんので。
【準備】
・一日、やることを整理しよう!
┗何をやるのか、覚えるのかを事前にリスト化。
※リストにする時間は掛けられないので、以下のような形にする。
例:↓↓
1:数学:解の公式チェック
2:理科:化学反応式見直し
3:英文法の現在完了形確認(過去分詞チェック)
というざっくりで構わないので、書いてみよう。(5分くらいで作ること)

・間違えたところの再チェック
┗過去問で間違えたところをチェックしよう。
同じ問題は出題されないけれど、同様の問題が出た時、解くきっかけになります。
・スペル、漢字、年号、公式の確認
┗つい勘違いして覚えているものを、また書いてしまうものです。
これも間違えたノートなどを見直して、しっかり得点しましょう。
・新しいものはやらず、とにかく復習・確認チェック
┗いまから詰め込んでも当日忘れてしまうと、本末転倒です。
・準備を早目にして、ゆっくり寝て、朝再度確認。
・試験は、配られたら先に目を通し、取り掛かる順番を決める。
┗時間を見ながら、解いている問題をやるのか、次に進むのかを考える事。
・見直しの時間は、絶対に確保すること。
┗普通に読み直すのではなく、「どこか間違っているかも」と見る事。
・「自分は合格するんだ」という気持ちで取り掛かりましょう。
┗緊張すると、頭が白くなりますので、深呼吸を忘れずに!
合格を勝ち取りましょう!
そのための準備をしっかりすることが大事です!!
-------------------------