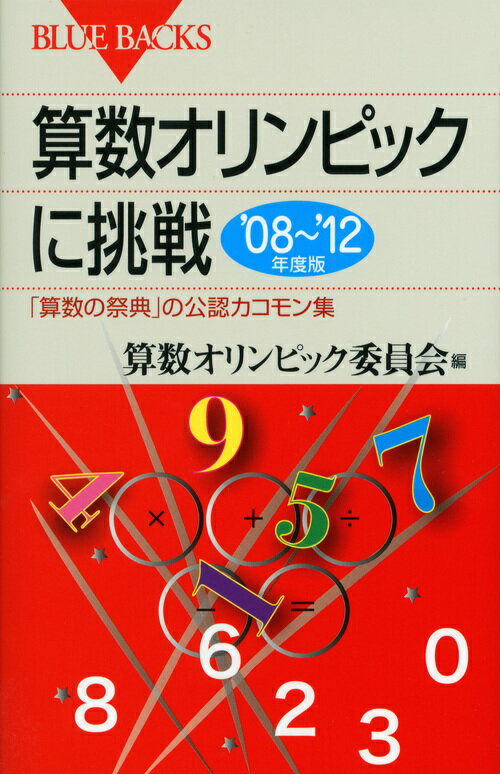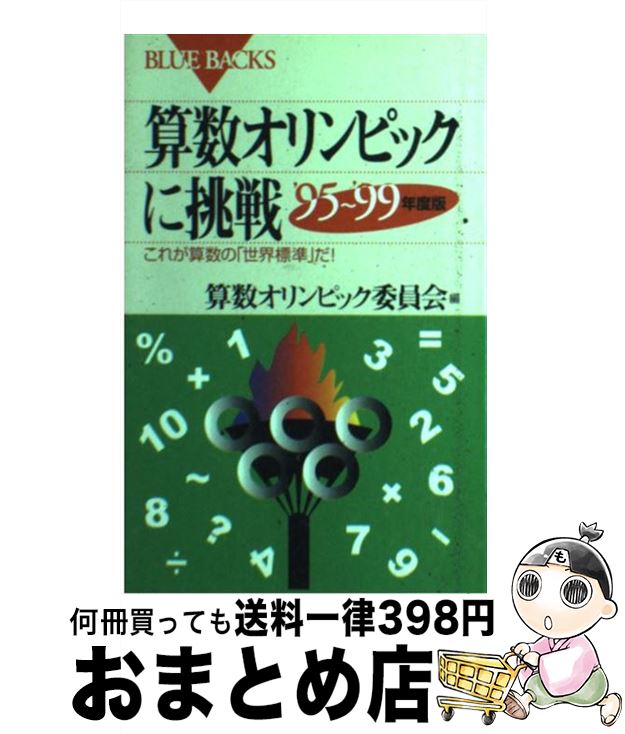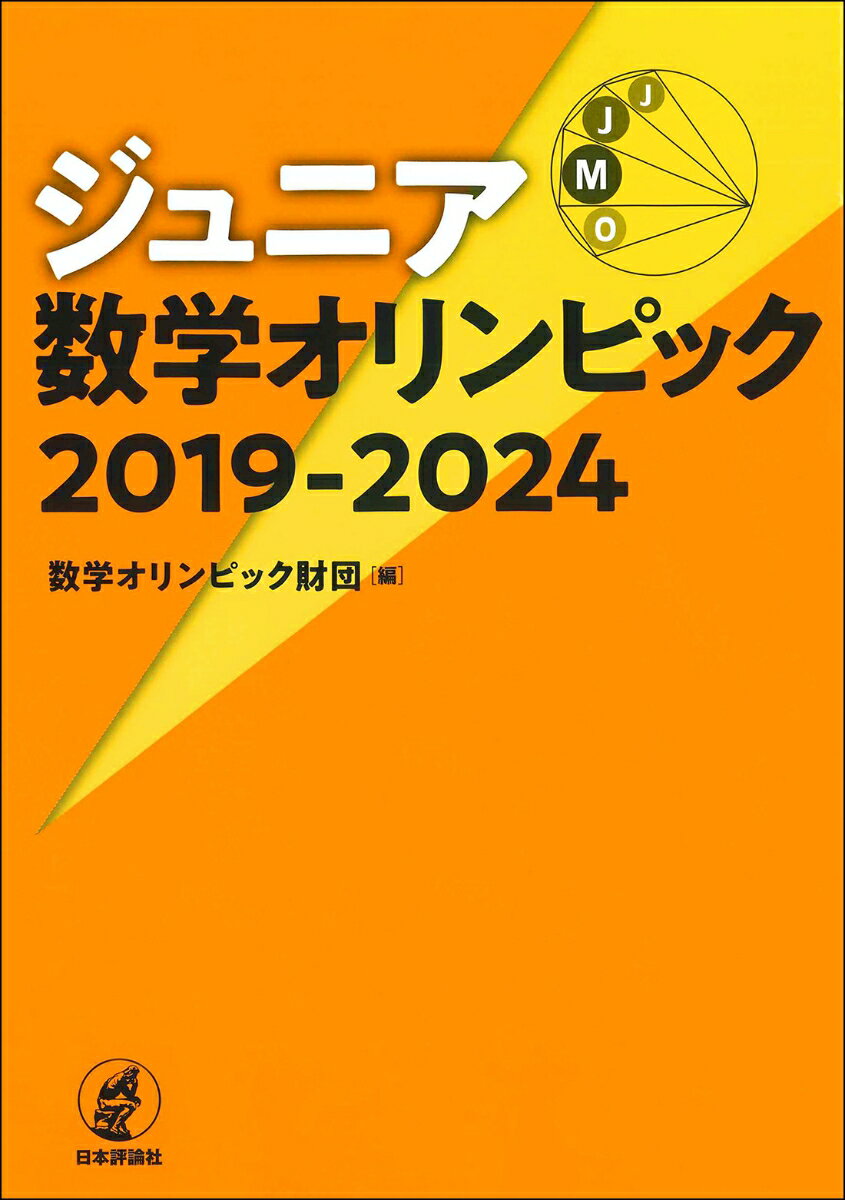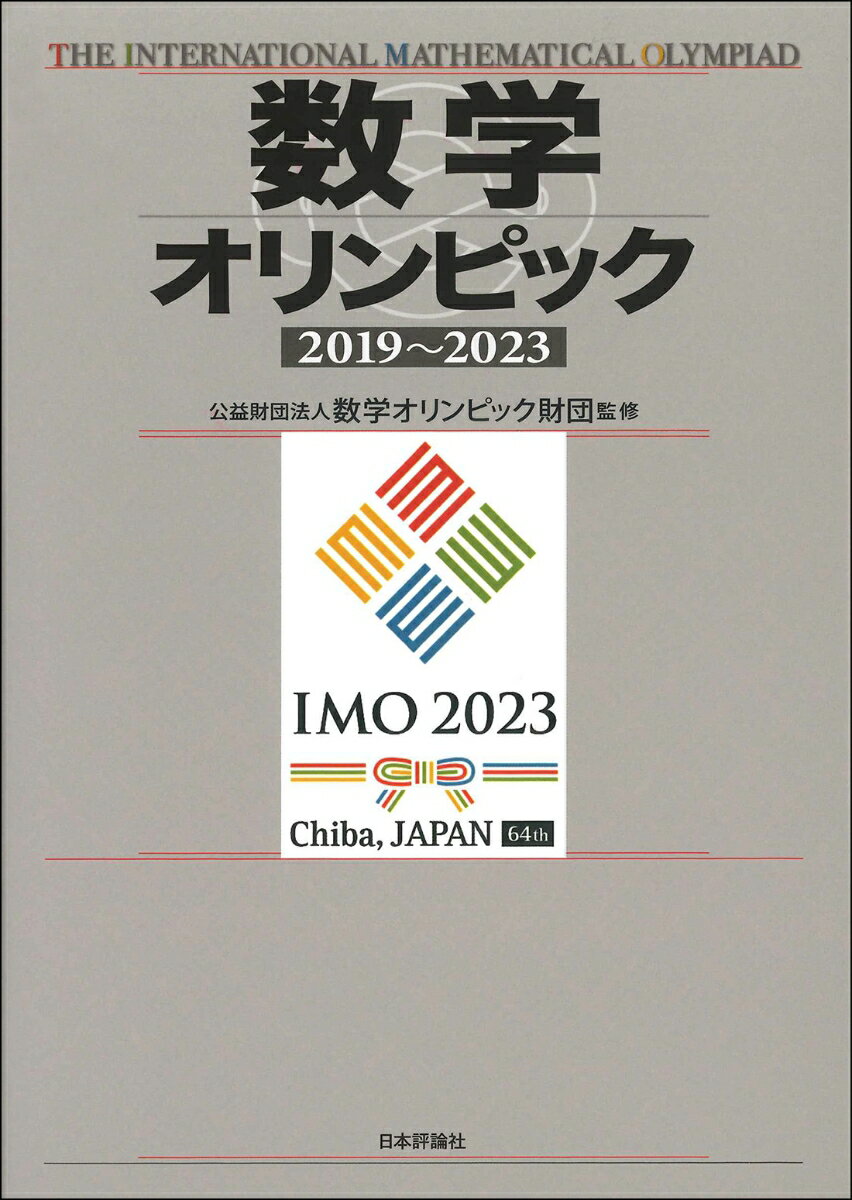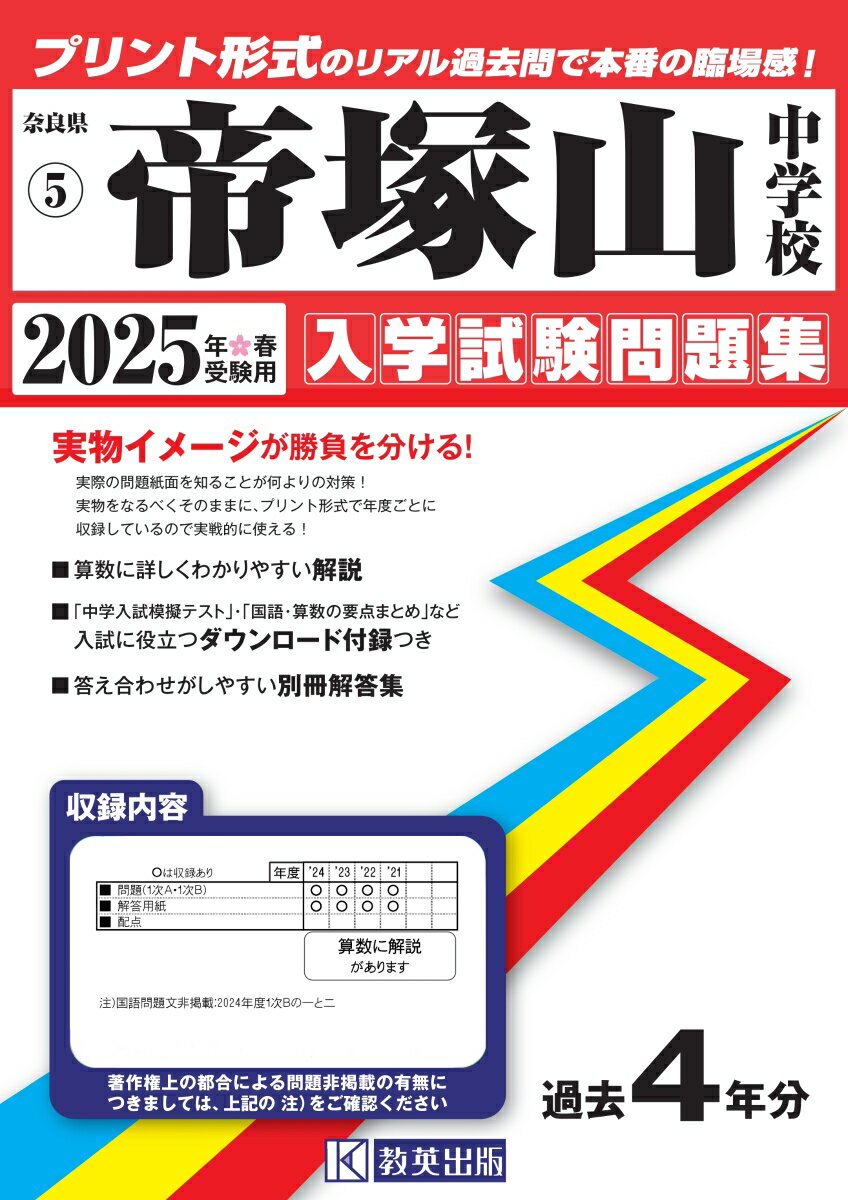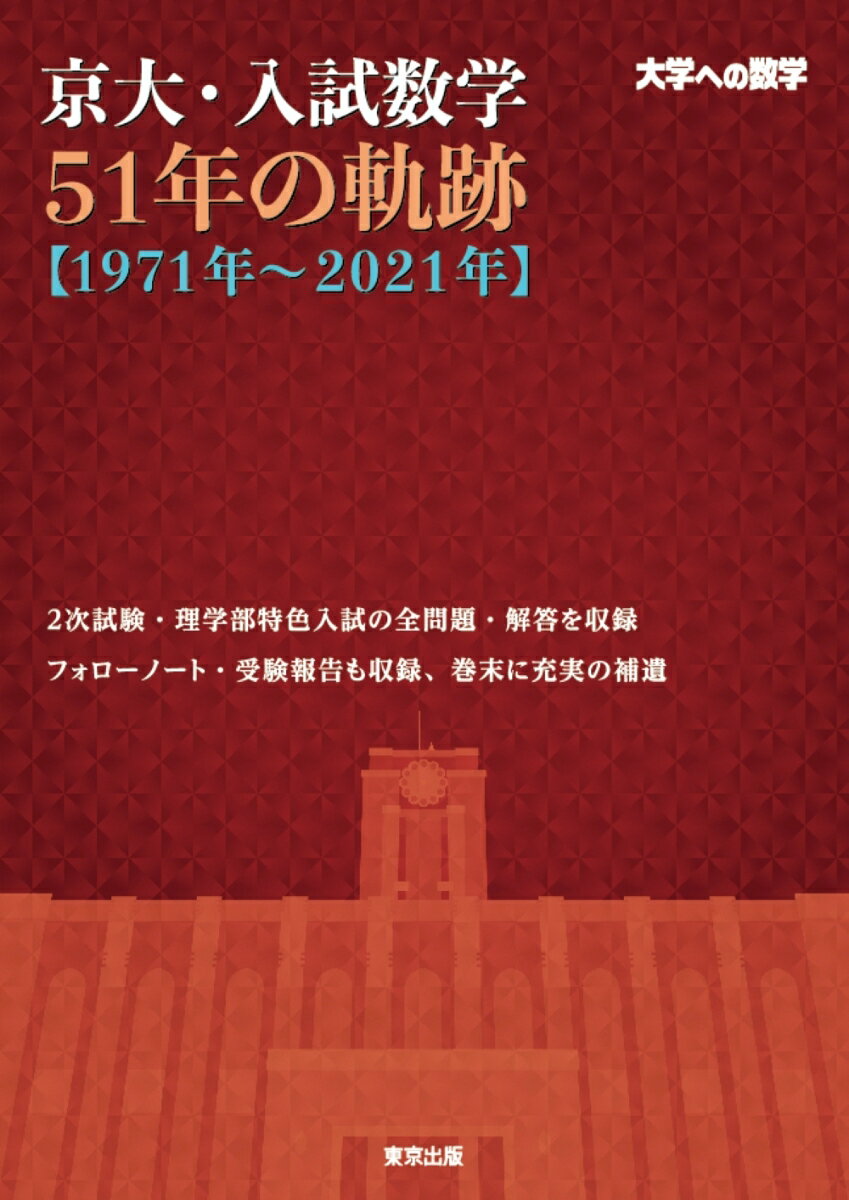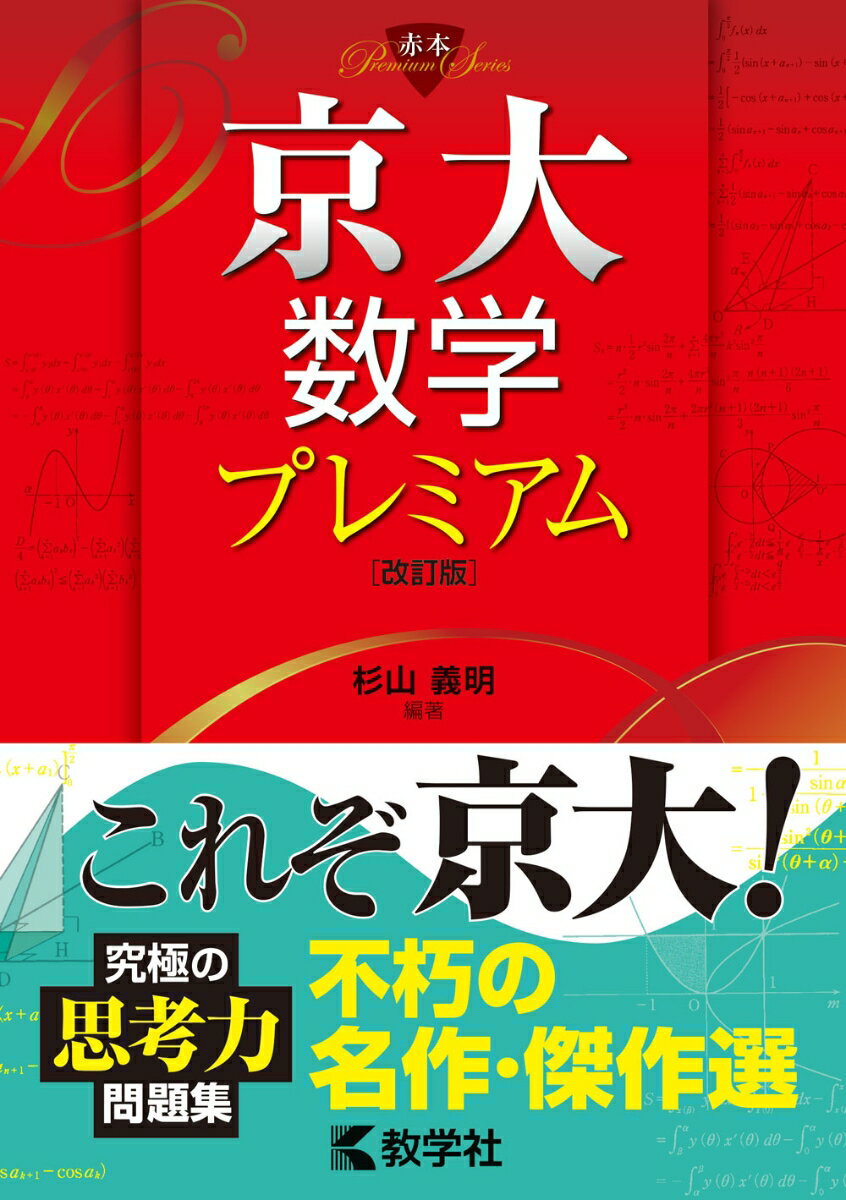一の位が0ではない整数があるとき、その数の各位の数字を逆の順番に並べた数を、元の数の「逆順の数」と呼ぶことにします。例えば、2019の逆順の数は9102です。また、48584のように、逆順の数と元の数が等しくなるような数を「回文数」といいます。
一の位が0ではなく回文数でもない数から始めて、一の位が0になるか回文数になるまで、次の操作をくり返します。
(操作)その数に、その数の逆順の数を足す
例えば、57から始めると、次のように2回で363となって操作が終わります。
(1回目)57+75=132 (2回目)132+231=363
1回で1111となって操作が終わる数をすべて求めると
[ ]
なので、ちょうど2回で1111となって操作が終わる数をすべて求めると [ ]
です。
算数オリンピックや数学オリンピックなどでも出される回文数の問題です(日本数学オリンピック2002年予選第1問、日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)2012年予選第2問、日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)2020年予選第3問など)。
前半の問題をカットすれば、算数オリンピックやジュニア算数オリンピックのトライアル対策にちょうどいいでしょう。
キッズBEEにチャレンジする子の場合、この問題の誘導(前半の問題)を利用して解けばちょうどいいでしょう。
結局のところ、覆面算を解くだけです。
詳しくは、下記ページで。