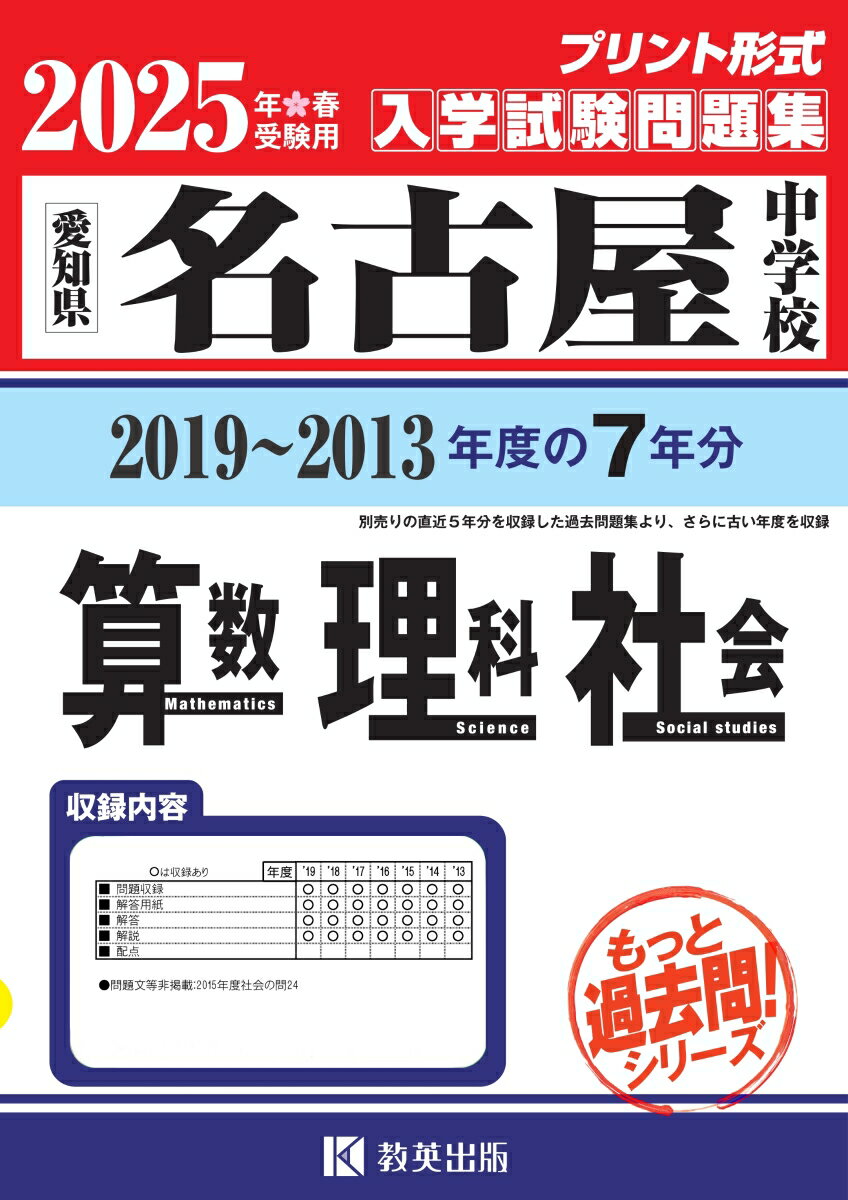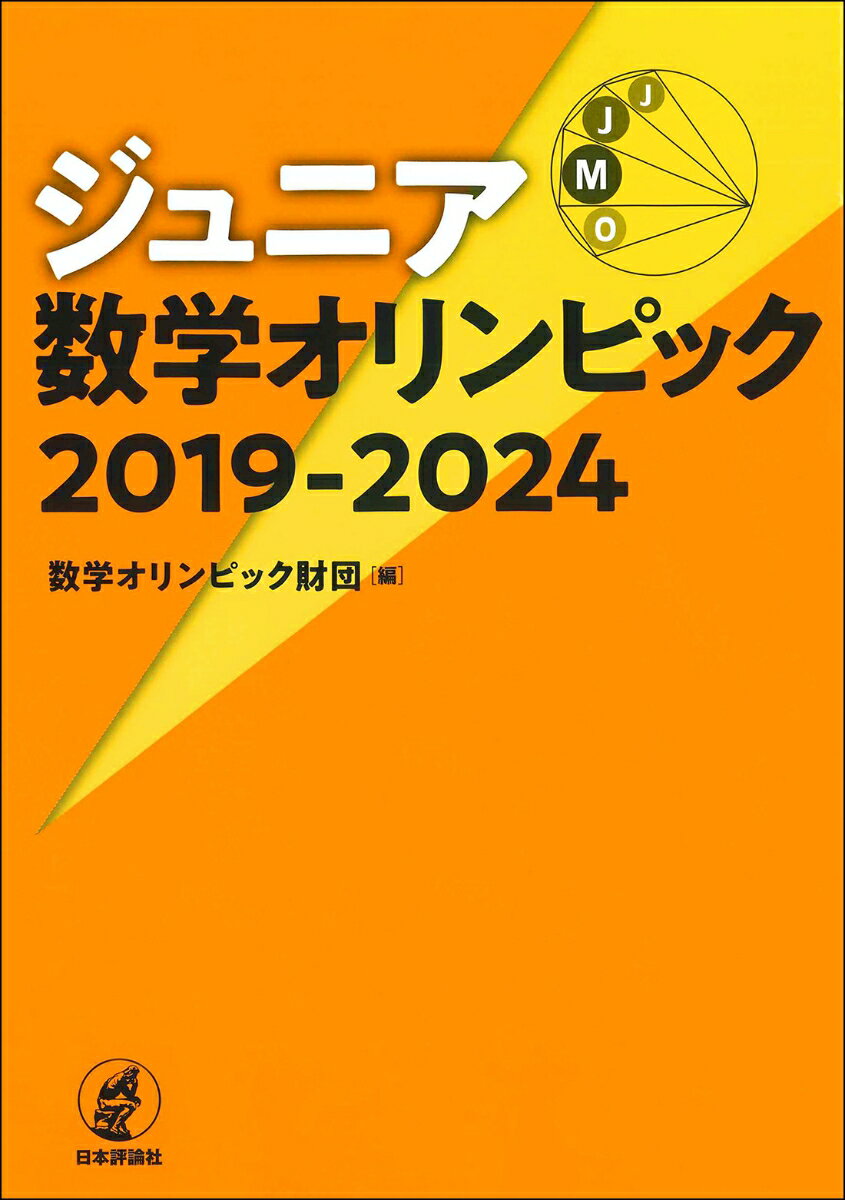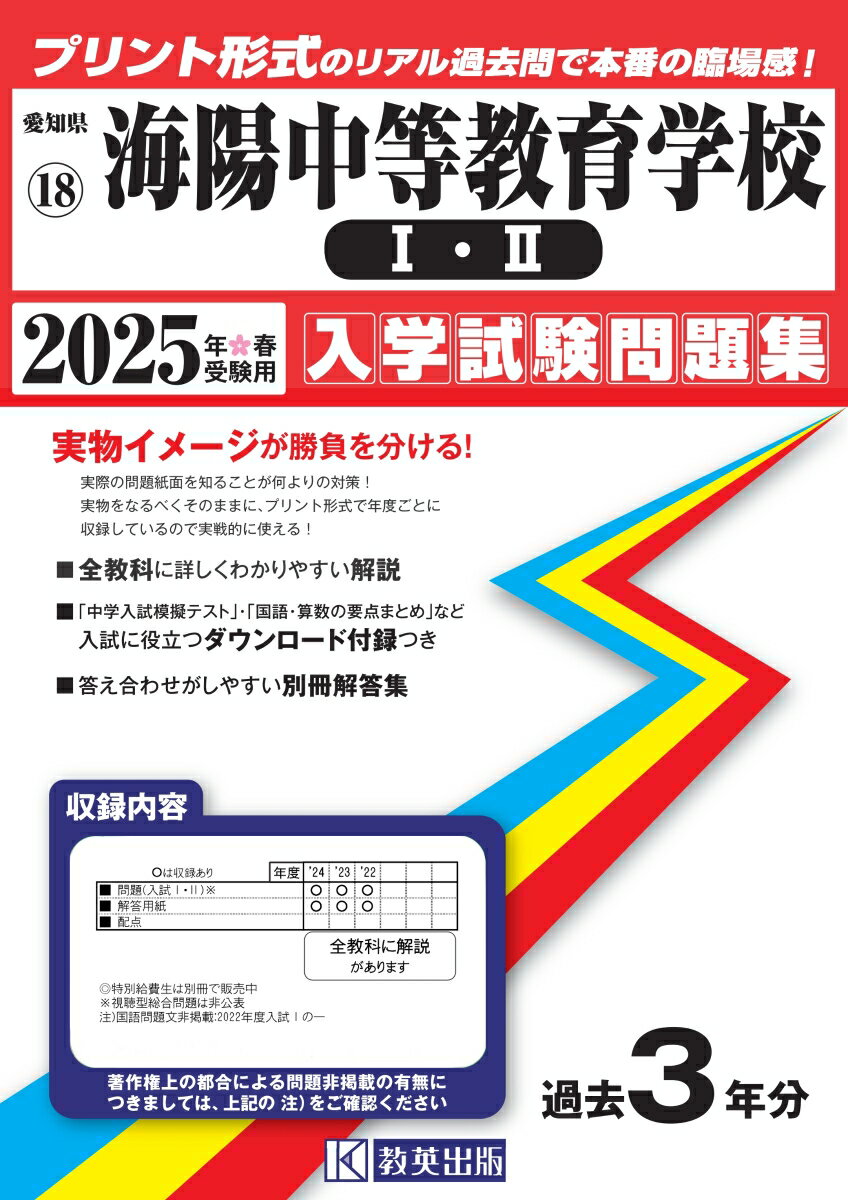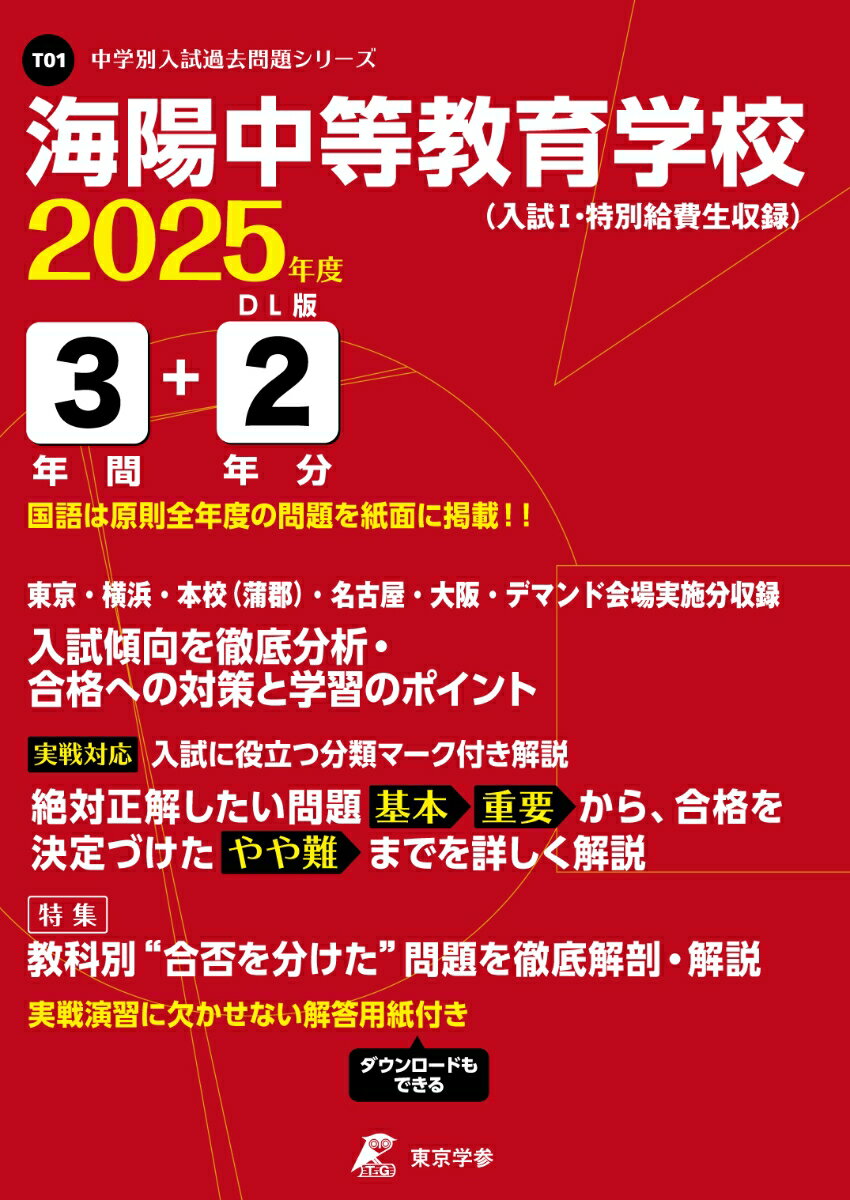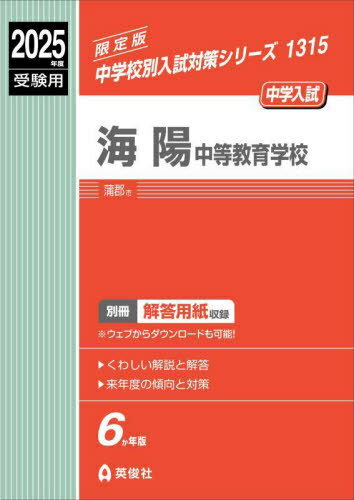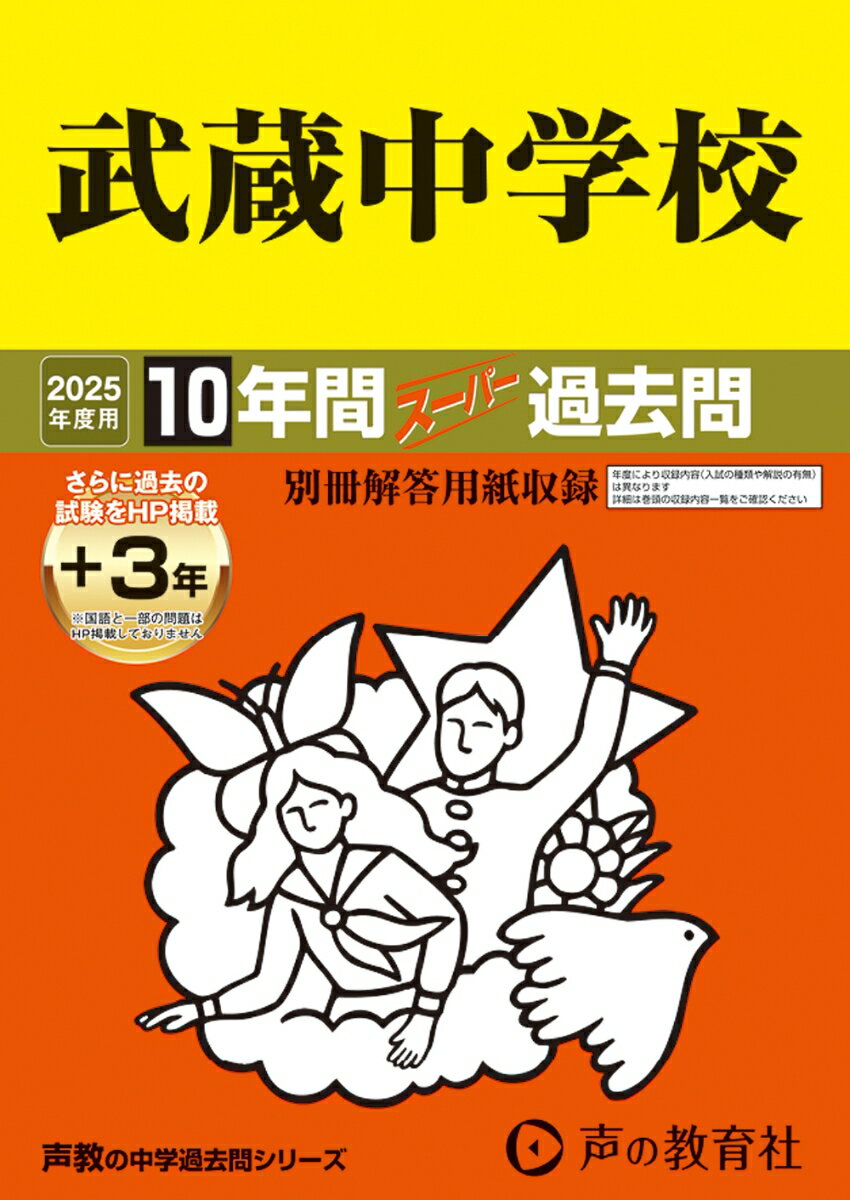日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)2023年予選の問題
今回は、日本ジュニア数学オリンピック2023年予選第4問を取り上げ、解説します。
算数オリンピック、ジュニア算数オリンピック、最難関中学校の入試問題で出されても何の不思議もない問題です。
「正の」というのは0より大きいということです。
与えられた10個の式の値はいずれも1+2=3以上ですね(下限チェック!)。
3以上の素数はすべて奇数(下限チェックをしたのは、唯一の偶数の素数2を排除したかったからです)だから、10個の式の値のうち奇数となるものが最大何個になるかをまず考えます。
5つの整数a、b、c、d、eの偶奇については次の6通りの場合が考えられます。
2整数の和が奇数となるのは、2整数の偶奇が異なるときであることを考慮すれば、10個の式の値のうち奇数となるものの個数がすぐにわかりますね。
(あ)偶数0個、奇数5個・・・10個の式の値のうち奇数となるものは0×5=0個
(い)偶数1個、奇数4個・・・10個の式の値のうち奇数となるものは1×4=4個
(う)偶数2個、奇数3個・・・10個の式の値のうち奇数となるものは2×3=6個
(え)偶数3個、奇数2個
(お)偶数4個、奇数1個
(か)偶数5個、奇数0個
10個の式の値のうち奇数となるものは最大で6個で、それは、(う)または(え)の場合となります。
したがって、10個の式の値のうち素数となるものは6個以下であることになります。
以下、実際に、6個となる場合があるかチェックします。
とりあえず(う)の場合について考えます。
小さい数から考えていくのがいいでしょう。
1、2、3、4,・・・とすると、1+4=2+3となり、奇数となるものの値が一致してしまい、駄目ですね(10個の式の値が「異なる」素数となっていないので、これでもいいでしょうが・・・)。
1、2、3、6、・・・(1、2、3、8、・・・)とすると、3+6=9(1+8=9)となり、奇数となるものの値が素数とならず、駄目ですね。
これらのことに注意しながら、5つの整数を確定させていきます。
とりあえず2を外してみます。
1、3、4、7の時点で、1+4=5、3+4=7、4+7=11となるので、あとは、1、3、7に同じ偶数を足して素数となるものを求めることになります。
10を考えると、1+10=11、3+10=13、7+10=17となり、すべて素数になりますが、4+7=1+10となるので、とりあえず別のものを考えてみます(先ほど書いたように、これでもいいでしょうが・・・)
12を考えると、12+3=15が素数でないから駄目(3があるから3の倍数は使えないことが確かめるまでもなくわかっています)で、14を考えると、1+14=1が素数でないから駄目(7があるから7の倍数は使えないことが確かめるまでもなくわかっています)ですが、16を考えると、1+16=17、3+16=19、7+16=23となり、しかも5、7、11、17、19、23は異なる素数となって、すべて異なる素数となっていますね。
したがって、10個の式のうち値が素数となるものの個数としてありうる最大の値は6となります。
因みに、5つの整数としては、(1、3、4、7、40)、(1、3、4、7、100)などたくさんあり、すぐに見つけることができます。
101、103、107、109、・・・というように、100以上の素数を小さいものからすぐに書き出すことができる人であれば、例えば、101、103、107から逆算して、奇数は1、3、7、偶数は100で、残りの偶数として、2は駄目で、4はオーケーだからと考えて(1、3、4、7、100)の組をすぐに見つけられますし、また、例えば、103、107、109から逆算して、奇数は3、7、9、偶数は100で、残りの偶数として、2は駄目で、4はオーケーだからと考えて(3、4、7、9、100)の組をすぐに見つけられます。
私自身も最初にこちらをすぐに見つけましたが、上の解説では誰でも思いつくだろうと思われる見つけ方をまず紹介しました。
なお、1から100までの素数は25個ありますが、エラトステネスの篩で簡単に書き出すことができます(自治医科大学2016年医学部数学第6問の解答・解説を参照)。
算数オリンピック・ジュニア算数オリンピック・キッズBEE対策プロ家庭教師の生徒募集について
算数オリンピック・ジュニア算数オリンピック・キッズBEE対策プロ家庭教師のお申込み・ご相談