森田ゆりさん講演会のお知らせ
しているのですが、今秋11月8日に森田ゆりさんをお招きして
講演会を開催することが決定しました

“生きる力” は本来誰しもが生まれながらに持っているものですが、
経験や環境などから来る抑圧により奪われていることが殆どです。
だからこその社会の現状であると思っています。
その“奪われたもの”を取り戻すための知識とスキルを
非常にわかりやすく丁寧に、そして納得のいくように
伝えてくれる方が森田ゆりさんです。
私がさまざまの気づきを得ていくきっかけになった
最初のヒントをいただいたのが
森田ゆりさんが日本に広めてくださったCAPの大人ワークです。
かみなりに打たれたように瞬時に固い硬い殻に一本の光が
差し込み、そこからひび割れが広がって明るさが増していった、
そんなイメージです。
「ああ、そうだったのか!・・・」
エンパワメントの第一歩でした。
その後森田ゆりさんの著書をむさぼるように読んだことを覚えています。
中でもエンパワメントと人権―こころの力のみなもとへは
私のバイブルとなっています。
育児支援グループを始めた時、まず森田ゆりさんを
お招きすることを決めていました。
詳しくはこちらをご覧ください。
森田ゆりさんの詳細に関してはこちらをどうぞ。
必見★子育てに苦しさを感じている親御さんへ★
こんなプログラムがあるのをご存じでしょうか?
皆さんにお伝えしたいのでご紹介させて頂きます!
2007年度参加者募集中
【子育てに苦しさを感じている親のための
MY TREE ペアレンツ・プログラム】
「子育てにしんどさを感じている」
「気がつけば子どもをたたいている」
「子どもを無視してしまう」
「このままではどうなってしまうのかととても不安」
そんなあなたを大切にするプログラムです。
少人数での語り合いを中心とした支え合いのグループです。
参加者の秘密は厳守されます。
安心してご参加して下さい。お待ちしています。
★日時・内容(全16回 中間個人面接と同窓会を含む)
いずれも金曜日 午前10時~12:30分
―――――――――――――――――――――――――――
【日時 】 【プログラムの内容】
―――――――――――――――――――――――――――
1.2007年 6/8(金) 安心な出会いの場:目的、約束事、身体ほぐし
2. 6/15(金) 安心な出会いの場:私の木
3. 6/22(金) わたしのエンパワメント
4. 6/29(金) 親と子のエンパワメント
5. 7/6(金) 気持ちを聴く
6. 7/13(金) 気持ちを語る
7. 7/20(金) 体罰の6つの問題
8. 7/27(金) 感情のコントロール
8/3(金) 〈中間面接〉
9. 8/17(金) やってみよう子育ての新しいアイデア
10. 8/24(金) 自己肯定感・否定的ひとりごとの掃除
11. 8/31(金) 自分をほめる、子どもをほめる
12. 9/7(金) 母親らしさ、父親らしさ
13. 9/14(金) MY TREE
12/7(金) 3ケ月後同窓会
2008年 3/7(金) 6ケ月後同窓会
――――――――――――――――――――――――――
◆テキスト:「しつけと体罰」森田ゆり著 (童話館・1400円)
「気持ちの本」 森田ゆり著 (童話館・1470円)
お持ちでない方は、申し込み時にその旨申し出て下さい。
◆参加費: 無料
◆保育: 無料。事前申込みが必要。
◆場所: 富田林市人権文化センター(近鉄長野線「富田林」駅から徒歩5分)
◆申込方法:電話またはFAXにて下記へお申し込み下さい。
住所、氏名、電話番号、保育の利用の有無をお伝え下さい。
後日電話にて「木もれ陽」スタッフより連絡致します。
■申し込み・問い合わせ先■
富田林市人権協議会 電話0721-24-3700 FAX 0721-25-5952
定員になり次第締め切りします。
この「MY TREEペアレンツ プログラム」は、
森田ゆり氏によって開発され、トレーニングを受けた専門スタッフ
(MY TREE実践グループ・木もれ陽スタッフ)が実施致します。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
大阪の富田林で行われるのですが、
市外や、大阪府外の方も、参加できるそうです。
自分自身が、堂々と、大地に根を広げて生きて行く
木のような気持ちになれることと思います。
◆募集人数:10名
定員が10名となっておりますので、
このプログラムを必要とされる方は、
お早めに申し込まれることをお薦め致します。
家族えん会議
週末、エンパワメント・センター主催、森田ゆりさんの
【家族えん会議ファシリテーター養成講座・基礎編】
を受講してきました。
世界各国で、“家族グループカンファレンス”などの名称で
実施され、大きな効果を発揮しているということです。
やはり根底にはエンパワメント、人権の尊重ということを
基盤にされています。
かなり画期的で、ぜひ日本でも他国のように
司法介入の元に定着してほしいと思います。
実際ロールプレイにおいて
いじめの加害少年役をやらせてもらった私は、
自分の当時を思い返し、ひねくれて自暴自棄な気持ちで
やらせてもらったにも関わらず、この会議の中で
みるみる自分の気持ちが変化していくことに驚きました。
「あぁ、こんなふうに変化していくのか・・!」
「私の時もこんな方法があったらなぁ・・」
などと思いつつ、本当に感嘆しました。
やはりこれは、行動や人格を責めるのでなく、
事実だけを述べ、加害者もその事実を認め、謝罪し、
ファシリテーターのエンパワメントを基盤にした進め方により、
参加した全員が問題を解決していくために
一人一人が何ができるのか、どうサポートするのか、
考えて納得して決めていくという過程の中で、
孤独や寂しさなどの絶望を抱えて問題を起こした加害者が
「人との繋がり」という暖かなもの、感じられなかったもの、
本当に欲しかったものを感じ取ることで、
自ら更正していこうという気持ちが芽生える、ということが
大きいのだろうなぁと思います。
罰を受けたくないから、ではなく、
自分が生まれ持つ生きる力への気づきを促し、
それを活用するためにサポートをしてくれる人がいる、
助けてくれる人がいる、と思えるように、当事者を囲む
コミュニティの力をも最大限引き出し利用するという
まさに人間の持つ内なる力を再確認できるような方法だと思います。
これはすごいなぁ・・!!と思ったのが率直な感想でした。
いつもながら森田ゆりさんの研修には実際に子どもの虐待など
さまざまな問題に介入している専門家の方が全国から集まるので、
それらを踏まえたいろんな質問や意見が飛び交いましたが、
どのようなケースにも即座にあらゆる角度から素早く思考を
巡らせて適切な応答をされることに驚いています。
さすが・・頭が切れるとはこういうことを言うんだろうなぁ、
アサーティブネスってこういうことだな、と今回もたくさんの
刺激を受け、興奮気味に帰路に着きました。
脳が満杯状態でとても書ききれないのですが・・
実践編もぜひ受けようと思っています。
めちゃくちゃ楽しいんですよね。
頭の中の霧がひとつひとつ晴れるような感覚もあります。
森田ゆりさんは、ほんとカッコイイ・素敵な方です^^
どんな人生にも意味がある
V.E.フランクルの言葉をご紹介します。
『あなたの存在、あなたの人生には、
すばらしい意味がある。
いかなる絶望にも希望がある。
人生はうまくいくようになっている。
ただ、そのことに気づきさえすればいいのだ。』
『“あなたを必要とする何か”がどこかにあり、
“あなたを必要としている誰か”
がどこかにいるはずです。
そしてその“何か”や“誰か”は、
あなたに発見されるのを待っているのです。 』
『人間の生きがいは、
その人が毎日行う行動の積み重ねである。』
神経科医であり、精神科医であった
ヴィクトール・エミール・フランクル。
ユダヤ人である彼は、ナチスの強制収容所に
捕虜として 捉えられた経験があり、
そうした究極の生き地獄の中でさえ、
絶望した人々にこの真実は通用した、
ということです。
それでも人生にイエスと言う/V.E. フランクル

¥1,785
Amazon.co.jp
その時には耐えがたかった苦しみや悲しみも
その後の生き方で、
それらがあったからこそ見えてくる、
すべてのものとの繋がり、
真実や、与えられた大きなものが、
「あぁ、そうだったのか」という感謝と感動とともに
舞い降りてくるように、大きく開示されるのですね。
人生で起こるすべてのことには意味がある。
私は、なぜ?と思う様な何かが起きたら、
「このことにはどんな意味があるのかな」
と思うようになりました。
自分を守るために~他者の怒りを背負わない~
自分の問題として背負わないための
ノウハウを持つ事はとても大切です。
例えば、子どもが家庭外(学校や園など)で
「適切でない行動を叱る」のではなく、
「単に怒り・ストレスをぶつける」という
言動に遭遇することもあると思います。
”怒りをぶつけてくる人”に遭遇しても
”他者は変えられない”ので、
ぶつけられる怒りに”どう対処するか”で、
自分がストレスを感じずに、
また、
”この人が怒るのは自分がわるいから”
という自己否定感を
感じずに済むことができるそうです。
子どもの成長とともに、学校など
親の目の届かない場面も出てきますよね。
そして
”他者の怒りを背負わない”ための
ノウハウを子どもが身につけていると
少しでも安心ですよね。
そのためには、
日頃から、家庭で親が、子どもが
してはいけないこと(危険なこと)をしたり、
親のして欲しくないことをしたとき、
(親がイライラを感じているときなど)
YOUメッセージで
「あなたが~~したからでしょ」
「だから言ったでしょ」
「わるいことをするからでしょ」
のように言ってしまうと、子どもは
”あなたの“せい”(責任)である”
というメッセージを受け取って、
”わたしがわるいんだ・ダメな子なんだ”
というふうに思ってしまうそうなんです。
これが日常化していくと、子どもは、
「怒られるのはわたしのせい(責任)だ、
わたしがわるいんだ」
という考え方になってしまい、
自分を責める脳の回路ができてしまうんだそうです。
また、そんなふうに怒られたり、
責められるのは誰でもいやなので
怒られるかもしれないから自発的に行動できない、
責められるかもしれないから自分に起きたことを言えない、
怒られたくないから本心も言えない、
となっていってしまうそうです。
”自分を守る”ために、そうなるですよね。
そして、「どうして言わなかったの?」
「どうしてできないの?」
”言えない・しない”ことを責めたら
追いつめられてしまいますよね。
そうすると、他者が
自分のストレスをぶつけているだけであっても、
「わたしのせいではないか?自分がわるいのか?」
と怒”られ”ていると受けとるようになっていくそうです。
なので、親は、
”してはいけないことを説明する”ことと、
”ストレスでイライラしている”ことを
分ける必要があるんですね。
ストレスを感じることは悪いことではないので、
「イライラしてたな~」と思えば、
「さっきはごめんね、
ちょっとイライラして言いすぎたね。
○○ちゃんは何も悪くないからね。」
とフォローすれば子どもにも解りやすく、
自分を責めずに済むそうです。
YOUメッセージで責められてない子どもは、
例えば誰かがイライラしてそれをぶつけたとしても、
自分が怒”られ”ているのではなく、
ああ、”この人が怒ってる”んだなと、
巻き込まれず、自分を責めずに済みます。
そして、
「この人は怒りをぶつけてくるかもしれない人」
という判断ができれば
その人から逃げる・離れる、
という選択もでき、
大人に気持ちや出来事を
そのまま伝えることもできるので、
危険回避ための
さまざまな手段を持てるんですね。
家庭での日頃の子どもとの関わりの中で、
こんなふうに、子どもが
”自分で自分を守るノウハウ”を
身につけることができるんですね。
感情と行動を分けて考える
以下のことを頭に入れておくと良いようです。
◆感情と行動を分けて考える。
感情・気持ちに良い・悪いはないんですよね。
感情をコントロールするとよく言いますが、
これは、思うこと自体を操作するのでなく、
“ 感じた気持ちを言動にどのように表すか ”
ということなんですよね。
例えば、
計画どおりに進まない、疲れている、
イライラしているときなど、
「もう何もかもやめてしまいたい」とか、
「どうでもいい」というような
投げやりな気持ちが湧いたとき、
「母親なのにこんなふうに思ってはいけない」
と思い直して自身を叱咤する、ようなケースです。
これは
「こんなことを感じたり思ってはいけない」
という“ 感情の否定 ”なんですね。
しかし、感情は“ 自然に湧いてくるもの ”
なのでどうしようもできないですよね。
そんなふうに否定すると、さらに
「こんなことを思うなんて」
という罪悪感も湧いて、
自己否定に繋がることもあるんですよね。
そうすると、やはり子どもにも同じようになり、
子どもが「あれがしたい、これがしたい」と言ったとき、
「何を言ってるの。そんなことできるわけないでしょ。」
自分に対して抑圧し、罰しているので、
無意識のうちに他者にもそうなってしまうようです。
すると子どもは、いろんなことを
最初からあきらめてしまうようになります。
「どうせこんなことを言っても相手にしてもらえない。」
「自分の思いはばかげたことだ。」というふうに、
“ やる気 ”が育たないんですね。
これでは子どもの希望を奪ってしまうことに
なるので、気を付けたいですね。
思うことはかまわない。
どんな感情を持ってもいい。
それを“ どう表現するか ”が大切なんですね。
怒りを感じた時、そのまま表現したら、
相手がイヤな気持ちになったり、
恐怖や嫌悪を感じるかもしれませんよね。
感じること、思うことはそのままでいい。
それをどう表現するか、伝えるか、
適切な表現を考えて、実行する。
こんなふうに、
“ 気持ちは責めず、肯定する ”
ことも、自分を大切にすることに
しっかりと繋がっていくんですよね。
子どもがコミュニケーションに困らないように
親が気をつけたいことのひとつですね。
気持ちを大切にするために、
この本はとってもよかったです。
気持ちの本/たくさんの子どもたち
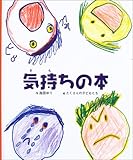
¥1,470
Amazon.co.jp
多様性の受容
高めるために重要なもののひとつに、
“ 多様性の受容 ”があります。
例えば同じ言葉でも、人それぞれ
いろんな受けとり方やイメージがありますよね。
それと同じく、ひとつの物事を
「こうするもの・こうあるべき」
というふうに固定してしまわずに、
あらゆる見方や考え方がある、
人によってさまざまである、
という柔軟な考え方ができる、そんな力です。
わたしはわたしのままでいい。
あなたもあなたのままでいい。
そんな思いやりにも繋がりますね。
これは、選択肢を広げることでもあります。
生きていく中で、自分の進む道を決めるとき、
日常の「どうしたらいいかな?」と思うようなときも、
選択肢や方法はたくさんあった方が
より自分らしい、自分に合った方法を
選ぶことができますよね。
白黒はっきりさせる、や、
0か100のどちらか、
というような二者択一の考え方は、
選択肢が二つ、と、とても少ないです。
十人十色と言うように、
0か100、ではなく
“ 100通り ”と考えるなら
100の選択肢があるので、
とても自由な感じがします。
ひとつの考えに縛られることなく、
多様な側面から考える力を取り戻すことは、
自由を取り戻すことでもあるんですよね。
「この方法が無理でも、まだまだたくさんの
選択肢があるから、大丈夫。」
そう思うことで安心感もありますね。
子どもがそんなふうに、
あらゆる可能性を吟味することができる、
多様な価値観が受容される、
いろんな側面から考えることができる、
という安心感を持てるように
親も視野を広げていきたいですね。
子どもの個性を伸ばすには。
子どもの持つ個性を存分に伸ばしてあげたいですよね。
そのために親はどうすればいいか?
ということなのですが、
子どもが小さいうちは個性を伸ばす、
という作業もなんだかまだ実体が掴み難いと思います。
しかし、実は小さいころからの保護者をはじめとする
周囲との関わりがとても重要な意味合いを持つそうです。
例えば、
義務教育を終えて、進路を決めるという時に
「自分が本当にしたいことって何だろう?」
と“ やりたいことがわからず ”に
特に目的もないけれどまだ働きたくないし、
とりあえず進学、や、何もせずブラブラ・・
そんな自暴自棄な状態は本人も充実感や
喜びを感じることが出来難く、辛いです。
そんな思いをさせないようにするためには、
得意なことがあれば苦手なことがあってもいい、
「無理やり苦手を克服させようとしない」
ことだそうです。
例えば勉強で、「どれも平均」
「みんなと同じ」
「世間一般でいう普通」
に合わせるために「苦手」で、
それ故に「嫌い/やりたくない」ことを
「どれもできるようになりなさい。」
と言われて無理にでも頑張ることが続くと、
「勉強=苦痛な時間」
になってしまうんですよね。
勉強に限らず
イヤなことを無理に
「させられる」ことって苦痛ですよね。
そうした「不快感」は脳に強烈に残ります。
良かったことより、イヤだったことの方が
よく憶えてるそうです。
「苦手を克服する」ためのエネルギーは
「得意を伸ばす」方に使うように
するといいそうです。
好きなことは、苦にならないし、
自然に集中できますよね。
得意なこと、好きなことがはっきりしていると、
例えばそのために
将来を見据えた行きたい学校などに進むための
進むための勉強もはかどるでしょうし、
合格することが目標ではなく、
受かったからここでこれを学びたい!
のような新たな目標も自然と出てきます。
いろんな分野で世界的に有名な方々も、
「得意・好き」を伸ばした結果なんでしょうね。
その「得意」は「親が決めたこと」
ではないと思うのですが、
そのことに気づいていないと、
自分と子どもの境界が引けなくなり、
親の理想を押し付けてしまうかもしれません。
「子どもがやりたい」ことなのか、
「自分が、やらせなければ・やらせたい」
と思っていることなのかを
考えるのはとても大切です。
それがなければ、やがて子ども自身も、
苦手と得意の境界が曖昧になってくるんですね。
自分の気持ちで動いていないので、
「これをするのが好き・得意」という
“ 気持ち ”がわからなくなってしまうんですね。
心配も、し過ぎると苦手ばかりが気になり
他の子どもと較べたりすることで、
焦ったり、期待しすぎたり、詰め込もうとしたり。
そんな子どもも自身も追いつめるような
状態に陥らないよう気を付けたいですね。
苦手も得意も大切なその子の個性。
どちらもあっていいんですよね。
比較という抑圧
ありのままの自分を尊重できるようになるためには
まず保護者自身が自分のありのままを
尊重することが大切ですよね。
そんな大切な自己尊重( 肯定 )感を
低くしてしまう原因として、
一番見え難く、しかも深く蝕まれるのが、
「 “比較”という抑圧 」なんだそうです。
私も自己尊重について学習して初めて、
「あぁ、これもあれも、それもそうなんだ」
と思ったくらい、それは身近にあるようです。
例えば「もっと強くなりたい」
という願望もそうなんですね。
失敗したり、何か落ち込むような出来事が
あったときなど、自分自身にそんなふうに
言い聞かせたり、願ったりするようなこと、
そして、子どもに対しては、
「~に負けない、強くたくましい子になってほしい」
というように願ったりすることです。
これらは、
「比較という抑圧」
を受けた考え方なんだそうです。
“ 強くなりたいと願う ”といういうことは
“ 弱い自分ではダメだ ”と思っているからですよね。
自分にバツをつけていることになってしまいます。
私は、人間は強いだけではなく、
強くて弱い、弱くて強いのだと思います。
「私は弱いからダメ」と感じてしまうのは、
それだけ抑圧を受けて、自分の可能性を、
内なる力(生命力)を信頼できなくなっているだけで
本当は「強さ」も持っているんですよね。
自信を奪われているだけなんですよね。
強くなろうとしなくていいんですよね。
自分のままでいいんです。
弱い自分も、強い自分も、大切な自分です。
強い弱いや勝ち負けなど、
“ 比較という抑圧 ”で
自分を傷つけることのないようにしたいですね。
イライラを減らす方法(限界設定)
専門家の方にアドバイスいただいた中に
自分自身の“ 限界設定 ”というのがありました。
例えば、
“ 母親だからこれぐらいできて当然だ ”
“ 母親なのだから子どもを思うなら
このくらいガマンして
~してあげるのが当然だ
(=育児は忍耐である) ”
というような価値観の刷り込みがあると、
とても疲れます。
もちろん、子どもの幸せを願って行動することは
とても素晴らしいことだと思いますが、
それも“ 自分自身の限界 ”を超えてしまうと、
ストレスになり、逆効果なんですね。
上記のような“ できて当然 ”と
“ 自分が思っている ”ことが
できない自分にイライラして
子どもにキツイ言葉を言ってしまったり・・
“ 私なんて母親失格だ ”
“ こんなこともできないなんて情けない ”
というふうに自分を責めてしまったり・・
それが重なり悩む人も多いようです。
私もそうだったので専門家の方に相談してみると、
「いくら母親、父親であっても
一人の人間だから、個性・特性があり、
子どもと遊ぶことが好きな人もいれば
どちらかというと苦手な人もいて当然なんですよ」
「なので、できないことがあっても
自分を責めなくていいんですよ」
「それは良い・悪いでなく、“ 個性 ”ですからね」
ということでした。
そうして自分の個性を知って受けとめ、
自身の“ 限界を設定する ”と、
ストレスになる前に対処できる、
ということで私もやりました。
◆子どもから何らかの要求があったとき、
1~2回までなら快く応対できるけれど、
3回目になると イライラするようだ
◆子どもと遊ぶのは30分くらいなら
苦にならない、楽しめる、が、
それ以上になると疲れてくるようだ、などなど。
そうやって事例ごとに自分の限界を設定しておくと、
イライラを感じたとしても、
「あぁ、限界を超えたんだな、」と思うことで、
「私は母親なのにこんなこともできないなんて」
というような隠れた劣等感、
自己否定のような感情を感じずに済みますし、
イライラする前に
「お母さん、用事があるから(ちょっと疲れたから)
あと一回(あと5分、とか)だけね。」
などと言っておくことで、
“ 子どもにも心の準備ができる ”
ということでした。
自分の限界を知り、
それに合わせて行動することが
ストレスを減らす第一歩になるんですね。
“ 母親らしく・父親らしくあらねばならない ”
といった刷り込みに気づき修正することも、
自分らしい、自分に合った育児ができる方法です。
子どももそうした価値観の刷り込みで
今後辛い思いをしたりしなくてすむんですよね。