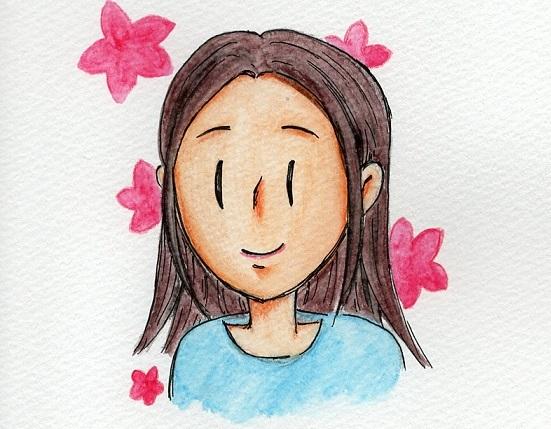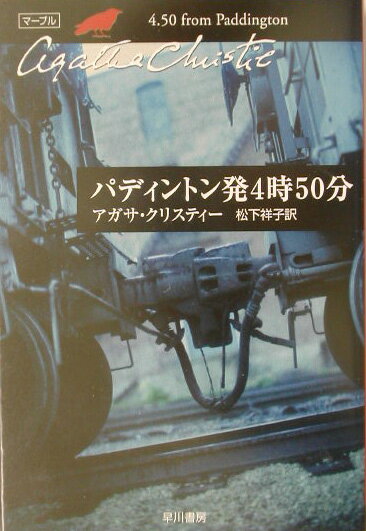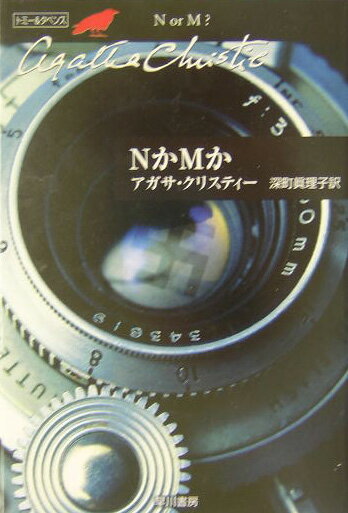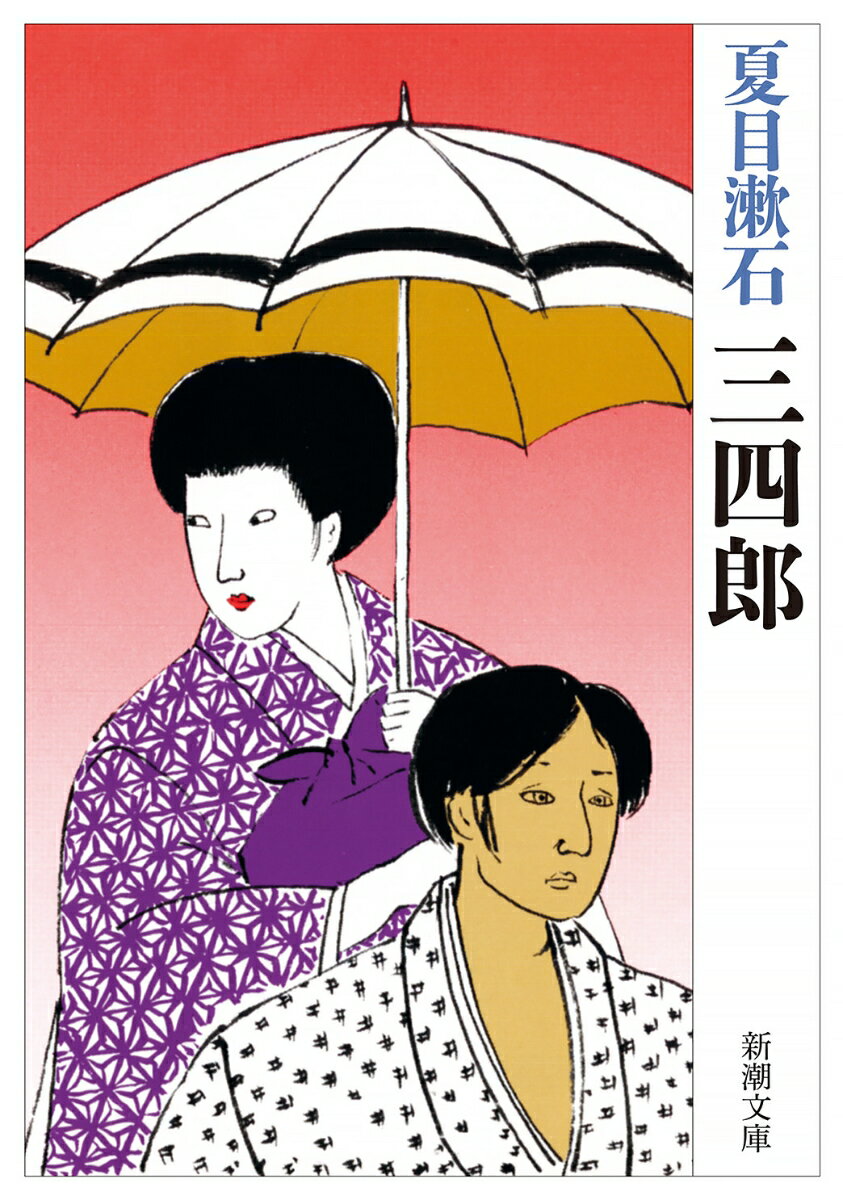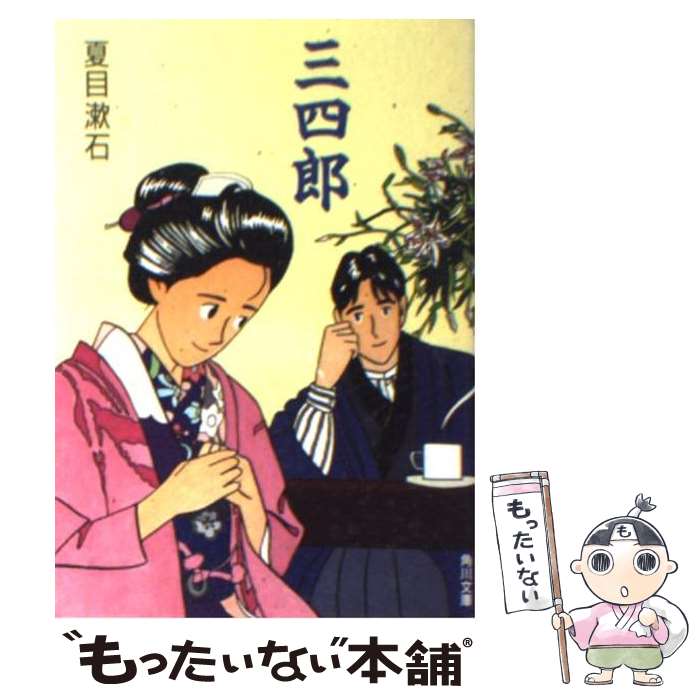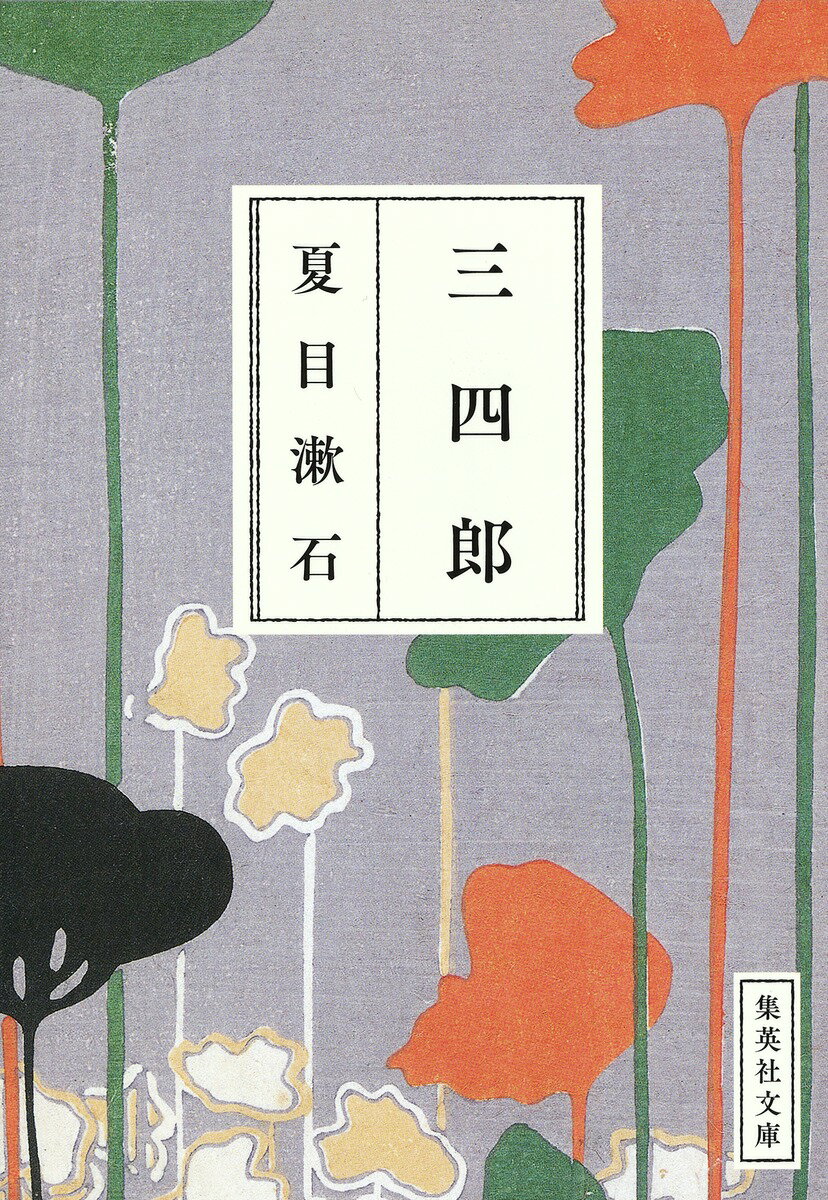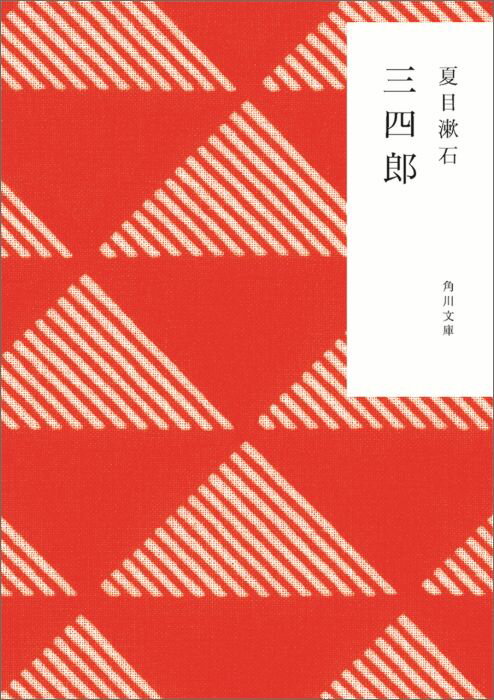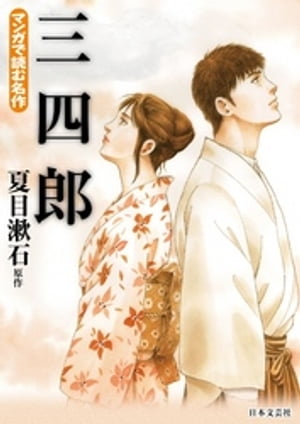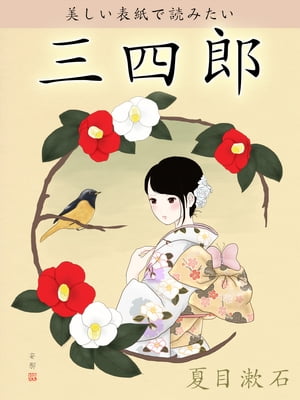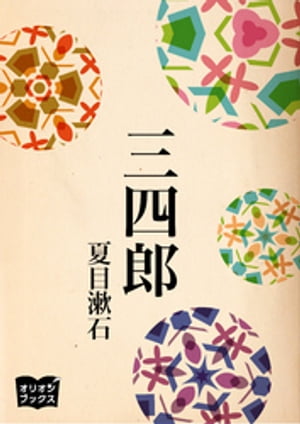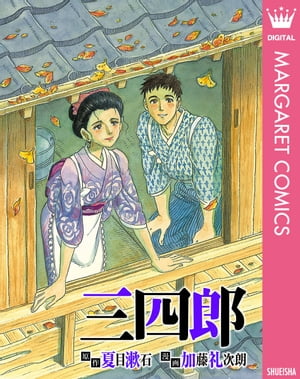2025年5月のテーマ
「私のあこがれの女性」
第三回は、
「お茶と探偵6 カモミール・ティーは雨の日に」
ローラチャイルズ 作、東野さやか 訳
ランダムハウス講談社 2008年発行
に登場する、
セオドシア・ブラウニング
です。
です。
今までに何度か記事を書いたことがある、"お茶と探偵"シリーズの一作です。
・・・結構書いてるな…。
それはさておき、まずシリーズの前提をご紹介します。
主人公のセオドシアは、サウスカロライナ州・チャールストンの歴史地区の一角にティーショップを構える妙齢の女性。熟練ティー・ブレンダーで古きよきものを愛するドレイトンと絶品スイーツを作る若きパティシエであるヘイリーとの三人で運営する彼女のティーショップは人気店の一つです。
好奇心旺盛で頭も切れるセオドシアは、知人を通じて地域のイベント会場で起きた事件を調べてくれと頼まれ捜査することになります。
毎回、ストーリーもさることながら、ティー・ショップで行われる"テーマのあるお茶会"や、結婚披露宴、美術館主催のパーティー、映画祭…などのゴージャスなイベントでのケータリングの描写などが盛りだくさんで、気分が華やかになるコージーミステリーです。
第6弾の「カモミール・ティーは雨の日に」は、歴史協会で開かれた<詩とお茶の会>で殺人事件が起きてしまうお話。
折しも外は嵐で、エドガー・アラン・ポーの詩の朗読の最中に一発の銃声が響き渡るという、映画のワンシーンみたいな状況で始まります。セオドシアたちのインディゴ・ティーショップはこの会のケータリングを担当しており、嵐のせいで会場が変更になったドタバタシーンから一転、事件の目撃者になります。
被害者はドレイトンの知人で警察の容疑者はヘイリーの友達となれば、セオドシアが真相究明に乗り出すのは自明の理です。
また、現時点で30冊近くあるこのシリーズで今回この作品を選んだ理由ですが、この作品以降セオドシアがぐっと人間らしくなるからです。
前回のルーシー・アイルズバロウもそうでしたが、セオドシアもスーパーウーマンです。
彼女はかつて広告業界で働いていましたが、目まぐるしい日常に疲れ果て、誰もが安らげるティーショップを自分で経営する道を選び成功した実業家。居心地のいい自分のティーショップを持ち、一緒に働く仲間たちとは同僚というより家族といった関係を築いています。
店では頻繁に"テーマのあるお茶会"を開催していて、そのどれもが素敵。お茶を使ったボディーソープなんかのオリジナルブランドも展開中。地域のイベントにもドレスアップして顔を出し、ケータリングの仕事を通じて歴史地区のハイソな住人達とも知り合いです。社会貢献にも熱心。
頭もよく、美しく、大型犬とランニングを欠かさないスポーツウーマン。
素敵な恋人もいて彼女を心配しつつも協力してくれ…ていました。第5弾までは。
この作品では、初めてセオドシアと恋人との間ですれ違いが生じて、彼女が悩む様子が描かれています。
また事件もこれまでに比べてちょっとシリアスというか、人間関係が生臭かったりもします。
第5弾までの作品では、周囲で起きた事件できりきり舞いするものの、プライベートのセオドシアはうらやましいくらいハッピーで、理解のある恋人とのひと時は彼女のモチベーション回復に一役買っていた感がありました。
そう、主人公がちょっと完璧すぎるようにも感じられたのです。
今作で、事件ではない、自分自身のことで悩むセオドシアが描かれたことによって、完璧な彼女がぐっと身近になったことは、私から見ればすごくプラス要素です。
だって、仕事でも調査でもすごく忙しいのに、ドレスをまとってチャリティーイベントとかにも参加して、恋人ともディナーを楽しみ、ティーショップ二階の自宅はアンティークの素敵な調度で飾られた居心地のいい部屋…っていつ掃除や洗濯しとるの???って思うじゃないですか。
まあ、そこは小説の中の話なので、リアリティがなくたっていいんですけど、私のようにあこがれが募るとちょっとでもまねできるところはないかしらなんて思っちゃうわけです。(ええ。身の程知らずですとも。)
だけど、
実際には無理!!!
こんなスケジュールで家のことまでできるわけないじゃん!!!
そうよね、実際にはこんな女性いるわけない。
悲しいことに、一つが作り物めいて見えちゃうと、作品世界に広がる一つ一つまで(ティーショップやイベント)非現実的に見えて魅力が薄れるような気がしてしまいます。
でも、第6弾以降、セオドシアのプライベートな部分が素敵な面だけじゃなく描かれるようになりました。
例えば、どの作品だったか忘れちゃいましたが、自宅で恋人が持ってきてくれた白ワイン(だったと思う)を飲もうという時に、セオドシアがしまってあったワイングラスに埃がついていることに気づいて、こっそり吹き飛ばすシーンがあります。
店のグラスはいつでもピカピカにしているけど、自宅のものまでは手が回らない。そこまで完璧にすることに人生の時間を費やしてはいられない。…というようなことを考えるのです。
いい意味で力が抜けてきたというか、私としては共感しやすくなりました。
また、この作品に限ってのことではないですが、セオドシアは地域への社会貢献に熱心です。
そのためいろんな人とつながりができますし、地元の活性化に一役買っています。
そういうところも私があこがれる要因です。
それから、美人で親切、魅力的な大人の女性でありながら、精神的にタフで芯が強いです。
無鉄砲なところもあって、毎回最後には犯人と直接対決する羽目になり、食いしん坊で腕利き刑事のティドウェル警部に助けられたり叱られたり。
この辺りは今月第一回目の記事で書いたタペンスに通ずるものがありますね。
"お茶と探偵"シリーズは、おいしい食べ物に、華やかなイベント、魅力的な主人公とミステリーの組み合わせで、コージーミステリーとして最高です。
ただし、私の中のミステリーファンの部分が、セオドシアは探偵としては優秀とは言い難いと言っています。容疑者を一通り調査するものの誰かわからず、犯人と接していた時にちょっとしたきっかけで今までのことが全部つながる…的なことがよくあり、そのせいで自分がピンチに陥ることもしばしばあるからです。
個人的に、犯人が油断しているうちに正体を突き止めて罠にかけ捕まえる…という展開が好きなので、そのせいかもしれません。
「カモミール・ティーは雨の日に」は現在絶版になっているはずなので入手しにくいかもしれません。
でも、"お茶と探偵"シリーズは原書房さんから新刊が出ているので、ぜひそちらも手に取ってみてください。
おすすめいたします。(*^▽^*)