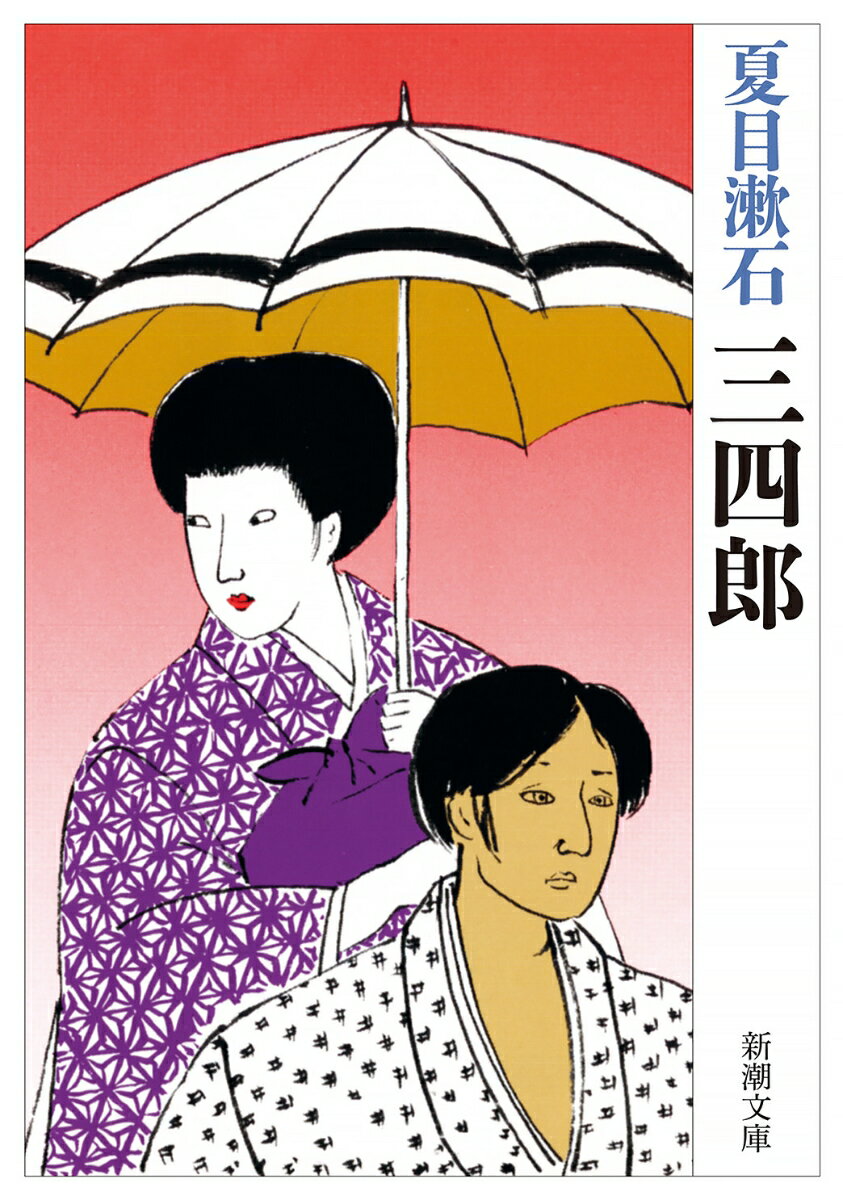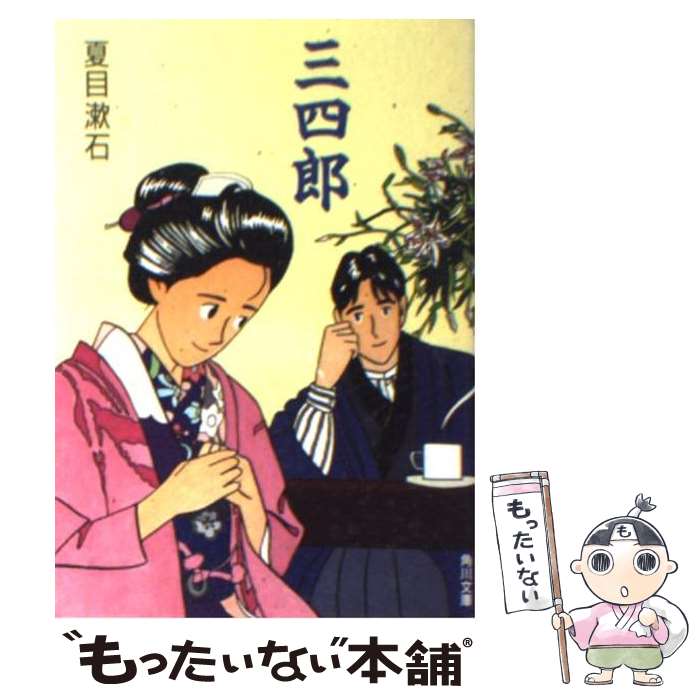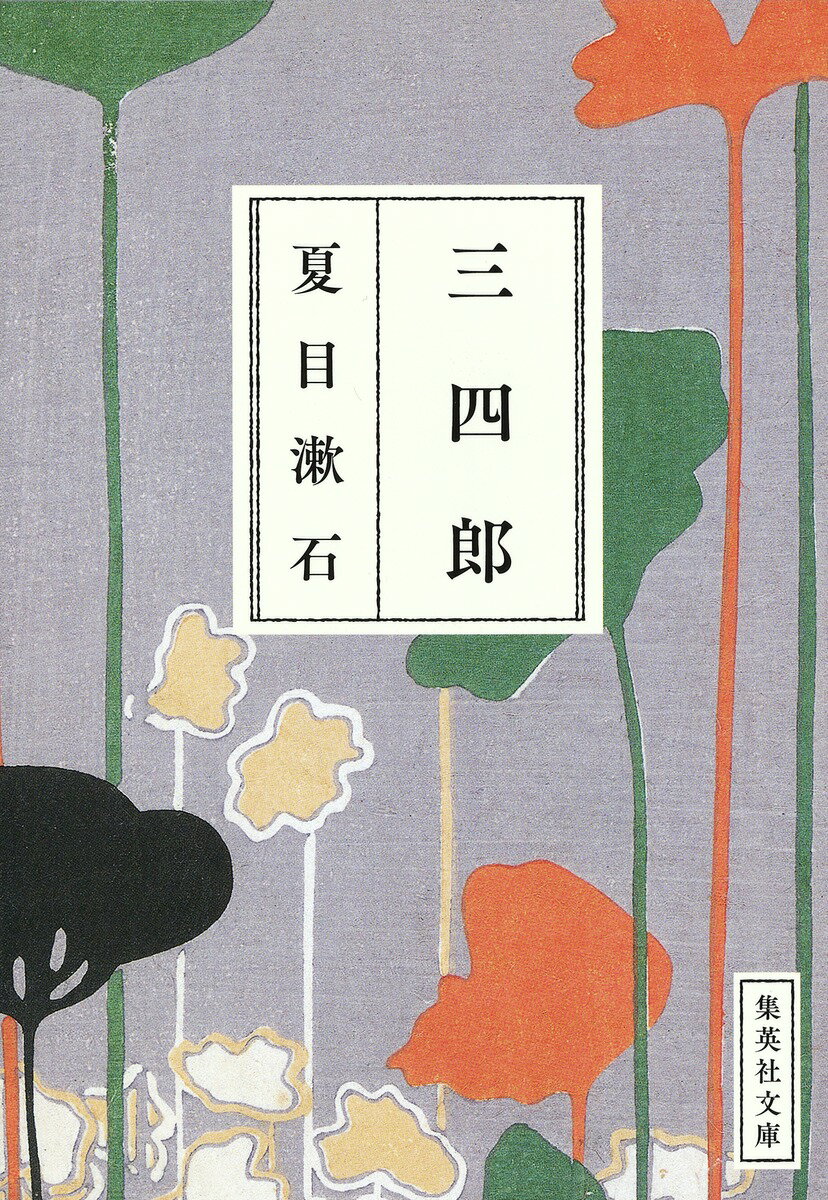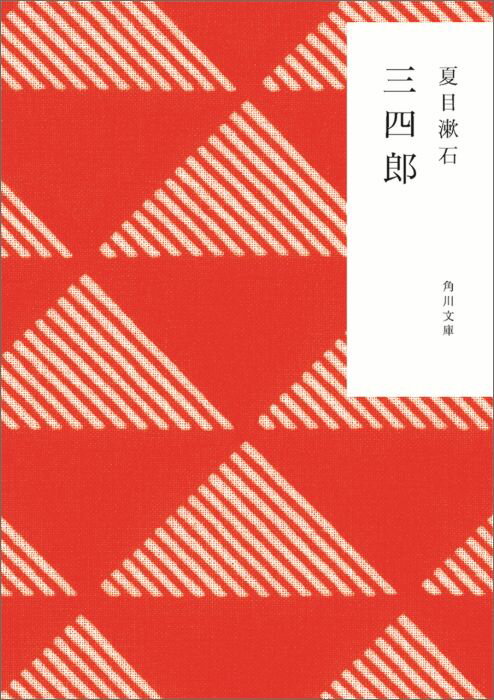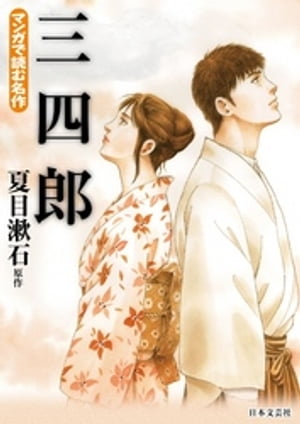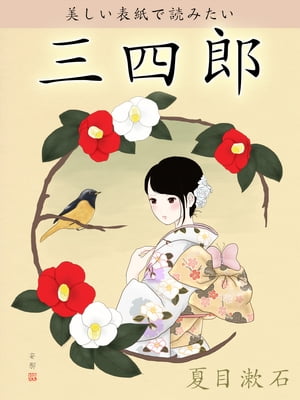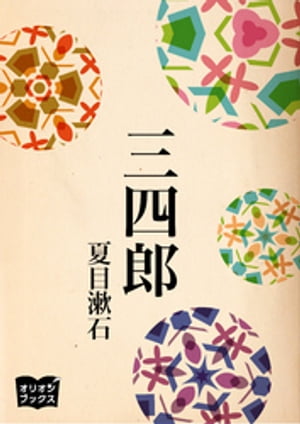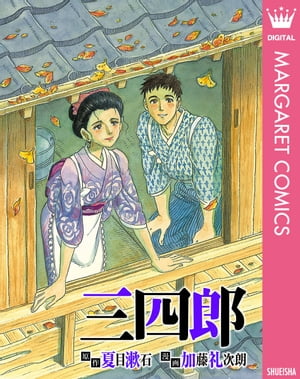2025年4月のテーマ
「青春小説に触れよう」
第三回は、
「三四郎」
夏目漱石 作、
新潮文庫 1948年発行(?)
です。
本書が手元になくて新潮文庫の発行年を調べたところ、新潮社のサイトで"発売日"となっているのが1948年なので、多分この年でよいかと思いつつも不安が拭えず後ろに"(?)"とさせていただきました。
言わずと知れた文豪・夏目漱石の青春小説です。
あらすじは…。
大学進学で九州から東京に出てきた小川三四郎は、同郷で大学教師の野々宮を訪ねた際に大学構内で美しい女性を目にします。その後、彼女(里見美彌子)と知り合う機会を得ますが、美しい彼女に恋慕する男性は数多く、三四郎も密かな恋心を抱きます。故郷とは違う大都会で、何もかもが新鮮な学生生活に、三四郎の世界は広がっていきます。
エピソードの一つ一つは三四郎の都会生活における新たな発見であったり、友人知人との交友、恋…と日常描写になるので、大きな事件を解決するとか恋敵と好きな女性を取り合うみたいな分かりやすいテーマが示された物語ではないです。
現在の刺激の多い作品("衝撃の結末!"とか、"こんな展開みたことない!"等の宣伝文句が帯やPOPにつくような作品)を読みなれている方であれば、退屈だと感じられることでしょう。
ストーリーでぐいぐい引き込むという物語ではなく、田舎から都会に出てきた青年が、違う土地・新しい生活の中でたくさんのことを学んでゆく日常を描いた物語だからです。
でも、だからこそ、興味深いところがたくさんあります。
例えば、三四郎が九州から列車で上京する場面で、遠いので途中の名古屋で宿泊することになり、そこで間違って女性と相部屋にされてしまいます。困っている女性を宿なしにするわけにもいかず、かといって明治時代には男女が相部屋なんてもってのほか!という価値観も今より強かったことでしょう。
三四郎は努めて女性を避けようとしますが、女性ははっきりとではないけれど誘惑するような雰囲気を出してきます。
三四郎としては訳が分からず、あいまいな態度で濁しながら警戒してかわしますが、翌日の別れ際に女性から「あなたは意気地のない人ですね」(この通りの文言ではないかもです。手元に本がないので…。)と言われます。
私は初読の時、物語の冒頭と言ってもいいところに、なんでわざわざこの場面が必要なんだろうと疑問に思いました。その後この女性と再会してなにか問題が起きたりする伏線なのかなあ…とか勘ぐったりして。
でもそれは私がミステリーばっかり読んでいる弊害で、伏線回収に目を光らせながら読む習慣がついているせいです。
作中でその女性は二度と出てきませんでした。だから、なぜこの場面が必要なのかと思ったわけです。
後になってから、郷里から出てきたばかりの三四郎が世間知らずで無垢であることや真面目な性格であることを読者に印象付けるエピソードだったのだと気づきました。はっきり物申すようなタイプではないということも分かります。
また、三四郎が列車に乗っている場面で、乗客が食べ終わった弁当の箱を窓から外に捨てる描写があります。私はそれを読んでびっくりしたんですが、当時はそれが当たり前だったというのを後で知りました。
東京に来てからの三四郎は、友人の与次郎と洋食屋にライスカレーを食べに行って「学問ばかりではなくて世間のことも知らなくちゃな」(文言は全然違います。意訳です。)と言われたり、美彌子も含めた数人で菊人形見物に行ったりと青春を謳歌してるな~と感じます。
何が言いたいかというと、「三四郎」は明治時代の平凡な学生である主人公を通して、当時の若者の青春を追体験する小説だということです。
三四郎は真面目で好青年だと思いますが、悪い言い方をすれば個性が感じられない人物です。
彼の周りで起きる日常の小さな事件は、誰にでも起こりうることです。特別稀有な出来事とは感じられません。
三人称で書かれており、三四郎の胸の内はそれなりに描かれてはいるものの、あからさまではありません。彼の行動や言葉から推測することになります。
恋のときめき、苦悩、友情など、時代は変われど普遍的な感情が描かれている一方で、明治時代の日常の描写は今の私たちの常識からはかけ離れている部分もあり、それを発見するのもこの小説の楽しみの一つだと思います。
この時代の価値観というものがあるので、恋愛一つとっても、親の許しがないと結婚できないだろうし、面識がなくても同郷の先輩が面倒を見てくれたり、ヒロインの美彌子は美しいだけでなく教養もあるのですが、それはともすれば生意気と捉えられたり…現在の価値観とはやはり違います。
しかし今は多様性の時代。価値観とは時代や場所、個人の置かれている状況や経験などによって変わるものです。明治時代の価値観は今の時代からは逆行してはいますが、自分とはちがう価値観で物事を見る練習にはなるという一面もあります。
以前にも書いたことがありますが、作品が書かれた当時の価値観を理解せずに現在の価値観でぶった切ってばかりでは、作品が伝えてくれる本質を捉えられずにもったいないばかりですので…。
さてさて、だらだら書いてしまいましたが、興味をお持ちになった方は、「三四郎」を読んで、明治時代の学生の青春を追体験しちゃいましょう。
私が読んだのは新潮文庫でしたが、角川書店や集英社、電子書籍でも出ているし、今は絶版になっているものも…とにかくたくさんいろんな版があるので、カバーデザインや文字の大きさなどお好みの本を探すこともできます。
(私は昔の角川文庫のデザインが好きで図書館で探す時にあればいいなーと思ってましたがなく、記事を書くにあたって調べた時に中古でしか発見できませんでした。残念ながら絶版になったみたいです。下に貼ります。)
おすすめいたします。(*^▽^*)