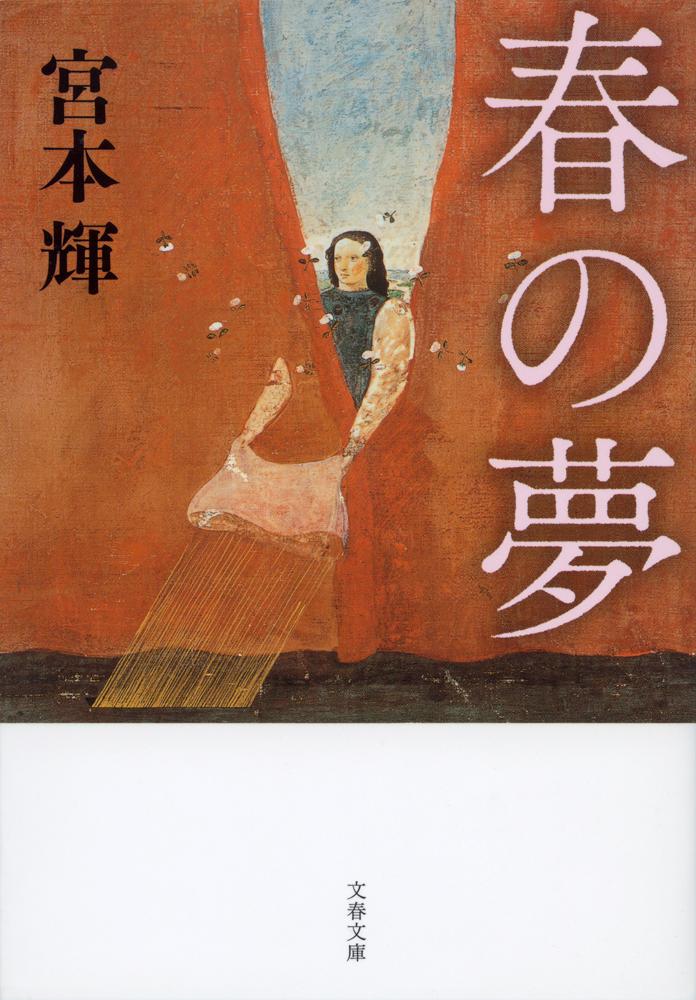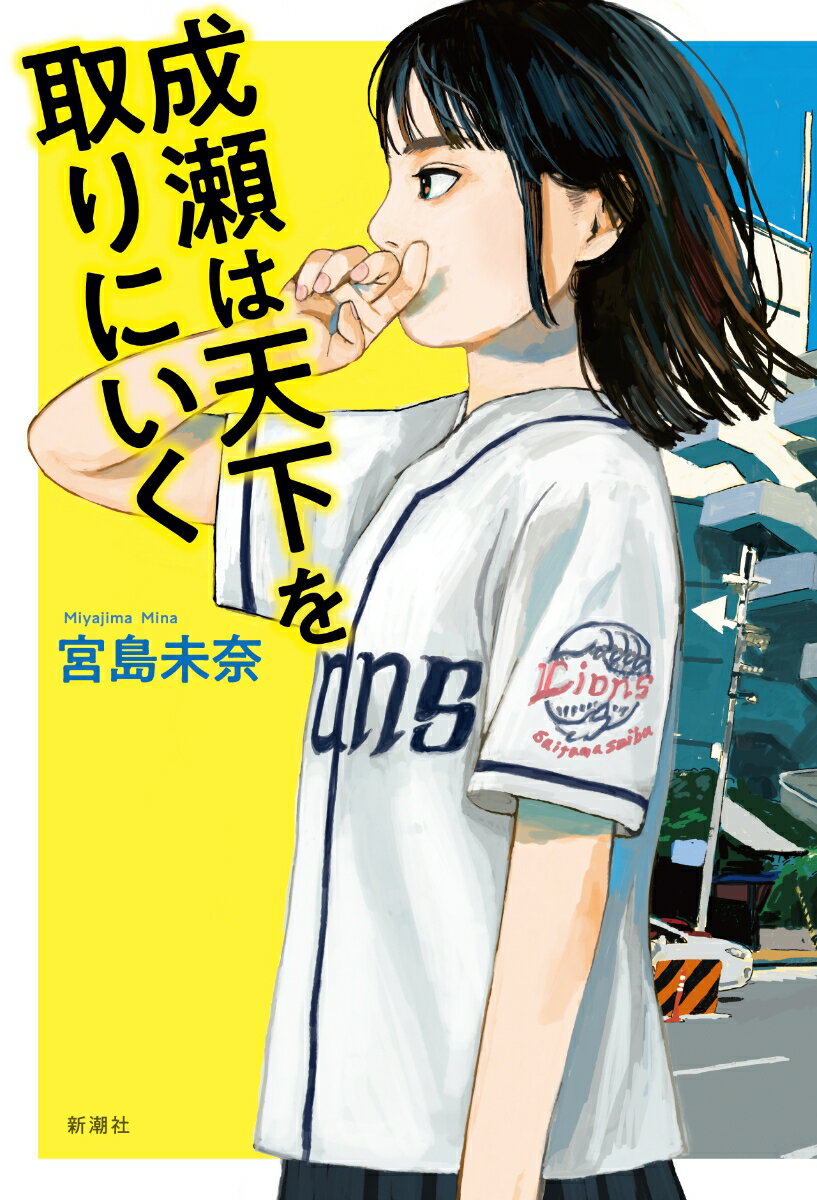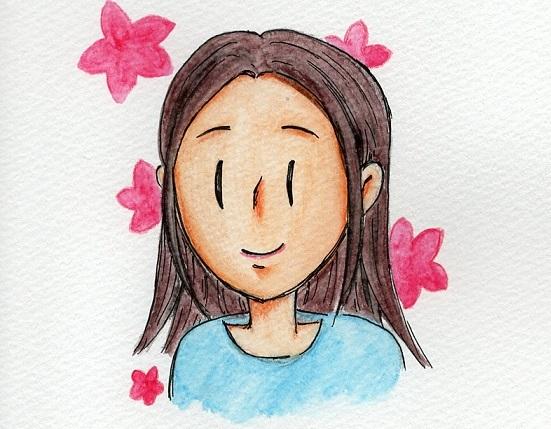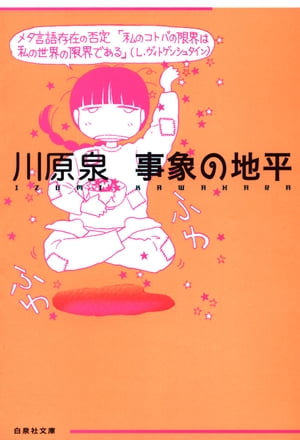2025年4月のテーマ
「青春小説に触れよう」
第二回は、
「春の夢」
宮本輝 作、
文春文庫 1988年発行
です。
今は新装版が出ているようなので、アフィリエイトに貼ったものと私が所持しているものとは解説とか違っているところがあるかもしれません。
さて、あらすじをば…。
亡き父親の借金を背負うことになった大学生の井領哲之は、母と離れて安アパートで独り暮らしを始めます。転居初日にまだ電気が通っていない暗い部屋の中、手探りで柱に釘を打ち付けたところ、誤って蜥蜴(とかげ)を打ち付けてしまったことに明るくなってから気づきます。痛々しい姿でありながらも蜥蜴はかろうじて生きており、釘を抜いてしまうとその行為で死んでしまうと思われたため、哲之は釘を抜くことができず蜥蜴の世話をすることに…。
あと一年で必ず卒業して社会人となることを心に決めた哲之は、借金を返すためにホテルのボーイのアルバイトをしながら学業に励みます。恋人の陽子は彼を支えますが、その彼女に思いを寄せる男性の登場に哲之の心は乱れます。
大学最後の一年を、お金もなく、唯一の支えである恋人との愛はおびやかされ、それでもひたむきに生きる青年の物語です。
このお話を初めて読んだのは私が主人公の哲之とあまり変わらない年齢であった頃でした。
とはいっても、出版されたのは10年以上も昔のことでしたから、社会の在り様や学生生活なんかは時代が違えば同じとは言えず、当時の私は主人公の哲之に対して親近感のようなものはあまり感じていませんでした。
男女の違いもあると思いますが(特に恋人に対する思いや異性に対してなにを魅力と感じるかなど、ぴんとこないところもあったので)、彼の境遇はあまりに厳しく、それも突然訪れた苦境だったので、想像することが難しかったからです。
彼にとっては大学のキャンパスでの学生生活よりも、アルバイト先のホテルでの出来事や、母と共に借金の返済に頭を悩ませたり、恋人との行く末を案じたりすることの方が生活の中心になっていて、とにかく必死で一年間頑張ろうとします。
それでも、気持ちが落ち込むこともあるし、苦悩の種は尽きません。
そんな時に、主人公は柱に打ち付けられてしまった蜥蜴に話しかけます。
この蜥蜴にはキンちゃんという名前が付けられ、主人公の同居人(?)として世話され、独白の聞き手にされています。
キンちゃんからするといい迷惑だと思いますが、哲之がちょっと重荷を下ろしたいときや、愚痴を言いたいときにキンちゃんに話しかけ、自分の気持ちを整理しているような場面がたくさん出てきます。
キンちゃんがいなければ、彼は一年を乗り越えることはできなかったかもしれません。
また、突然柱に打ち付けられ身動きが取れないまま生き続けているキンちゃんはこの物語の象徴なのです。
実のところ、私は遥か昔に読んだこの小説の細かい内容やエピソードはほとんど忘れてしまっています。
でもキンちゃんのことは覚えているし、キンちゃんに象徴されるこの小説の大まかな内容は覚えています。
この作品は、苦境にひたむきに立ち向かう青春のエネルギーを描いた小説だと思います。
主人公を取り巻く状況は厳しく、楽しくてハッピーなお話でないことは明白です。
しかし、何の悩みもない、ただただ楽しくてハッピーな物語(そういう物語があると仮定しての話ですが。)なんて、何が面白いのでしょうか?
現実逃避する(場合によっては癒されるのかもですが…。)こと以外に、その物語から得られるものはありますか?
この物語は明るいお話ではないですが、主人公が格闘した一年間でつかみ取ったものは彼の人生の土台になり、未来への希望を感じます。少なくとも、読んだ当時に主人公と同世代で人生経験もあまりなかった私には、想定外の苦境が訪れた時に、それと格闘することの大変さだとか、それでも戦い続けることの大切さだとか、学んだことがたくさんあったと思います。
この小説は、1982年から二年余りにわたって雑誌に連載されていた作品だそうで、掲載当時は「棲息」というタイトルだったようです。(本書の解説より)
それがなぜ「春の夢」というタイトルになったのか…ここまで記事で書いてきたことを読んでくださったなら大方の予想はつくかもしれませんが、作品を読んでみれば実感として分かります。
最後に、ちょっと脱線しますが、昨今、昭和の時代にスポットを当てたテレビ番組や動画配信なども多く、そういったものを見た時に私は"昭和の頃って色々乱暴な時代だったけど活気はあったよね"という制作側のコンセプトを感じます。(すべてにおいてではないですが。)
実際にバブル期なんかもあったし、日本の景気が良かった時代ではあったとは思うんですけど、昭和末期ごろに書かれたこの小説では主人公は本当に貧乏で、景気のよさとか活気とかはあまり感じられません。
テレビ番組や動画配信で目にする昭和の姿とはまた別の、当時の時代感なんかも感じられると思います。
昭和末期の大学生が人生と格闘する姿を描く青春小説です。おすすめいたします。(*^▽^*)