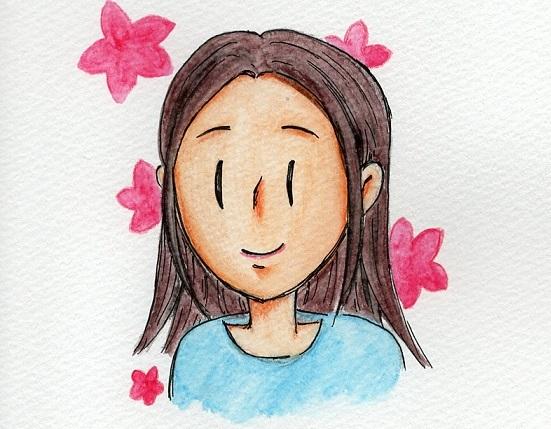2022年2月のテーマ
「紅茶×ミステリーな本」
第三回は、
「お茶と探偵18 オレンジ・ペコの奇妙なお茶会」
ローラ・チャイルズ 著、東野さやか 訳、
原書房、2018年発行
です。
これまで何度もこのシリーズの本をおすすめしてまいりましたが、今月のテーマにはぴったりのシリーズなのでご勘弁を。
ティーショップを経営している女性が主人公であり、毎回魅力的なお茶会のイベントが盛りだくさんのこのシリーズの中でこの本を選んだのは、冒頭で起きる殺人が前回おすすめした「ポケットにライ麦を」を彷彿とさせるからです。
といっても、その後の展開は全然違いますけどね。
まずはストーリーから・・・。
豪邸で催される「ネズミのお茶会」に招待された主人公セオドシアとティーショップの仲間であり粋な紳士のドレイトン。ネズミの被り物にお仕着せ姿の給仕たちが料理や紅茶を運ぶ奇妙なお茶会で、いつもとは逆にもてなされる立場を楽しんでいましたが主催者ドリーンの夫がオレンジ・ペコを飲んだとたん苦しみ悶えて死んでしまいます。てっきりお茶に毒が入っていたものと思われますが、事件はそう単純ではなくて…。
冒頭の展開が「ポケットにライ麦を」と重なりませんか?
まず、「ネズミのお茶会」って何ぞや?って感じですが、ちゃんと歴史上のお茶会のオマージュのようです。
この物語の舞台となっているアメリカのサウスカロライナ州チャールストンでかつて人口増加に伴ってネズミが爆発的に増えた際に、公衆衛生上取られたネズミ撲滅作戦(駆除剤を含んだ餌を仕込むなど)がありました。その活動を上流階級の夫人たちが支援した際に行われたのが「ネズミのお茶会」だそうです(ドレイトン談)。
もっとも、当時はお茶会の目的が「ネズミ撲滅」だということを示していただけで、被り物などの扮装は主催者ドリーンのアレンジといったところですが、とにかく、慈善家で名が通っているドリーンがかつての「ネズミのお茶会」を復活させたというわけです。
奇妙なお茶会でお茶を飲んだ屋敷の主人が倒れるなんて、不思議の国のアリスっぽいというか、ちょっと現実離れしたシュチュエーションが目を引きます。
しかし、そのあとは現実世界に引き戻された感じで、手段・機会・動機を吟味して殺人犯を特定していくミステリー。
被り物で顔が隠れていた給仕たち、被害者の家族に事業の共同経営者、何故かなんにでもくちばしを突っ込んでくる被害者の広報担当者、被害者に投資させていた詐欺師など、だれもかれもが怪しく見えます。
事件の捜査をしながらも、日々のティーショップでの仕事や主催するイベントに大忙しの主人公の姿勢には、毎度頭が下がります。
"リア充"という言葉がありますが、本人が口にする言葉というよりは他人から見てそう見えるという時によく使われる言葉だなあと私は感じています。
セオドシアは一言で表すならこの"リア充"がわかりやすいと思うんですが、あまりそう表現したくないなというのが正直な気持ちです。
彼女が忙しくしているのは、人生を一生懸命に、自分のやりたいように思い切り生きるために行動している結果なのです。
たくさんイベントのお茶会を開くのも、大切なティーショップを経営する上での戦略ですし、一つのイベントが大盛況に終わったとき、仲間のドレイトンと「今日もささやかな成功を収めた」と満足し、店のメンバー全員で努力が報われたことを称えあいます。
こういうことってとても大事だなと毎回考えさせられます。
なので、彼女が行動した結果、精神的に満ち足りるということが本質なのであって、プライベートで忙しくしていることやうまくいっていそうに見えることを指す言葉としての"リア充"とはちょっと違うなと感じるのです。
でも、もともとは"リア充"っていう言葉の本来の意味はセオドシアが体現しているようなことだと思うんですよね。みんなが便利にこの言葉を使いすぎて、本来の意味でない時に乱用された結果、現在では私が抱いているようなイメージで使われているのではないでしょうか。
もし、私のイメージの方が間違っているのなら、お恥ずかしい限りですが・・・。
話が本筋からそれてしまいましたが・・・お茶と探偵シリーズで「お茶に毒」の殺人で始まる事件といえば、シリーズ1作目の「ダージリンは死を招く」か、シリーズ8作目の「ロンジン・ティーと天使のいる庭」あたりが真っ先に浮かびますので、そちらもご興味ありましたら読んでみてください。
今回は、「オレンジ・ペコの奇妙なお茶会」をおすすめいたします。(*^▽^*)