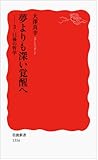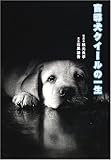読んだ論考
もう一つのメディアとしての博覧会――原子力平和利用博の受容
吉見俊哉
所収
土屋・吉見(編)
占領する眼・占領する声
CIE/USIS映画とVOAラジオ
東京大学出版会
2012年7月
先日ブログに書いた、同じ著者、吉見俊哉の、ちくま新書「夢の原子力」は2012年8月10日発行であった。こちらは2012年7月31日である。ほとんど同時に出されている。
新書では書かれなかった細やかな情報が得られるのではないかと期待して読んだところ、すぐさま、以下のことに気づいた。
この論考は、実は、新書の第II章の内容とほぼ同一である。
にもかかわらず、どこにもクレジットがなかった。
たとえば、書籍版では、こう書いている。
「正力松太郎を社主とする読売新聞社は、1954年8月に新宿の伊勢丹百貨店で「だれにもわかる原子力展」を開催し、翌年5月には、原子力潜水艦を建造したゼネラル・ダイナミクス社社長らを招いて日比谷公会堂で「原子力平和利用大講演会」を開催した。」(293ページ)
これと新書の、次の文章を比較してみよう。
「正 力は、1954年8月には新宿の伊勢丹百貨店で「だれにもわかる原子力展」を開催し、翌年5月には、原子力潜水艦を建造したゼネラル・ダイナミクス社社長 のホプキンスらを招いて日比谷公会堂で「原子力平和利用大講演会」を開催し、この戦略の日本側の窓口となっていた。」(122-123ページ)
この二つの文章を、まったく別の文章と思う人は、まずいないであろう。
このあとも、ほぼ同一の内容が続く。一部削除や加筆もあるが、誰が読んでも、元は同じテキストであると感じるくらいに、違いは少ない。
書籍のほうは、おそらく校閲はあるものの、ほとんど編集者とのやりとりがない、と想定しうる。その一方で、新書収録の際には、編集者とのやりとりが多いにあったと思われる。
そもそも、こうした、重複した内容を掲載する場合、できることなら、初出なり、なんらかの断り書きがあってほしいものである。それが、読む側に対する敬意というものであろう。
内容的にはとてもすぐれたものなのに、こうした本の作り方は、読者からみると、残念に思ってしまう。
しかし、ここで書きたいのは、そういったことではない。もっと本質的なことである。
私がここで問いたいのは、吉見が、東大出版会の本と新書で、「被爆」と「被曝」の使い分けについて、大きく変えていることである。
これは、原爆や原発を考えるうえでの根幹にかかわってくる。
吉見がどのようにこの二つの語彙を用いたのかを見直すことは、誤植とか校正の次元ではなく、私たちが、被爆や被曝とどうかかわって生きてゆくのか、どう考えてゆくのか、その一つの方向性を示しているように思われる。
ただ、勝手に推測すると、編集サイドから「ここはすべて「被爆」で行きましょうよ」などと促され、その結果、同意して、「被曝」を「被爆に」変えるか削除したのではないか、と思われる。
きっかけはここでは問わない。両者の異同が、結果として、何を語っているのかを、私たちはしっかりと見届ける必要がある。
***
書籍に収録されている論考をベースにして、以下、差異をみてみる。
前段が書籍版で、後段が新書版である。「被爆」の「爆」には青色をつけた。「被曝」の「曝」には赤色をつけた。
「平和記念館(第二会場)が当てられていく。こうして開館したばかりの施設での原爆資料展示は、博覧会会期中、近隣の公民館に一時的に移され、本来の展示場所から排除されることになった。」(300ページ))
↓
「平和記念館(第二会場)が当てられていく。被爆のシンボル的空間での開催である。こうして開館したばかりのこれらの施設での原爆資料展示は、博覧会会期中、近くの基町の公民館に一時的に移されることになった。文字通り、原子力の「被爆」の展示は、原子力の「未来」の展示に取って代わられたのである。」(148ページ)
上記については、おそらくこの二カ所は加筆されたものと推測される。いずれも「爆」の文字を使用している。これらは、ヒロシマ・ナガサキに対して「被爆」という表記をしている。これはごく一般的な用法である。
「原爆資料の移転についても、無数の被爆者たちの神聖なる遺品を含む展示品が」「なぜそれを被爆者救済の福祉予算に使わないのか」(301ページ)
↓
(削除)
上記は、まるごとその行が削除されている。以下しばらく、いくつか「爆」の字が両方で使用されている箇所が続く。変更なしか削除なので、特にコメントは入れない。
「被爆体験の原子力平和利用への取り込みは」(302ページ)
↓
「被爆体験の原子力平和利用への取り込みは」(149ページ)
「広島と長崎の被爆者を巻き込み」(302ページ)
↓
(削除)
「被爆経験の悲惨さと原子力の平和利用がもたらす夢」(303ページ)
↓
「被爆経験の悲惨さと原子力の平和利用がもたらす夢」(152ページ)
「被爆直後の広島市街」(303ページ)
↓
「被爆直後の広島市街」(152ページ)
「被爆直後の降雨状態」(303ページ)
↓
「被爆直後の降雨状態」(152ページ)
「被爆時の写真や模型」(303ページ)
↓
「被爆時の写真や模型」(152ページ)
「被爆体験と平和利用」(303ページ)
↓
「被爆体験と平和利用」(152ページ)
ここまでは元の文が「爆」であったが、以下は書籍版では「曝」のものが登場する。ただしこの三カ所、新書版では削除されている。これも行ごとの削除であり、特に内容的な変化は見られない。
「被曝経験の恐怖から取り組みが立ち遅れている。」(305ページ)
↓
(削除)
「広島、長崎での被曝」(305ページ)
↓
(削除)
「核兵器による被曝と電線への感電はまったく別次元の事柄である。」(306ページ)
↓
(削除)
注目は、以下である。
書籍版は、はっきりと「爆」と「曝」を区別していると思われる箇所である。書籍版では、第五福竜丸の事故に対しては「被曝」を用い、ヒロシマとナガサキには「被爆」を使っている。しかし新書の方は、「被曝」を文中に一切使用していないのである。すべて「被爆」に変えられているのだ(もしくは削除された)。
「1950年代の原子力平和利用キャンペーンが戦後日本社会にもたらした影響には、この国特有の文脈において考えるべきことも多く存在した。キャンペーンが本格化する直前には、ビキニ環礁での水爆実験により、第五福竜丸の被曝事故が生じていた。この事故により、日本人の間には広島と長崎での被爆の記憶」(311ページ)
↓
「50年代半ばの日本では、一方でビキニ環礁での第五福竜丸の被爆から始まった原水爆禁止運動、他方では中曾根康弘らによって主導された原子力関連予算と原子力三法による原子力政策の推進が、ほぼ同時並行で対抗的に亢進していた。」(192ページ)
また、下記は、書籍版では「被爆」が使われていなかったところを、新書ではあえて新たに「被爆」へと書き直された場合である。ここでは、第五福竜丸事件に対して「被爆」が用いられている。
「第五福竜丸事件の直後」(312ページ)
↓
「第五福竜丸被爆の直後」(193ページ)
そして、最後。ここでも第五福竜丸は「被曝」から「被爆」へと書き換えられている。
「広島・長崎から約10年で第五福竜丸がまたしても被曝し」(312ページ)
↓
「広島・長崎から約10年で第五福竜丸がまたしても被爆し」(193ページ)
この最後の文は、ヒロシマ、ナガサキと第五福竜丸を同じものとして扱っているので、「またしても」という言葉が使われている。はたして、この両者は同じものだろうか。他の個所でも、二つの原爆被害と第五福竜丸事件を、同じ言葉でくくることができるかどうか、これは重要な問いであるが、書籍版でも新書版でもそれは説明されていない。
それどころか、吉見は、書籍版では、被爆と被曝を分けて使用していた。分けているにもかかわらず「またしても」と言って両者を同一のものとみなした。ここには矛盾がある(もしくは、この矛盾があったために、新書版ではすべて「被爆」を使うことで矛盾を解消したと解釈することも可能である)。
つまり、この二つのテクストのあいだにおいて、被爆と被曝は混乱したまま使用されている、と考えられる。
もっとも致命的なのは、新書のほうのあとがきである。こうある。
「な ぜ、広島と長崎、ビキニ環礁と三度も被爆を重ねてきた国が、世界第三位の原発大国になったのかという問いがあるが、むしろ被爆国であったが故に・・・だか ら福島の事故による放射能被害が広がったとき、「これは四度目の被爆だ」と思ったのは私だけだったろうか。」(295-296ページ)
フクシマまで「被爆」とされてしまっている。
フクシマに対して、「四度目の被爆」と思ったのは、おそらく吉見、ただ一人である(もしくは、編集者を含めても二人である)。
ヒロシマ、ナガサキ、とは、意図的に原子力を暴発させた「原爆」による米国の攻撃(がもたらした事象)である。これらは「被爆」であったであろう。
第五福竜丸事件とは、意図的に原子力を暴発させた「実験」に巻き込まれた被害である。これは、「被曝」もしくは「被爆」であったであろう。
そして、フクシマとは、大きな地震と津波の影響で「想定外」に電源喪失し原子炉が制御できなくなったことによってもたらされた被害である。これは、どう考えても「被曝」である。
「被爆」と「被曝」は、使い分けねばならない。それが基本である。これを一緒にしてしまうと、おかしなことになる。
第五福竜丸事件に対しては、水爆実験による爆撃の影響であるから「被爆」という言葉を使用することも可能である。ただ、そうした説明は加えるべきだろう。
だ が、フクシマに「被爆」という言葉を使うのは、どういう意図があってのことだろうか。
「被爆」という言葉に、原発事故による被害を指す意味など、ないはずだ。「被曝」は狭く、放射能に身体が曝されることであるから、フクシマの場合には用 いられうるが、ヒロシマ、ナガサキ、第五福竜丸事件は、すべての症状が「放射能」の影響とは特定しがたい、とされている。もちろん「被曝」の被害がないわけではないが総括的に「被曝」と言い切ることが難しい。だから「被爆」を用いる、というのが筋ではないだろうか。
一緒にしうるとすれば、それは「原子力」や「核エネルギー」による「被害」という表現になるはずである。
これを混同するということこそ、戦後の言説史における最大の課題ではないだろうか。
吉見の新書版におけるテキストから伺えるのは、戦後史を連続したものととらえ、出発であるヒロシマ、ナガサキから、第五福竜丸、そして、フクシマを同質のものとして理解しようという意識である。「四度目の被爆」という言葉は、それを言い表している。
すぐに問うてみたいのは、ヒロシマ、ナガサキ、第五福竜丸が、米国によって被ったもの、であるのに、対して、フクシマは少なくともそうであるとは言い切れないはずである。
確かに「夢の原子力」で描かれているように「原発」もまた、米国の国際戦略のなかで日本に導入された、という経緯は確実にある。だからこれをも「米国によって被ったもの」とみなしたい気持ちは、分からないではない。
しかし、原発は、それだけでは済まされない。つまり、米国による文化的圧力の典型としてだけみては、ならない。
原発には、核物理学者たちの、原子力工学研究者たちの、夢も含まれていたであろうし、過疎化し運営もままならない地方行政が賭けた、夢も含まれていた。そして、政治家である中曾根康弘や、実業家であり政治家にもなった正力松太郎を通じて表出された「私たちの願望や夢」も含まれていたはずだ。要するに、私たちは、米国に無理やりそそのかされてではなく、自ら選択し、希望を託して、原発とともに生きてきたのではないか。
それをどこかで、他者のせいにする言説にすりかわる、そのさまを、まざまざとこの両者のテキストの差異にみることができたのだった。
こうして、吉見のテキスト自体が、「核言説の歴史」における一級の史料となるのである。
もう一つのメディアとしての博覧会――原子力平和利用博の受容
吉見俊哉
所収
土屋・吉見(編)
占領する眼・占領する声
CIE/USIS映画とVOAラジオ
東京大学出版会
2012年7月
先日ブログに書いた、同じ著者、吉見俊哉の、ちくま新書「夢の原子力」は2012年8月10日発行であった。こちらは2012年7月31日である。ほとんど同時に出されている。
新書では書かれなかった細やかな情報が得られるのではないかと期待して読んだところ、すぐさま、以下のことに気づいた。
この論考は、実は、新書の第II章の内容とほぼ同一である。
にもかかわらず、どこにもクレジットがなかった。
たとえば、書籍版では、こう書いている。
「正力松太郎を社主とする読売新聞社は、1954年8月に新宿の伊勢丹百貨店で「だれにもわかる原子力展」を開催し、翌年5月には、原子力潜水艦を建造したゼネラル・ダイナミクス社社長らを招いて日比谷公会堂で「原子力平和利用大講演会」を開催した。」(293ページ)
これと新書の、次の文章を比較してみよう。
「正 力は、1954年8月には新宿の伊勢丹百貨店で「だれにもわかる原子力展」を開催し、翌年5月には、原子力潜水艦を建造したゼネラル・ダイナミクス社社長 のホプキンスらを招いて日比谷公会堂で「原子力平和利用大講演会」を開催し、この戦略の日本側の窓口となっていた。」(122-123ページ)
この二つの文章を、まったく別の文章と思う人は、まずいないであろう。
このあとも、ほぼ同一の内容が続く。一部削除や加筆もあるが、誰が読んでも、元は同じテキストであると感じるくらいに、違いは少ない。
書籍のほうは、おそらく校閲はあるものの、ほとんど編集者とのやりとりがない、と想定しうる。その一方で、新書収録の際には、編集者とのやりとりが多いにあったと思われる。
そもそも、こうした、重複した内容を掲載する場合、できることなら、初出なり、なんらかの断り書きがあってほしいものである。それが、読む側に対する敬意というものであろう。
内容的にはとてもすぐれたものなのに、こうした本の作り方は、読者からみると、残念に思ってしまう。
しかし、ここで書きたいのは、そういったことではない。もっと本質的なことである。
私がここで問いたいのは、吉見が、東大出版会の本と新書で、「被爆」と「被曝」の使い分けについて、大きく変えていることである。
これは、原爆や原発を考えるうえでの根幹にかかわってくる。
吉見がどのようにこの二つの語彙を用いたのかを見直すことは、誤植とか校正の次元ではなく、私たちが、被爆や被曝とどうかかわって生きてゆくのか、どう考えてゆくのか、その一つの方向性を示しているように思われる。
ただ、勝手に推測すると、編集サイドから「ここはすべて「被爆」で行きましょうよ」などと促され、その結果、同意して、「被曝」を「被爆に」変えるか削除したのではないか、と思われる。
きっかけはここでは問わない。両者の異同が、結果として、何を語っているのかを、私たちはしっかりと見届ける必要がある。
***
書籍に収録されている論考をベースにして、以下、差異をみてみる。
前段が書籍版で、後段が新書版である。「被爆」の「爆」には青色をつけた。「被曝」の「曝」には赤色をつけた。
「平和記念館(第二会場)が当てられていく。こうして開館したばかりの施設での原爆資料展示は、博覧会会期中、近隣の公民館に一時的に移され、本来の展示場所から排除されることになった。」(300ページ))
↓
「平和記念館(第二会場)が当てられていく。被爆のシンボル的空間での開催である。こうして開館したばかりのこれらの施設での原爆資料展示は、博覧会会期中、近くの基町の公民館に一時的に移されることになった。文字通り、原子力の「被爆」の展示は、原子力の「未来」の展示に取って代わられたのである。」(148ページ)
上記については、おそらくこの二カ所は加筆されたものと推測される。いずれも「爆」の文字を使用している。これらは、ヒロシマ・ナガサキに対して「被爆」という表記をしている。これはごく一般的な用法である。
「原爆資料の移転についても、無数の被爆者たちの神聖なる遺品を含む展示品が」「なぜそれを被爆者救済の福祉予算に使わないのか」(301ページ)
↓
(削除)
上記は、まるごとその行が削除されている。以下しばらく、いくつか「爆」の字が両方で使用されている箇所が続く。変更なしか削除なので、特にコメントは入れない。
「被爆体験の原子力平和利用への取り込みは」(302ページ)
↓
「被爆体験の原子力平和利用への取り込みは」(149ページ)
「広島と長崎の被爆者を巻き込み」(302ページ)
↓
(削除)
「被爆経験の悲惨さと原子力の平和利用がもたらす夢」(303ページ)
↓
「被爆経験の悲惨さと原子力の平和利用がもたらす夢」(152ページ)
「被爆直後の広島市街」(303ページ)
↓
「被爆直後の広島市街」(152ページ)
「被爆直後の降雨状態」(303ページ)
↓
「被爆直後の降雨状態」(152ページ)
「被爆時の写真や模型」(303ページ)
↓
「被爆時の写真や模型」(152ページ)
「被爆体験と平和利用」(303ページ)
↓
「被爆体験と平和利用」(152ページ)
ここまでは元の文が「爆」であったが、以下は書籍版では「曝」のものが登場する。ただしこの三カ所、新書版では削除されている。これも行ごとの削除であり、特に内容的な変化は見られない。
「被曝経験の恐怖から取り組みが立ち遅れている。」(305ページ)
↓
(削除)
「広島、長崎での被曝」(305ページ)
↓
(削除)
「核兵器による被曝と電線への感電はまったく別次元の事柄である。」(306ページ)
↓
(削除)
注目は、以下である。
書籍版は、はっきりと「爆」と「曝」を区別していると思われる箇所である。書籍版では、第五福竜丸の事故に対しては「被曝」を用い、ヒロシマとナガサキには「被爆」を使っている。しかし新書の方は、「被曝」を文中に一切使用していないのである。すべて「被爆」に変えられているのだ(もしくは削除された)。
「1950年代の原子力平和利用キャンペーンが戦後日本社会にもたらした影響には、この国特有の文脈において考えるべきことも多く存在した。キャンペーンが本格化する直前には、ビキニ環礁での水爆実験により、第五福竜丸の被曝事故が生じていた。この事故により、日本人の間には広島と長崎での被爆の記憶」(311ページ)
↓
「50年代半ばの日本では、一方でビキニ環礁での第五福竜丸の被爆から始まった原水爆禁止運動、他方では中曾根康弘らによって主導された原子力関連予算と原子力三法による原子力政策の推進が、ほぼ同時並行で対抗的に亢進していた。」(192ページ)
また、下記は、書籍版では「被爆」が使われていなかったところを、新書ではあえて新たに「被爆」へと書き直された場合である。ここでは、第五福竜丸事件に対して「被爆」が用いられている。
「第五福竜丸事件の直後」(312ページ)
↓
「第五福竜丸被爆の直後」(193ページ)
そして、最後。ここでも第五福竜丸は「被曝」から「被爆」へと書き換えられている。
「広島・長崎から約10年で第五福竜丸がまたしても被曝し」(312ページ)
↓
「広島・長崎から約10年で第五福竜丸がまたしても被爆し」(193ページ)
この最後の文は、ヒロシマ、ナガサキと第五福竜丸を同じものとして扱っているので、「またしても」という言葉が使われている。はたして、この両者は同じものだろうか。他の個所でも、二つの原爆被害と第五福竜丸事件を、同じ言葉でくくることができるかどうか、これは重要な問いであるが、書籍版でも新書版でもそれは説明されていない。
それどころか、吉見は、書籍版では、被爆と被曝を分けて使用していた。分けているにもかかわらず「またしても」と言って両者を同一のものとみなした。ここには矛盾がある(もしくは、この矛盾があったために、新書版ではすべて「被爆」を使うことで矛盾を解消したと解釈することも可能である)。
つまり、この二つのテクストのあいだにおいて、被爆と被曝は混乱したまま使用されている、と考えられる。
もっとも致命的なのは、新書のほうのあとがきである。こうある。
「な ぜ、広島と長崎、ビキニ環礁と三度も被爆を重ねてきた国が、世界第三位の原発大国になったのかという問いがあるが、むしろ被爆国であったが故に・・・だか ら福島の事故による放射能被害が広がったとき、「これは四度目の被爆だ」と思ったのは私だけだったろうか。」(295-296ページ)
フクシマまで「被爆」とされてしまっている。
フクシマに対して、「四度目の被爆」と思ったのは、おそらく吉見、ただ一人である(もしくは、編集者を含めても二人である)。
ヒロシマ、ナガサキ、とは、意図的に原子力を暴発させた「原爆」による米国の攻撃(がもたらした事象)である。これらは「被爆」であったであろう。
第五福竜丸事件とは、意図的に原子力を暴発させた「実験」に巻き込まれた被害である。これは、「被曝」もしくは「被爆」であったであろう。
そして、フクシマとは、大きな地震と津波の影響で「想定外」に電源喪失し原子炉が制御できなくなったことによってもたらされた被害である。これは、どう考えても「被曝」である。
「被爆」と「被曝」は、使い分けねばならない。それが基本である。これを一緒にしてしまうと、おかしなことになる。
第五福竜丸事件に対しては、水爆実験による爆撃の影響であるから「被爆」という言葉を使用することも可能である。ただ、そうした説明は加えるべきだろう。
だ が、フクシマに「被爆」という言葉を使うのは、どういう意図があってのことだろうか。
「被爆」という言葉に、原発事故による被害を指す意味など、ないはずだ。「被曝」は狭く、放射能に身体が曝されることであるから、フクシマの場合には用 いられうるが、ヒロシマ、ナガサキ、第五福竜丸事件は、すべての症状が「放射能」の影響とは特定しがたい、とされている。もちろん「被曝」の被害がないわけではないが総括的に「被曝」と言い切ることが難しい。だから「被爆」を用いる、というのが筋ではないだろうか。
一緒にしうるとすれば、それは「原子力」や「核エネルギー」による「被害」という表現になるはずである。
これを混同するということこそ、戦後の言説史における最大の課題ではないだろうか。
吉見の新書版におけるテキストから伺えるのは、戦後史を連続したものととらえ、出発であるヒロシマ、ナガサキから、第五福竜丸、そして、フクシマを同質のものとして理解しようという意識である。「四度目の被爆」という言葉は、それを言い表している。
すぐに問うてみたいのは、ヒロシマ、ナガサキ、第五福竜丸が、米国によって被ったもの、であるのに、対して、フクシマは少なくともそうであるとは言い切れないはずである。
確かに「夢の原子力」で描かれているように「原発」もまた、米国の国際戦略のなかで日本に導入された、という経緯は確実にある。だからこれをも「米国によって被ったもの」とみなしたい気持ちは、分からないではない。
しかし、原発は、それだけでは済まされない。つまり、米国による文化的圧力の典型としてだけみては、ならない。
原発には、核物理学者たちの、原子力工学研究者たちの、夢も含まれていたであろうし、過疎化し運営もままならない地方行政が賭けた、夢も含まれていた。そして、政治家である中曾根康弘や、実業家であり政治家にもなった正力松太郎を通じて表出された「私たちの願望や夢」も含まれていたはずだ。要するに、私たちは、米国に無理やりそそのかされてではなく、自ら選択し、希望を託して、原発とともに生きてきたのではないか。
それをどこかで、他者のせいにする言説にすりかわる、そのさまを、まざまざとこの両者のテキストの差異にみることができたのだった。
こうして、吉見のテキスト自体が、「核言説の歴史」における一級の史料となるのである。
- 占領する眼・占領する声: CIE/USIS映画とVOAラジオ

- ¥5,670
- Amazon.co.jp
- 夢の原子力: Atoms for Dream (ちくま新書 971)/吉見 俊哉

- ¥945
- Amazon.co.jp