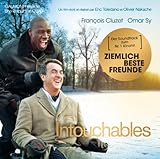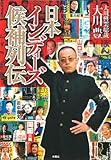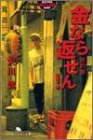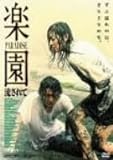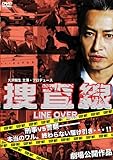読んだ本
恋する原発
高橋源一郎
講談社
2011年11月
ひところ感想
原発の事故は、一人のすぐれた作家の心を相当揺さぶったのだな、と思う。これは、おもしろい、とか、おもしろくない、とか、そういう言い方で感想を言いにくい。おもしろくない、と言ってしまうことも、許されない。この作品から「原発」に対するさまざまな作家の感受性を読みとり、評価することが、求められている。ただ、このことは、一読者としては、うれしくない。
本書の構成
メイキング1 ホワッツ・ゴーイン・オン
メイキング2 恋人よ、帰れわが胸に(ラヴァー・カム・バック・トゥ・ミー)
メイキング3 この素晴らしき世界(ホワット・ア・ワンダフル・ワールド)
メイクング4 虹の彼方に(オーヴァ・ザ・レインボー)
メイキング5 恋するために生まれてきたの(アイ・ウォズ・ボーン・トゥ・ラヴ・ユー)
メイキング6 守ってあげたい
震災文学論
メイキング7 ウィー・アー・ザ・ワールド
震災文学論で参照されているトピック
スーザン・ソンタグ(明示されていないが、「この時代に想う テロへの眼差」か?)
カワカミヒロミ「神様(2011)」
ミヤザキハヤオ「風の谷のナウシカ」(完全版)
ヤマモトヨシタカ「フクシマのゲンパツ事故をめぐって」
イシムレミチコ「苦海浄土」
****
本書は「メイキング」と「震災文学論」から構成されている。
「メイキング」とは、何らかの作品が作られている途中の「舞台裏」のようなものであろう。
すると、本編は「震災文学論」であり、この舞台裏が「メイキング1~7」ということになるのであろうか。
私は彼のよい読者ではないので、なぜ、震災文学論のところで、人名や題名の、ところどころが漢字ではなくカタカナになっているのか、よく分からないが、いかつい感じの山本義隆が妙にかわいらしく、ヨシタカちゃん、と言いたくなるような効果を狙ったのかもしれない。
震災文学論のところで語られていることは、加藤尚武や大澤真幸も語っている、「過去や未来の他者への責任」論である。これは、常識的であり、言いたいこともよく分かる。
しかしそうしたテーマ以上に、高橋が強調しているのは「順序」である。
高橋は、この「震災文学論」が、ただちに読まれることを拒んでいる。
「おそらく、ここには、「順番」の問題がある。」(201ページ)
二つの例が挙げられている。
一つは、震災に対する感想として、ある人物がマスコミのインタビューで述べた言葉「ぼくはこの日をずっと待っていたんだ」、それは実際には掲載はされなかった、ということ。
もう一つは、ソンタグが9.11に対して、卑劣な攻撃ではなく、相手に正当な理由があっての攻撃であると(こちらははっきりと)書いたことに対する、米国内の憤激について。
直接明示しないにせよ、最初に必ず、疑いえない真理を「書く」――ソンタグの場合、はっきりと述べている。
「数千の自国民の犠牲を目にして、なお、「テロとは何か。時に、テロを必要とする者もいるのではないか」という議論を冷静にできる国家(民)は、如何なるテロによっても毀損されることはないはずだ。ソンタグがいちばんいいたかったのは、そのことではなかったろうか。」(203ページ)
では、これを高橋の作品に適用させてみよう。
原発事故のあと、数千万人の人々が放射能被害の恐怖にうちふるえているなかで、なお、「原発とは何か。時に、原発を必要とする者もいるのではないか」という議論を冷静にできる国家(民)は、如何なる人々によっても毀損されることはないはずだ。
題名の、恋する原発とは、すなわち、憎むべき原発、を前にしてもなお、私たちは、原発に恋焦がれることが可能でなければならないということ、または、今までそうしてきたはずだったことを思い出すべきであること、そうしたことを示唆した物語を、前に置かねばならない、ということを指し示しているのだろう。
ところで、この「前に置かれた」ものは、本作品においては、「メイキング」である。
メイキングでの物語はこうである。もっぱら性欲を「処理」するために使用される「作品」を制作するはずのアダルトビデオ監督が、なぜか、その目的とは異なることに執着し、作品を作ってしまう、というものだ。
だとすれば、こういう解釈でいいのだろうか。
私たちは、今まで、原発が好きで好きで、たまらなかった。だって、それは二つのまちを一瞬で壊滅させた原爆を落とした国からの贈り物だったから。あんなにすごい力を見せられたら、もう、降参しかないわよね~。本当に凄かったわねあの二発は。だから今、こうして放射能こわ~い、とか言ってるけど、ほんとは、自業自得なんだし、けっこうギリギリで防いで、チョーヤバイというほどの被害はなかったし~、やっぱラッキーっつうか、すげーっつうか。
って、おまえは、誰だ。
うまく書けないが、とにかく、高橋がここで書こうとしたことは、単純ではないことは確かである。
しかし、しかし。
メイキングのところは、「小説」としては、はっきり言って、おもしろくないのだ~!
もちろん、考えさせられるけれども、作家のすることではないのではないか。
こうした仕事を行うのは、詩人や哲学者ではないのか。
作家は、小説を、小説として自立させてほしい。
高橋のこの作品は、小説ではなく、「評論」であり「思想」である、と私は考えた。であるならば、腑に落ちる。私にとって小説とは、「物語」であって、「メタ物語」に堕ちてはならないと思っている。
しかし彼は言う。
「いうまでもないことだが、これは、完全なフィクションである。」(7ページ)
フィクションと言ったからには、「小説」として、まっとうすうべきではないのか。
私にとって本書は、「若干のフィクションと若干のリアリティの混ざった、物語」である。
こうした私のような考えは、本書が、最初から排除している。
「もし、一部であれ、現実に似ているとしても、それは偶然にすぎない。そもそも、ここに書かれていることが、ほんの僅かでも、現実に起こりうると思ったとしたら、そりゃ、あんたの頭がおかしいからだ。
こんな狂った世界があるわけないじゃないか。すぐに、精神科に行け! いま、すぐ! それが、おれにできる、唯一のアドヴァイスだ。じゃあ、後で。」(7ページ)
これは、どう受け止めればよいのだろうか。
私は「ここに書かれていることが、ほんの僅かでも、現実に起こりうると思った」が、病院に行け、とただ高橋は言いたいだけではないだろう。
むしろ力点はこちらではないか。
こんな狂った世界があるわけないじゃないか。
そうなのだ。文学、小説、フィクション。こうした、私たちの能力の一つである、現実にありえないことを書くような人にとって、この原発事故は、まさしく、ありえない「現実」だったのであろう。
だから、「狂った世界」なのである。
「狂った世界」にふさわしい「物語」とは、こういう形をとるしかないのかもしれない。
*この作品はもっとはやく読みたかったのだが、図書館の予約が30人待ちくらいで、半年以上待たされてようやく読めたのだ。
*カワカミヒロミの作品は、はじめて知ったが、このような二つの作品の組み合わせ方は、私は、楽曲で、知っているものがある。
アンダーグラフ 2111~過去と未来で笑う子供達へ
恋する原発
高橋源一郎
講談社
2011年11月
ひところ感想
原発の事故は、一人のすぐれた作家の心を相当揺さぶったのだな、と思う。これは、おもしろい、とか、おもしろくない、とか、そういう言い方で感想を言いにくい。おもしろくない、と言ってしまうことも、許されない。この作品から「原発」に対するさまざまな作家の感受性を読みとり、評価することが、求められている。ただ、このことは、一読者としては、うれしくない。
本書の構成
メイキング1 ホワッツ・ゴーイン・オン
メイキング2 恋人よ、帰れわが胸に(ラヴァー・カム・バック・トゥ・ミー)
メイキング3 この素晴らしき世界(ホワット・ア・ワンダフル・ワールド)
メイクング4 虹の彼方に(オーヴァ・ザ・レインボー)
メイキング5 恋するために生まれてきたの(アイ・ウォズ・ボーン・トゥ・ラヴ・ユー)
メイキング6 守ってあげたい
震災文学論
メイキング7 ウィー・アー・ザ・ワールド
震災文学論で参照されているトピック
スーザン・ソンタグ(明示されていないが、「この時代に想う テロへの眼差」か?)
カワカミヒロミ「神様(2011)」
ミヤザキハヤオ「風の谷のナウシカ」(完全版)
ヤマモトヨシタカ「フクシマのゲンパツ事故をめぐって」
イシムレミチコ「苦海浄土」
****
本書は「メイキング」と「震災文学論」から構成されている。
「メイキング」とは、何らかの作品が作られている途中の「舞台裏」のようなものであろう。
すると、本編は「震災文学論」であり、この舞台裏が「メイキング1~7」ということになるのであろうか。
私は彼のよい読者ではないので、なぜ、震災文学論のところで、人名や題名の、ところどころが漢字ではなくカタカナになっているのか、よく分からないが、いかつい感じの山本義隆が妙にかわいらしく、ヨシタカちゃん、と言いたくなるような効果を狙ったのかもしれない。
震災文学論のところで語られていることは、加藤尚武や大澤真幸も語っている、「過去や未来の他者への責任」論である。これは、常識的であり、言いたいこともよく分かる。
しかしそうしたテーマ以上に、高橋が強調しているのは「順序」である。
高橋は、この「震災文学論」が、ただちに読まれることを拒んでいる。
「おそらく、ここには、「順番」の問題がある。」(201ページ)
二つの例が挙げられている。
一つは、震災に対する感想として、ある人物がマスコミのインタビューで述べた言葉「ぼくはこの日をずっと待っていたんだ」、それは実際には掲載はされなかった、ということ。
もう一つは、ソンタグが9.11に対して、卑劣な攻撃ではなく、相手に正当な理由があっての攻撃であると(こちらははっきりと)書いたことに対する、米国内の憤激について。
直接明示しないにせよ、最初に必ず、疑いえない真理を「書く」――ソンタグの場合、はっきりと述べている。
「数千の自国民の犠牲を目にして、なお、「テロとは何か。時に、テロを必要とする者もいるのではないか」という議論を冷静にできる国家(民)は、如何なるテロによっても毀損されることはないはずだ。ソンタグがいちばんいいたかったのは、そのことではなかったろうか。」(203ページ)
では、これを高橋の作品に適用させてみよう。
原発事故のあと、数千万人の人々が放射能被害の恐怖にうちふるえているなかで、なお、「原発とは何か。時に、原発を必要とする者もいるのではないか」という議論を冷静にできる国家(民)は、如何なる人々によっても毀損されることはないはずだ。
題名の、恋する原発とは、すなわち、憎むべき原発、を前にしてもなお、私たちは、原発に恋焦がれることが可能でなければならないということ、または、今までそうしてきたはずだったことを思い出すべきであること、そうしたことを示唆した物語を、前に置かねばならない、ということを指し示しているのだろう。
ところで、この「前に置かれた」ものは、本作品においては、「メイキング」である。
メイキングでの物語はこうである。もっぱら性欲を「処理」するために使用される「作品」を制作するはずのアダルトビデオ監督が、なぜか、その目的とは異なることに執着し、作品を作ってしまう、というものだ。
だとすれば、こういう解釈でいいのだろうか。
私たちは、今まで、原発が好きで好きで、たまらなかった。だって、それは二つのまちを一瞬で壊滅させた原爆を落とした国からの贈り物だったから。あんなにすごい力を見せられたら、もう、降参しかないわよね~。本当に凄かったわねあの二発は。だから今、こうして放射能こわ~い、とか言ってるけど、ほんとは、自業自得なんだし、けっこうギリギリで防いで、チョーヤバイというほどの被害はなかったし~、やっぱラッキーっつうか、すげーっつうか。
って、おまえは、誰だ。
うまく書けないが、とにかく、高橋がここで書こうとしたことは、単純ではないことは確かである。
しかし、しかし。
メイキングのところは、「小説」としては、はっきり言って、おもしろくないのだ~!
もちろん、考えさせられるけれども、作家のすることではないのではないか。
こうした仕事を行うのは、詩人や哲学者ではないのか。
作家は、小説を、小説として自立させてほしい。
高橋のこの作品は、小説ではなく、「評論」であり「思想」である、と私は考えた。であるならば、腑に落ちる。私にとって小説とは、「物語」であって、「メタ物語」に堕ちてはならないと思っている。
しかし彼は言う。
「いうまでもないことだが、これは、完全なフィクションである。」(7ページ)
フィクションと言ったからには、「小説」として、まっとうすうべきではないのか。
私にとって本書は、「若干のフィクションと若干のリアリティの混ざった、物語」である。
こうした私のような考えは、本書が、最初から排除している。
「もし、一部であれ、現実に似ているとしても、それは偶然にすぎない。そもそも、ここに書かれていることが、ほんの僅かでも、現実に起こりうると思ったとしたら、そりゃ、あんたの頭がおかしいからだ。
こんな狂った世界があるわけないじゃないか。すぐに、精神科に行け! いま、すぐ! それが、おれにできる、唯一のアドヴァイスだ。じゃあ、後で。」(7ページ)
これは、どう受け止めればよいのだろうか。
私は「ここに書かれていることが、ほんの僅かでも、現実に起こりうると思った」が、病院に行け、とただ高橋は言いたいだけではないだろう。
むしろ力点はこちらではないか。
こんな狂った世界があるわけないじゃないか。
そうなのだ。文学、小説、フィクション。こうした、私たちの能力の一つである、現実にありえないことを書くような人にとって、この原発事故は、まさしく、ありえない「現実」だったのであろう。
だから、「狂った世界」なのである。
「狂った世界」にふさわしい「物語」とは、こういう形をとるしかないのかもしれない。
*この作品はもっとはやく読みたかったのだが、図書館の予約が30人待ちくらいで、半年以上待たされてようやく読めたのだ。
- 恋する原発/高橋 源一郎
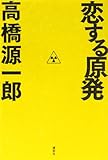
- ¥1,680
- Amazon.co.jp
- 「あの日」からぼくが考えている「正しさ」について/高橋 源一郎

- ¥893
- Amazon.co.jp
- 神様 2011/川上 弘美

- ¥840
- Amazon.co.jp
- あの日からのマンガ (ビームコミックス)/しりあがり寿

- ¥683
- Amazon.co.jp
*カワカミヒロミの作品は、はじめて知ったが、このような二つの作品の組み合わせ方は、私は、楽曲で、知っているものがある。
アンダーグラフ 2111~過去と未来で笑う子供達へ